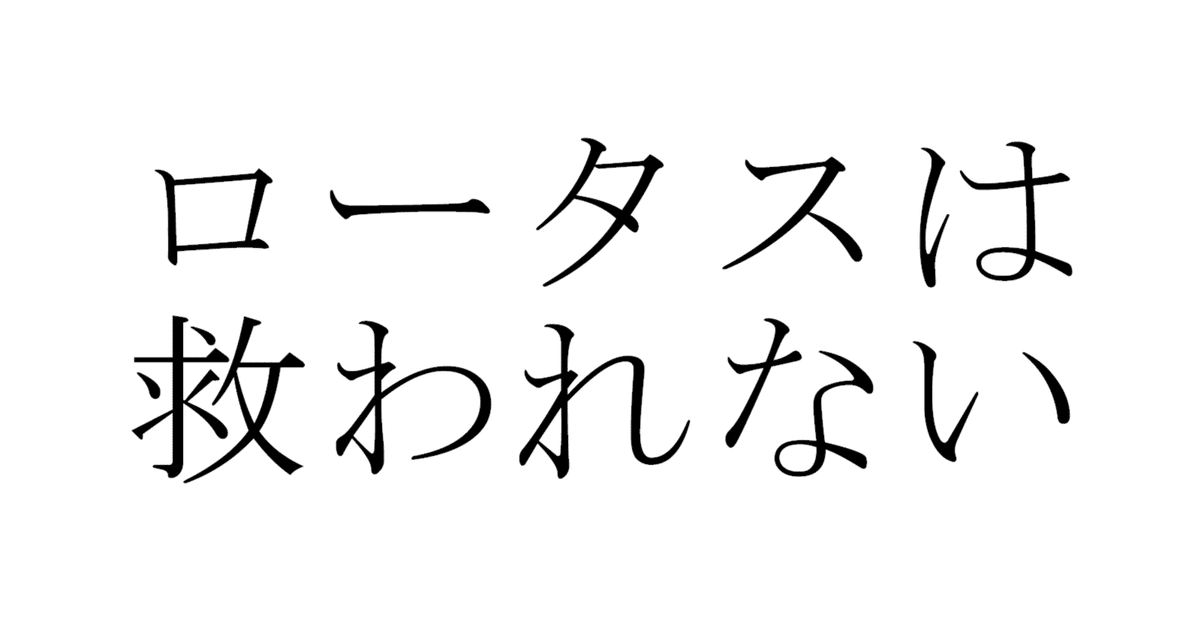
【創作大賞2023】ロータスは救われない 1/2
あらすじ
都内のコンビニで勤務するフリーター林裕樹は、客として訪れた浪人生の嶺井菜乃花と運命の出会いを果たす。自殺志願者を殺害する殺人鬼・裕樹と、死を望む自殺志願者・菜乃花は、奇妙な三ヶ月だけの同居生活を始めた。
同居生活の中で彼女の価値観に触れ、誰にも言えない告白をし、自身の変化を感じる裕樹と菜乃花の三ヶ月はあっという間に過ぎ、裕樹は約束通り菜乃花を殺害。
しかし殺害後、自身は菜乃花に惚れていた事に気付くと同時に、自身の手では菜乃花を救えなかった事に気付き後悔する。その後悔を抱きながら裕樹は自首。過去の殺人が立件され、死刑判決が下されるのであった。
死刑執行のその瞬間まで、裕樹は菜乃花の事だけを想っていた。
分厚いアクリル板の向こう。安っぽいスーツを着た若い男の弁護士が何かを言っている。本音では僕の弁護など引き受けたくはなかったのだろう。面倒そうに裁判でどう争っていくかを呟く声色がそれを物語っていた。そんな名前も憶えていない弁護士を無視して、僕は口を開く。
「僕はね、彼女を救ってあげたかったんです。他の皆と同じように」
頭の中に鮮明に浮かぶ、彼女の最期。安らかな死に顔は、一縷の希望も宿していなかった。
「今でも、悔やんでいます。あの三ヶ月で僕は彼女に何をしてあげられたのかと。やり直せるのなら、彼女に出会ったあの日に戻って、彼女を救いたいんです」
弁護士が小さく溜め息を吐いた。だが本人は小さく吐いたつもりでも、この暗い面会室にはよく響いた。弁護士の乾いた溜め息を取り繕うわざとらしい咳払いに僕は笑って言葉を続ける。
机に肘をつき体をアクリル板に傾けると、ぎいっと安物のパイプ椅子が音を立てた。
「あれは、半年前。雪が予報されていた寒い日の事でした」
◇◇◇
今日の天気予報では気象予報士が、「雪が降るかもしれません」と都民を脅しかけていた。ダウンジャケットにマフラーに手袋。防寒装備一式を身に着けて僕は玄関を出る。鍵を閉める手はどうしたって冷たい。
寒さに重くなる足を引きずってアパートの階段を下り、自分のバイクに跨る。ヘルメットを被ってエンジンをかけると、今日もバイクは元気な音を立ててくれたが、僕に元気はなかった。
「あー、くそっ。こんなに寒くなるならもっと前から言ってくれればいいのに。最悪だ。シフト変わってくれる奴もいないし。あー、最悪だ」
働いているコンビニへとバイクを走らせながら愚痴を呟く。よく「バイクって夏は涼しそうでいいよね」なんて言う人がいるが、生憎とバイクは夏は暑いし冬は寒い。こんな寒い日の運転は最悪と呼べる。向かい風があまりにも冷たい。防寒装備を突き破って来る勢いだ。
しかしどれだけ愚痴を並べても、寒さは変わらないし今日のシフトも変わらない。面倒この上ない嫌な気分を抱えたまま、家から少し離れた勤務先のコンビニに到着した。バイクを停め、「おはようございます」と言いながら店内に入り、すぐに裏へ。
防寒装備一式を脱ぎ、制服を羽織って胸に名札を付け店内に戻る。三人程並んでいたレジの一番手前の客に声をかけ、もうひとつのレジを開けて手慣れたバーコードの読み取り作業をする。「ありがとうございました」と愛想笑い十割で出来た笑顔で客を見送り、次の客の対応。
それは寒い冬の日のいつも通りの光景のはずだった。
「肉まんひとつください」
レジで小銭の追加作業をしていた僕にかけられた声。なんて事はない、いつも通りの客からの注文の声だ。僕は「かしこまりました」と返し、両手を一度消毒してからトングを握り、熱々の肉まんを紙の袋に入れる。今日は寒いから肉まんがよく売れる。そんな程度の事を思いながら、次は小さなレジ袋に詰めたそれを客に手渡そうと視線を客に向ける。
瞬間、目を見開いた。
一見、至極普通に見える少女からは、生気が感じられなかったからだ。
なのにその身に纏う服や鞄等は嫌味にならない程度に高価な物である事が窺い知れるし、それを身に纏う事への優越感はなく、常日頃からそれが当たり前である事を体現していた。光が当たれば薄っすらとだけ茶色がかる、人工物に染まっていない自然な黒髪は、別の客の来店と同時に入店した冷たい風に小さく靡けば最上級の絹糸のように柔らかく宙を舞う。
少女からは一目で、きっと裕福な家庭の子供なのだろう事が確かに感じられる。他人が羨むような、何不自由ない生活が保障されている事は確かだろう。そう、その裕福の象徴と生気のない顔がアンバランスだった。少女の姿はあまりにも、アンバランスだった。僕は、目を離せなかった。
だって少女の顔は僕が何人も見てきた、「死にたがっている人間の顔」だったから。
「……何ですか……?」
「……いえ、すみません」
僕の態度に怪訝な顔をして見せた少女に謝罪を口にすれば、少女は携帯電話に表示したバーコードを見せる。手早く会計を済ませた少女にレジ袋を手渡す直前、その小さなレジ袋にそっと小さなメモ用紙を忍び込ませた。レジ袋を受け取った少女の後ろ姿を、僕は見送る。
あの少女は必ずメモ用紙を見る。そして必ずそこに書かれているIDのSNSアカウントを見に行く。
あの少女は必ず、僕の助けが必要になる。そう確信して、見送った。
「休憩入ります」と他の従業員に一声かけてから、僕以外誰もいない休憩室で休憩を取る。安くぼろぼろの椅子に腰かけ、のんびりと携帯電話の画面を見てみる。するとそこには一件の通知。犯罪者御用達の一定時間でメッセージが消え、復元不可能なメッセージアプリの通知だ。
そのアプリは見知らぬアカウントからのメッセージが来ている事を僕に知らせる。僕はゆっくりとほくそ笑んで、画面をタップする。
「シフト終わりの時間を教えてください。店の前で待ちます、か。やっぱりな」
この状況で見知らぬ相手から僕宛てのメッセージに「シフト終わり」と「店の前」と言う単語が出せる相手はひとりだけ。やはりあの少女は「死にたがっている」ようだ。僕は「夕方六時」とだけメッセージを返し、携帯電話をうつ伏せで机に寝かせた。
死にたがっている人を死なせてあげる。それが僕の唯一の生き甲斐だ。普段はSNSを駆使して、自殺志願者を探しては自分の自殺幇助を匂わせたSNSアカウントへと誘導し、メッセージアプリを介して連絡を取っている。
だが稀に今回のように、たまたま顔を合わせた相手が自殺志願者だったと言う事もある。そう言う場合はああして、僕のSNSアカウントへと誘導するのだが、メモ用紙を渡す相手を間違えた事は一度もない。
何人もの自殺志願者を見るうちに僕は「本当に死にたがっている人」を見分けられるようになった。死を願う人の独特の空気感、一瞬だけ垣間見える本当に追い詰められた人間にしか出せない絶望の顔。僕はそれを見逃さない。そして僕はそんな彼ら彼女らを、救ってあげているのだ。
人間誰しも、わざわざ痛い思いをして死にたくはない。苦しい思いをして死にたくはない。出来るのならば眠るように死ねる「安楽死」を望んでいる。僕はそれを叶えてあげているだけ。そう、救ってあげているだけなのだ。
この世の全てに絶望した彼ら彼女らに、一縷の望みを、希望を与えてあげているだけなのだ。とは言え、この日本と言う国において自殺幇助は立派な犯罪。自殺が認められている国ですら、色々と条件が面倒だ。だから僕はこうして尻尾を掴まれないように回りくどく、救ってあげている。
ああ、いつか僕のこの救いが認められればいいのに。そう思いながらコーヒーにミルクを加えた。真っ黒なコーヒーに白いミルクが落ちて、溶けていく。コーヒーは喉を通らせたくなる茶色へと変化した。
シフトの終わりまで、まだあと三時間。
◇◇◇
仕事が終わった。僕の次のシフトに入っている人に「お先です」と挨拶をしながら店を出る。ポケットから取り出した携帯電話の画面は、六時過ぎを表示していた。軽く辺りを見回すと、少し離れた場所に立っていた例の少女と目が合った。
僕は少女に向けて一度バイクの鍵を振って見せてからバイクを取りに行く。エンジンはかけずに押して短い距離を歩き、少女の元へと辿り着けば少女は、「殺してくれますか?」とだけ呟いた。それは僕にだけ聞こえる程度の小さな声。心のどこかが何かに震えた。
「もちろん。じゃなきゃメモを渡してません」
「三ヶ月」
僕の返答に間髪を入れずに返って来た声。主語のないそれの意味は測れず、僕は言葉の続きを促すように少女を見た。
淀み。諦め。悟り。そして純粋。相反するものが混じったようなその黒曜石のような綺麗な目から、僕は少しだけ目を離せなくなった。やはりアンバランスな少女だ。実に歪な少女だ。
そしてアンバランスな少女はそのアンバランスさを保ったまま、僕に向かってにこりと笑った。
「三ヶ月、俗世から離れてから死にたいんです」
少女は続けて、「叶えてくれますか?」と笑う。僕は予想外の言葉に一瞬思考を停止した。
冷静に考えれば却下だ。大体の自殺志願者には即日から一週間を目途に死ぬ準備をしてもらっている。最長でも一ヶ月だ。あまり長期間に及ぶと警察に嗅ぎつけられるリスクが格段に跳ね上がる。
だから冷静に考えれば却下だ。長くて一ヶ月だと返すべきだ。
「構いませんよ。三ヶ月、好きに過ごしてください」
そう分かっていたのに僕は首を縦に振っていた。無意識の何かに支配されたように、首を縦に振っていた。黒曜石が嬉しそうに微笑む。
今にして思えば、僕は初めて少女を見た瞬間から、少女の何かに惹かれてしまっていたのかもしれない。
そう、全て今にして思えばの話だ。時間は巻き戻せない。
◇◇◇
「へー、結構綺麗にしてるんですね」
「まあ、物がないだけですけど」
少女の最期の三ヶ月。てっきりひとりで過ごすのだと思っていたが少女は「じゃあ今日から三ヶ月よろしくお願いします」と言って、五十万円の入った銀行の封筒を差し出してきた。
僕は呆気に取られつつも冷静さを手繰り寄せて、三ヶ月もの間少女と共に過ごすのはリスクが高いとの判断を下す。さすがにそれは聞き入れられないと断りを入れる。足がつきやすくなると言って断る僕に少女は、「家から出なければ一緒でしょ?」と笑った。
その言葉に再度呆気に取られ、言い返す言葉を見つけられなかった。結局僕は彼女の押しに負ける形で、「本当に一歩も外へ出ないのなら」と念押しをし、少女と共に防犯カメラの少ない裏道を使って遠回りをし、自宅アパートへと戻った。
少女、いや彼女は名前を「嶺井菜乃花」と言った。明け透けに本名と、それの証明である身分証明書を見せられ、またも呆気に取られる。自殺志願者は身元を明かしたがらない人がほとんどだ。
「自分が生きていた痕跡を消してしまいたい」という願望が根底にあるが故、自分を知る人を増やしたがらない。僕もそれで構わないからこそ、SNSアカウントの名前である「ルイ」以外を名乗る事もほとんどない。
自分を知らない人。必要最低限だけの情報しか知らない相手。それが自殺志願者には安心を与えられる。もう何も深く考える必要はないのだと、安心させてあげられるのだ。
しかし彼女は自らの身元を何の躊躇いもなく明かす。都内の高級住宅街に住む十九歳。幼稚園から高校まで私立のお嬢様学校に通い、成績は常に上位。だが大学受験にわざと失敗をした。家族構成は父・母・彼女・弟の四人。父親は内科医、母親は弁護士、弟は父親の後を継ぐべく医者を目指している。福岡県に父方の祖父母、高知県に母方の祖父母が住んでおり、帰省の際には蝶よ花よと可愛がられている。
どこを切り取っても何ひとつ不自由のない人生だと言えるだろう。医者を目指さずに私立の大学へとエスカレーター式に行くところを公立の美術大学に変更しても、家族の反対はなく応援をされ、落ちても叱る事なくやりたい事をやればいいと見守ってくれる。人が羨む満たされた人生のはずだ。
なのに彼女は死を望んでいる。少なくとも僕の知る自殺志願者とは正反対の人生を与えられ、約束された彼女が、死を望んでいる。
その事実に僕は少し、彼女を知りたくなっていた。
「嶺井さんは」
「菜乃花でいいですよ。名字ってなんかつまんないし」
「……じゃあ、菜乃花さん。三ヶ月も家を出ていて、捜索願は出されないんですか? 話を聞く限りじゃ心配して出しそうな両親だと思いますが」
「出しませんよ。出さないように私が仕組みましたから」
肩にかけていた自分の鞄を下ろして床に置いた彼女、菜乃花さんはそう呟いて笑う。わざわざ五十万円を用意していた彼女の事だ。その「仕組んだ」と言う言葉を偽りだと一蹴しようとは思わなかった。「どうやって?」と問いかければ、やはり彼女は何の躊躇いもなく明け透けに答える。「そう言う子だと思わせている」と。
「時間をかけて家族、親戚、友達。私と関わりがある人全員に、私は突飛な事を仕出かす不思議ちゃんだって信じ込ませてきましたから。長期休暇の時は、勝手に遠出をして勝手に帰ってくるを何度も繰り返しました。高校も卒業したんで三ヶ月くらいはいなくても捜索願なんて出す訳がありませんよ」
彼女は一体いつから死ぬ事を決めていたのだろうか。そんな感想が素直に頭に浮かんだ。なんて事はないように、まるで「今日も天気がいいですね」と話しているように彼女は言葉を口にしているが、自分と関わりがある人間全員を欺く事が簡単である訳がないし、昨日今日で出来る訳がない。
無論、彼女が魔法使いであるか、もしくは常人には理解出来ない程の洗脳技術を持っているのならば話は別だが、豊かな人生と自殺願望を与えられただけの普通の十九歳。そんな彼女が時間をかけ、家族、親戚、友人の全てを欺いて生きてきたと言うのだから、一体いつから死ぬと決めていたのかと思うのは至極当然とも言える。
だから僕はその疑問を自然と口にした。何でも明け透けに語る彼女でも、「何故死にたいのか」を答えるのは嫌がるだろうかと言う部分で、僕の中で「今までの自殺志願者とは正反対な彼女」への解像度を上げようとしたかったのだ。
「いつから死のうと思ってたんですか?」
「んー、いつ……ああ、小学生ですね。三年生くらいだったかな」
小学校三年生。そのあまりにも早過ぎる人生の終焉への覚悟は、僕を驚かせるのに十分だった。だが彼女はそんな僕を見てからからと笑うだけ。そして、そのからからと笑った顔のまま、腕にかけていたコートのポケットから取り出した携帯電話を、彼女は一度ちらりと見てからリビングのローテーブルへと置いた。
とうに電源の切られた画面は真っ暗なままだ。
「昔からあんまり人が好きじゃなかったんですよ。いや、逆かな。好きだったからこそ、疲れちゃったのかも」
「疲れる?」
「そう。人に。疲れちゃって」
コートは彼女の腕から鞄の上に置き場所を変えられ、その変更主である彼女はまるで自宅にいるかのようにソファーに腰を下ろす。そして自身の膝に肘を置き、頬杖をついて僕を見た。
「三ヶ月後。ちゃんと私を殺してくださいね。ルイさん」
僕はその言葉に頷き、彼女の隣に腰を下ろした。
僕が二十三歳、彼女が十九歳の寒い寒い歪な冬。それは僕と彼女の、たった三ヶ月だけの恋の始まりだった。
「ほら餌の笹代だ」的な感じでサポートよろしくお願いします! ポチって貴方に谢谢させてください!!!
