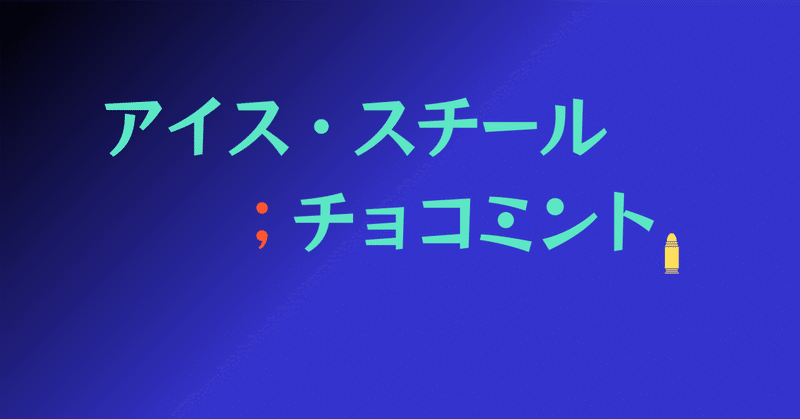
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 一章 2話 その仕事、業務範囲外
2話 その仕事、業務範囲外
ほとんど自宅と化した安いゲストハウスで、アイスは朝を迎えた。
朝食の定番は、買い置きしておいたパンと豆乳。時間に余裕がある日は、階下のフードコートまで下りる。オフのこの日は、グリーンカレーヌードルをテイクアウトしてきた。
食後は新聞を斜め読みしながらインスタントコーヒを飲むのも習慣になっている。ベッドだけでスペースがほぼ埋まる狭い宿泊部屋で、ドリップコーヒーなど望めないし、なくてもいい。お手軽第一のコーヒーで充分なのがアイスの味覚で、ゆったりした気分が味わえれば満足だった。
なので、くつろいでいるところにかかってきた内線電話のコール音は無視しようとした。こんな時間にかけてくるのは会社ぐらいだ。
わかっているくせに受話器をとってしまった。一応でも社内№2の立場にいる。トラブル処理の相談だとしたら、後になるほど片付けるのに手間がかかることになる。
そう思ってとった電話でオフが消えた。
アイスがやって来たのは、配送センターや製造業の社屋が集まっている地区の一角。凹凸のないシンプルな社屋には、<ABP倉庫>の社名を入れたプレート看板が掲げられている。
梅雨の湿度で左膝から下が重だるい。しかめそうになる眉を笑みで強引にひらき、屋内へと足を踏み入れた。
なじみの整体師のリハビリ予約まで、あと半日ほど。彼女の手にかかれば、いっときでも楽になる。それまでは、いま少しの我慢だ。すれ違う同僚たちと挨拶をかわしながらオフィスの奥へとすすんだ。
社長の権威をあらわすような重厚な扉に、儀礼的なノックを食わせる。返事を待たずに入った。
呼んだ男がボスにおさまっていても、上下関係は形式的なものでしかない。本来はビジネスパートナーの関係だった。
「オフを中断させられたから急ぎだと思ってきたけど、出直したほうがいい?」
オーダースーツを着た同年代の男に声をかける。アイスを呼び出した麻生嶋ディオゴは、背後に護衛をひかえさせ、三人の地区幹部と膝を突き合わせている最中だった。
ソフトシェルジャケットにアウトドアパンツというカジュアルな格好のアイスは、散歩途中のおばさんにしか見えない。そんな彼女を幹部トリオが、しかめ面で出迎えた。古顔だからといって、なんだその格好? といったところ。
それとは対照的なのが護衛役の男だった。
黒スーツにあわせたダークカラーのシャツ。文字どおりディオゴの影になっている末武《すえたけ》が、わずかな好奇心をのぞかせてアイスに会釈した。こちらは、急ぎで呼び出される仕事とはいったい……とか考えていそうだった。
当のディオゴは幹部トリオの反応を無視して、
「タバコ休憩してきてくれ。続きは三〇分後」
人払いをして、アイスとの密談を優先させようとした。
「こっちの仕事は後回しで充分ってことですか?」
幹部トリオのなかで年かさの男が、メモをとる姿勢のままで言った。ボスの意向を伺うような形にしていても、表情には不満があふれかえっている。
「頭が悪いな、タニガワ」
タニガワの手から奪いとったボールペンをディオゴが右手の中に握り込む。セルロイドのボディがあっさりひしゃげた。
「記録は弱みにもなる。ミーティングの内容ぐらい頭ん中に書き留めろ」
それから幹部トリオを睨めつけた。
「おれは『休憩』と言ったんだ」
動こうとしない黒ジャケットの護衛にも、
「末武、おまえもだ」
「おれのことは気になさらず――」
「アインスレーがおれに何をするっていうんだ。いいから」
それでやっと足を動かした。アイスも、
「悪いね、末武」
別に悪くはないのだが、一言いれておくと後腐れがない。
アイスとしては待たされる方がまだよかった。後回しにされた幹部トリオのトゲトゲしい視線で刺された後頭部がむずかゆい。ディオゴに苦笑した。
「あたしを悪者にしてまで早く進めたい話って?」
「悪気はなかったんだ。ちょっとその……繊細な話だから、アインスレーが適任なんだ」
でた。悪気はなかった。
こういう弁解のときは、たいてい悪いと自覚できていない。何度となく繰り返されてきたので、あきらめが先にきていた。
「じゃ、早くすませて、タバコ休憩を長引かせないようにしよう」
本革のソファに勝手にすわった。
無垢材をつかった高級品なのに、クッションが柔らかすぎて身体が沈み込む。楽なようでいて姿勢が崩れて好きではないのだが、ディオゴがこのソファにこだわった。
スーツの上着を脱いだディオゴが、対面にどかりと座りなおる。
アイスに警戒心がおきた。上着を脱いだのは、ざっくばらんにプライベートが入った話をする可能性が大きい。ビジネスライクに切り捨てられない、長い付き合いがあった。
「怜佳と子どもを連れ戻してきてほしい」
怜佳というのはディオゴの妻だ。やはり予感が当たった……ちょっと待て。
「子ども?」
想定外のワードに、思わずおうむ返しをしてしまった。
「怜佳さん、いつの間に産――」
「産んでいない。預かってたんだ。名前は、高須賀未央」
「その子を怜佳さんが連れて逃げたと」
「居場所がわかったから、アインスレーが迎えにいってくれ」
「愛想つかされたなら、あきめるか、改めるかしないと。急いで元のサヤにおさめようとするより、別居して時間をおいたほうがいいんじゃない?」
「もうちょっと優しい返しはできねえのか? あと、愛想をつかされたわけじゃない」
「迎えなら自分でいきなよ。そのほうが誠意も伝わる」
「おれが動くと、その……まわりに知られる」
「妻に逃げられた男って?」
「ほんとストレートな言い方をするよな、アインスレーは」
「褒めても何も出さないよ」
「報酬はおれのポケットから出す。引き受けてくれるな?」
「答える前から、こっちが了承したように言いなさんな。それはともかく、呼び出されたわけがわかったよ。あたしになら知られて恥ずかしいことなんて、もうないもんね」
部下たちに、妻もコントロール《支配》できない男と見られたくないのだ。
面目にこだわる性分は、そこここに出ていた。痩せ型のディオゴだが、ワイシャツの首周りや肩の生地は余っていない。スーツはもちろん、シャツまでオーダーメイドだからだ。安物を着ていたら相手にナメられるというのが本人の弁だった。
そして怜佳はディオゴより二〇歳ほど若い。自分よりはるかに若い女を妻にしたのも、見栄のひとつといえる。
「女房を連れ戻すなんてアインスレーにしか頼めない」
「わかった、わかった。子どものことをまず聞かせておいて」
古い相棒に甘いのでなく、アイスにとっては断るほうが面倒だった。
こうなった怜佳との顛末を訊くつもりはない。知らない方が仕事がスムーズにいく。ただ子どもの周辺事情よっては、仕事の難易度が変わる可能性がある。そこだけは確かめておきたかった。
「そう言うと思って用意してある。いまの髪は肩先に届く程度にのびてる」
まずは写真を受けとった。卒業アルバムから複製したのか、ショートヘアに制服姿の未央が、バストショットでこちらに視線をむけていた。
「この子のご両親は?」
「亡くなった」
「怜佳さんが後見人だったとか?」
「おれが知らないうちにな」
ふと思い浮かんだことが当たっていた。ディオゴが渋い表情になったのは、直感で言い当てられた悔しさか、怜佳が〝主人〟に黙って勝手なことをしていたせいか。
ともあれ写真を見れば、ディオゴが高須賀未央を引き戻したい理由がわかった。
ミオが着ている制服は、北摂エリアにある有名私立中学のものだ。ここに通わせることができる経済的余裕が保護者にあった。そこから推察できるのは、遺産があるといった金絡みだ。
ディオゴは表の帳簿にのせない<ABP倉庫>の販路拡大を計画している。買収や抗争諸々のための資金を喉から手が出るほど欲していた。
ディオゴは暴力に対しては用心深い。社内での幹部会議にすら護衛の末武を控えさせるぐらいだ。ちょっとしたプライベートの外出でも、最低二人の護衛をつれて歩いた。その反面、経営面となると大胆だった。
アイスとしては<ABP倉庫>の体力からして、小規模堅実路線がいいと考えていた。
商売を大きくして儲けを増やせば、それだけ危険やトラブルも増える。さして大人数の構成員がいるわけではないから、対処しきれなくなる危うさを秘めていた。
<ABP倉庫>の代表にディオゴをすえたのは、取引相手との暗黙の配慮が必要になると考えたアイスが身を引いたのだが、当の本人はそこには思いが至らない。
社名にしても、荷物をいれる大きな入れ物だから「BP《ビック・ポケット》倉庫」という社名候補の頭に、麻生嶋をあらわす「A」をつけた。立ち上げたのは、佐藤アインスレーと麻生嶋ディオゴのふたりでだったのだが。
安着な社名が表すとおり、倉庫事業は裏仕事のカモフラージュとしてスタートした。それがいまでは正業として安定し、社員には保険や手当をつけている。
なのに思い出したように経営が傾くときがあった。不相応の販路拡大や売り込みをかけるディオゴの悪癖がおさまらないのだ。そのたびにアイスら裏事業担当者が仕事を増やして資金を調達し、それを元に倉庫スタッフが奮闘して立て直した。
ワンマン社長を辞めさせるのは難しい。かといって、スネに疵持つ身の転職は選択の余地がなく、裏仕事に戻りたくない倉庫スタッフは他所にいくこともできない。
唯一、ディオゴに物申すことができるアイスは、現状打破を期待する視線を浴びること度々だった。
アイスとて、立ち上げた<ABP倉庫>に愛着がないわけではない。かといって、ディオゴとのあいだに波風を立てる気力はすでになかった。ディオゴと組むことを決めたのは、自分にない才をディオゴに認めたアイス自身であることもあり、ただもう引退後の生活に思いを馳せるばかりになっている。
仕事に区切りをつけられる頃合いからして、あと少しで望みが叶いそうというところだった。
「で、怜佳さんが実家に帰ってるっていうのは確か?」
アイスは念押しで訊いた。行ったけどやっぱり不在の無駄足は踏みたくない。
「あいつの父親は、下請けを出している運送会社の社長だ。そこの従業員から連絡してきた。怜佳に泣きつかれたとはいえ、発注元の機嫌を損ねるのが怖かったんだろう」
「ふうん……」
生返事をかえす。怜佳のことをよく知っているわけではないが、不自然に感じた。
ディオゴには愛人がいて、婚外子もひとりいる。怜佳はそれを知りつつ怒ることはなかった。これは、ディオゴとのあいだに子どもができなかった引け目のせいではないだろう。
夫と仲がいいわけではないが、言い争いをするのでもない。付かず離れずの関係は、怜佳が何かしらの打算を働かせているようでもある。感情のままに行動をとるタイプにはみえない。
それに、理学部か理工学部だったかに在籍していたと聞いていた。理系なら論理的というわけではないが、所在をくらますのに実家に戻ったというのは不可解だ。
高須賀未央の手には、数年後に遺産が入ってくる。金目当ての人間が食らいついてくる対策に、とりあえず実家に逃げたにしても、ほかに策を持ってのように思えた。
「楽な仕事だろ?」
ディオゴの問いに相槌は打たなかった。かといって不審な顔も見せない。
アイスはいつもの、ゆるい笑みで応えた。警戒心を抱かせない微笑みで、相手の本音を引き出し、自分の本心をガードする。そんな表情にディオゴは疑いをかけることもなかった。
「休みに呼び出した色もつける。頼まれてくれるよな」
引き受けると信じている口調にアイスは水をさした。
「もうひとつ確認しておきたい」
「女と子どもを連れ帰るだけだぞ? ぐずぐずするうちに怜佳が出たら、あとを追うのが難しくなる」
アイスと違ってディオゴは、こうと決めたらすぐに動く。考え方が反対のところがあるこそ、この男と組むことにした理由のひとつだった。
「怜佳さんの隠れ場所をつかんだのは誰?」
「一太《いちた》だ。サポートを必要なら一太を使ってくれ」
「本人がすすんで動いたの?」
「おれが指示した……なんだよ、その顔」
チェ《崔》一太はディオゴの愛人の息子だ。その一太に行かせたのか……。
一太は<ABP倉庫>の裏作業を担う実行班員に、自ら希望して入ってきた。ディオゴも目をかけてはいるが、あくまで構成員としてだ。会社の外で、息子として向き合っている様子はうかがえない。一太がまだ幼い頃、子どもが好きなわけでもないアイスが、代わって構っていたぐらいだった。
引退を考え始めているアイスとならんで、ディオゴも後継候補をしぼりはじめている。そのなかに一太も入って入っているからこそだろうが……
「いや、なんでもない」
相手がディオゴでも、家のなかの事情に口出しはしたくない。親子体験がない身としても、アドバイス的なことは何も出てこなかった。
「ひとりで行ったほうが穏便にすませられる。応援はいらない」
アイスは高須賀未央の写真をテーブルにおいた。怜佳が身を寄せているという運送会社の住所メモにもう一度目をとおして覚え込む。不要になった紙切れもおいて立ち上がった。
「あたしの迎えを怜佳さんが拒否したらどうするの?」
「拒めんさ。断ったらどうなるか、怜佳だってわかっている」
「怜佳さんにまで裏業界ルールを適用するんだ」
「したくないからアインスレーに行ってもらうんだよ」
「たまには楽しい仕事がしたい」
「楽しくないから金になるってもんさ。休日出勤させた振替休日も用意しておく」
「お気遣いどうも。じゃあね」
アイスはさっさと社長室から退却する。夕方過ぎに私用があった。欠かせなくなっている身体のメンテナンスのための予約で、施術者とは個人的なつきあいもある。
終わったあと食事に誘って、少し呑むのもいいかなと考える。プライベートで会ってくつろげる、貴重な存在だった。
時間に遅れないために、頼まれ仕事はとっとと片付けてしまいたい。
社長室をでたアイスが事務所を通りすぎようとしたとき、
「ご苦労さまです」
さきほど話題に出たばかりの当人、チェ一太につかまった。
ディオゴに似たのは少しばかり小柄な身長ぐらいで、ルックスはいい。くっきりした目元は母親譲りだった。
「オフでしたよね。なのに子どものお迎えを引き受けられたのですか?」
「みんな忙しいからね」
「社長の頼みとはいえ、ご老骨に鞭打たなくてもよろしいのに」
さわやかな笑みをうかべながら、出てくる言葉は辛辣だった。
「社長には、おれが最後までやると言ったんですよ。身内のゴタゴタみたいなものですし」
机についている事務スタッフたちの手が止まっている。ランチタイムには、新旧構成員対決続編として広まっていそうだ。一太がぶつかってくるのは、今日に限ったことではなかった。
「身内案件だから古馴染みのロートルにまわってきたんだよ」
身内を強調する一太が不憫にも思える。そこはおくびにも出さず、へらりと笑って、ぬらりとかわす。
「老後の資金が心細いから稼がせて」
うわべの笑みさえ一太は消した。
「ハデに遊んだりしないあなたなら蓄えだってあるはずだ。余生を楽しんだらどうです?」
伝票を手に事務所のドアをあけた倉庫スタッフが、一太の表情を見てUターンした。言葉は穏やかでも、これから裏仕事にいくような剣呑な顔つきでは無理もなかった。
アイスは場所をかえないまま話を続ける。誰かに聞かせた方が、話に尾ひれがつきにくい。
「目下の課題である、販路のトラブル解決とボスの身内問題。将来ある構成員の一太が販路の解決で経験積んで、下り坂しかないあたしが身内問題。役目のふりわけはこれが正解でしょ?」
「チェさん」
倉庫スタッフと入れ替わって入ってきた十二村が、一太をうながす。もとはディオゴの手足となっていた十二村だが、最近はもっぱら一太について動いていた。
「……これで失礼します」
何かまだ言いたげな一太だったが、背中を向けて出ていく。十二村がいつもの陰鬱な視線をアイスにやってから、あとを追った。
ふたりが外に出た途端、事務スタッフたちが安堵の息をついた。
「仕事のジャマして悪かったね」
ペーパーワークスタッフにいらぬ緊張を与えてしまった。
「腹が立たないのか? 若造に好き勝手いわれて」
そばの机にいた年かさのソボンだけが、メガネを外してアイスを見上げた。<ABP倉庫>を育ててきた初期からの同僚だった。
実行班員には事務屋を下に見る者が多い。一太もそのひとりだ。
腹を立てながらも、台詞の後ろ半分が小声になったのは、実行班の急先鋒に成長してきた一太への恐れがあるせいだった。
「ボスにしたって商売をひろげるより、〝社交費〟を見直してほしいとこだし」
アイスも声をひそめて言った。
「営業がド下手なあたしに代わって一手にやってくれてるんだけど、見栄っ張りなとこが……ね。工面で手間かけさせて、ごめん」
「そう言ってもらえるだけでも報われるよ」
目尻のしわを深くしてソボンが苦笑する。追加のグチを聞いてから事務室から出た。
古参にありがちな威圧感がないアイスになら、大声で言えないことも話しやすい。これでガス抜きをしてもらって要望を聞き、希望をもってもらう。内容によってはディオゴにそれとなく伝え、改善を提案してみる。長い間アイスがやってきたことだった。
玄関口まできたところで、ソボンが追いついてきた。ひとけのないトイレの前まで引き戻された。
「チェが最近持ち出した備品のことで、耳に入れといてもらった方がいいかと思って」
味方はつくっておくものだ。ソボンは備品のすべてを保管管理している。こういった物の出入りで、社員の動向がみえることもあった。
仕事の失敗は、いつもわずかな綻びからおこる。たまたまタイミングが重なっただけかもしれないが、だからこそアイスは気に留めておいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

