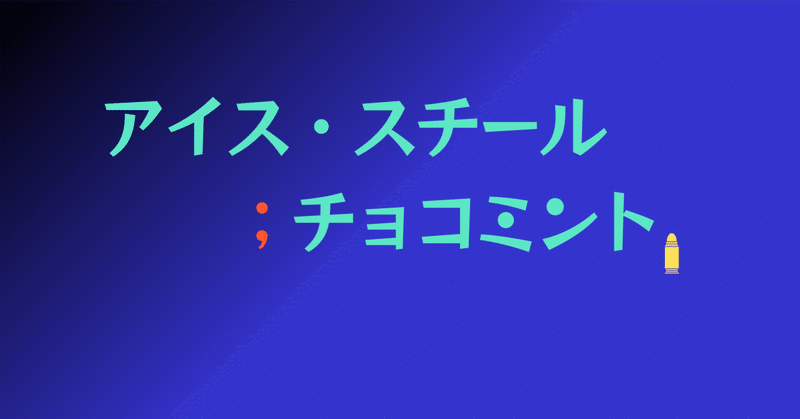
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 一章 1話 逃走は女の子をつれて
1話 逃走は女の子をつれて
佐藤アインスレーの容姿で目立つところといえば、平均より少し高い身長ぐらいしかない。略名の「アイス」からアイスクリームを連想する者もいたが、ふくよかな体型というわけでもなかった。
アイスがまだ十代の頃、北欧系の血が混じっていると、遠い親戚筋から聞いたことがある。あやふやなのは、両親そろって不明のうえに、ご先祖などアイスにとって、どうでもいいことであるからだ。その親戚とは元から疎遠だったこともあり、真偽を確かめないままになった。
北欧系といっても容姿にあらわれているのは、グレーの瞳と、アジア系にしては肌が白い程度。移民が少なくないミナミにいると簡単に埋没した。
もっとも仕事柄、外見の没個性を普段から心がけている。ジャケットは近所のホームセンターで買ってきたようなソフトシェルジャケット。下はライトベージュのアウトドアパンツ。フィクションの登場人物でいえば、エキストラその3といった出立ちだった。
ただ着ている服が、埃でマダラ模様をつくっているとなると話は別になる。
さらに、歳の離れた連れが同じような汚れをつけているとなると。
アイスのすぐ後ろを歩くのは、まだ十代半ばの女の子だった。こちらもアイスほどではないものの、うっすら汚れている。
タンクトップの上に重ねたオーバーサイズのストライプシャツや、白のハーフパンツはシンプルでも、タグネームには名の知れたブランドが記されている。その一品が、繊維の中まで入り込んだ埃と乱暴な運動でシルエットも崩れ、すっかり安っぽい服に変貌していた。
すれ違う人が時折り、アイスたちの汚れた服に視線を送ってくる。すぐに興味をなくしてくれるのだが、このちょっとした動作がアイスには気がかりだった。
追っ手の目をひかないとは限らなかった。
さいわい今のところ、アイスが気づく範囲では無事だ。
心許ないのは、痛み出した左のふくらはぎに注意力を散らされていること。可能な限り尾行の距離をとり、確実に捕まえられるところまで潜んでいるかもしれない相手を見落としているかもしれなかった。
「どこいくの?」
アイスは振り返ることなく、背後で不意に足先の向きを変えた女の子に声をかけた。
全方向に注意をはらっていたのは、追っ手のためだけではない。消極的選択でついてきている女の子が起こしうる無謀を警戒していた。
女の子の足が、入ろうとしていた路地の手前でとまる。きらいな食べ物を口いっぱいに詰めたような表情で、振り返ったアイスを無言で睨んだ。
「逃げてくれてかまわないよ。ミオ……さんがいなくなれば、あたしもお役御免になって自由になれる」
「受けとった報酬もネコババできるし?」
高須賀未央が顎をあげて言った。
身長がすでにアイスと同じぐらいあるので、そうするとまるで見下ろしているようになる。挑発しているつもりなら、かわいいものだ。
「金は返すよ」
「返すっていっても、怜佳さんは……」
「もう死んだってあきらめてる?」
「そんなことない! ちゃんと怜佳さんに返してよね」
「念押ししなくても大丈夫。食うに困ってるわけじゃない。あたしから逃げて困るのは、新たに頼る先を探さないといけないミオさんのほうだ」
「警察にいく。そこから福祉事務所に連絡してもらう」
「そ。じゃあ気をつけるんだよ。人込みは隠れやすいけど、それは敵にも当てはまる。慣れてないと人波で目が迷って、そばに来られてても気づけなかったりするからね」
女の子からの返事はない。アイスも無言で背中をむけて歩き出した。
人込みの雑音のなか、小走りで近づいてくる気配。すぐに声をかけられた。
「わたしの方なんか全然見てなかったのに、なんでわかったの?」
「見てなくたって、気にかけてる人間がいなくなったら、なんとなくわかるよ」
「……そうなんだ」
無視されているわけではないことに納得したのか。ミオは黙ってまたついてきた。
アイスは速い歩調で歩く。左足の痛みは抱えている故障ゆえで、我慢することにも慣れていた。
周囲に視線だけをめぐらせて警戒し、店のウィンドウを利用して背後をさぐった。
前から歩いてきた中年過ぎの女性がアイスに気づき、不快そうに眉根を寄せた。立体的な仕上がりから、オーダーメイドとわかるスーツに埃が移るといわんばかりに、混み合う通りの中でも距離をとってすれ違った。
まだ明るいせいもある。オフィスワーカーが多い繁華街で、汚れた服は周囲から浮いている。おまけにアイスは、片手をジャケットの下に潜り込ませていた。人によっては何か隠し持っているように感じて、不審感が大きくなる。
脱がないとしょうがないか……。アイスは、こちらを見る人の目がないタイミングでジャケットを脱いだ。すぐに丸めて左脇腹にそわせて抱えもつ。
そういえば、額を切っていたと思い出した。雑にぬぐっただけなので血がまだ残っているかもしれない。そんなことにも気づけないほど、連れているミオに注意をとられていた。
仕事で誰かを、ましてや子どもを保護するなどないことだった。独り身のアイスにとって、子どもとのコミュニケーションなど未知の領域で、ミオがこっそり離れようとしたことに気づいたのは、それだけ気を遣っていたからでもある。
「ミオ……さん、アウターシャツを脱い……いや、やっぱりいい」
「年頃の女の子をタンクトップ姿で繁華街を歩かせられない――とか考えるほど、年寄りじゃないでしょ? 下着になるわけじゃないんだし脱ぐよ。汚れてるの、気になってたの。あと、呼び捨てでいい。変に気を遣われるほうが気持ち悪い」
妙に察しがいい子どもも、ますます苦手だった。
それに「年寄りじゃない」と真っ向から否定できる年齢でもなくなりつつある。事実から目を背けるつもりはないが、他人から言われると刺さるものがあった。
同年代と比べれば、体力も柔軟性もはるかにある。しかし、苛辣な仕事をしてきた身体は、加齢によって治癒力をなくし、怪我がそのまま故障となる。若い頃についた右肩の脱臼癖にくわえ、左下腿部の筋挫傷がそれだった。
人波にぶつからないよう、不規則なステップをおりまぜての早足は膝に負担をかける。後遺症が残る左足の痛みが徐々に強くなり、アイスの眉間に峡谷をつくろうとしていた。
元からそんなコンディションなのに、本来の目的とは逆の依頼を受けてしまった。
かつてない不覚の原因--ミオをともなって、アイスは先を急ぐ。
アーケード街に入ってからも人込みは変わらないが、人の流れに規則性ができる。横道からいきなり人が出てくることが少なくなり、お呼びでない人間の発見が多少やりやすくなった。
「追っかけてくるやつ、いる?」
ミオが周囲を振り返ることなく訊いてきた。逃げるための注意を守ってくれていることに感心しつつ、アイスは首を小さく横にふる。
「大丈夫。いまのところは」
「罰に、ここで別れていいんだよ? そうすれば、あなたに危険がおよぶこともないんでしょ?」
思わず足をとめそうになった。子どもがしなくていい心配だ。
「引き受けたんだから、中途で投げ出したりしない」
「お金に困ってないって言ってたけど、ここまできて報酬をなくすのは、やっぱりもったいない?」
「あんたの依頼主から提示されたのは、失っても惜しくない額。けど、身体が動くうちに稼げるだけ稼いでおきたいっていう本音もある。ピンならともかく、あたしみたいなキリの報酬なんて、そういいもんでもないからね」
十代の子ども相手に、こんな答えでいいのかわからなかったが、ミオだから本音を言っておいた。
反発するところを見せてはいても、アイスを巻き込んだことを理解している。大人びた気遣いも、ひとりにされる不安からきている気がした。
「ミオにも用心してほしいから、はっきり言っとく。相手が子どもだろうが、麻生嶋ディオゴは金になることを簡単にあきらめたりしない。好き勝手されたくないんなら、気を抜かないで」
「そういうこと笑顔で言うなんて、どうかしてる」
困惑と軽蔑がまじったミオの視線をうける。アイスはゆるい笑みをうかべていた。
「笑んでいるのは、あたしのポリシーみたいなもんだから気にしないで。ウソでも笑っていれば気持ちが深刻になりすぎない。頭も柔軟に回転する。行き詰まっても何とかできるアイデアが出てくる」
追手のほかにも探しているものがある。視線を周囲に走らせながら応えた。
「じゃあ、怜佳さんのことも考えてる? どうやって無事を確かめるつもり?」
「その話は目的地についたあとで。もうすぐだから」
返事をごまかしたのではない。怜佳が「麻生嶋の妻」であることで、話が複雑になっていた。
怜佳はクライアントであるのと同時に、ディオゴとはビジネスパートナーであるアイスを裏切り者へと方向転換させた張本人でもある。コンパクトに答えるには複雑すぎた。
こうしているあいだも左脇に、生ぬくく湿った感触が広がる。見なくてもわかった。当てているアッシュブラウンのソフトシェルジャケットが、黒褐色の領域を確実にひろげている。
左脇を斬られていた。
深くはない傷で、出血も酷くはない。しかしミオを預かったあとでは、最優先事項が手当よりミオの安全確保になる。そうして動き回っているうちに傷口がひろがった。
失血で動きが鈍くなる前に早く処置しないと、休むどころか永眠してしまいそうな気がしてきた。こんな気の持ちようでは駄目だとわかっている。しかし、あまりに想定外の展開で、いつもの〝慎重な楽天的思考〟が追いつかない。
笑むことで他人事のようにして、客観的判断が発揮できるようにしてきた。なのに、ベテランと呼ばれて久しいここにきて、怜佳に覆されるとは。
「ちょっと……ほんとに足の故障だけなの? 顔色が悪いよ?」
「ミオもちょっと休まなきゃね」
答えをはぐらかせた。正直に答えても不安を与えるだけだ。
やっと目当てのものを見つけ、歩む方向を変えた。韓食酒房と日本式居酒屋のあいだにある公衆電話へと、人の流れを横切った。
途中、会社員風の男にぶつかりかけた。左足が痛むとはいえ、よけきれなかったことが少しショックでもある。この頃とみに電池切れのタイミングが早くなってきていた。体力が落ちているのは間違いない。
引退の現実味が増してくる。現役に未練はないけれど、麻生嶋ディオゴにボスを任せてきたことが、ずっと心のすみに引っかかったままだった。
ワンマン気質のディオゴは、密かに進行している跡目争いをよそに、いまだ勢力拡大に夢中になっている。贔屓目にみても、そんな余力がある組織とはいえない。他のことに力を割いていては、いまの商売が傾いてしまうというのに。
影の調整役として働いていたアイスだったが、身体のメンテナンスに時間がかかるようになると、抑える気力も失いつつある。
もう頃合いだった。
報酬を散財せずにきたから、そこそこの蓄えができている。早めの引退をきめて小さな店をもつ。そうして細々とでも、ゆっくりできる生活を夢見ていた。楽しみをかなえないまま死んでたまるかという気概だけが残っている。
アイスは周囲に追手の影がないことを再度確かめてから、少額コインを公衆電話に落とした。
回すダイヤルは暗記している。体力を過信せずに何度も連絡をとるうち、覚えるつもりのないクリニックの直通ダイヤルを覚えてしまった。優秀が助手がいるから問題ないのだが、早めの晩酌にドクが突入するのを防いでおく。
ミオが離れずにいることを視界のすみにおきながら呼び出し音を聞いた。
故障の調整のために、いつもの整体師のほうの予約もとってある。遅刻しても待っていてくれると助かるのだけれど……
この思いは、かなわないほうが良かったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

