
不安障害における不安の的中率とノーシーボ効果の影響についての研究(笑)
0.注意事項
本記事は正式な学術論文ではありません!
したがって、書式とかもテキトーですし、記事の内容の正確性についても責任を負いかねます。
私は心理学や精神医学については独学でちょこっと勉強した程度の素人ですし。
(記事の内容の正確性については、読んでもらえばわかると思います。笑)
ただ、自分のように不安障害の人や不安になりやすい人のため、ひいては精神医学や心理学の発展のためになればと思い、本記事をまとめました。
それでは本文を、どうぞ!
1.はじめに
心配事や不安の9割は、実際には起こらないらしい。
どっかの大学のちゃんとした研究結果(詳細は覚えてません)らしいが。
ただ、これは健常者の話。
私は現在、不安障害(社交不安障害、広場恐怖らしい)に罹患してひきこもり状態にある。
そこで私は疑問に思った。
『不安障害患者の場合には、不安の実現率はどれくらいなのか?てか、そもそもホントに9割の不安が実現しないの?』(疑問1)
あと、ノーシーボ効果が不安の実現にどのような影響を及ぼすのかも気になった。(疑問2)
ノーシーボ効果ってのは、簡単に言うと悪い結果を気にしすぎて実際にそうなっちゃう、みたいなやつ。思い込みの力、みたいな感じかな。
プラシーボ効果の逆。
プラシーボ効果とノーシーボ効果について、上手く説明できないので、良くまとまってるサイトを貼っときます。笑
さて、本研究の目的だが、上述の疑問1,2を確かめること、とする。
ちなみに仮説としては、不安の対象の事を気にしすぎて、ノーシーボ効果が生じる結果として不安の実現率は健常者のそれ(1割)より高くなる、とする、
予想される因果経過の図

2.方法
不安障害でひきこもり状態にある私がちゃんとした研究を行う事は不可能。
したがって今回は、不安障害の患者たる私が不安に思う事を書き出し、その実現の有無を確かめる方法を試みた。
朝、起床後に、その日一日の内で不安に思う事を紙に書き出し、その各々が実現したか否かを記録する。
これを約1ヶ月計353個の不安について検討した。
また、結果に影響を与えうる要因となるかも知れないその日の調子についても記録した。
介入行動について。
今回は薬物療法開始前までの不安に限定して検討する。薬物療法の効果が反映されると、自ずと本研究の結果に影響すると考えられるからだ。
なお、私は一刻も早く不安障害から元気になりたいので、瞑想や筋トレといった介入行動を、研究対象期間一定して行ってきた。
さらに心理学や精神医学の勉強が、認知行動療法的効果をもたらしている可能性もある。
したがって、これらの介入行動の影響についても視野に入れつつ検討する。
3.結果
計353個の不安の内、実現したものは88個であった。
約25%の不安が実現する結果となった。
外れた不安は約75%だ。
また、不安の実現率が高い日は調子が悪い日、不安の実現率が低い日は調子の良い日だった。
4.考察
本研究の目的は、不安障害患者における不安の実現率の検証と、それに対するノーシーボ効果の影響の検討であった。
計353個の不安の内、実現したものは88個で、約25%の不安が実現する結果となった。
健常者の不安実現の割合(10%程度)よりも有意に高いもので、誤差とは言えないだろう。
これは、不安の対象を意識しすぎる事による実現、ノーシーボ効果によるものと考えられる。
したがって、仮説は支持されたと言えよう。
支持された因果経過の図
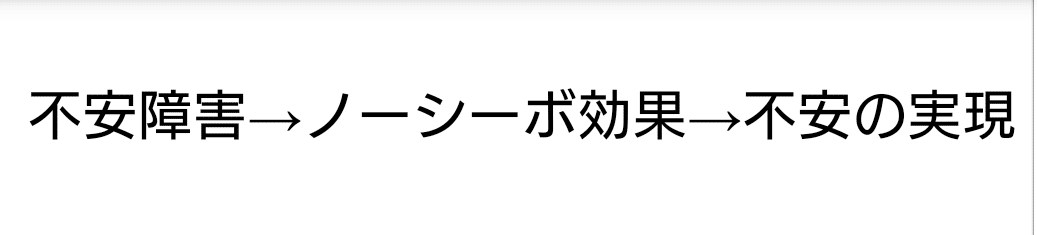
また、その日の調子によって不安の実現率が異なるので、その日の調子も不安の実現に影響すると考えられる。
調子が悪いときというのは、不安の対象に多く注意が向いてしまっている状態であり、この不安の対象に過剰に注意を向ける状態が、ノーシーボ効果を生じさせているのかも知れない。

なお、この結果は、有名な瞑想による不安低減効果を追認するものとも言えよう。
なぜなら、瞑想は注意力、注目先のコントロール意識的に行うものであり、ノーシーボ効果発生を抑制する一助になると考えられるからである。
また、不安障害をはじめ、精神疾患は、その症状に波がある(日や時間によって調子の良し悪しが変化する)事が知られている。
そのため、不安障害のみならず広く波のある精神疾患患者の場合には不安の実現率がその日の調子によって異なる可能性がある。
なお、前述のように今回の研究は瞑想や筋トレ等の介入の効果を排除していないので、その点は留意すべきであろう。
5.まとめ(本研究の限界、展望、意義)
まず、本研究はどう考えてもちゃんとした研究じゃない。
研究期間が短すぎる(約1ヶ月)事や、研究対象が私一人のみである事、瞑想や筋トレといった介入行動の効果を排除できていない事からしても、この事は明白。
これが本研究の限界だ。
したがって、これから先は本研究のこうした問題点を是正した上でしっかりと不安障害とノーシーボ効果、不安の実現率について検証する事が必要だ。
ちなみに、私の個人的な話になるが、薬物療法が始まったので、その効果を確認する意味でも本研究は続けるつもりである。
最後に本研究の意義について。
本研究では不安障害をはじめとする精神疾患がノーシーボ効果を介して不安の実現率を高める可能性が示唆され、ノーシーボ効果発生による不安の実現を瞑想が抑制しうる事も考察された。
この事は、本研究がちゃんとした研究でない事を前提にしてもなお、科学的に有意義な話なのではないか、と思う。
さらに本研究は、(個人差はあろうが)不安障害の場合でも不安の的中率は約25%であり、しかも瞑想によって不安実現率を更に低下させる可能性を主張するものだ。
不安障害患者をはじめとして、『不安との上手い付き合い方を提案する』という意味でも有意義なのではないだろう。
不安は、自分が恐れている程現実化しないっぽい。
不安に振り回されすぎないように瞑想を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
