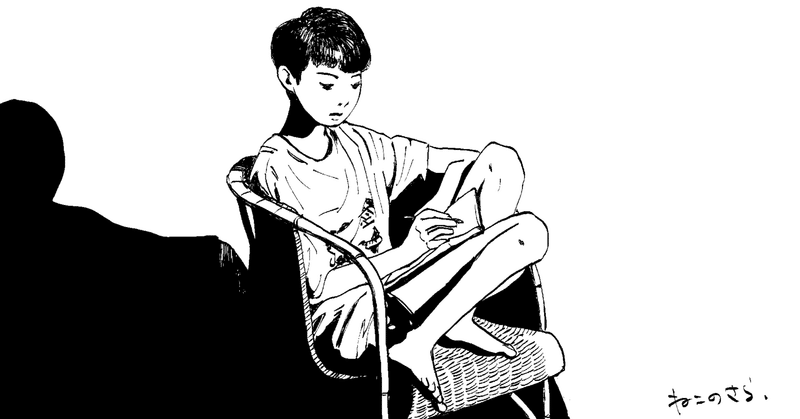
【夢日記】モノクロ世界に閉じ込められて
僕は喫茶店に居た。綺麗な内装をしていたが、店員さんらしき人は誰も居なかった。営業をしているような活気はまるで感じられなかった。もしも「喫茶店サンプルルーム」という場所が存在するのであれば、こんな装いで、こんな雰囲気を漂わせているのかもしれない。綺麗なんだけど、いやむしろ、綺麗過ぎて、どこか落ち着かない。居心地が悪い。
店内のテーブルには高校のクラスメイト達が座っていた。各々が数人のグループを形成して歓談している様子ではあったが、どの人も、生気が感じられなかった。なぜなら、彼らはモノクロだったからだ。一目見て「あぁ、今、僕の目の前に居るわけじゃないんだな」と分かるぐらいに、モノクロだった。白黒だった。過去の記憶をファインダー越しに眺めているような感覚にとらわれる自分が居た。楽しそうにしていればしているほど、居心地が悪い。
僕は人を探しているようだった。この場における「人」とは、前述した、モノクロの人ではなく、生気を感じられる人、つまり、モノクロではなく、今まさに、僕と同じ時間軸で生きている人のことを指している。
僕は喫茶店を端から端まで歩き回った。居ない。どこにも居ない。いるのはモノクロ人間だけ。それも、みんな、楽しそうにしている。やめてくれ。お前の笑顔はもう見たくない。見れば見るほど、今の自分に対する「僻(ひが)み」の念が強くなってしまう気がするから。決して戻ることの出来ぬ過去に想いを馳せるのは、もうごめんなんだ。僕は今を生きる。今を生きている人に会いたいんだ。誰でも良いから、会いたい。
ふと気付く。モノクロ人間のテーブルに、一人だけ座っている人が居る。Mだ。でも、彼女は笑っている。まるで目の前に人が居るかのように。いったい誰と話しているんだろうか・・・。
思考を巡らせようとした直後、ハッとする。Nだ。Nしか居ない。Nしか考えられない。Mの彼氏のNだ。客観的根拠とギリギリ呼べそうなものは「二人掛けのテーブル席だったから」しか無いが、僕は、Nであると確信した。
その視点で他のテーブル席を見渡すと、ポツポツと、一人だけで座っているけれども、他の人と楽しそうに話している素振りを見せる女子が居た。その光景を見た僕は、どの人も、本当は目の前に彼氏が居るのだが、僕の目には見えないようになっているのだ、と思った。まるで、僕の記憶の中で抹消したかの如くに。
Mは、高校の入学式を終えて、各々のクラスに移動した際に、思わず一目惚れしてしまった女子だった。僕は是が非でもお付き合いしたいと思って懸命にアプローチした。感触はそれほど悪くはなかった。夏休みを迎える前にはアタック(告白)出来る状態にまで持って行く。それでダメなら仕方あるまい。ベストを尽くしたならばどんな結果になったとしても受け入れる覚悟は出来ている。
そんなことを思いながらMと接していたある日。いや、ある日、ではない。忘れもしない。5月中旬の頃だ。彼女は、同じクラスの男子であるNと、交際をスタートしたのである。
Nとは、メチャクチャ仲が良い、とは言えないまでも、連絡先をお互いに知っているぐらいには、親交があった。世界史の授業中、二人で居眠りをしていて、先生に怒られて、クラスのみんなに笑われて、僕とNは顔を見合わせて笑う、というプチエピソードもあるぐらいには、仲良くしていた男子ではあった。
MがNと付き合っているという事実を知った僕は、上辺では祝福ムードに努めていたが、心の中では、まるで奈落の底に突き落とされたかのような想いになったのを、今でもハッキリと覚えている。
そのせいで、という言い方をするとMにもNにも失礼に当たるので、自分の未熟さゆえに、という言い方にしたいのだが、僕は、Mの「代わりに」、交際を迫ればOKを貰えそうだと感じたKにアタック(告白)してみて、狙い通りお付き合いをすることが出来た。
「代わりに」を強調させたのは、Kのことが好きになったから交際を迫ったのではなく、Mと付き合う未来線しか思い描いていなかったのにもかかわらず、アタック(告白)せずして失恋したような心持ちになって、居ても立っても居られなくなって、”もう付き合えるなら誰でも良い”、という自暴自棄にも似た気持ちが芽生えて、手っ取り早く恋愛が成就しそうな相手としてKを選んだ、その事実を、僕自身が一番、よくわかっているからである。いわば、懺悔(ざんげ)として、強調したのである。
長くなってしまったが、僕とMとNの関係性はそんな感じだった。ゆえに、二人掛けのテーブル席で、Mだけ座っていて、けれども、Mは楽しそうにしている、という状況を見た際に、直感的に「彼氏のNは本当は座っているけど僕の目には見えないようになっているんだ!」と悟るのも、無理はないと言えよう。
僕は反射的にMに触れようとした。頭を撫でるように触りにいったのだが、手は空を切った。薄々分かってはいたが、やはり、モノクロ人間には実体は無いようだ。分かっていたはずなのに、いざ試してみて、やっぱりそうなんだ、と知ると、急に、寂しさが増大するような心持ちになって、居た堪(たま)れなくなった。
どれだけ探してもモノクロ人間しか居ない。モノクロ人間には実体が無い。モノクロ人間はみんな笑っている。笑っていないのは僕一人だけ。もう、心身が疲れ切っていた。これ以上歩ける気力はどこにも残っていなかった。
僕は、途方に暮れるように、その場に座り込んだ。Mの目の前で座り込んだ。モノクロ人間だったとしても、Mの横顔は、やはり、とても可愛かった。何にも気にせず、誰にも邪魔されず、思う存分眺めることが出来た。それこそ、ファインダー越しに見つめるように、じっくりと、眺めることが出来た。
高校生の頃のMが僕の目の前に居る。僕はもう二十九歳だ。今年誕生日を迎えたら三十路だ。僕の記憶の中のMは高校生のままで止まっている。そう考えると、どれだけ探し歩いたとしても、モノクロ人間しか見当たらないのは、無理も無いと言えるだろう。高校時代のクラスメイトは、みんな、僕の記憶の中では、高校生のままで止まっているのだから。
僕はMをただただ眺めていた。それはまるで、高校の卒業アルバムで、Mが笑っている写真を、ひたすら眺めているかのようだった。まさに、ファインダー越しに見つめる、という表現がピッタリだなぁ、などと思っていた。
やがて、目を覚ました。
冬の朝の寒さが、いつにも増して、厳しく感じられた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
