
「誰も知らない音楽誕生の秘密」連載第1回テーマ:日本人と音楽
皆さん、お久しぶりです!寅次郎です♪
いきなりですが笑
今回から連載企画スタートです!
(前回の投稿から長い休載期間に入ってしまったのは、今回に向けて古文書などを調べ研究を続けてきたためです汗)
「この世界に如何にして音楽が誕生したのか、原始の音楽とは何か」
「”音楽”と”言語”と”音”、この世界に最初に生まれたのはどれか」
などを徐々に解き明かしていきます!
(注)全体を通して論じる内容は、私個人の見解から導き出した考察です。なるべく事実に忠実であるよう努めますが、その点をご了承ください。
はじめに
なぜ音楽研究&執筆をしているのか
まず、「なぜ音楽を自ら研究し、執筆しようと思ったのか」をご説明します。
無類の音楽好きで、兼ねてより音楽史を文献等で紐解いてきた私は、音楽が民族史・歴史・神話にいかに密接な存在か知っていくうちに、
「未だ解明されていない音楽の秘密があるのではないか」
「音楽とは(本質的な意味で)一体何なのか」
と考えるようになりました。
そこで、仮説を立て検証する作業を繰り返しながら「音楽の謎」解明にあたり、(更なる音楽の魅力を提起する意図も込めて)皆さんに発信しようと考えたのが音楽記事執筆のきっかけです。
今回の連載企画の意図
前回の記事を公開して以降、縄文人・音楽の起源に興味が湧き、古文書・論文・専門書籍などを手に取り、調査を続けてきました。
様々な民族・言語・楽器・神話・歴史に触れる中で、それぞれが一つに繋がるような不思議な感覚が芽生えました。
それと同時に、
「音・音楽・言語のうち最初に生まれたのはどれか」
という大きな謎が立ちはだかりました。
この謎を解明したいという好奇心から調査を進めた結果、”ある説”に辿り着きました。
私がどのような答えを導き出したのか、その過程を連載企画を通して読み取っていただければと思います。
また、一見関連性のないような項目が並びますが、読み進めていくうちに全て繋がっていきますので、その”繋がっていく感覚”もまた楽しんでいただければと思います♪
「ボンゴ」から生まれた謎 〜音の響きに対する探究の始まり〜

皆さんは、ボンゴという楽器をご存知でしょうか。
ラテン音楽で使用される太鼓の名前です。
始めは楽器自体を調べていたのですが、その過程で「ボンゴ」という牛科の哺乳類・「梵語(=サンスクリット語)」など同音異義語も見つけ、同じ言葉の響きで”生物”にも”言語”にもなるという事象自体に興味を持つようになりました。
『もし、言葉の響き自体が重要だとしたら・・・世界に数多くある言語の大元となる響き自体を紐解くことができるのでは・??』
そして、人間の首の後ろの中央のくぼんだところの名前が「盆の窪」。
首は言語を発する重要な箇所。その箇所にも「ボン」という言葉が付く。
今度は、「ボン」という響きに意味があるのかと調べたところ、
・多く複合語の形で用い、よい、うまい、などの意を表すフランス語の「bon」
・ドイツ西部の都市「Bonn」
・チベット古来の民族宗教である「ボン教」
※「ボン教」については後ほど詳しく触れます。
など言語・都市・宗教にまで繋がり、多国間で同じ音の響きを共有していることが「原始に存在した最古の音」への興味を強くそそりました。

そして、「ボ」という音自体に重要な意味があるのではと考え、私が思いついたのが「母」音。
まさに”母なる音”であり、実は全言語が母音中心で構成されているのは日本語とサンスクリット語だけなのです。
ここに来て、はじめに解明しようとした「ボンゴ=梵語(サンスクリット語)」とも結びつきましたね。
日本語とサンスクリット語もまた共通点が多いので、ご興味がありましたら調べてみてください♪
そして、面白いことにヒンドゥー教における聖音(宇宙の始まりの音)もまた「AUM」であり母音で構成されているのです。原始の音が母音で構成されているというのは、果たして偶然なのでしょうか。
さらに、聖音は日本語でいう阿吽と響きが重なります。
阿吽とは・・・
「サンスクリット語のア・フームa-hūmの音写。密教では、「阿」は口を開いて発音する最初の音声で、すべての字音は阿を本源とし、「吽」は口を閉じて発音する音声で、字音の終末とする。また、阿は呼気、吽は吸気であるとともに、それらは万有の始源と究極とを象徴する。
始まりにして終わりも表す音。まさに母なる音であり、日本人の文化とも密接な音と言えます。
最後に、母音に関して面白い解釈があるので、ご紹介します。
以下は、作家・井上ひさし氏の著書「自家製 文章読本」について触れたものです。
井上さんは、「ア」の音を抱擁力を持ち、すべてを受け入れる音と解釈しているが、古神道でも「ア」の音は、始まりを表す音、天を意味する言霊とされている。神道において宇宙の創造主とされる「天之御中主大神(アメノミナカヌシオオカミ)」もアから始まる。そして、人間も、頭から生まれてくるから「頭」にアの文字がついているのかもしれない。
そういえば、「愛」という語もアで始まる。ちなみに「イ」は意志や命を意味する音で、「愛(アイ)」は、天意、天の意志ということになるらしい。ひじょうに深い話である。そしてその感覚は日本人だけのものではないようだ。梵字においても「ア」は口を開けて最初に発する音であることから、万物の始源を象徴するものとされているし、ギリシャ語のアルファベットの第一文字も「A(アルファ)」だし、英語も「A」で始まり、Aは「ア」と発音する。「ア」の音が始まりを意味し、大きなものを包み込むというイメージは世界共通なのかもしれない。
単に音の響きが一致するだけではなく、意味や位置付けまで世界で共通していることがお分かりいただけたかと思います。
個人的な考察ですが、「アルファ」の反対は「オメガ」であるため、「ア」で始まり「オ」で終わること自体が母音(ア・イ・ウ・エ・オ)と考え方が共通しているようにも思えるのです。
日本人と音楽
ここから先は日本人の人体構造や言語などを分析し、更なる謎に迫っていきます。
日本人の脳・呼吸法
まずは、こちらの図をご覧ください。

こちらは東京医科歯科大学教授(当時)角田忠信氏による研究データから引用したものです。
図を見ると、西欧人は言語は左脳でそれ以外は全て右脳で処理していることがわかります。
一方で日本人は邦楽器音・感情音・鳴き声など自然界にある音全てを左脳で処理し、人工音は右脳で処理していることが分かります。
さらに、角田氏は以下のように述べています。
日本語で育った人たちの場合には、母音の持っている僅かな周波数の揺らぎに対応するようなスイッチの特性を持って育つけれども、日本人以外の人は、子音の破裂音のようなはっきりしたFM(注:周波数の変調)が加わった場合に、それを言語脳の方に振り分ける、そういうスイッチの特性を持っている。
それでは、なぜこのような違いが生じるのでしょうか。
角田氏は、母音優勢の言語を使っているかどうかが脳の左右差の原因となっ
ていると分析しています。
日本人の脳には母音に対応した特性があり、「母音」が脳の発達にまで影響を与えるのは非常に興味深い発見です。
私は、角田氏があげた理由に加え、日本人の「アニミズム信仰」にも着目したいと思います。
日本は、縄文時代より自然を崇拝するアニミズム信仰を持った民族でした。
信仰対象である”自然”や”動物”の音が重要な意味を持っていた縄文人だからこそ、言語野で理解するようになったとも考えられないでしょうか。
「アニミズム信仰」、そして「動物とコミュニケーションできる可能性」については、また改めて触れたいと思います。
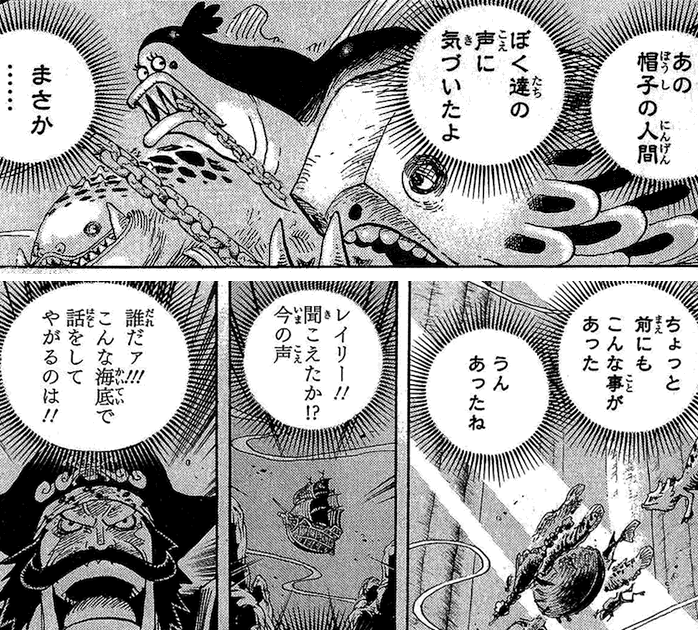
また、尺八演奏家の中村明一氏は日本人が音・倍音に敏感である点に着目し、敏感である要因として「密息」について言及しています。
密息とは、骨盤を後ろに倒し、お腹を膨らませたまま、横隔膜だけを上下させて呼吸する呼吸法のことをいいます。江戸時代までの日本人は、皆、この呼吸法を使っていたと考えられます。この呼吸法を行うことにより、身体が安定し、動きがなくなります。そしてさまざまな要素に敏感になります。そうした身体性を背景に、日本の文化が強い特殊性を持つものとなったと考えられます。
かつての日本人は皆この呼吸法をしていたということは、日本人の音楽性を紐解く上で重要であるだけでなく、この呼吸法を紐解くことで縄文人の音楽性を知ることにつながるかもしれません。
また、密息は日本の音楽自体に大きな影響を与えています。
密息を行うことで変化した身体は、外的な要素に対し、非常に感度の高い「受信機」になります。
すると、聴覚における感度が上昇します。腹式呼吸で生活している西洋では、音楽においては、音高、時間的位置、音量などの要素が主で倍音は副次的な要素と考えられてきました。いわば、音楽の構成要素に階級があったのです。リズム、旋律、ハーモニーを音楽の三要素とする考え方は、そういった中から出てきたものです。ところが、密息により「受信機」の感度が上昇し、すべての要素が差別なく受信できるようになると、階級は取り払われ、倍音などの微細な部分が立ち現れます。すべての要素が平面に並んだものとして、平等に受診されるのです。受信されるものが変われば、送信されるものも変わります。音楽も変わっていきます。このようにして成立したものが日本の音楽です。
江戸時代以前の日本人は、聴覚の感度が高くすべての音を等しく聴きとることができた、またそれによって音楽まで変貌を遂げたというのです。
母音(またはそれによる脳の発達)・姿勢・呼吸法までもが日本人独自の感性・音楽性を生み出していた事実。
『より日本(人・語)を深く研究すれば、謎も解け、音楽の起源も見えてくるかもしれない』
そう考えた私は、日本の古代史・古代言語などを紐解くことにしました。
今回は、ここまでです笑
まとめ・次回予告
いかがだったでしょうか??
音の響きを追ううちに、神話や人体の神秘にまで繋がり、日本人の謎も見えてきたと思います。
連載企画一発目で文量が論文並(前回の記事)になってしまっては読者の皆さんが疲れてしまうと考え、ここで筆をおくことにします。
まだ書きたい話・全体像の1割にも達していないので・・・苦笑
次回は、日本の古代史・古代言語、縄文人について触れていきます。
現在、鋭意研究も進めておりますので、お楽しみに!
ちなみに、「この文献・記事・サイトは参考になるかも」というものがございましたら、どうぞお気軽にコメント欄まで。情報お待ちしています!
それでは、また次回!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
