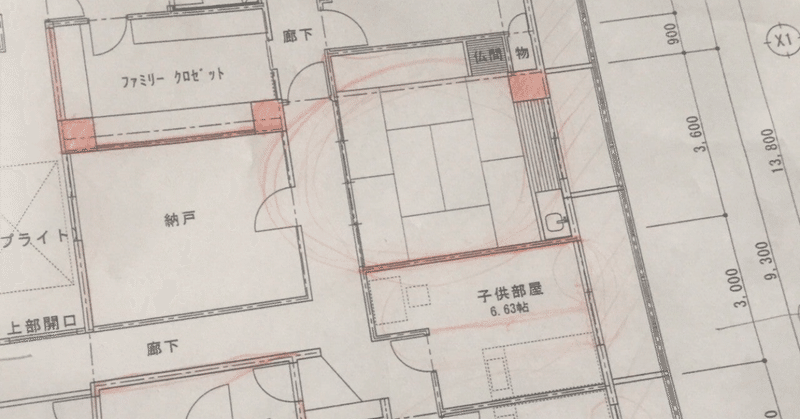
プロットは作ろう
小説やストーリーを書くときに『プロット』という用語をよく見かけます。
簡単にいえば小説作りにおける設計図ですね。
箱書きというもので、キャラクターが何をするか、どんな事件が起こるかなど、ストーリーがどう動くのかを簡単に書いていきます。
プロットを長く書く方もいれば、ほんと箇条書きぐらいしか書かれない方もおられます。
ただ作家の中にはプロットなんかいらないよ、という方もおられます。
ここは作家ごとにいろんな意見があるんです。結論からいえば、プロットは必要です。
1 プロットなしで書けるのはプロだけ
プロット否定派の方がよくいうのは、「プロットを作ると物語が予定調和でになる」みたいな意見ですね。
予定調和とはありきたりでわかりやすいということですね。ストーリーというのは意外性が肝となるので、プロットを作ってあらかじめ筋立てを決めてしまうと、その意外性が消えてしまうというわけです。
週刊漫画連載方式とでもいうんでしょうか。作家がこの先どうなるんだろうと思いながら書けば、読者もハラハラドキドキしてくれるという寸法ですね。
中にはミステリー小説で、犯人やトリックを決めずに書きながら考えるという作家さんもおられます。
この意見を鵜呑みにして、「そうだよな。俺もプロットなんかなしで書こう」となると失敗に終わります。
プロットなしで物語が破綻せずに書けるのは、プロ作家ぐらい技術があってこそなんですよね。
作家志望者の方が挑戦されるとまず失敗されるので、まずはプロット作りからはじめるのがおすすめです。
2 プロットのあるなしはジャンルによる
プロットなしでもいけるのはラノベ小説やキャラクター小説、漫画などの、キャラクターが中心のものです。
キャラクターの魅力でひっぱっていく作品は、プロットなしで書いた方がいい場合があります。
純文学もここに属するかもしれません。
ただ最近はこれ以外のジャンルはかなり構成が緻密になってきているんですよね。わかりやすい筋立てだと、読書を嗜む人にはなかなか読んでもらえない。
ミステリー以外のジャンルでもどんでん返しを使ったり、伏線回収のテクニックを使ったり、時系列をいじったりして意外性を追加します。
こういう書き方をすると、プロットは必須になります。プロット段階で綿密に計算しないと、ストーリーが破綻するんですよ。
3 プロットを書かないでいると、あらすじがうまく書けない
新人賞の公募などで原稿の他に『あらすじ』を求められます。その小説の全体の内容を短くまとめたものですね。
選考者はこのあらすじを見ながら小説の全体像を把握するんですが、このあらすじが面白いかどうかがかなり重要なんです。
あらすじが面白くないと、小説そのものも面白くないといわれています。
一次選考を通らないと悩んでいる方って、あらすじにそこまで力を入れてないんですよね。変な言い方ですが、本編の小説ぐらい丁寧に書かないとダメなんです。
あらすじを面白く書けない人の小説が面白いわけないんですよ。
で、プロットを書かない人が書くあらすじは、たいてい面白くないんです。不思議と。
さっきジャンルによってはプロットは書かないでもいけると書きましたが、プロットを書く訓練を積んでいる方が、あらすじもうまく書けます。
4 プロになってから苦労する
プロの作家になると編集者さんに、「まずプロットを見させてください」と言われることが大半です。
とくに新人作家さんはそうですね。編集者さんもプロットを見てその作品がいけるかどうかの判断や、修正箇所を指示したいんです。
でも「いや僕、プロットを書くタイプじゃないの作家じゃないんで」といきなり原稿を書いて編集者に読んでもらうと、編集者の手間は増えてしまいます。
さらにプロットを書いていれば、あらかじめその段階で修正の指示をもらえたんですが、ぶっつけで原稿にしてしまうともう直すのが大変です。
下手すれば全部ボツなんてこともあります。
そういう意味でも、プロになる前の段階でプロットを書けるようになった方がベターです。
よろしければサポートお願いします。コーヒー代に使わせていただき、コーヒーを呑みながら記事を書かせてもらいます。
