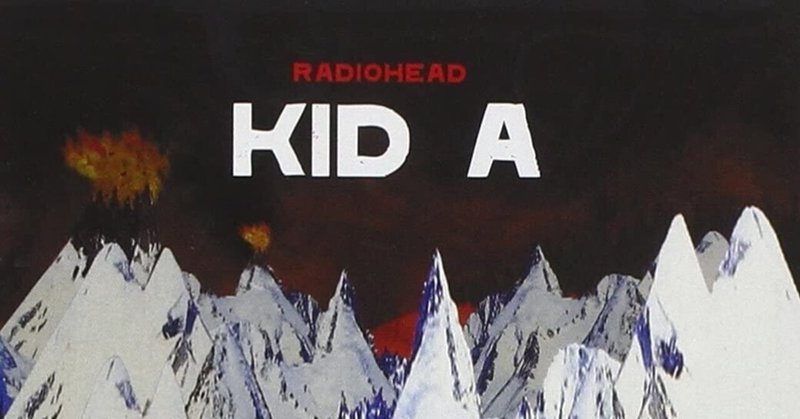
「KID A」「Amnesiac」再考:ポストロックとエレクトロニカ
昨年、「KID A」そして兄弟盤「Amnesiac」の発売から20周年を記念して2枚と未発表音源を合わせた企画盤「Kid A Mnesia」が発売されたのはご存知の通りである。トムヨークのソロ、ジョニーグリーンウッドの劇伴製作など各メンバーは精力的に活動している一方、2016年以来5年間オリジナルアルバムは発表されていないわけで、何かしら出すしか無かったのかなと勘繰りたくなるが、この2作品を改めて語る絶好の機会になったことは間違いない。
このnoteでは「KID A」「Amnesiac」に改めて触れながら(後述するが)この2枚の作品を「ポストロック」であると定義した上での魅力を改めて語る。
■KID Aについて
ロックミュージックの歴史は破壊と解体の歴史だった。あるいは如何に変容していくかの歴史だった。後に名盤カタログに載るのは過去の焼き直しを行った作品ではなく、自らのディスコグラフィーを踏襲した上で新規軸を提示した作品である。そう、Radioheadの作品はディスクガイドで選盤される量が多い。ロッキンオン社が発行した「rockin'on BEST500 DISC 1963~2007」ではツェッペリン、ビートルズに次いで4枚が選出されている。「Creep」における「ガガッ」というディストーションギターのサウンドがもたらす不穏な興奮を拡張させながら1枚に納めた「The Bends」、バンドの生々しさにデジタルの冷たい質感を付与した録音芸術「OK Computer」…と時勢を捉えつつ時代を俯瞰し、前作の流れを踏まえながら明らかな進化を見せる。
「KID A」までの3枚においては厭世的なトムの歌唱を軸にした''「演奏者」の集まりとしてのバンド形態''の持つダイナミズムを活かした作品作りにRadioheadの魅力を見出だすことが出来る。
そして2000年に発売されたのが「KID A」だった。初期の2枚でフューチャーされていた「3本のギターが織り成すアンサンブル」や「破滅的なギターソロ」は排されている。その代わりに全編を覆うのは冷たい電子音である。ダブやアンビエントを織り込みながらAphex Twin、オウテカ、当時のビョークなどに通じるエレクトロニカに分類されるのが相応しい。
日本におけるRadiohead受容の拡大の一躍を担った田中宗一郎はこの転換についてこう語る。
「キッドA」のポイントというのは、自分が一番表現したいものを自分自身の表現にのせてしまうことに対する躊躇があったということなんですよ。彼らが明確に言っていたのは「政治的なダンスアルバムを作りたい」で、それが「キッドA」のスターティング・ポイント。明確なステイトメントをそのまま伝えようとするのではなくて、自己表現ではない形で伝えたかった。なおかつダンスアルバムにしたいというのは、もう感情表現として作りたくないというのがあったんでしょうね。
田中宗一郎氏は「KID A」について自己表現の場であり主張の場でもあったロックミュージックから主体性を排除しようとする試みだったと評している。また、以下のようにも語る。
彼らの動機というのはすごく個人的なもので、マーケットに対して作品を商品として提供しないといけないことに大して嫌気が差していたと思うんです。彼らからするとオウテカのようなアーティストはそういったコネクションと関係のないところで自分たちの作品を作っている。それを自分たちが違う方法でやるにはどうしたらいいかというところから制作のスタイルもプロセスも変えたんじゃないかな。
マーケットやトレンドへの応対という要素を排除しようとした試みでもあった。そういった要素の排除は迎合を避ける動きは社会へのカウンターになりうる。とはいえ極東日本でも死ぬほどオリコン三位と売れまくったわけだが。
ここまでをまとめると、エレクトロニカの質感というアプローチは社会へのアンチズムと同時に社会からの逃避を表しいていて、時代と迎合しないレディオヘッド自身を映し出している。また、デスクトップ上で孤独と向き合い電子音の世界を作り上げていたエレクトロニカ周辺のアーティストとも共鳴するところがあった。
ただ、ただ「バンドサウンドから離れたエレクトロサウンドで『ロックバンド』というフォーマットから脱した革命的名作」と判を押すだけではこの作品を評価しきれない。一昨年から昨年にかけて、レディオヘッドはいくつかのライブ映像を公開した。その中の2001年にフランスで行われた公演の映像を見て「KID A」の見方が変わった。
この映像から分かるのはバンドサウンドで『KID A』をアウトプットする窮屈さ、そして肉体的なグルーブの伴う演奏による狂暴さや暴力性だ。パンクやレイブカルチャーに見出だせる社会への反抗的な態度をストレートに見出だせるのではないだろうか。トムも感情を昂らせながらこの世界の窮屈さに苦しむように体中を震わせ、動かしている。「冷たい電子音」とそれに相反する「熱を伴う演奏の激しさ」が共存したパフォーマンスである。
ライブ映像から得たその視点から「KID A」を再び鑑賞しよう。「The National Anthem」において楽曲全体を引っ張るベースラインは同じフレーズを繰り返しながらも同じ演奏のループではない。強弱のニュアンスは整地されておらず、指先の情動が少し歪んだ音としてストレートに伝わっていることに気づく。「Optimistic」「In Limbo」「Idioteque」は「in rainbows」などで見られたクリーントーン~クランチ、エフェクターを多用したギタープレイが主体となっていて、電子音の冷たさと共に生々しいバンドアンサンブルを味わうことが出来る。
また、「電子音の人間性を排した冷たさ」にこそ人間らしさが溢れると論じた文章があるためそれを引用する。
電子音楽やテクノロジーを恐れる必要はない。なぜならそういうものを欲望し、生み出し、用いるのはあくまでも人間であり、その限りにおいてもまた、どこまでも「人間的」である。
「破壊と解体の歴史」であるロックミュージックの文脈において冷たさを伴う電子音を取り入れた、という貪欲さも含めて人間的でロック的な熱を伴うロック的な側面を備えているのが「KID A」 と言っていいだろう。
そして上記の「バンドの熱」を伴いながらアルバムという形態にその熱を「冷たさ」を伴うアプローチで音響的に配置したもの、というと何が思い浮かぶか、私は「ポストロック」を挙げたい。
ポストロックというジャンルはかなり広く、正直「ポストロック」と呼称されるアーティストの極同士を並べたら同じジャンルと判断するのが難しい場合もあるだろう。このnoteでは「ポストロック」を「生演奏の素材を編集し、加工し、音を付け加え、配置し、アルバムという空間を作り上げた」作品指すジャンルとして定義する。
この定義に当たる、というか私のポストロック観を定義してしまったのがtortoiseであり「TNT」だ。プロツールズを用いてロックミュージックにコンピューターでの「編集」という概念を持ち込んだ名作である。1曲目の印象的なギターリフからは生楽器であるギターの弦の震えを感じる。それと共にリフ同士が接続している様子は見えず、録音されたフレーズがコラージュ的にちりばり、さらに多様な電子音やエフェクトが空間を彩る。多くのロックミュージックはドラムが作るリズムに合わせて演奏を積み重ねるが、ドラムさえアルバムを作り上げる断片として配置される。あらゆる楽器は生の響きを保持しながらあくまで素材として作品において用いられ、その編集作業の過程で独特のグルーブが新たに付与される。
「TNT」の面白い点はさらに作品自体がエレクトロニカにまで接続していることだ。「TNT」にはボーナストラックとしてジャパニーズエレクトロニカの重鎮・竹村延和による「TNT」リミックスが収録されている。stemデータを「編集」しエレクトロニカのミニマムな音像とループの快楽を供えた形にした1曲だ。ポストロックの作品である「TNT」で用いられた手法はスムーズにエレクトロニカと接続が出来ることの証左である。
エレクトロニカに連なるようなポストロック作品は多数存在していて、C'mon/Town and Country、Niun Niggung/mouse On Mars、Stereolab諸作等を挙げることができる。
同様の要素は岡田拓郎主宰・森は生きているにも存在している。彼らの音楽は岡田拓郎らメンバーの即興的・あらかじめゴールが決められていない演奏を録音しそれを軸にデスクトップ上でエフェクトの付与、加工、ミックスを行うという手法で製作されている。その編集の効果で部屋の中のように閉じているのに自然の中で鳴るようなオーガニックな響きを備えた「森は生きている」にしか存在しない音が生まれている。上記の私が思うポストロックの定義に沿った作品だ。
日本のポストロックの雄・toeにも同様の視点を向けることが出来る。日本において、ポストロックは残響レコーズの影響もあり、マスロック(テクニカルなギターや変拍子を多用した複雑ながらそれ以上の疾走感をもつジャンル)と同様のジャンルとして語られることが多い。toeも柏倉のあり得ない手数と正確さをもったドラミングや変則チューニングと高速アルペジオによるギタープレイで完全にマスロックといって差し支えないだろう。一方でフロントマン美濃はミックスエンジニアとしての一面もあり、toeの作品の完成度の高さにおけるポストプロダクションの寄与度合いは高いといえるのではないだろうか。
こうみると「KID A」がポストロックと定義されたとしても違和感は無いだろう。録音した「生」の質感がある素材に編集・加工段階で新たな色を与え、その延長線上にはエレクトロニカの質感がある。この生と死が混じり合うような歪つながら完璧なバランスこそがポストロックの魅力であり同時に「KID A」の魅力と結論付けることが出来る。
同様の要素を「Amnesiac」からも見出だせる。「KID A」のような全体を貫く統一性には欠けるが、即興演奏とポストプロダクションによるアンビエンスの生成というチャレンジをこれ以上無い形でなし得ている。むしろ「KID A」よりも楽器やスタジオ自体の響きは豊かであり先程のポストロック的魅力を強く味わえる名作と言い切れる。
以上が「KID A」「Amnesiac」の持つポストロック性である。では何故今これを論じる意味があるのか、それはこのポストロック性を構成するポストプロダクションの段階が2020年に入ってより一層の重要性を持ちはじめているように思えるからである。サムゲンデル、フローティングポインツといったアーティストは生演奏に対してポストプロダクションの段階でサイケデリック、エレクトロ、アンビエント、ダブといった質感を付与することで非常に評価の高い作品を発表した。DTMの急速な拡大とコロナウイルスの影響もありこの流れは数年続くだろう。
現状のレディオヘッドの最新作「AMoon Shaped Pool」も「KID A」「Amnesiac」の手法を受け継いでコロナにおける廃退的な世界に適した(適してしまった)作品となっている。20世紀の終わりから21世紀の始まりにかけて発表されたこの2枚が音楽史上で重要な作品だということは間違いないし、その輝き(と絶望)は未だ褪せる気配が無い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
