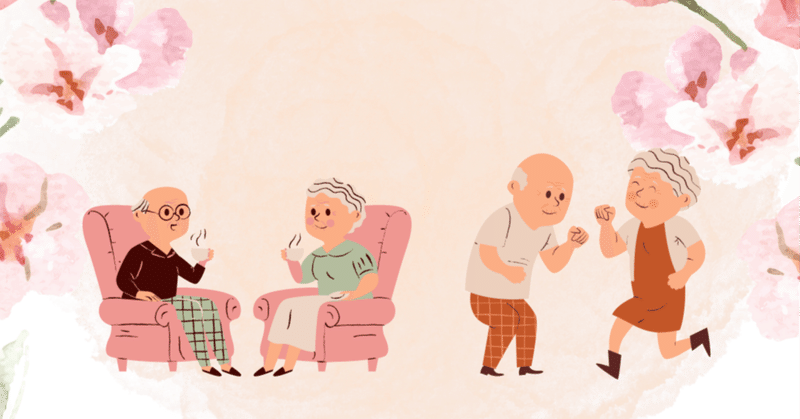
認知症は予防も回復もできるという希望
「フレイル(虚弱・身体機能が弱った状態)の時点で気づき、対策すれば回復できる」というお話は希望があるなと思ったので、2022年4月30日まで期間限定で無料公開されていた、浦和歯科医師会【市民公開講座】の「歯・口から始まる認知機能低下」(濱崎清利先生)を視聴した備忘メモと認知症と栄養についてのまとめです。
高齢の両親を見ていて気をつけていることがおおむね正しい方向だったことがわかったし、高齢の親のケアや今後の自分、子どものためにも役立つ内容の動画でした。
必要な人に届きますように。
1.爆発的に増加している認知症は、予防も回復もできる
浦和歯科医師会【市民公開講座】「歯・口から始まる認知機能低下」を視聴した備忘メモです。
日本では、認知症は爆発的に増加しているそう。2020年600万人、2025年には65歳以上の認知症患者は700万人になるそうです。
認知症は40代からアミロイドβペプチドが脳に蓄積していって、70代くらいで発症するのだそう。
「認知症は早すぎる脳の老化そのもの。薬で治るという病気ではない。個人個人スピードは違うが、誰の脳でも起きている生理的な現象。」とのこと。
認知症は、サルコペニア(身体機能障害/要支援・要介護状態)になると回復が難しいため,フレイル(虚弱・身体機能が弱った状態)の時点で気づき、対策すれば回復できるということ。
「フレイルは衰弱して介護されないと回復できない状態ではなく、自分の生活の工夫で改善が容易に期待できる状態」をいうそうです。
「高齢者フレイルと認知症の関係と栄養障害」という報告もあるため、認知症と栄養も大事な視点ということ。
脳科学的に正しい歯科治療(歯周病治療,かみ合わせ治療など)をして,脳科学的に正しい運動(口腔機能のための運動・体操)で脳血流を上げて,脳の代謝を助ける運動をして姿勢制御に結びつけると、脊椎のゆがみや矯正にもつながり,健康状態を保って生きていけることになる。
かみ合わせの治療も歯の土台が緩む年齢になっても歯科で管理を続ければ,認知症から遠ざかって生きていかれる。
良い睡眠や適切な食事,脳に良い運動,口腔疾患管理,解毒機能維持をすると,脳を若く保つことができる。
脳を若く保つ努力をすると,身体機能や内臓機能も保たれ,アンチエイジングになる。すなわち、脳を大事にすることで,老化から遠ざかる。
最近は,緩やかに老化するスローエイジングという言葉が使われている。老化を予防するという意味。
老化をゆっくり進めましょう。
濱崎清利先生は、以上のようなお話しをされていました。
2.認知症予防
【指輪っかテスト(サルコペニアチェック)】
利き足でない方の足のふくらはぎの一番太いところで輪を作る。健康な人は輪より足が太い状態。
【咀嚼と血流】
よく噛むことは消費カロリーが増え,余分な脂肪を減らすなど良い効果ばかり。
脳の血流を簡単に上げる方法は咀嚼や運動。噛むことで脳血流を上げられる(アスリートがガムを噛む)。一回噛むごとに3~4㎖の血流が脳に送られる。
脳血流を増やすと脳の代謝能力も上がるので,最終的には脳の容積維持につながる。
海馬という記憶に関する脳の部位も噛むことで血流が上がる。脳血流の低下が認知機能にも関係している。
高齢者の血流を上げることはとても大事なことなのね。
噛む行為はアスリートの研究でも見られるように,身体機能とも深く関係している。
残っている歯でしっかり噛める。合わなければ義歯を入れたり調整して,噛む能力を維持することが,認知機能低下を防止する。
【口腔体操】
口舌の動きをスムーズにする動きは、口の中で舌を左右に動かす、パタカラ、唾液腺マッサージ、リンパ腺マッサージ、早口言葉など。
口腔機能トレーニングは自律神経(交感,副交感のバランス)を整える効果がある。
口腔体操で自立神経を整えることで,免疫機能の維持が可能。コロナ予防にも重要。
【姿勢制御・体操】
脳血流を上げるのには,運動が一番簡単。
脳科学的に姿勢を維持することが血流を増やすことがわかっている。
脳をさぼらせないよう、脊椎立てて足裏をしっかり床につけて姿勢制御する。
姿勢を保つ運動は,足の感覚情報を常に脳にフィードバックして,倒れないようにする状態を作っている。それが,脳血流を上げることになる。
子どもが姿勢を保って食事をするのに,足裏をつけた方が良いのは,脳の血流を上げることに影響していることが脳科学的にわかる。
「コツを身に着ける」コツとは,正しい動きを繰り返していくこと。口腔機能を維持する動きもコツ。
正しい動きを繰り返し,コツといわれる正しい噛み方を身に着けることが重要で近道。だから体操が重要。
濱崎清利先生の「認知症バイバイ体操」[1]にはさまざまな体操が紹介されています。
バランス能力を見るには,立って横に手を上げる。水平にできないと,バランス能力が低下している。
脳科学的に正しい運動(咀嚼も含め)は脳血流を上げ,脊椎のゆがみを正し,姿勢を良くする可能性がある。フレイル予防にもつながる。
3.認知症予防に関する書籍
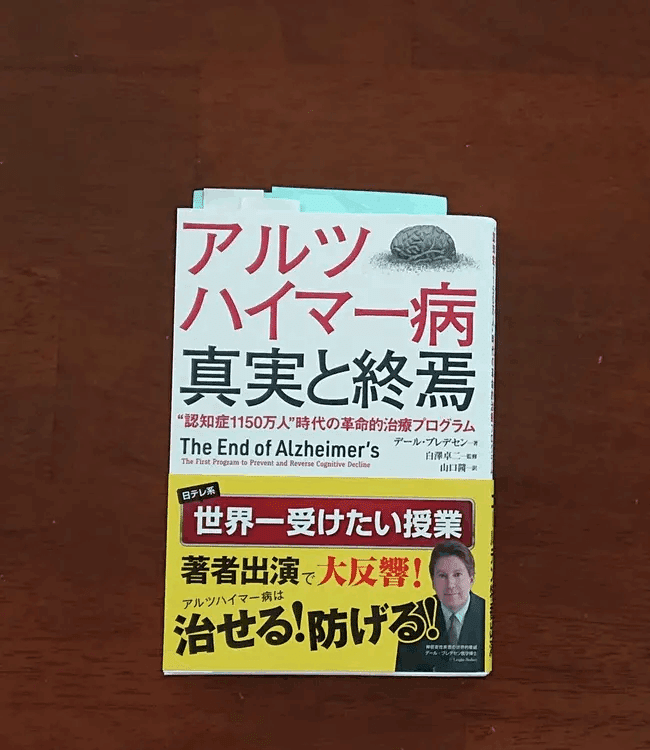
そうそう、これこれ。
買ったまま積読だった!「アルツハイマー病真実と終焉」[2]また思い出して、読み始めました。
アルツハイマー病にならないための食生活についても詳細に書かれているので、興味深い。
その他にも、認知症と食に関する書籍や運動に関する書籍もいつの間にか増えていました。うちの高齢者の認知症予防だけではなく、40代から徐々に発症すると言われる認知症だし、若年性認知症っていうのもあるから、自分自身や家族のためにも知識を入れておきたいから。

これらの書籍には、運動や食事のコツが書かれています。
やはり、脳と体と心は繋がっているし、人は食べたものでできている❣ということがよくわかる。
4.認知症と栄養
金沢大学大学院再生脳外科科長の山嶋哲盛先生は、リノール酸が多いオメガ6(サラダ油等)の摂りすぎや、油を加熱すると出るヒドロキシノネナールという毒性の物質が脳にダメージを与えると言っています。衝撃的な山嶋先生のお話はまた別の機会に書きますね。
脳は脂質60%、タンパク質40%でできているのだから、脂質が重要なのは当然ですね。
油については、様々な書籍を読むと気をつけるポイントが分かると思います。
さらに、脳はタンパク質40%だし、フレイル予防にはタンパク質なのだから、タンパク質も重要ということですよね。
白澤先生[3]によれば、小麦や乳製品、加工食品を避けることもポイントだそう。
認知にはビタミンB群(豚肉、鶏肉、鯖、カツオなど)も重要な栄養ですね。
ある認知症のお医者様は、認知症の原因は「糖」だと断言されていたとのこと付け加えておきます🥰
口から入る食べ物も、もちろん大いに認知症に関係しているというわけです。
それから、今野先生[4]認知症はビタミンD(干し椎茸やきくらげなど)も関係しているそうだから、お日様に当たることも大事!
5.血流を上げる
濱崎清利先生のお話にも出てきましたね、血流、脳血流、姿勢、運動。
どうりで、療育整体の施術をすると、アラ100の大叔母や、高齢の両親が喜ぶわけです。血流を上げ、骨軸で立つ(姿勢を整える)のが療育整体なのですから。
血流の上げ方は、簡単でお金かからず時間がかからないので、「療育整体」がお薦め。
6.まとめ
認知症予防には、口腔管理、咀嚼、姿勢、血流、脳血流、運動。そして油の選択、栄養、瞑想などがポイントのようですね。
「フレイル(虚弱・身体機能が弱った状態)の時点で気づき、対策すれば回復できる」こともポイント。
意識すれば全部、簡単に、安価に今日から、今からできることばかり🥰
人間の体って凄い力を持っているのです。
だから、体の力を信じて、諦めないで少しずつ良いと言われることをやっていきましょう。
認知症、予防したり、少しでも改善させていかれたらいいですね。
参考文献
[1]濵﨑清利(2018)『医者が発見した認知症バイバイ体操』東邦出版
[2]デール・ブレデセン著 白澤卓二監修 山口茜訳(2018)『アルツハイマー病真実と終焉』ソシム株式会社
[3]白澤卓二(2018)『Dr.白澤の アルツハイマー革命 ボケた脳がよみがえる』主婦の友社
[4]今野裕之(2018)『最新栄養医学でわかった!ボケない人の最強の食事術』青春出版社
#認知症予防 #高齢者#予防と回復#認知機能低下#口腔管理#歯・口#口腔機能トレーニング#サルコペニア#フレイル#口腔体操
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
