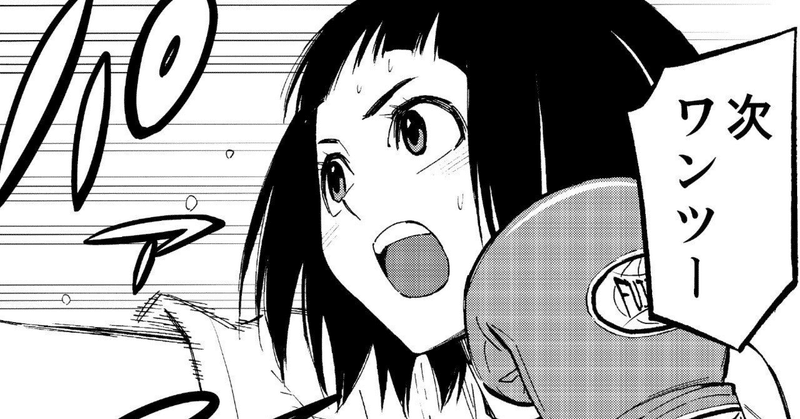
役に立つモノが涵養されていましたね
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
ここ最近、色んな人の“仕事”の話を聞かせてもらっている中で、段々と見えてきたコトがあります。
それは、
「“仕事で成果を出せる人”と“仕事で成果を出せない人”の違いがどうして出てくるのか?」
についてです。
もしかしたら、書店のビジネス書コーナーに並んでいる本を眺めていくと、これと同じようなことが書いてありそうな本を見つけることができるのかもしれませんが、僕はあまりビジネス書コーナーを眺めて歩くことはしないので実際にそういう本があるのかどうかはわかりません。ただ単純に、「こういう題名の本ありそうだなぁ」と思っただけなんですがどうなんでしょうか。
「いつもどこかで誰かが言っていそうな内容だよな」と自分でも思いつつ、最近の自分の気付きとして書いておこうと思ったので、これを読んでいる人がいたら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
ということで、見えてきたモノが一体どういうモノなのかと言えば、“観察”です。
このnoteを度々読んでくれている人だったら“頻出ワード”としてよく見かけるかもしれないこの“観察”という言葉ですが、これが出来るか出来ないかが“仕事の成果”に大きく関わってくることになりそうだというのは、まあまあ新しい話なんじゃないかと思っています(過去に書いたかどうかは、書いた本人の記憶が曖昧なので覚えておらず断言できませんが)。
じゃあ、この“観察”というものが、「一体どういう風に“仕事の成果”に繋がってくるんだろうか?」というのを考えてみようと思います。
そもそも“観察”と一言で言っていますが、“観察”って何をすることなんでしょうか?
そう問われて即答できる人が一体どれくらいいるんでしょうか。ちなみに、僕は即答できなかったので、とりあえず辞書で意味を調べてみようと思います。
観察(かんさつ)
かん‐さつ〔クワン‐〕
[名](スル)
1 物事の状態や変化を客観的に注意深く見ること。「動物の生態を―する」「―力」
2 《「かんざつ」とも》仏語。智慧によって対象を正しく見極めること。
こんな意味が出てきました。
とりあえず、<1>の意味を見ていくと、「物事の状態や変化を客観的に注意深く見ること」とあります。
「物事の状態や変化を」見るということは、例えば容器に入った氷が置いてあったとすると、その氷の状態をよく見て、更にその氷が徐々に溶けて水になっていく様をを見ていくことが、「状態や変化を見る」ということなのかもしれません。
そして更に「客観的に注意深く見る」ということは、氷が水になっていく様子を見ながら、例えば氷と水の温度を計測したり、室温を計測したり、時間を計測したり、そしてそれを自分以外の誰かとも共有できるようにそれらを全て記録しておいて後で誰でも見れるようにしておくことも「客観的に注意深く見る」ことなのかもしれません。
例えばこんな風に「容器の中の氷が溶けて水になる」ということすらも“観察”してみたとすると、色んなことの理解に繋がったり、色んな“問い”を持つことに繋がってくる可能性が出てきます。
例えば、「固まっている物(個体)はどんな物でも温度の変化で溶けていくのか?」なんて“問い”が出てくると、例えば「めちゃくちゃに硬くて色んな物に使われている鉄も温度次第で溶けるのかな?」という疑問が生まれたりするかもしれません。そうして製鉄という仕事を知ったりとか、なんてことに繋がったりする可能性も出てきます。
もちろん、観察が無くても「氷は温度変化で水になるし、水も温度次第では氷になる」という知識があるだけでも同じような“問い”に辿り着くこともあるかもしれません。こういった物質に限った話であれば。
でも、“観察”の力が大きく発揮されるのは「物質の変化」よりも「人や社会の動きや変化」を観察した時にこそ発揮されるんじゃないかと感じています。
何しろ、人は物質と違って、行動しますし話をしますしそれらによって関係性がめまぐるしく変わりますし、そもそも、その人自身が行動やコミュニケーションを経て刻一刻と変化していきます。その変化は、本当に留まることを知らず変化し続けます。
例えば、僕が朝目覚めてからの一日をずっと観察していたとしたら、世間一般の人よりも明らかにエネルギーレベルが低めですし活動量も低めであるにも関わらず、他者から客観的に見た時に目に見える活動だけでも、観察記録をつけようと思うとそれなりに大変だろうなと思います。
それに加えて、もしも、僕の頭の中で起きている思考が外からモニタリングできるような装置があったとしたら、それを記録するのは恐らくとんでもなく大変な作業だろうなと思います(そもそも、自分が考えていることの極一部をこうやってnoteに文字として書き出すだけでも大変ですから)。
そして、行動やコミュニケーションによって自分の内側に起きている思考によっても、自分自身が変化していることを実感することはよくあるわけです。特に、それが仕事に関係することについての“対話”ともなれば、それはもう変化することばかりになってきます。
主観的に“自分自身”について観察してみると、こんな風に様々な変化が見て取れるわけですが、これを外から見ていて一体どれくらいのモノを見て取れるかはわかりません。
だからこそ、“仕事”で関わる人達については“観察”しておく必要があるんじゃないかと思うんです。人はこんな風に、自分の外側の環境に身を置いたり他者と触れ合うだけで変化が起きているわけですが、それを自覚できているかどうかは全く別の話ですし、そもそも、その変化が外側から見て取れるかどうかもまた別の話です。
だから実は“観察”ってとっても難しいわけですが、そんな難しい“観察”を、日々の中でずっと繰り返し取り組んできて観察眼や観察力を鍛えて養った状態で社会に出てくる人達がいるというのが分かってきました。
それは、いわゆる“対人の競技”をやってきた人達に多くいます。
例えば、攻守が入れ替わるスポーツ(野球など)だとそこまで観察の必要性は高くなさそうですが、複数人が入り乱れて攻守が同時に行われているようなスポーツ(ラグビーやサッカーなど)だと観察は大事になってくるでしょう。
でも、特に、武道や格闘技のような“1対1で攻守が同時に行われる対人競技”をやってきた人達の観察眼や観察力は、それらの経験がない人と比べると「ちょっとした超能力」に感じるかもしれません。
でも、ちょっと考えてみると当たり前の話なんです。
何しろ、競技の特性上「相手のことをどれだけ観察できたか」によって競技の成果が左右される可能性がとっても高くなります。だから必死で相手を観察することになるわけです。そして、その観察をしながら自分も相手に観察されながら、時にはその裏をかくための行動をしながら、試合を自分の優位に進めるために動き続けるわけです。言って見れば「観察ができなければ勝つことはできない」と言えるかもしれません。
とは言え、時折、類まれなフィジカルで成果を出せてしまう人もいるので一概に「対人競技をやっていれば誰でも観察ができる」というわけでもない、ということも見えてきているところです。
そんな、“観察力を磨いてきて観察を身に付けている人”は大抵が“仕事で成果を出せる人”になっています。
なぜなら、
「この仕事の目的は何だ?この目的に求められることは何だ?これをすると相手はどういう反応をするのか?これをしないと相手はどう出てくるのか?あっちでは?こっちでは?ということは、どうすることが成果につながりやすいのか?」
なんてことを、“教えてもらったこと”や“観察して手に入れた、どうやって使ったらいいかもよくわからないような微細な情報の数々”などを、その場で組み合わせてその時その場の最適解を組み立てて試してみて、その反応をまた観察して、勝手にフィードバックを拾い集めて成果に向けて試行し続ける。
なんてことをしているんじゃないか?と思っています。
そして当然ながら、こういう観察力や思考力や試行力を身に付けているのは、武道・格闘技経験者だけではありません。
それらと同じように、もしくは、それ以上の“観察”が必要になるような何かにずっと取り組んできていた経験があれば、その経験をそのまま“仕事”に生かすことができますし、もしも、「そんな経験は全くない」としても後天的に“仕事”を通じて後から身に付けることができた人もいるのを知っています。
もちろん、観察力があろうがなかろうが、その仕事を教える側が懇切丁寧に教えてあげて、できるようになるまで関わってあげられることが一番なのは言うまでもありません。
そういった仕組とは全く別な話としての“仕事における成果を出せる人”の特徴についての話です。
もちろん、そういう経験があるからと言って必ず成果が出せるようになるかどうかはわかりませんが、その仕事をするようになる以前に、どんなことに取り組んでいて、それに取り組んでいたその“取り組み方”についての話には、とっても興味が出てきているところです。
どんなことをどんな風に考えてどういう行動をしていたのか?そして、それをやってみたらどうなったのか?
それがどんなことであれ、どんな経験であれ、そういう話を聞かせてもらうことができたら、それはきっと途轍もなく興味深い話なんじゃないかなと思っています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
