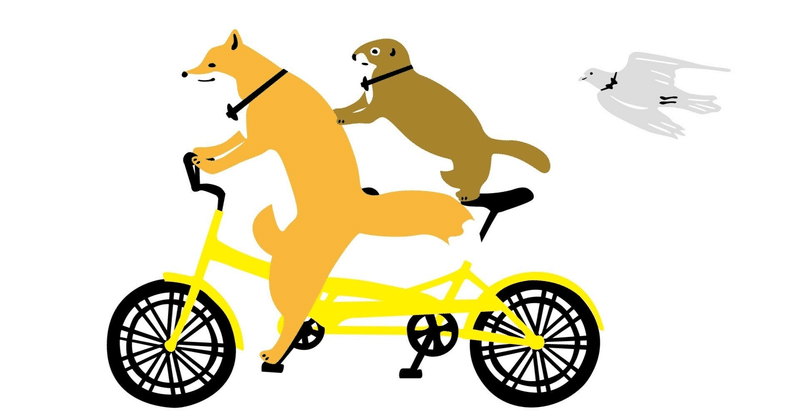
とにもかくにも楽をしたいんです
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
かの山本五十六の「やって見せ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」という有名な言葉があります。
他社の組織開発と人材開発に関わらせてもらうえで、この言葉がしょっちゅう思い返す機会があるんですが、その度に「これって本当に真理だよなぁ」と感じます。
と言うのも、様々な組織の中で「人がなかなか育たない」とか「人がなかなか定着しない」とか「人を育てるのって難しい」という声が上がっているのを見聞きするわけですが、そういうところで“人を育てるためにやっていること”を見聞きすると必ず冒頭の言葉のようには関わっていないことがハッキリしてきます。
例えば、「やって見せ させてみて 言って聞かせず誉めてもやらない」とか、「やって見せ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらずにダメ出しをする」とか、「まずとりあえずさせてみて 誉めてるつもりでダメ出しをする」なんていうのがよくあるパターンかもしれません。
“人材育成が上手くいかない現場”では「山本五十六の言っている通りに実施している」ということがありません。
逆に、“上手くいっている現場”では意識しているかどうかはわかりませんがそのほとんどが山本五十六の言っている通りになっているのがほとんどです。
とは言え、今こうして山本五十六の言葉を引用したり、これをお手本にして他者に関わることを推奨している僕自身が、過去に「人材育成が全くできていないクソ上司だった頃」には、まさに冒頭の言葉とは全て真逆のことをやっていました。
「やりもせず 言い聞かせもせず させてみて ダメ出しをして問い詰める」なんて具合に。
この時期を今振り返ってみると実際にはあまり長い期間ではありませんでしたが、その当時は毎日の仕事が全く上手く進まずに、僕と部下との関係性は日に日に悪くなっていき、その全てを「全く仕事ができない部下だな」と完全に他責にしながら、全然進まない仕事を抱えながら「地獄にいるみたいだな」と思いながら指折り“次の休日”までの日数を数えながら毎日日付が変わるのを会社の時計で眺めながら残業をしていました。
それからしばらくして、自分達の部署の仕事量が一気に増えたり、自分の部下の人数が“社命”によって一気に数倍にまで増えたりして、ようやく「ああ、これは自分が残業したところで絶対に完遂できない仕事量だな」ということがハッキリしたところから“他者に動いてもらって成果を出す方法=マネジメント”というモノの存在を知り、仲間と一緒に自分達の手で独学で学びを進めてマネジメントの実践をしながら“他者にしてほしい仕事をしてもらって成果を出す”ということが出きるようになっていきました。
その中で、冒頭の山本五十六の言葉を知り、それをそのまま実践していくと部下との関係性がスムーズになり、やって欲しい仕事の進め方で、出して欲しい成果を出してもらうことが可能になっていき、段々と自分達も残業をしないで仕事を終えられるようになり、他者はもちろんですが結果的に「自分が楽をする」ということができるようになりました。
そんな自分の経験を踏まえて思い返すと、「マネジメントというモノへの誤解というか理解不足が自分の中に確実にあった」と断言できます。と言うか、そもそも僕自身は人生で初めて部下をもって仕事をするとなった時にはマネジメントという概念も山本五十六の言葉も知りませんでした。
だから、マネジメントを実践したことも無ければその威力も知りもしませんでしたので、“上手くいかない現実”が起きている理由や原因が全くわかりませんでした。
でもマネジメントを勉強することで、自分のやっていた“上司としての振る舞い”や“仕事の仕方”が全て間違っていたということがハッキリわかりました。
そんな自分の経験もそうですし、これまでに見聞きしてきた他社で起きている他者の“上手くいかない事例”も総合すると、明確に断言できるのが、「とりあえず、山本五十六の言う通りに他者に関わっていきましょう」ということです。
本当に“人材育成”をしたいなら。
本気で「自社の社員に育ってほしい」と思うなら。
とりあえず、まずはこの言葉通りにやってみるといいんじゃないかなと思っています。
「やって見せ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」
この言葉の順番通りに、まずは“お手本”になって、実例をやって見せてあげましょう。そうすれば、本人が初めてやる時には既に「こうすればうまくいく」というイメージを持たせてあげることができて、最初の一歩の不安を軽減させてあげることに繋がります。
次に、“お手本”を詳細に解説してあげましょう。実例を見たうえで注意点などを解説してもらうことで「失敗したらどうしよう」という不安の軽減にもつながりますし、わかっている安心感によって最初の一歩を踏み出しやすくなるでしょう。詳細な解説を聞いてからだと「よし、じゃあとりあえずやってみるか」と思うことが容易になります。
そして、本人にやらせてみてあげましょう。もちろん、初めてやることだったり慣れていなかったり未熟だったりするので“上手”にできるはずがないのは前提です。問題は“完成度”や“クオリティ”ではありません。とにかくまず「やってみる」ということが大切です。“やってみた体験”の積み重ねが大事です。少ない回数やってみたからって「はい、やったんだからもう大丈夫だよね」というのは“できる人の論理”です。最初から、未熟なうちから、“できる”んであれば、そもそも誰かがついて教えてあげるなんてことは全く必要ありません。でも、「育ってほしい」と思うから“教える”という行為が発生するわけですし、それに時や手間やお金をかけるわけです。であれば、しっかり“教える”ということだけを考えていなければいけないんじゃないかなと思うんです。
最後に、誉めてあげましょう。さっきも書きましたが、まずは“完成度”や“クオリティ”では無く、「やってみた」という行動について誉めてあげましょう。「ナイスチャレンジ!」と不慣れなはずなのに、やりたくないことかもしれないのに「チャレンジした」という事実を誉めてあげましょう。そうしたら、また次に「チャレンジする」ということが本人の中に選択肢として浮かび上がってくるはずです。ここを、「やったけど、やり方がよくなかった」とか「やっただけで、クオリティがひくすぎる」とかの理由で、不慣れな人や上手くできない人がしたチャレンジに対して「ダメ出し」を“親心”かなんかだと言いながらガッチリ詰める人がたくさんいます。もちろん、これは昔の自分に対しても思っていることです。自戒を込めて。
とにかくまずはこれだけを他者に向けてやってみて、それを継続してみると、「人材育成が上手くいかない」という困りごとから解放されるのは間違いありません。
これをやれば、必ず人は動きます。
「やって見せ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」
山本五十六が言っている通りです。
恐らくいないとは思いますが、もしも「そんなの嘘だよ」と思ったとしたら、まずは山本さんの言っている言葉通りに実践してみるといいと思います。必ず、自分以外の他者も動いてくれるようになりますので。
ただ、これをそのまま実践してみると、しばらく後で、もしかしたらこんな困り事が出てくるのかもしれません。
「動いてはくれるようになったけど、なかなかクオリティが向上していかないなぁ」なんて。
そうなったら、と言うか、それよりも前からこういうこともやってみるといいのかもしれません。
それは「動いた後の適切なフィードバック」です。
これをしていくことで、段々と“基準”が出来ていきます。
何が良くて、何がダメなのか。そういう基準が段々と形成されていきます。もちろん、フィードバックをする側に明確な基準が存在していることは大事になるのは言うまでもありません。
「やって見せ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」
その後で、
「動いたらできるだけ即時に適切なフィードバックをすると人が育って欲しい成果が手に入るようになっていきます」
山本五十六の名言に、こんな一文を付け加えて実践してみると、きっと「人が育たない」という困りごとが解消されて、自分の周囲の人も、自分自身も、とっても「楽ができる」ようになっていくので、“楽をする”のが好きな人にはずっとオススメしていますし、これからもしていきたいと思っています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
