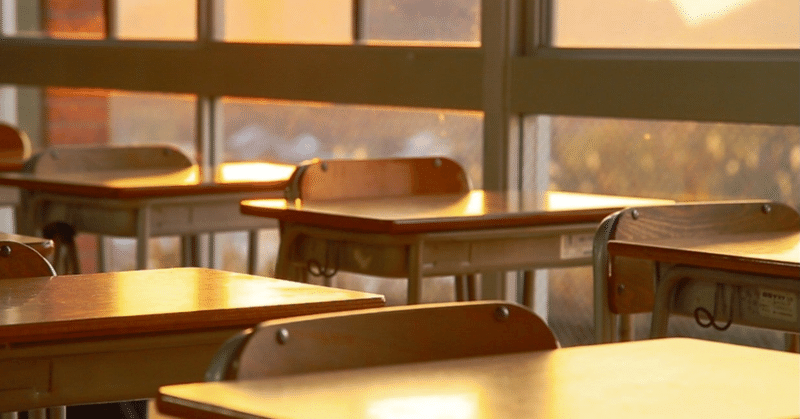
これが自分にも起きていたんだなんて
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
ここ最近、とてもよく実感するのが「学校教育の効果の凄まじさ」です。
僕自身は、長年生きてきた中で、“自分自身の事”としてそれを実感する事はほとんどありませんでした。
と言うか、むしろ、これまでの学生生活を思い返すと、僕個人の感想としては、あまり尊敬できないような先生達や教育的指導の負の側面のようなモノにとてもたくさん出会ってきたと感じているので、「学校教育への恨み言」みたいなモノを感じる事ばかりだったような気がしています。
でも、休日に子どもと一緒に遊んでいると、冒頭の「学校教育の効果の凄まじさ」を強く感じる事がたくさんあるんです。
例えば、テレビゲームの“あつ森”をしている時に、少し前までは「これ何て書いてあるの?」とか「これどういうこと?」と質問される場面がとてもたくさんあったので、僕自身がやっていないゲームにもかかわらずほぼ付きっ切りで見ていないといけないような状況でした。もちろん、児童用の本を読むにしてもそうですし、録画していたテレビ番組を見るにしても同様でした。
ただ、そんな回数が月日の進み具合と同時に、どんどん減っていっているんです。
特に顕著なのは、以前だったら“漢字”が出てきたらフリガナがふっていなければ100%「これなんて書いてあるの?」と質問されていたのが、今では読める漢字も増えてきて、しかも、読めない漢字を推測して読むという事をし始めています。さすがに、自分の中で「これはあやふやだな」と思っているような漢字は質問してきますが(恐らく、自分で推測して読んでみて意味がわからずしっくりこないモノについて質問しているようですが)、ひらがなやカタカナだけであれば「意味の分からない言葉」だけの質問になりました。
正直、この「読めない文字について質問される」というのが減ってきてくれたのは休日の僕にとっては僥倖でした。
子どもがゲームをしていたり本を読んでいる横で、自分も本を読んだりする事ができる機会がどんどん増えてきたからです。
そんな「文字を読む」という事ができるようになってきたのに併せて、今度は別の部分で「学校教育の効果の凄まじさ」を目の当たりにする事ができるようになってきました。
それは、“ルールの理解と実践”です。
文字を読んで理解する事ができるようになってきて、今度は、色んなゲームのルールを理解してそれを実践する事が出来るようになってきています。
以前は、テレビゲームをしていても“ゲームのルールや目的”を理解してやっているそぶりはありませんでした。「ただボタンを押して、それに反応する自分のキャラクターを動かすのを楽しんでいる」というだけのゲームのやり方だったので、「まあ、そういう楽しみ方ができるのもテレビゲームの醍醐味だよな」と思っていたんですが、それがいつの頃からか、段々とゲームの世界の中で目的を持って遊ぶようになってきました。
それと並行して、いわゆる“テーブルゲーム”にも興味を示し始めてきました。
僕がドラえもん好きというのもあり、ドンジャラがウチにもあったので、子どもが文字を読めるようになる前からたまに適当に牌をガチャガチャやって絵を並べて遊ぶというのをやってみたりしていましたが、それは本当に偶にやってみては直ぐに飽きてしまっていたので、年に数回出すだけのものでした。それが、最近は登場回数が増えて、しかも、一応ちゃんと“ドンジャラ”になってきています。
また、UNOも何度かやるうちにルールをしっかり把握して、今では小学校高学年や中学生の子達と一緒にUNOが楽しめるようになってきました。
そんな風に、「具体の文字」を扱えるようになる様子と、「抽象のルール」を扱えるようになる様子を、子どもを通して見る事で、「ああ成長したなあ」という感想も抱きつつ、それよりも「学校教育の効果の凄まじさ」というモノを目の当たりにする事が出来て、僕の中に長年あった「学校教育というモノへの漠然とした恨みツラミのような“ワダカマリ”」が氷塊してきているのを感じています。
自分自身もかつては、「文字も読めないしルールという概念を理解する事もできていない」という事を理解も自覚もできていなかった“小さな獣”として生きてきていたはずでした。
それが、義務教育を受けさせてもらった事によって「(自分の体感としては)とても自然に、いつの間にか」文字も読めるし漢字も読めるし概念を受け取って理解して実践できるようになっていました。かといって、それが特別な事だとも思ってもいませんでしたし、別に“それ”ができるのは他の子達と比べてもいわゆる「当たり前のこと」でした(その証拠に、僕はクラスの中でも勉強が苦手な部類だった自覚があります)。
だけど、今、自分の子どもを見ていて、文字も読めず概念の理解もできていなかった「“小さな獣”状態」から、かなりの短期間で「(学年に適正な状態で)漢字も読めるし概念を理解してゲームを楽しんでプレイする事もできる状態」になっているのを見て本当に感心しています。
「これが、“公的な学校教育”というモノの体系立てられてきたシステムの凄さなのか」と。
身近な生活の中で、学校教育に対して、まさかそんな実感を持つようになる日が来るとは想像もしていませんでした。でも、確かに間違いなく、「そこいら辺にいる普通の子どもがそこいら辺にある普通の学校に通っているだけで起きるごく普通の変化としての、学校教育というモノの効果の凄まじさ」が目の前にあるわけです。
それを実感すると、僕がこれまでの人生の中で感じてきた「学校教育へのワダカマリ」は、「自分自身に起きていた変化を、僕自身が体感することが出来なかった愚かさゆえに生じていたから起きた誤解だったのかもしれない」という反省が湧いてきています。
それと同時に、「これだけ凄まじい効果を生み出す“教育という仕組み”について大人の自分もしっかり興味を持って知っておく事は大事なんだろうな」とあらためて感じています。
そんな事を考えると、自分達の会社を「対話の会社」として位置づけたことと、「“主体的・対話的で深い学び”というモノが学習指導要領に入ってきた」という事についての関連性も、なかなか良い着眼点だったのかもしれないぞ、と(誰も言及してはくれないので)自画自賛しておこうと思いついついビールが進んでしまう休日の夜でした。おやすみなさい。。
あかね
株式会社プロタゴワークス
https://www.protagoworks.com/
#ビジネス #仕事 #群馬 #高崎 #対話 #組織開発 #人材開発 #外部メンター #主役から主人公へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
