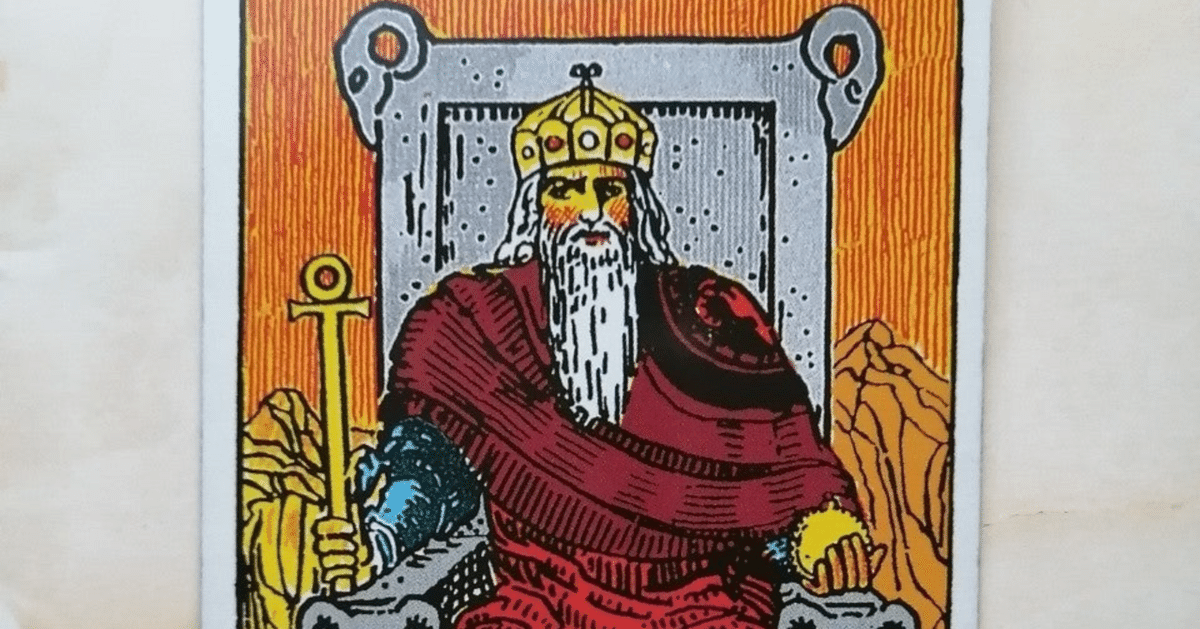
「自己組織化」的に《独裁化》を抑制する仕組みになる? (エッセイ)
今、世界で起きていることから、《独裁政権》に関わる記事を1週間にふたつ書きました。
➀ 自国の《独裁》が完了に近づいた《独裁者》は、必ず、次のステップとして、より弱い(と判断した)国を侵略する。侵略戦争を未然防止するためには、《独裁政権》の発達を抑制するしかない。
➁ 国連の仕事として、地球上の《独裁者地図》を整備し(尺度を作り、危険度を色分けして、全世界に警鐘を鳴らす)、常に作り変えていく長い取り組みが必要。
しかし、ご存じのように国連は無力です。最強の独裁者が私物化している国が常任理事を務めているのですから。
《問題点》から《課題》を抽出し、《具体的方策》を考えるのは重要でも、実行できない方策は《空論》です。
うーん、と思っていたら、今朝(2022/3/19)の新聞に《目から鱗のナルホド記事》がありました。
ESG(環境・社会・統治)投資の中で、「E」(環境)にばかり目が向きがちでしたが、ロシアのウクライナ侵略を機に「G」(統治)の重視に脚光があたっている、という記事を引用します:
大和証券の尾谷俊シニアストラテジストが主な新興国18カ国について、世界銀行が公表するESG指標を分析した。
ロシアは「汚職対応」と「法の支配」で最下位となるなどガバナンスに関する項目が特に悪かった。トルコやメキシコ、ブラジルも下位となっている。尾谷氏は「国家としてのルールが整備され、独裁体制でないことは国債などの債務返済への意識を高める」と指摘する。
ある欧州系運用会社では2014年のクリミア危機以降、ロシア国債の組み入れ比率を「アンダーウエート(弱気)」とし、ベンチマークとなる新興国債券指数の組み入れ比率よりも減らしていた。運用で参照していたESG指標ではロシアの環境の値は及第点だったが、ガバナンスの値が低くなっていたからだという。
同社の運用部長は「債務不履行(デフォルト)懸念でロシア国債が急落した運用損を抑制でき、救われた」と話す。ウクライナ危機をきっかけに投資段階から「G」を重視する動きが広がる可能性もある。
つまり、独裁政権国家の債権はリスクが高く、以前から「G」を重視していた投資会社は、今回の損失を少なくできた、というのです。
この考え方は、国債だけでなく、独裁国家に基盤を置き、独裁者と深く繋がる企業への投資にも波及するでしょう。
グレタさんらが《温室ガス排出規制》を訴えても、当初これを「非現実的」と冷ややかに見る動きがありました。
けれど、《「E」SG投資》の考え方が進むにつれて、二酸化炭素排出削減に逆行する企業への投資を止める各国の年金基金や投資会社が増え、まさに「自己組織化」的に、脱炭素の動きは世界的潮流となりました。
(こちらは今回のエネルギー危機で揺り返しもありえますが)
今回の危機を契機に、
《独裁者が牛耳る国家への投資が大きなリスクである》
ことが浸透すれば、この考え方が、経済的側面から、
《独裁の発生・成長・完成》
の各段階を「自己組織化」的に抑制できるのではないか、と期待したい。
ただ、「プーチンのロシア」を見ていると、国民の苦しみより政権の維持を最優先する《独裁者》にどこまで通用するだろう、と思わないでもありませんが……。
やはり、《独裁》途上のうちに止めなければ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
