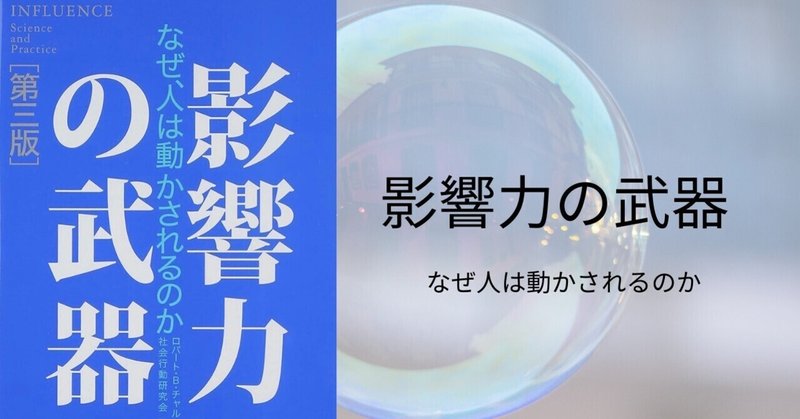
【読書】影響力の武器
取ってしまった行動について、ふとしたときに後悔したり、疑問に思ってしまうことはないでしょうか。
2点以上で20%オフだから購入したけど、あまり使っていないなぁ
Ubereats初回利用がお得だったから始めたけど、気がついたらずっと注文しているなぁ
人はどのように説得され、なぜ望まれた行動をとってしまうのかについて、心理学的側面から分析・解説した著書、「影響力の武器」を読んでみました。分厚い本で読み進めるのになかなか苦労しましたが、面白い内容でしたので、記事にしてみたいと思います。皆さまのライフスタイル変容や企業様の海外進出への一助となれば幸いです。
1. 行動を導き出す6つのアプローチ
本著書では、自身の「思わず買ってしまった」「つい寄付してしまった」などの体験を事例としてあげながら、「人を説得し、その人から望む行動を導き出すための“武器”(=アプローチ)」には、6つのパターンが存在すると説いています。
マーケティング活動により、最終的には「購買」や「成約」させることを考えることが重要です。そのための売り込み技術が必要となります。そこで力を発揮するのが、6つのアプローチです。
2. 返報性(reciprocation)
一つ目のアプローチは、「受けた恩は、返したくなる」という人間の心理に基づいたもの。つまり、他人から何かしら施しを受けたとき、人は恩義を感じ、それを返したいという気持ちを持つ傾向がある。
『施されたら、施し返す。恩返しだよ。』半沢直樹というドラマの中で、銀行員である大和田常務のセリフですね。あんなに本質的な仕事をしない人でも、返報性によって行動を導き出されています。
ある日、商業施設に入った時、時計ブランドが一輪の薔薇を無料で配っているイベントを開催していました。薔薇を受け取ると、お店まで案内され、ブランドストーリーを細かく紹介いただき、購入に至りました。これは、無料で薔薇を受け取った事による、返報性により、その後の行動を導き出され、断りにくくしていますね。
マーケティングでこのアプローチを活かすには、企業側から出し惜しみせずターゲットが求めるコンテンツを提供し、「恩義」を感じさせることが重要だと語っています。また、それが個人宛てにパーソナライズされたものであったり、相手が想定しているタイミングや情報量を上回るものであると、より深く「恩」を感じさせることができます。こちらから進んで何かを提供し、恩を感じさせるということは、それを返す何かをしなくてはいけないという気持ちにさせることであり、導きたい行動(購買や成約など)にターゲットが無意識に向かうような状況を整えてしまうのです。
サンプルの配布によって、製品・サービスに一度「無料」で触れてもらい、購入の意欲をより高める手法も、この心理を利用したものになります。
3. 希少性(scarcity)
「限られたものほど、欲しくなる」という心理を利用するというアプローチになります。“モノ”の希少性を高める方法として、個数限定、シーズン限定、地域限定などの表現方法を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。ECサイトの時間限定のセールなども、このアプローチの典型といえます。また、希少性を高める方法としては、ターゲットの“権限”を限定するという手法もあります。会員登録した人にのみ展開される特典を訴求し、プレミア感を出したり、ターゲットとの関係性を深化させるといったことです。
商品特長ではなく、提供方法によって“特別感”を演出することと、行動しなかったときに失うものを想像させることで希少性をさらに感じさせるということ。つまり、希少性が商品自体にない場合でも、どのように提供するかによってそれを生み出すことができます。
4. 権威(authority)
「肩書きや経験などの“権威”を持つ者に対して、人は信頼を置く」ことから、権威づけを活用したアプローチも人の行動に大きな力を発揮する武器です。その分野において知名度の高い組織や発言力のある人などの意見に従うのは、まさに権威を求める人々の心を刺激した結果と言えます。
このアプローチをマーケティングに活用する際に、押さえておかねばならない重要なポイントは、ターゲットにとって信頼できる「権威」とは誰なのかを中心に考えること。ターゲットが誰に憧れ、誰を信頼しているのかを正確に理解することができれば、「ターゲットにとって権威のある人物像」から推奨のコメントをもらう、プロジェクトに参画してもらうなど、力を借りた権威付けも活用することができます。
5. コミットメントと一貫性
人は誰しも約束を守ろうとする気持ちを持っている。なぜなら、社会では一貫性のある人物が評価される傾向があるため、自分が決めたことを口にしたり、書面に残したりすると、それを守ろうとする気持ちが強くなる。
マーケティングでこのアプローチを取り入れる際には、最初にコミットさせる内容は小さなアクションである方が結果につながりやすい。前述のバラがその一例でもある。この特性を活かし、よりレベルの高い内容へと移行させ、購買プロセスの中でのステップアップを図り、そして最終的に導きたいコンバージョンへとつなげていく。
6. 好意
「好きな人に同意したくなる」気持ちも、人の心を大きく動かす。仲の良い友人のおすすめ商品を購入したり、お気に入りの店員からたくさんの商品を買ってしまうなど、好意があったからその行動をとったというよう経験がある人は多いのではないだろうか。つまりは、ターゲットに「好意」を抱かせるようなアプローチも有効な影響力の武器。
人が好意を抱く理由には「自分に似ている」「自分を褒めてくれる」「同じゴールを目指す仲間である」という3つがあるという。これら3つのポイントは、コンテンツの中でも特にSNS上で展開されるものにおいて非常に重要な要素だという。なぜなら、インターネットの発展により、ターゲットがさまざまなプラットフォームで人や企業とつながりを持ち、能動的に「共感する」「好きになる」場が拡大しているからだ。つまり、“人と人”だけでなく、“人と企業”の間においても「好感」や「共感」を表明できる場が増えている。そのような状況で先ほど述べた3つのポイントを押さえた“好ましい”コンテンツを提供することができれば、ターゲットとポジティブな関係を構築することができるだろう。
7. 社会的証明
「周囲の動きに同調したくなる気持ち」も、実は人の行動を大きく左右する要素だ。たとえば、街頭で多くの人が空を見上げていたら、その場に遭遇した人のほとんどは同じように空を見上げます。これは「みんながやっているからには何か理由や価値があるに違いない」という心理が働き、他者の行為を自分の行為に反映させる傾向があるためである。この心理を突いたアプローチが、社会的証明という影響力だ。
マーケティングにおいても頻繁にこのアプローチは活用されている。「売上No.1」を謳う、ユーザーの体験談を紹介する、などがその一例だ。この心理は一般消費者だけではなく、BtoBマーケティングにおいても活用が可能だ。例えば、どのような企業をクライアントに持つのかを公表することで、多くの企業と取引しているということをアピールし、信頼性やサービスの安定感を創出することができる。多くの人から支持されていることを強調することは、社会的に信頼できるという安心感を生みだすのだ。
8. まとめ
七面鳥の母鳥はひな鳥のピーピーという鳴き声によって、母親らしい反応を見せます。天敵であるイタチの剥製から発せられても等しく母親らしい反応を見せるのです。これは人間にも同様に固定動作パターンがあって、行動の多くはトリガーによって導き出されています。
これを機会に自分の行動や考え方を振り返る時間を持つと、この激動の時代を生き抜くヒントが生まれるかもしれません。
・返報性
他者から何らかの恩恵を受けたら、そのお返しをせずにはいられなくなる。
無料試供品の配布
無料で使ったんだから、注文しなくちゃ悪い
・コミットメントと一貫性
一度決定を下すと、そのコミットメントと一貫した行動を取り、自らの決定を正当化しようとする。
日常生活において、一貫している事は望ましいとされる。
考えている事や行っている事と、実際の行動が一致しない人は裏表のある人だと疑われてしまうからである。
立場に一貫性を持つことで、思考をするエネルギーをセーブしている。
・社会的証明
「他人が何を正しいと考えているか」に基づいて、物事の成否を判断する。
特定の行動をする人が多いと、それが正しいとみなす。
入場制限をして、長蛇の列を作り店のブランディングを図る。
・好意
自分が好意を感じている人からの頼み事は受け入れる傾向にある。
外見のよさが才能、誠実さ、知性を持っていると自動的に考えてしまう傾向がある。
好意を生み出す最も影響力のあるものは「類似性」である。
服装、経歴、趣味、年齢、宗教、喫煙の習慣などがこの類似性に当てはまる。
・権威
権威者に命令されると、それに従う事が自分の利益になると重い、自動的に行動する。
考慮する必要が無いからである。
肩書き、服装、高価な装飾品が例。
・希少性
手に入りにくくなると、その機会がより貴重なものであると考える。
数量限定の戦術。
時間制限を設けて買う決心を促す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
