
共感の可能性【本:経済学は人びとを幸福にできるか】
感動と知的な衝動。この本を読んで思った。経済学は、これほどまでに広かったのか、ということ。合理的に、正解のある答えをもとめる数値結果だけではなかった。ある限られた知識人だけの専門領域ではなく、皆、それぞれ「幸福」を考えながら、それぞれの時代を生きていたんだな、と俯瞰することもあった。でも、何よりも、この「広い」のは、経済学が、というよりも、宇沢弘文氏の知的好奇心の広さと深さによるものなんだろうなと思う。アダム・スミスが『道徳感情論』を書きあげてから、およそ20年の歳月を経て1776年に『国富論』が出版された。この2冊で、大方、この世界を生きる人々が求めている「コタエ」があるような気がするのと同時に、アダム・スミス自身が人生をかけて、その知的好奇心や人間の苦悩、生き様、発展などを考え抜き、20年という歳月をかけて書き出したものを想うと、数年という歳月がとても尊く感じる。そして、スミスの『国富論』に始まる古典派経済学の本質を極めて明快に解き明かしたのが、1848年に刊行されたジョン・スチュアート・ミルの『経済学原理』(Principles of Political Economy)。国富論から約70年後のこと。で、この本で、まさか「竹」や「スリランカの農業」、「町づくり」「建築」に出会うとは。スリランカの話については、また別のnoteでも書こうと思う。
「経済学は貧しい者のためにある」

シカゴ大学は、90人近いノーベル賞受賞者を出している一方、マンハッタン計画やベトナム戦争で使用された枯葉剤の開発にも深く関わっている。宇沢氏が在籍した1960年代のシカゴ大学は、ミルトン・フリードマン率いる新自由主義者の牙城だった。宇沢氏が、市場原理主義を厳しく批判し、その理論の限界を指摘するのは、このときの経験があったから。
フリードマン流の市場原理主義に辟易し、ベトナム戦争に反対することで、アメリカを去り、日本へ戻る。日本へ戻ると、自動車事故や大気汚染など人々が安心して暮らすことのできない環境にあることに気づく。
そこで、宇沢氏は、「現代の貧困」を解決するための研究を新たに開始。「社会的共通資本」こそが大切なのだということに気づく。
世界各地で「環境難民」が続出する。南アジアのバングラデッシュは深刻。1991年に同国を襲ったサイクロンでは、実に国土の3分の1が海面下に水没し、数百人が住民を失い、20万人の死者が出た。
経済学をいかした「大気安定化国際基金」
炭素税を発展させたもので、発展途上国の国の一人当たりの国民所得に比例させることが考えられる。各国政府は、比例的炭素税の収入から育林に対する補助金を差し引き、残りの額のうちの一定割合(たとえば10%)を大気安定化国際基金に拠出。そうして集まった資金を開発途上国に配分。
宇沢氏の問題意識であり、研究テーマ
「社会的共通資本がうまく機能するためには、どうしたらいいか」
例えば、農業にコモンズを
日本の豊かな自然を守るためには、日本の農業を再建・維持・発展しなければならない。これまでの日本の農政は、農業を資本主義的な産業として捉え、農業に従事する人々を経済人とみなし、効率性のみを追うという方法をとってきた。それではいけない。コモンズのような共同体を農村に復活させ、人間的な営みを作り出さなければならない
数学は、論理だけで成り立つ学問。しかし、人間社会は、論理の美しさで解決できるものではない。
宇沢氏の知的探求の軌跡をたどると、結局は、経済学の道に入るきっかけになった『貧乏物語』の問題意識に戻ってきた。貧困に怒り、貧困を解決しようとする。そこには論理が必要。
経済学者に必要なのは、cool head and warm heart冷静な頭脳と温かい心。
市場原理主義:Market Fundamentalism/ Neoliberalism
デヴィッド・ハーヴェイ:2005年にA Brief History of Neoliberalism
Libertarianism:自由主義、人間が人間らしく生きて魂の自立を守り市民的な権利を充分に享受できるような世界を求めて、社会的、政治的な運動に携わる。人間の心。
リベラルアーツ:専門を問わないで、人類が残してきた遺産、それは芸術でも、学問でも、技術でも何でもいい。専門分野をいっさい問わないで、ただひたすら学んで、吸収して、一人ひとりの生徒の人間的な成長をはかり、同時に次の世代に伝えるところである
シカゴ大学は当時、経済学の研究のメッカだった。アメリカの大恐慌の後、いわゆる新自由主義的な、新古典派的な経済政策が破綻して、新しいケインズ的な経済政策の原理が確立していく。それが結局1960年代のベトナム戦争を契機として崩壊していく。
マーケットというのは、将来のことも、また他の人がどういう行動をとるかもわからない。そこでマーケットという場で均衡点を見出そうとする。トリクルダウン理論:金持ちに恩恵を施すと、雫の落ちる如く貧しい人にもしたたり落ちる(trickle down)と。だから、まず減税は金持ちからやるというのが市場原理主義の主張。今回のサブプライム金融恐慌の原因の一つであるブッシュ政権の減税政策は、このトリクルダウン理論を適用したものだった。
究極の市場原理主義:
エントホーフェンDeath Ratioという概念を導入。これは、一人の患者が死ぬまでの年々の医療費を最小にしようという医療費抑制政策。とくに60歳以上の老人に焦点を当てた。エントホーフェンは、ベトナム戦争時45歳くらいで、マクナマラ国防長官の信任を得て、国防次官に任命されて、ベトナム戦争の実質的な責任者になった人物。その彼が使ったのがkill-ratio。殺戮比率、ベトコン1人を殺すのに何万ドルかかるかで戦略、戦術を考えるというもので、kill-ratioをできるだけ低く抑えるような作戦を各部署で実行に移す。つまり、限られた戦争予算のもとで、できるだけ多くのベトコンを殺すと言うのをベトナム戦争遂行の目的に揚げた。これをニューヨークタイムズの記者がすっぱ抜いて、世界中からごうごうたる非難が沸き起こった。マクナマラ長官は、追い詰められ、カナダで演説しているときに突然、今度のベトナム戦争はアメリカ史上最悪のことだ、倫理の崩壊、アメリカの名誉はここで地に落ちたという「名演説」をして、辞任においつめられた。
ハルバースタムは『ベトナムの泥沼から』(The Making of a Quagmire)という書物を1960年代半ばに出してベトナム戦争に非常に大きな影響を与え、その後『ベスト&ブライテスト』(The Best and the Brightest)という歴史的な本を書いた人。
昭和天皇の言葉。
「君!君は、経済、経済、というけど、人間の心が大事だと言いたいのだね」
経済学の基本的な考え方はもともと、経済を人間の心から切り離して、経済現象の間に存在する経済の鉄則、その運動法則を求めるものであった。経済学に人間の心を持ち込むことはいわば、タブーとされていた。私はその点について多少欺瞞的なかたちで曖昧にしていた。この私がいちばん心を悩ましていた問題に対して、昭和天皇の言葉は、私にとってコペルニクス的転回ともいうべき一つの大きな転機を意味していた。
ヨハネ・パウロ二世からの手紙に対して、私は「社会主義の弊害と資本主義の幻想(Abuses of Socialism and Illusions of Capitalism)」こそ、新しいレールム・ノヴァルムの主題にふさわしいというお返事を差し上げた。そして、21世紀への展望を考えるとき、制度主義の考え方こそ人類が直面する問題を解決するための重要な概念で、それは、資本主義とか社会主義という、経済学のこれまでの考え方では決して解決できない。地球環境、医療、教育を中心とする社会的共通資本の問題をもっと大切に考えて、一人ひとりの人間が人間的尊厳を守り、魂の自立をはかり、市民的自由を最大限に発揮できるような安定的な社会を求めて、私達は強力しなければならないことを強調した。
社会主義のもとで、人々の自由は失われ、市民の基本的権利は完全に無視されて、多くの人々は苦しみを味わい続けてきた。しかし、容易に資本主義に移行しても、問題は決して解決されない。ヨハネ・パウロ2世はさらに、社会主義と資本主義とを問わず、過去半世紀にわたる経済発展の結果、自然環境の破壊が地球的規模にまで拡大化されてきたことを深く憂慮されて、私達経済学者に対してつぎのような設問を投げかけられたのである。それは、資本主義と社会主義という2つの経済体制を超えて、すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できるような経済体制は、どのような特質を持ち、どのようにすれば具現化できるのか、という問題提起である。
学問的能力にすぐれ、社会的正義感のつよい学生ほどベトナム反戦運動に深くかかわって、その多くの人々は、大学を去って、経済学の研究者になることを断念するか、あるいはアメリカで生きること自体を否定せざるを得ないような状況に追い込まれていった。
すぐれた分析的能力と洞察力と謙虚な人柄。すぐれた才能をもち、するどい社会正義の感覚をもっていた経済学の学生の多くがベトナム反戦運動に関わって、姿を消してしまった。人間的魅力にあふれた数多くの学生たちが、ベトナム戦争の奔流に巻き込まれて、悲惨な人生をおくり、なかには、若くして、この世を去ってしまった人も少なくない。
上田秋成『雨月物語』
アメリカがベトナム戦争の泥沼に落ち込んで、史上最悪の暴虐行為をおこないつつあったとき、学生が救いを求めた書物は、大江健三郎の『ヒロシマ・ノート』の他にもう一つあった。それはトールキンの『ホビットの冒険』である。
エドワード・ギボン
1764年、27歳のギボンは、2年間の予定で大陸旅行に出かけた。当時、大陸旅行はリベラル・アーツの教育の重要なコースで、いうまでもなくイタリアが中心であった。
ギボンの『ローマ帝国衰亡史』は、歴史を社会科学の重要な分野として位置づけた歴史的な書物。同じ年1776年には経済学を社会科学の重要な分野として位置づけたアダム・スミスの『国富論』(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) が出版。この2冊の書物の生成には、偉大な哲学者、歴史家、そして経済学者でもあったデヴィッド・ヒュームがふかく関わっていたのであって、たんなる歴史的偶然の産物ではない。
ベトナム戦争に始まるアメリカ帝国の非人道的、非倫理的な行動を考えるとき、ローマ帝国の末期とあまりにも類似点が多かった。
「僭見」なき日本の官僚
日本の官僚は、官庁という政治的な組織の中で、その組織にどれだけ貢献できるか、そして自分がその中でいかにうまく生きていくか、という点だけにしか行動規範をもたないようにすら思える。彼らには「思いあがり」はあっても、思想と、信条とか、人間性の深みというものが欠けているように思う。こうした高級官僚を生んだのは、東京大学をはじめとするいわゆるエリート大学である。また、これらの大学の学者が、さまざまな審議会の座長を務め、官僚機構の意思を具現化する役割を果たしている。大学の独立性とか、学者としてのプライド、あるいはディシプリンと矛盾することが多いのではないか。
1997年「論争東洋経済」
私はもう20年以上も前から日本の官僚に幻想を抱かなくなった。ちょうど共通一次試験を受けて大学に入学した人たちが、官僚になり始めたころである。彼らは、生きる姿勢も低いし、社会正義に対する意識もない。能力的にもかなり劣っていて、ただ点数を取れば、試験に受かればいい、とする人たちのように思えた。
一人ひとりの研究者、学生の魂の自立、願望、職業的プライドをまったく無視して、行政的な辻褄だけを合わせようとする文部官僚の本質を垣間見た思い。
私は、数学から経済学に転じた。そのとき、私はある悲愴な決意をした。一切の人間的絆を断ち切って、経済学研究のために、一生を捧げるという、いまから振り返るといささか面映ゆい決意を固めた。
ケインズ『一般理論』:現在資本主義制度のもとにおける資源配分は必ずしも効果的ではなく、またそのときの所得分配は公正なものではない。経済循環のメカニズムもまた安定的ではない。現代資本主義が安定的に調和のとれた形で運営されるために、政府がさまざまな形で経済の分野に関与しなければならない。ケインズがその一生をかけて研究していったのは、理性的な財政政策と合理的な金融制度に基づいて、完全雇用と所得分配の平等化を実現することが可能であるという、すぐれて理性的な立場であった。この理性主義的な考え方が、たんなる幻想に終わるものではなく、経済的、社会的、財政的制度の進化の法則に適合するものであって、網の目のように張り巡らされた既得権益の構造のなかに埋没されるものであってはならないというのがケインズの信条でもあった。
ケネディ大統領によってはじめられたベトナム戦争。その当時、私はシカゴ大学にいた。史上最強の軍隊をもったアメリカが、その全軍事力を投入して、アジアの一小国ベトナムに対して、社会正義に反して侵略戦争を展開したのがベトナム戦争だった。アメリカ軍がベトナムでおこなった大量殺人、残虐行為、自然と社会の徹底した破壊もまた、史上最大の規模をもつものであり、この残虐行為に対して、良心のあるアメリカの人々は憤激し、全米のいたるところではげしい反戦運動が展開された。アメリカ社会はずたずたに分断され、南北戦争以来の社会的混乱と政治的分裂を経験することになった。
ミルトン・フリーダム『資本主義と自由』(Capitalism and Freedom)
教育は、人間が人間として生きてゆくということをもっとも鮮明にあらわす行為である。学校教育の本質について深い洞察をもって、するどい分析を展開したのがジョン・デューイであった。デューイの教育理論はリベラリズムの思想にもとづいて展開された。つまり、それは、人間的尊厳を守り、市民的権利を最大限に確保するような社会的、経済的条件を求めて、ユートピア的運動なり、学問的発展をはかろうとすることを意味していた。
デューイが学校教育の果たす第一の機能として取り上げているのは、社会的統合である。子どもたちが、各自の育った狭い家庭的、地域的環境を超えて、多様な文化的、民族的、社会的背景をもった子どもたちと、学校でともに学び、遊ぶことによって、お互いに人間的共感をもち、社会的存在としての意識を育てるのが、学校教育の果たす重要な機能であるとデューイは考えた。第二の機能は、平等にかかわるものである。子どもたちの一人ひとりが、その経済的、地域的、社会的集団の枠を越えて、学校教育を享受することができるようにすることに、デューイは注目した。第三の機能は、子どもたちの知性、精神的、道徳的な発達をうながすという点であった。学校教育を通じてこれらの潜在的能力を充分に発達させることが可能になってくるとデューイは主張したのである。
日本の教育体制として、新しい学校教育制度が具現化される過程で、文部省は、国による財政的負担を奇貨として、極めて中央集権的なかたちで、基礎教育制度を運営してきた。教育委員会は、国という官僚機構の下部組織として末端に位置づけられ、小中学校の校長は、そのまた下に置かれた下級官僚となってしまった。小中学校の教師は、教育サービスを売る労働者となり、聖職としての教師の職業的規範も誇りも失わざるを得なくなってしまった。文部省はまた、教科書検定制度を悪用して、自民党のもっていた、時代錯誤の、偏向したイデオロギーを基礎教育に持ち込んだ。日本社会は現在、経済的、技術的観点からみて、世界でもっとも高い水準を誇っているが、その反面、知性の欠如、道徳的撤廃、感性の低俗さという面で、おそらく日本に比較できる国は少ないのではないかと思われる。その、もっとも大きな原因は、戦後50年間にわたって、日本の基礎教育が文部官僚によって管理、支配されてきたことにあるといっても過言ではないだろう。文部官僚はまた、陰湿な、抑圧的性向をもって知られている。日本の基礎教育制度の欠如を象徴する「いじめ」の現象の原点は、文部官僚による学校関係者に対する「いじめ」にあるといってもよい。
経済学部における経済学教育のもっとも大きな問題点は、カリキュラムの過密にあるように思われる。このため、学生が講義で学んだことについて、充分に時間をかけて、復習したり、関連する書物、文献を読んだり、また友人と議論をする時間的余裕がほとんどない。できるかぎり少人数のセクションに分けて、演習方法をできるだけ取り入れ、学生が経済理論の基礎を実践的に理解できるようにすべきである。そのためにはどうしても大学院生がティーチング・アシスタントとして学生の指導に当たることが必要になってくる。
超過密カリキュラムを強いられる学生
共通一次試験ほど非人間的で野蛮な制度はないと思う。とくにコンピューターを使って採点するため、試験問題の性格も限られてしまって、どうしても浅薄な記憶だけに頼る「くさった」問題が中心となってしまう。そのうえ、受験生は鉛筆で小さなところをつぶす訓練を受けなければならない。
ビールを飲みに行く心のゆとり
リベラルな雰囲気をもつアメリカの大学では、大学人が何ら外的な規則や不文律にとらわれることなく、自らの倫理的規範と職業的性向にしたがって、自由に、生き生きと行動することができた。
アダム・スミスの『道徳的感情論』は経済学の原点をみる思い
ハチスン、ヒュームの思想を敷衍して、共感(sympathy)という概念を導入し、人間性の社会的本質を明らかにしようとしたのであった。人間性のもっとも基本的な表現は、人々が生き、喜び、悲しむというすぐれて人間的な感情であって、この人間的な感情を素直に、自由に表現することができるような社会が新しい市民社会の基本原理でなければならないと考えた。「共感の可能性」を持っているということが人間的感情の特質であって、人間存在の社会性を表現する。その20年前に書かれた『道徳感情論』には、Nation (一つの国の国土と、そのなかに住んで、生活している人々の総体を指すもの) という言葉には、統治機構を意味する State (国家) とは異なる、ときとしては対立的な概念を指すものであることは留意する必要があるとする思想的原点がある。
ベトナム戦争が終わってもう30年近く経つが、ベトナム戦争によって受けたアメリカ社会の傷は深く、いまなお重いものが残っている。大学周辺の雰囲気もすっかり変わってしまい、今は殺伐として、非人間的なものになってしまった。
シカゴ大学に招いたジョーセフ・スティグリッツは2001年にノーベル経済学賞を受賞。2003年4月、私は同志社大学に新設された社会的共通資本研究センターの所長に任命された。その際、スティグリッツを中心として、社会的共通資本研究センターの設立に賛同し、センターの運営に積極的に関わってくださることに。同志社大学の創立者新島襄はアマースト・カレッジの卒業生であり、新島襄はアマースト・カレッジを一つの規範として同志社大学を創立したといわれているが、たまたま、スティグリッツもアマースト・カレッジの卒業生だった。このセンターには「竹の高度利用に関する応用工学研究」という部門があり、この同志社大学の工学部がある京田辺は、トマス・エディソンがつくった最初の電球には八幡の竹林からとった竹である。
竹の高度利用
地球資源の有限性と大気中のCO2の増加に目を向けるとき、化石資源から再生産可能な天然資源への転換を図ることは極めて重要な意味をもつ。再生産可能な天然資源のなかで中心的な役割を果たすのは森林であるが、森林の再生産期間は一般に長く、現在の木材の消費量の下で、世界的な規模で森林破壊が進みつつある。しかもその最終処分として焼却されるとき、大量のCO2が排出される。これに反して、竹は、その再生産期間が極めて短く、また多様な構造的特質をもち、その工業的利用の可能性も大きい、わが国で唯一の持続可能再生産可能な天然資源といってもよい。しかし、竹の工業的利用は極めて限定的であり、また、その有効利用と潜在的機能に関する研究も充分におこなわれていない。竹は東南アジアに広く自生する熱帯性植物であるが、その他の地域には、中南米の一部とアフリカのごく一部を除いては、自生していない、極めてアジア的な植物である。わが国でも、東北の一部、北海道を除いて、全国的に幅広く分布する。わが国の代表的な竹である孟宗竹や真竹は長さ10~15メートル、直径15センチメートル以上、1本の重量は40キロを超えるが、成竹までに1ヵ年を要しない。また、竹は、一平方メートル当たり5~15本も密生して生育する。
竹は、昔から、強くて、軽い材料として、土壁の保護骨、天井材など、日本家屋の建築材料として用いられてきた。現在でも、東南アジアの国々では、建築用の足場パイプなどの構造部材として用いられている。竹の強くて、軽いという特質は、竹の中空構造に加え、極めて特徴的なミクロ構造による。竹の長手方向に貫く維管束鞘は3~5本の竹繊維束と導管、師管から構成されているが、竹繊維は比強度が高く、「天然のガラス繊維」と呼ばれている。竹の繊維を、かつ効率的に取り出すことができれば、ガラス繊維やその他の石油合成系繊維の代替になり得る。また、維管束鞘を取り巻く木質部の主成分はリグニンであり、新たな利用が模索されている。竹のもつ強い抗菌機能の有効利用のための技術開発や、その他の生態保全物質の探求が望まれている。
イワン・イリッチ「脱学校の社会」
学校教育に対する公的な支出の増大が必然的に社会的な差別を形成し、分極化を促進し、学校のもつ破壊性が強化されると主張する。
「価値の制度化をおし進めていけば必ず物質的な環境汚染、社会の分極化、および人々の心理的不能化をもたらす、そして非物質的な要求が物質的なものへの需要に変質させられるならば、この破壊の過程がいかに促進されるか」
イリッチは、人々の基本的欲求が社会的な制度のなかに組み込まれていったとき、必然的に環境汚染、社会の分極化、心理的不能化をもたらすという現象を、教育、交通、医療についてみたのであるが、このイリッチ的な現象はたんにこの3つの分野だけでなく、われわれの生活のあらゆる面にわたってみられ、社会的不安定性を加速度的に高めている。
共同体の形成論理
スミスの『道徳的感情論』は、ハチスン、ヒュームの思想を敷衍(ふえん)して、共感(sympathy)という概念を導入し、人間性の社会的本質を明らかにしようとしたものだった。しかし、このような市民社会を形成し、維持するためには、経済的な面である程度ゆたかになっていなければならない。健康で文化的な生活を営むことが可能になるような物質的生産の基盤がつくられていなければならないとスミスは考えて、それから20年の歳月を費やして、『国富論』を書きあげた。
持続的発展(Sustainable Development)
スミスの『国富論』に始まる古典派経済学の本質を極めて明快に解き明かしたのが、1848年に刊行されたジョン・スチュアート・ミルの『経済学原理』(Principles of Political Economy)。その結論的な章の一つに定常状態(Stationary State)という章がある。ミルのいう定常状態とは、マクロ的に見たとき、すべての変数は一定で、時間を通じて不変に保たれるが、ひとたび社会のなかに入ってみたとき、そこには、華やかな人間的活動が展開され、スミスの『道徳感情論』に描かれているような人間的な営みが繰り広げられている。新しい製品がつぎからつぎに創り出され、文化的活動が活発におこなわれながら、すべての市民の人間的尊厳が保たれ、その魂の自立が保たれ、市民的権利が最大限に保障されているような社会が持続的(sustainable)に維持されている。このようなユートピア的な定常状態を古典派経済学は分析の対象としたのだとミルは考えた。
国民所得、消費、投資、物価水準などというマクロ的諸変数が一定に保たれながら、ミクロ的にみたとき、華やかな人間的活動が展開されているというミルの定常状態は果たして、現実に実現可能であろうか。この設問に答えたのが、ソースティン・ヴェブレンの制度主義の経済学である。それは、さまざまな社会的共通資本(social common capital)を社会的な観点から最適な形に建設し、そのサービスの供給を社会的な基準にしたがっておこなうことによって、ミルの定常状態が実現可能になるというように理解することができる。現代的な用語法を用いれば、持続的発展の状態を意味したのである。
20世紀は資本主義と社会主義の世紀であるといわれている。資本主義と社会主義という2つの経済体制の対立、相克が、世界の平和をおびやかし、数多くの悲惨な結果を生み出してきた。この混乱と混迷を超えて、新しい21世紀への展望を開こうとするとき、もっとも中心的な役割をはたすのが、制度主義への考え方である。制度主義は、資本主義と社会主義を超えて、すべての人々の人間的尊厳が守られ、魂の自立が保たれ、市民的権利が最大限に享受できるような経済体制を実現しようとするものである。
社会的共通資本の考え方
社会的共通資本は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような自然環境と社会的装置を意味する。社会的共通資本は、一人ひとりの人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な役割をはたすものである。
社会的共通資本はいいかえれば、分権的市場経済制度が円滑に機能し、実質的所得分配が安定的となるような制度的諸条件であるといってもよい。ヴェブレンの制度主義の思想的根拠は、これもまたアメリカの生んだ偉大な哲学者ジョン・デューイのリベラリズムの思想にある。したがって、社会的共通資本は決して国家の統治機構の一部として官僚的に管理されたり、また利潤追求の対象として市場的な条件によって左右されてはならない。社会的共通資本の各部門は、職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規範にしたがって管理・維持されなければならない。
社会的共通資本は自然環境(大気、水、森林、河川、海洋、土壌など)、社会的インフラストラクチャー(道路、交通機関、上下水道、電力、ガスなど)、制度資本(教育、医療、金融、司法、行政など)の3つの大きな範疇にわけて考えることができる。(この分類は、必ずしも網羅的ではなく、排他的でもない)
「文化」というとき、伝統的社会における文化の意味と、近代的社会において用いられる意味との間に本質的な差異が存在する
アン・ハイデンライヒとデヴィッド・ホールマン(Ann Heidenreich and David Hallman)の論文「売りに出されたコモンズー聖なる存在から市場的財へ」(From Sacred Being to Market Commodity: The Selling of the Commons?)
伝統的社会では、文化は、「社会的に伝えられる行動様式、技術、信念、制度、さらに一つの社会ないしコミュニティを特徴づけるような人間の働きと思想によって生み出されたものをすべて含めて、一つの総体としてとらえたもの」を意味する。他方、近代社会においては、文化は「知的ならびに芸術的な活動」に減的して考えるのが一般的である。マサイ族の若者が「文化」というときには、同年代の若者たちのことを想起し、伝統的な制度のもとで、社会がどのように組織され、自然資源がどのように利用されているのかに思いをいだす。しかし、北ヨーロッパの人々が「文化」というときには必ず、芸術、文学、音楽、劇場を意味する。
環境の問題を考えるとき、宗教が中心的な役割を果たす。宗教は、自然を創り出し、自然を支配する超人間的な力の存在を信じ、聖なるものをうやまうことだからである。
自然と人間との間の相関関係が具体的なかたちで表現されるのは、自然資源の利用という面においてである。伝統的社会では、人やものの移動がきわめて限定されているため、生活を営む場所で利用可能な自然資源に頼らざるを得ない。したがって、これらの自然資源の枯渇はただちに、伝統的社会の存在自体を危うくする危険を内在している。伝統的社会の文化は、地域の自然環境のエコロジカルな諸条件にかんして、くわしく深い知識をもち、エコ・システムが持続的に維持できるように、その自然資源の利用にかんする社会的規範をつくり出してきた。
自然資源の利用にかんして、長い、歴史的な経験を通じて知識が形成され、世代からつぎの世代に継承されていった。自然環境にかんする知識と、その世代間を通ずる伝達によって、文化が形成されると同時に、文化によって新しい知識が創造されてゆく。何世代も通じて知識が伝達されてゆくプロセスで、社会的制度がつくり出される。そして、日常的ないし慣行的な生き方が、社会的制度として確立し、一つの文化を形成することになる。自然と人間との間の相関関係がどのような形で制度化されるかによって、人間と人間の間の社会的関係もまた規定されることになる。どのような自然資源を、どのようなルールにしたがって利用すべきかが文化の中心的な要素となる。したがって、年長者の教示ないしは指示に重点が置かれ、自然資源の利用は、社会のすべての構成員に対して公正に、また利用可能となるような配慮が、どの伝統的社会についても充分払われている。
人間の移動が自由になるとともに、文化、宗教、環境の乖離は拡大化されていった。伝統的な自然環境と密接な関わりをもつ知識は、経済発展の名のもとに否定され、抑圧されていった。
論文ではまた、近代キリスト教の教義が、自然の神聖を汚し、伝統的社会における自然と人間との乖離をますます大きなものにしていった経緯がくわしく論ぜられていることは興味深い。
環境と経済の関係は、この30年の間に本質的な変化が起こりつつある
国連の主催のもとに開かれた環境問題にかんする2つの国際会議のテーマ
・1972年、ストックホルムで開かれた第一回の環境会議
・1992年、リオ・でジャネイロでの第三回の環境会議
1960年代:自然破壊とそれによって引き起こされた公害問題
当時、スウェーデンでは一万を越える湖沼の大半が死んでしまったといわれていて、水質の悪化によって、魚やその他の生物が住むことができなくなり、周辺の森林でも多くの樹木が枯れ始めた。その直接的な原因は酸性雨によるものであった。大部分、イギリスや東ドイツ、ポーランドなどの東欧市の社会主義の国々における工業活動によって惹き起こされることが綿密な調査によって明らかにされていった。日本における水俣病問題や四日市大気汚染後代に象徴されるように、産業活動の結果、自然環境にのなかに排出される化学物質によって惹き起こされたものである。
公害問題に対する社会的関心は、産業活動のあり方に対して大きな反省を迫り、公害規制のためにさまざまな政策が実行され、数多くの制度的対応がとられることになった。その後、30年程の期間に、産業活動にともなう公害に対して、かなりの効果的な規制がとられ、少なくとも資本主義の多くの国々については、工業化、都市化にともなう公害問題は基本的に解決の方向に進みつつあると言ってよい。
1992年のリオ環境会議の主題は、地球規模における環境の汚染、破壊についてであった。地球温暖化、生物種の多様性の喪失、海洋の汚染、砂漠化などの問題。地球温暖化は、主として、科学燃料の燃焼によって排出される二酸化炭素が大気中に蓄積され、いわゆる温暖化効果が働き、地上大気平均気温の上昇を惹き起こすことによって、地球規模における気象条件の急激な変化をもたらすことに関わる諸問題を指す。温室効果は、二酸化炭素の他に、メタン、亜酸化硫酸、フロンガスなどのいわゆる温室効果ガスによっても惹き起こされる。
経済学はグローバル・チェンジを考察できるのか?
スティーブン・シュナイダー『地球温暖化で何が起こるか』
(アメリカのスタンフォード大学の生物学教授で、気候物理学を専門とする科学者であり、『地球温暖化の時代』などの著書を始めとして地球温暖化にかんして積極的な啓蒙活動にたずさわってきた)
現在起こりつつあるグローバル・チェンジにかんして、これまで蓄積されてきた科学的知見は膨大な量に上り、しかも高度な信頼性と厳密性をもつ。しかし、すべての科学的知見がそうであるように、100%の確実性をもつ予測はあり得ない。地球科学者たちがえがく地球温暖化のシナリオは、基本的な点では一致しているものの、細部にわたる点についてはかなりの差異が見られる。叡智(えいち)とオリジナリティをもって蓄積した科学的知見の信ぴょう性を生半可な知識をもって批判する経済学者たちがいる。イェール大学のウィリアム・ノードハウスを中心とした一群の経済学者たちである。
もっぱら化石燃料の大量消費に依存せざるを得ない歪んだ経済構造と非人間的な社会的性向をもつアメリカの異常な政治的条件を反映したもの。現在の経済学の理論的枠組みのなかで、地球温暖化に象徴されるグローバル・チェンジを分析し、その経済的、社会的影響を科学的に考察することはもともと不可能である。じじつ、グローバル・チェンジを考察することのできる経済学の理論的枠組みをどのようにして構築するか、という課題は心ある経済学者にとって現在もっとも優先度の高い研究テーマである。
シュナイダー博士の謙譲な、理性的で、しかも人間的魅力にあふれた科学者らしい対応と、ノードハウスたちの奢りきった、非理性的な応対とがあまりにも対照的であることに経済学を専門とするものとして恥ずかしい思いをもたざるを得ない。グローバル・チェンジにかんするノードハウスたちの政治的な意図にもとづく非理知的な主張と、シュナイダー博士に代表される理性的な考え方との緊張、対立の関係は、地球環境問題にかかわる政府間の国際的な交渉の過程に色濃くあらわれている。(1999年)
スリランカの溜池灌漑
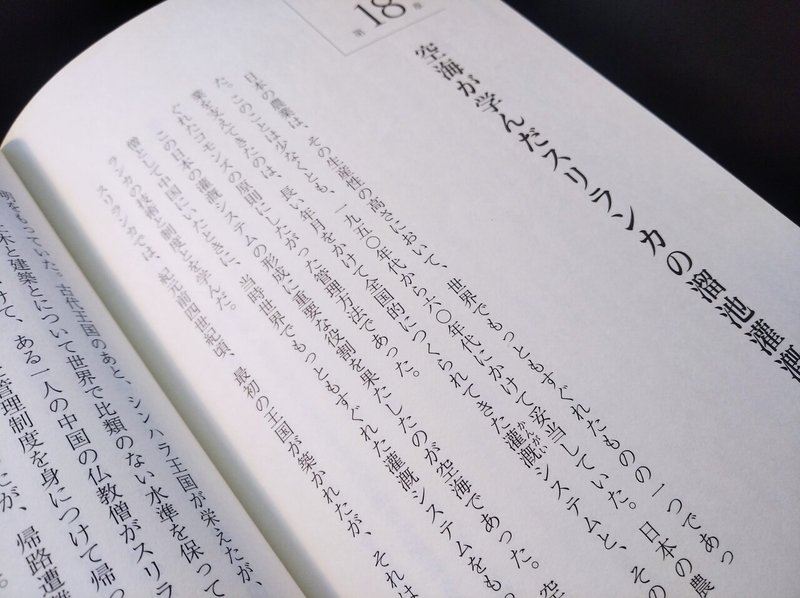
人間的な都市を求めて
・エベニーザ・ハワード:田園都市
・パトリック・ゲッデス:より広い地域全体の都市景観
・ル・コルビュジェ:輝ける都市、近代建築の5つの原則
・ジェーン・ジェイコブズ:アメリカの大都市の死と生、四大原則
近代都市の理念は、19世紀の終り頃、エベニーザ・ハワードが提起した「田園都市」(Garden City)の考え方にはじまる。産業革命のあと、18世紀から19世紀にかけて、イギリスの各地には、新しい、近代的な工場が数多くつくられ、経済の規模は飛躍的に拡大した。しかし、ロンドンをはじめとして、イギリスの大都市における一般の人々の生活は貧しく、悲惨であった。このとき、ハワードはロンドンの郊外にまったく新しい住宅地をつくって、そこに貧しい人々を移した。新しい町は、ゆたかな自然にかこまれて、家々の間もゆとりがあったので「田園都市」と呼ばれるようになった。ハワードの田園都市は、21世紀に入り、新しい町づくりの考え方を象徴するものになった。ハワードの考え方は、パトリック・ゲッデスによって受け継がれ、ひろい地域全体についての都市計画に発展。ゲッデスは、すべてを合理的に計算して、人々の住む環境をつくっていった。ゲッデスは、すべてを合理的に計算して、人々の住む環境をつくっていった。ハワードやゲッデスの考え方は、ル・コルビュジェによって「輝ける都市」として21世紀の都市のあり方に大きな影響をおよぼすことになった。
ル・コルビュジェの「輝ける都市」は美しい幾何学的なデザインをもち、抽象絵画をみるような芸術性をもっている。しかし、生活を営む人間の存在が「輝ける都市」には欠如している。ル・コルビュジェの都市は、そこに住んで、生活を営む人々にとって、じつに住みにくく、また文化的にもまったく魅力のないものだった。
ちなみに、日本にも、ル・コルビュジェ建築の建物が1つだけある。東京・上野にある「国立西洋美術館」。「ピロティ」と呼ばれる柱で支えられた吹き抜け空間「自由な平面」「自由な立面」「独立骨組みによる水平連続窓」「屋上庭園」を近代建築の5つの原則と設定した。
第二次世界大戦後から1960年代の終りにかけてのアメリカ的な経済発展のプロセスによって破壊された自然環境を再生し、失われた文化を復活させようと言う動きが、ヨーロッパのいたるところでみられるようになったのは、1980年代の半ば頃。ベルギーの新しい大学町、ルーヴァン・ラ・ヌーヴ。
ジェイコブスの四大原則
1.都市の街路は必ずせまくて、折れ曲がっていて、一つ一つのブロックが短くなければならないという考え方(自動車の通行を中心とした、幾何学的な道路が縦横に張り巡らされたル・コルビュジェの「輝ける都市」とまさに正反対の考え方をジェイコブスは主張した)
2.都市の各地域には、古い建物ができるだけ多く残っているのが望ましい。そのつくり方も、さまざまな種類のものがたくさん混ざっている方が、住みやすい町。「新しいアイデアは古い建物から生まれるが、新しい建物から新しいアイデアは生まれない」
3.ゾーニングの考え方を否定。商業地区、住宅地区、文教地区などのように各地区がそれぞれ一つの機能をはたすように区分けすることをゾーニングというが、この一つの機能しかはたさない地区ができると、夜とか、週末には、まったく人通りがなくなってしまい、非常に危険となる。
4.都市の各地区の人口密度が充分高くなるように計画したほうが望ましい。人口密度が高いのは、住居をはじめとして、住んでみて魅力的な街だと言うことをあらわすものだから。
筑波では、交通手段は自動車のみであり、非常に大量に自動車が使われている。これは、エネルギー大量消費に大きく依存した都市計画である。人々は誰もが一つのところから他の場所への移動に車を使わねばならない。学校の外で買い物をしたり、公園に行って休んだり、研究室や学校や何かの行事に参加しようとするならば、かなりの距離があり、車を使わねばならない。エネルギーの大量使用型である。
石川幹子氏『都市と緑地ー新しい都市環境の創造に向けて』
レーチェル・カーソン氏『沈黙の春』
ジェーン・ジェイコブス氏『アメリカの大都市の死と生』
思想的、文化的、社会的、経済的な役割。人間と社会の正気をどう捕り物スカ。工業化と都市化。自然と都市の破壊。人間と社会の破壊。
宇沢 弘文(うざわ ひろふみ、1928年7月21日 - 2014年9月18日)
経済学者。専門は数理経済学。東京大学名誉教授。意思決定理論、二部門成長モデル、不均衡動学理論など。シカゴ大学教授、アメリカがベトナム戦争にコミットしていたことに反し、アメリカから日本帰国。日本の社会問題、とくに公害や環境問題に関心を寄せる。趣味はジョギングや山歩き。東京大学までジョギングで通っていた。
「フリードマンらが提唱した理論は、自己の利益を追求することが社会的満足度を向上させるとした、アダム・スミスの言葉を反映しているようにも思います。自己の利益の追求というと貪欲であれ、と言っているようで、貪欲であることはよいことのように聞こえてきます。」
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
