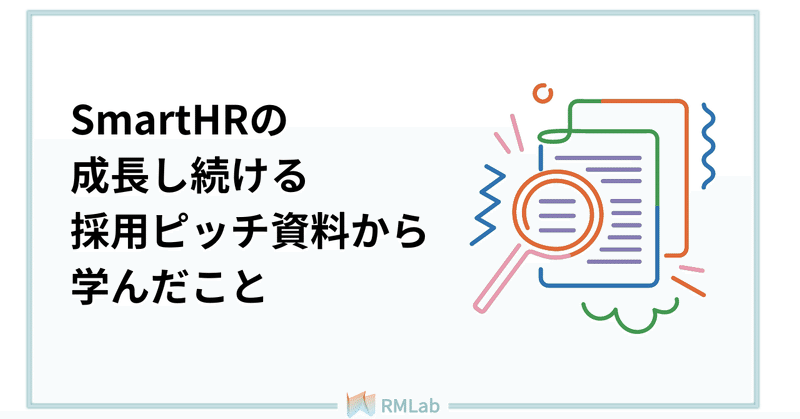
1年ぶりにSmartHRの採用ピッチ資料を見たら学びがたくさんあった話
はじめまして、もしくはお久しぶりです。採用市場研究所でコンサルタントとしてクライアントワークを担当している木下です。
採用や採用広報を担当されたことのある方のなかには、自社や部門の採用ピッチ資料を作成した経験がある方も多いのではないでしょうか。
最近SmartHRさんの採用ピッチ資料を1年ぶりくらいに拝見したところ、「あれ?前にみた時と違うぞ?」と思いました。手元にたまたま1年前の構成を書き起こしたメモがあったので比較してみたところ、成長するSmartHRさん同様、これは「成長する採用ピッチ資料だ! 」と思ったので、その内容を解説してみたいと思います。
この記事ではこんなことをお伝えします。
採用ピッチ資料とは
採用ピッチ資料とは、候補者やエージェントが自社や部門、特定のポジションについて効果的に理解し、興味を持ってもらうために、一般的にスライド形式で公開される資料です。
自社や部門、特定のポジションについて理解してもらえる状態とはどういう状態でしょうか?わたしは、企業や部門、特定のポジションそれぞれの「カラー」を伝えることだと思っています。
これは物理的な青、赤、緑といった色そのものを伝えるのではなく、企業の文化、価値観、魅力を伝える印象を伝えるものとして表現しています。
候補者体験において、認知から興味、比較、決定までのファネル、どこのシーンでも立ち戻って見直される可能性の高い採用ピッチ資料は、企業の文化、価値観、魅力を印象として伝えながら、候補者の知りたい情報を的確に伝えることが求められます。
SmartHRさんの採用ピッチ資料は、数ある企業の採用ピッチ資料のなかでも「お手本」とされることが多く、候補者が知りたい情報と企業が伝えたい情報を端的かつ網羅的に表されています。
採用ピッチ資料の作成が難しいと言われる理由
企業のフェーズやどこの部署が作成するかによっても理由は異なりますが、おおまかに以下の観点によって難易度が上がることが多いのではないでしょうか。
・採用担当が作ろうとすると、日常の業務が忙しすぎる
・自社/部門/ポジションの魅力が言語化されているようで実は曖昧
・ステークホルダーが多く、内容の確認・承認プロセスが複雑
つまり、採用担当の方が作成される場合、忙しい業務の合間を縫って、自社/部門/ポジションの魅力を言語化し、数々の確認、承認を経て公開へ至るわけです。
デザインを自社内で行うか、外部のデザイナーに依頼するかによっても変わってきますが(そもそも会社としてのデザインシステムがあるかどうかでも初手が変わります)、企画から公開まで早くて3ヶ月、社内稟議が長くなりがちな大企業だと公開まで半年かかってしまうなんてこともあったりします。
SmartHRさんの事例から紐解く「成長する採用ピッチ資料」
公開するだけでも大変、、、そんな採用ピッチ資料ですが、忘れられがちなのが「更新(アップデート)」です。
今回この記事を書くきっかけとなったSmartHRさんの2024年4月時点の採用ピッチ資料は、約1年前の内容から継ぎ足し継ぎ足しではなく、綺麗な形でアップデートされています。
なぜこんなことがわかるかというと、以前勉強のために手元で書き起こしていたメモがありまして、今回久しぶりにSmartHRさんの採用ピッチを見た時に、全体から受ける印象は変わらないのに、新しい情報が増えていることに気づいたためです。
2024年4月現在の資料構成内容はこちら

手元のメモと見比べると、大きく違うのは、コーポレートミッションが反映されているということ。
ただ細かくみていくと、1年前にはあったコンテンツがなくなっていたり、項目は同じようでもマイナーアップデートされているものがあったりと、継ぎ足し方式ではなく全体の情報を編集しなおした印象を受けます。
大項目自体が増えていたり、大項目は同じでも中身が変化していたり、より充実していたりと、かなり変化があることがわかりました。
これは作成観点からすると、結構なパワーがかかっているのでは?という推測ができます。少なくとも継ぎ足し継ぎ足しの一番楽なやり方ではなく、伝えるべき内容の取捨選択をするという会社の意思が反映されていると感じました。
SmartHRさんのコーポレートミッション「well-working」自体は2022年8月に制定されたとのこと。時を経て2023年の12月頃から、「well-workingの現在地」として、コーポレートミッションの実現に向き合う社員の方の姿の発信もされています。
コーポレートミッションも作って終わり!ではなく、作ったミッションが浸透しているか、社員の方にとって自分ごと化されているかを追ってそれを公開されているのも「SmartHRさんらしいなぁ」と思いますし、その印象自体が「SmartHRのカラー」としてブランド形成の一端を担っているのではないでしょうか。
資料を更新する際に気を付けるべきこととは
資料を作成した担当者と、更新する担当者が違う、ということもありますよね。
その際にありがちなのが、最初に作成された部分と、追加された部分がつぎはぎの印象になってしまうことです。
採用ピッチ資料が、企業の「カラー」を伝えながら、候補者の知りたい情報を的確に伝える資料であるのであれば、その「カラー」は、全体を通して一貫性があることが求められます。
*ここでいう「カラー」はデザイン要素としての色ではなく、企業の文化、価値観、魅力を伝える印象のことを示しています。
その「カラー」が、作成者によって異なってしまったら?
読み手は混乱をしてしまうのではないでしょうか。
情報を追加する際には、その情報がもたらす印象を意識しながら、読み手にとって違和感がないか、読み手が必要としている情報になっているかの視点が必要です。
SmartHRさんの採用ピッチ資料の作成者がずっと同じなのか、担当が引き継がれているのかは外部から窺い知れないことではありますが、初版が2018年に公開されているのをみると、おそらく複数名の手によって更新され続けているのではないかと推測できます。
この長い期間、更新をつづけながら、「SmartHRらしさ」を保っているということは、それだけ社内に自社の「カラー」が浸透しているということではないでしょうか。
このあたりは別の記事でも書いていきたいところですが、会社の「カラー」を外部に発信する前に社内に「カラー」を浸透させることって、とても重要ですよね・・・。
まとめ
採用ピッチ資料は「一度作っておわり!」のものではなく、候補者の動向や、企業のフェーズ、状況によって更新し続けていく必要があります。
更新時には、自社の伝えたい文化、価値観、魅力を伝える「カラー」に一貫性があるか、その印象が読み手に伝わる状態になっているかを意識することが大切ということを、あらためてSmartHRさんの資料から感じました。
今回はSmartHRさんの事例を参考にさせていただきました。SmartHRさんの成長し続ける採用ピッチ資料、これからの更新も楽しみにしています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
