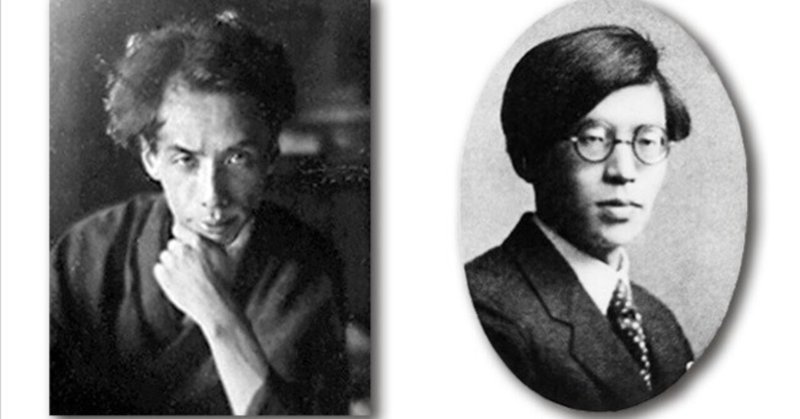
教師が文学の授業のやり方を知らないから授業がつまらない
「文学の授業のやり方を知らない教師が多すぎる」
物語文は必ず主人公がいて、主人公の気持ちが変わっていきます。
一番主人公の気持ちが変わるところを「クライマックス」と言います。
しかしながら文学というのは作家から一旦書きはなされたら、もう作者の手を
離れて今度は読み手の解釈でどうにでも感じ方が変わっていきます。
なので「クライマックス」も人により様々です。
もちろん、より多くの人が感じるクライマックスはあります。
「山場」ですね。
よって、「クライマックスはどこか」を話し合うことにより
内容を精査し、主人公の気持ちを探ることになるのです。
したがって学校での国語の文学の授業は
「クライマックス」=「主人公の気持ちが一番変わったところ」
はどこなのかを話し合うと、議論が白熱し、結果、内容読解が進むのです。
しかしこういった「話し合いのキモ」を知らない教師は
いつまでも
「この時の主人公の気持ちは?」
「この時は誰がどうした?」
と、単に物語をなぞるだけの授業になってしまうのです。
(教師の赤本=アンチョコ=指導書はそうなっています)
これでは実につまらない授業です。
そしてこんなつまらない授業をやっている教師はごまんといます。
だから国語の授業がつまらないのです。


実はビッグデータの解析で、文学には6つのパターンしかないことがわかっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
