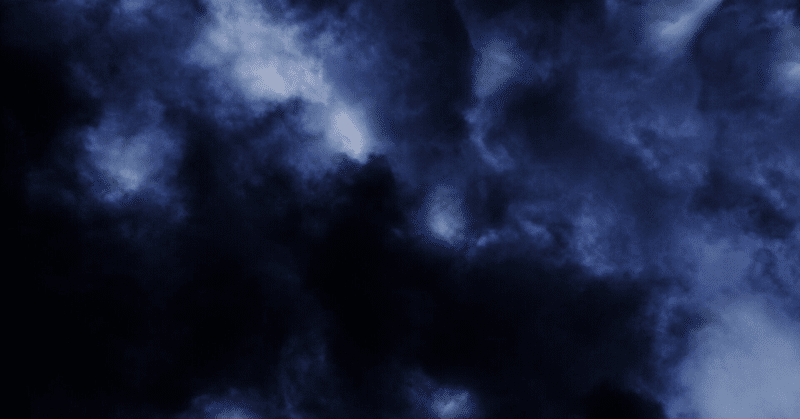
【紫陽花と太陽・中】第七話 賽は投げられた
あらん限りの力を振り絞って、僕は全速力で走っていた。
いつもは自転車で出勤しているのに今日に限って朝小雨が降っていた。自転車を使えばたった十分で店から自宅まで帰れるのに、どうして今日に限って……。
奥歯を噛み締め、両手を強く握りしめて走った。
あずささんから電話をもらったのは、今からほんの五分くらい前だった……。
家に着いた。背負っていたリュックサックからチャックを開けるのでさえもどかしく家の鍵を取り出した。手が震えて鍵を開けるのにいつもより時間がかかってしまい、イライラする。
ようやく開けて、家に足を踏み入れた。
「あずささんっ‼︎」
家の中は真っ暗だった。僕が呼ぶ声以外はしんと静まり返っていた。……いや、違う、かすかに聞こえた。小さく嗚咽する声が。
玄関で靴を乱暴に脱ぎ散らかし、廊下をまっすぐ歩いていく。左手に洗面所、右手にトイレ、階段に続いて、また左手に台所、そしてダイニングテーブルのある広い部屋まで行き、リビングもぐるりと見渡してみた。
僕がここに到着する前、あずささんは……。
泣きじゃくりながらそれでもなんとか電話で助けを求めてきた、あずささんの震えた声を思い出した。
電話。……電話が置いてある棚。……いた。
あずささんが、家の固定電話を置いてあるキャビネットの下に、両足を抱え込みながらうずくまっていた。
部屋に入った瞬間からかすかに臭う違和感に気が付きつつ、あずささんを見つけたので電気のスイッチへと手を伸ばした。
「あずささん、大丈夫? 今、明かりをつけ……」
「つけるなッ‼︎」
スイッチを押そうとしたら、ピシリと強い口調で遮られた。一瞬動きが固まった。
しばしの沈黙。
でも、ずっとこうしているわけにもいかない。
「……でも、でもね。あずささんの状態が分からないと、僕も何もしてあげられないんだ。もしかしたら血が出てるかもしれないでしょ?」
「……」
「明るいところで、ちゃんと、どこがどうなっているのか、確かめたいんだ」
「……」
「明かり、つけるね?」
「……うん……」
スイッチを押す。パッと廊下だけが明るくなった。カーテンを締め切ったままの室内で急に明るくなったらびっくりするかと思い、とりあえず廊下の電気だけつけた。
あずささんを見やった。
驚愕した。
髪は乱れ、服はしわくちゃで、かろうじて肌が隠れるくらいに破れていた。足を抱えた腕は袖がまくれていて、いつかの「あの時」のように、手首に赤黒いあざがくっきりと付いていた。玄関にはあずささんの靴はなかったけれど、今目の前の彼女の足は、左足が靴下、右足は裸足だった。
そして、身体中に、頭にも白い液がこびりついていた。
震える声で、僕はあずささんに聞いた。
「……立てそう? 足とか血が出てるかもしれない……」
少しの間があって、俯いたあずささんがゆっくりと立ち上がった。
両足の間から、ドロリと白い液体が流れ出た。
僕は背筋が凍りついた。
太腿には、引っかき傷はあるものの、例えば刃物で切られたような傷は見られない。あずささんの顔はずっと見えないけれど肩が震えて歯がカチカチ鳴っている音がする。……だって、これは、どうみても……。
「あずささん」
あずささんの両肩がビクンと震えた。
「救急車、呼ぶね」
「……で、も……」
「今僕が見ている限りだと、ものすごく血が出ている感じじゃなかった。でも身体の中がどうなっているのか、僕にはやっぱり分からない。だから分かる人にきちんと診てもらいたい」
「……う……でも」
僕からはあずささんのつむじしか見えない。だから少しかがんで話した。
一瞬あずささんと目が合う。でもすぐに目を逸らされた。
「僕はあずささんに何かあってほしくない。大事だから。……元気なら、元気だってお医者さんに言ってもらいたい。だから、救急車を呼びます」
あずささんは逡巡した後、小さくコクンと頷いた。
レイプされた。
おそらく、あの液と匂いは……。
救急車を待つ間、乗り込んで発車を待つ間、病院に向かっている間、僕は血が出るほど両手を強く握りしめていた。
相手の心当たりとして一瞬あの男の顔が頭をよぎったが、あずささんは何も言っていない。別人が犯人の可能性だってある。決めつけるわけにはいかない。
室内に犯人がいなくて良かったと思った。あずささんを見つけて救急車を呼ぶまでは必死で頭が回らなかったけれど、犯人が中にいたのだとしたらもっとひどいことになっていたかもしれない。
僕とあずささんを乗せた救急車は、今にも雨が降りそうな曇天の中、産婦人科へ真っ直ぐ向かって走っていった……。
人生で初めて足を踏み入れた産婦人科は、壁や調度品がパステルカラーでかわいい小綺麗な病院だった。
緊急のことだったので——確か裏口から院内に通されたと思うのだが——あずささんは肩からブランケットをかけてもらいながら処置室に向かっていった。
静かな待合ベンチにゆっくりと座って、両手を膝のあたりで組んだ。ふーっと大きく息を吐き出す。そこで自分がずっと極度に緊張していたことを自覚した。仕事用リュックサックに手近にあった自分の財布だけをとりあえず投げ込み、急いで救急車に乗り込んできたので、今手元に本すらなかった。仮に本があったとしても活字なんて頭に入り込んでこないだろうけれど。
もう一度息を吐き、頭を膝の上の手に乗せた。前かがみになる姿勢になった。
お腹がチクチク痛いような気がした。目を閉じ、呼吸を整える。
ふいに、処置室から悲鳴が聞こえた。今まで聞いたことのないくらい痛々しい悲鳴だった。誰が叫んでいるんだ、そんなこと、あずささんに決まっている。
痛い、やめて、嫌だ、そんなような声が泣き声に混ざって聞こえてくる。
眉間にシワが寄る。あずささんが、今、闘っている。
代わってあげることができたらどんなにいいか……。
悲鳴がだんだん小さくなり、しばらく聞こえなくなった。それからまたしばらく待って、かなり待って、僕は診察室へ呼び出されたのだった……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
