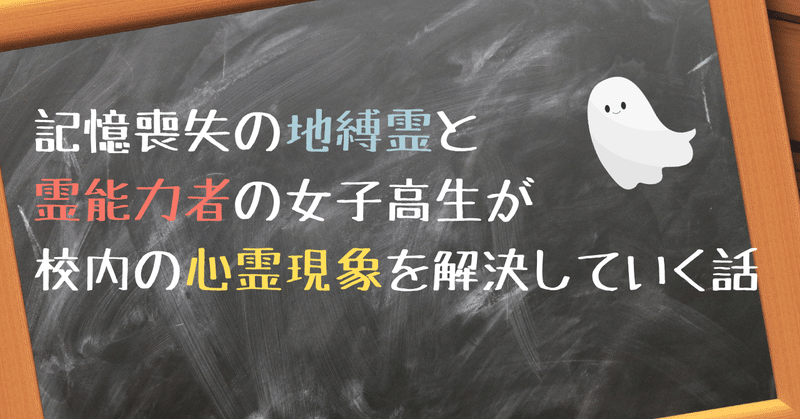
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #17
第3話 死神の見識――(4)
第一図書室で発生していた怪奇現象は、幽霊不在のポルターガイスト現象だった。
あとから合流してきたハギノモリ先生曰く、これは昔からよくあることなのだそうだ。だから、手順に従い、場の浄化を行えば、それであっさり解決するらしい。
「でも、ポルターガイストって、幽霊がものを動かす現象のことを言うんじゃないの?」
アサカゲさんが先に始めていた浄化作業を引き継ぎ、無事に事態を収束させたハギノモリ先生は、そのまま図書室に残り、散らばった本の片づけを手伝っている。アサカゲさんは先の話の通り、先生と交代で授業に戻ったあとだ。
俺はこの現象について知りたくて、図書室に残り、先生にそんな質問を投げかけた。
「この学校が、死者の魂の通り道になっているという話は、以前にもしましたよね? そういった場所は、悪霊にも生霊にも成りきれない〈よくないもの〉の吹き溜まりになりやすいのですよ」
「それが、今回の惨状の原因ってこと?」
「平たく言えば、そうですね。ただ、〈よくないもの〉は様々な意識や思念の集合体のようなもので、明らかな害意はありません。だから、こうして無意味にものを動かす程度のことしかできないのです。今までも、勝手に扉が開いたり閉まったりする程度のことはよく起きていましたが、ここまで大規模なポルターガイストは久しぶりでした」
「へえ。どれくらいぶり?」
俺の問いかけに、先生は記憶を辿るように、そうだなあ、と間延びした声を発する。
「着任した当初は結構ありましたから、十数年ぶりでしょうか。校内に結界を張り巡らしてからは、かなり落ち着いていたんですけれどねえ」
言って、先生は苦笑した。
それはつまり、今の結界がそれだけ弱まってきているということなのだろう。或いは、結界を張りさえしていれば霧散していく〈よくないもの〉が、これまで以上に集まりやすくなってきているのかもしれない。
「もしかして、今アサカゲさんがやってる結界の補強って、かなり重要任務だったりする?」
「お恥ずかしい限りですが、その通りです。ただ、彼女には内緒ですよ。あまり彼女にばかり気負わせたくはないので」
先生は、眉根を下げてそう言った。
「わかった」
あくまでもアサカゲさんはこの学校の一生徒であり、決して専任の霊能力者ではない。
先生の言うところの意味は理解できるし、それには俺も全面的に同意する。
「内緒と言えば、もうひとつ」
と、先生は床に散らばった本を拾い集めながら、言う。
「アサカゲさん、貴方が現れるようになってから、とても楽しそうにしていますよ。なにかにつけ、ろむがろむがって、楽しそうに話してくれています」
「ええ、そうなの」
それは、嬉しいような哀しいような気分になる。
俺は、アサカゲさんと過ごす時間が楽しいと思っている。彼女もそう思ってくれているのなら、それは嬉しいことこの上ない。けれど、彼女の話題の中心が俺であるというのは、突き詰めて言ってしまえば、生者との関わりが薄いということになるのだ。
「貴方の心配するところはわかりますよ」
本を拾い上げ、書架に本を戻しながら、先生は言う。
「けれど、春先はずっと眉間にしわを寄せていた朝陰さんが、最近は笑顔になることも増えてきたんです。たとえそれが微々たるものでも、良い変化であると、僕は思っています」
「それは……確かにそうかも」
主な話し相手が俺という幽霊であっても、孤立状態から脱却し、表情も徐々に柔らかくなってきたという点においては、確かに、アサカゲさんにとっては良い変化なのだろう。
人生は長い。ましてやアサカゲさんは高校一年生――まだ十五歳なのだ。未来ある若者に、幽霊である俺ができることと言えば、成仏するその日まで隣に居ることだけだ。たったそれだけ。だけど今は、それこそが大事なのかもしれない。
と。
先生とそんな話をしているうち、六限目の終わりを告げるチャイムが鳴った。
「あ、それじゃあ先生、俺、アサカゲさんのところに行くよ」
先週から進めている結界の補強は、まだまだ道半ばだ。少しでも効率良く進められるように、俺は今日の順路を脳内で組み立てていく。
「はい。ろむ君も頑張って――む?」
笑顔で俺を見送ろうとしていた先生は、しかし途端に、厄介なものを発見したような険しい表情になった。
「どうしたの、先生?」
「これは……ああ、朝陰さんが言っていたものですね、ふうむ」
気配を探るように独りごちていた先生は、なにか納得したように頷くと、ろむ君、と俺のほうを向いて言う。
「詳細はこのあと朝陰さんから聞くでしょうから、僕からはこれだけ言わせてください」
「な、なに?」
「大丈夫ですから、逃げちゃ駄目ですよ」
そんな不穏過ぎる言葉を受け、今度は俺が険しい表情をする番だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
