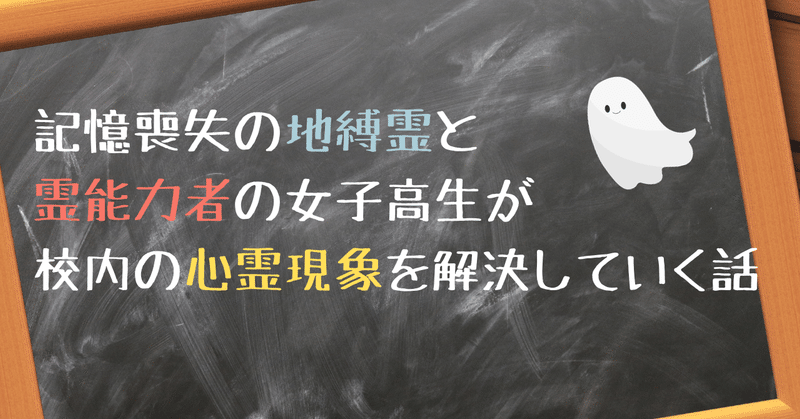
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #12
第2話 延長線上の哀歌――(10)
朝からいろいろとあったが、気を取り直し、放課後――になる、少し前。
俺は六限目の終わり頃に、一足先に旧校舎へ来ていた。
授業が終わるのを待って、アサカゲさんと一緒に来ることも考えた。が、朝のことから顧みるに、人の多い時間帯は彼女と別行動をしたほうが良いのかもしれない、と判断したのである。俺だけなら別に、見た目でぎょっとされるのは当然だから構わないけれど、俺が隣に居る所為で、アサカゲさんに辛い思いはさせたくなかった。
「あ、ろむさん、こんにちは。今日からよろしくお願いしますね」
するりと壁を通り抜けて音楽室に入ると、ユウキさんが出迎えてくれた。
彼女の足元には、相変わらず悍ましいものが巻きついているが、少なくとも悪化はしていないようである。
「こんにちは、ユウキさん。ユウキさんこそ、ピアノの指導、頑張ってね」
「はい、頑張ります!」
鼻を鳴らし、意気込むユウキさん。
その様子が昨日よりも元気そうで、俺は内心でほっと肩を撫で下ろす。幽霊相手に元気もなにもないのかもしれないが、こういうのは気の持ちようだ。ユウキさんにもオオモモくんにも、この三日間を悔いなく過ごしてもらいたいものである。
「そういえばさ、これは素朴な疑問だから、不快なら無視してくれて構わないんだけど」
慎重に前置きをし、俺は言う。
「オオモモくん、どうして『きらきら星変奏曲』を弾こうと思ったのかって、ユウキさんにはわかる? 彼、ピアノは初心者なんだよね? あの曲は少し難易度が高くない?」
「ああ、それなら、たぶん――」
言いながら、ユウキさんは思い出を辿るように、ピアノを見遣る。
「――たぶん、大桃くんが初めてここに来たとき、私がその曲を弾いていたからだと思います」
ユウキさんは、懐かしいなあ、と零すようにそう続けた。
「思い出の曲なんだね」
「はい」
そう言って、ユウキさんは微笑んだ。
その表情を見る限り、昨日よりもだいぶ緊張が抜けているように思える。落ち着いた状態で臨めるのなら、なによりだ。
ユウキさんとそんな雑談をしているうちに、六限目の終わりを告げるチャイムが鳴った。
放課後になり、一気に生徒が動き出す。旧校舎にも届くその音に耳を傾けつつ、雑談を続けていると、音楽室の戸が勢いよく開かれた。
「早いね、アサカゲさん。まだ授業が終わってから五分も経ってない――ん?」
俺はてっきりアサカゲさんが来たものだと思い、そう言いながら開いた戸のほうを見た。が、そこに立っていたのは、オオモモくんだったのである。
「え、早くない? 昨日は十七時過ぎに来てたよね?」
「大桃くんは普段から、授業が終わったらすぐ来てますよ。それにしたって、今日は早いですけど。新記録かもしれません」
アサカゲさんが来ていない今、俺たちの姿は彼には視えていないはずだ。それでもなんとなく、俺とユウキさんは小声でそんなやりとりをしていた。
オオモモくんはといえば、不安げな表情で音楽室を見回していた。ユウキさんの姿を探しているのは明白だったが、如何せん彼に伝える手段がない。
「ど、どうしましょう、ろむさん」
「え? いやいや、俺、ポルターガイスト現象とか起こせないよ? ユウキさんこそ、なにか合図を送れたりしない? 昨日、オオモモくんの肩に触れたら反応してたじゃん」
「あれはたぶん、空気の流れのようなものを、奇跡的に感じ取ってもらえていただけで、具体的なコミュニケーションはとれたことないんです」
アサカゲさんもすぐに来るはずだとわかっていても、オオモモくんをこのままにしておくのは心苦しい。どうにかできないものかと、二人してわたわたしていた、そのとき。
「……なにやってんだ、お前ら」
半ば呆れたような声と共に音楽室に入ってきたのは、アサカゲさんだった。
歩を進めながら、俺とユウキさん、それからオオモモくんを見遣り、なんとなく状況を読み取ったのか、
「あー、遅れて、悪かった……?」
と、多少正解の言葉か迷いつつ、謝罪の言葉を口にした。
「いや、僕が早く来ちゃっただけなんだ。朝陰さんが謝る必要はないよ」
オオモモくんはすかさずフォローに入ったが、アサカゲさんは、いやどっちかっつうと、と言いながら俺のほうを見る。
「ろむと結城先輩が慌ててたみたいだから。今日は担任に呼び止められて遅くなったけど、明日はすぐ来れるから、心配すんな。つうか、大桃先輩こそ早くねえか? あんた、昨日は十七時過ぎにここに来てたろ?」
アサカゲさんからの問いかけに、オオモモくんは照れくさそうに頭を掻いて、言う。
「昨日は委員会があったから、その時間になったんだ。今日は、その、先輩に会えるんだと思ったら、居ても立っても居られなくなって、小走りで来ちゃったんだ」
「……無理はすんなよ、マジで」
それは彼の怪我の後遺症のことや、祠の神様からの災厄のことも指しているのだろう。そう言ったアサカゲさんの声音には、警告の色が濃く含まれていた。
「ま、ともあれ、まずはピアノのレッスンだよな」
アサカゲさんは思考を切り替えるようにそう言って、一度大きく手を叩いた。
一瞬、全身を撫でるような、微弱な風が通ったように思ったのも束の間。
「――……先輩、結城先輩……!」
オオモモくんが、絞り出すような声で、そう言った。
アサカゲさんが霊術を発動させ、彼の目でも幽霊が視えるようになったのだ。であれば、俺の姿も彼には視えているはずだが、彼の眼中に俺が居ないのは当然と言えよう。
オオモモくんはユウキさんだけを見据え、まるで衝動的に動いたら壊れてしまうのではと思っているかのように、慎重に近寄っていく。うわ言のように、先輩、先輩、と繰り返しながら。
そうしてユウキさんの前に立ったオオモモくんは、震える声で、言う。
「僕、先輩と、この音楽室で過ごす時間に、ずっとずっと救われてきたんです。だから、先輩が亡くなったあとも、ここでピアノを弾いていれば、あのときに戻ったみたいに思えて……そのうち、先輩が隣に居てくれてる感じがして、心地良ささえ感じて……。だけど僕は、こんなことがしたかったわけじゃないんです。ごめんなさい、先輩。本当に、ごめんなさい……」
こんなこと。
オオモモくんの未練と執着で、ユウキさんの成仏を妨げてしまっていること。
本人が意図してやったことではない、偶然の結果であったとしても、きっと彼の目に、ユウキさんの足元に巻きつくそれは、ひどく惨たらしく映ったのだろう。
「ううん、良いのよ、大桃くん。私だって、気まぐれに君を演奏に誘って、君に後悔の種を植えつけちゃったんだから。おあいこってやつよ。私も気にしてないから、君も気にしなくて良いわ。ほら大桃くん、ピアノ、弾きましょう?」
そう言って、ユウキさんはオオモモくんの肩に手を置いた。オオモモくんはほとんど反射的にその手を掴むと、俯きがちに頷いた。
「……ろむ、オレらは向こうに行こうぜ」
と。
アサカゲさんは、ユウキさんたちの再会にほっと息を吐いた俺の腕を掴むと、ぐいっと力強く引っ張った。部外者はさっさと退散しようと言わんばかりの力の入り具合に、俺も無言で首肯し、大人しく彼女に連行されることにした。
俺たちが隣の準備室へ移動してから、ほどなくして音楽室からピアノの音が鳴り始めた。
たどたどしい音の後に、素人でもわかるくらい滑らかで表現力に富んだ音が響く。
俺とアサカゲさんは、どちらが言い出すまでもなく、黙ってその音色に耳を傾け続けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
