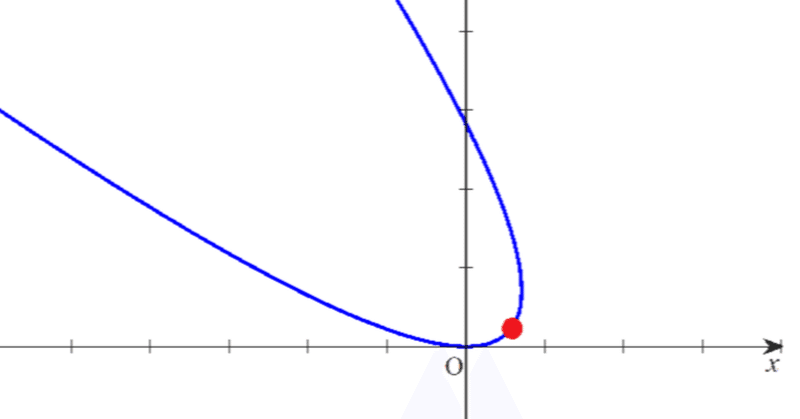
国立大学医学部医学科に塾なしで現役合格する方法 ⑤数学の勉強法
こんばんは。一昨医です。
今日も投稿読んでいただいてありがとうございます。
いよいよメイン教科ラスト、数学編です。
数学は本当に思い入れがある科目ですね。
そんな時にとある数学の先生が僕をクラス全員の前でしっかりディスってくれたんです。クラス平均を下回って、自分史上過去最低の点数をたたき出してしまったテストの時でした。
「お前とかがさ、こんな点数で本当にいいの?」
さすがにヤバいと思いました。
そこからは、出された課題を(ある程度)理解できるまで地道にやるようにしました。その結果、数学に何とか最後救われたのですが、あの時あの先生に愛のあるスイッチを入れてもらわなかったらどうなっていたかと思うと、とても恐ろしいです。
https://note.com/ototoi_2daysago/n/n0da5f082f65b?magazine_key=m66a9a587de0b
中学生の時はほとんど、授業で出た課題しか勉強していなくて、テスト前に重要問題だけ復習して80点みたいな、そんな感じの教科でした。
それが高校数学を学び始めてからそのメッキがべりべりと剥げ落ちて、こんなエピソードを生み出すような状態にまで落ちていました。
もともと中学受験の時から苦手意識があって、特に図形問題とかは苦手でした。全然何が起きているのかイメージができなくて。
そんな状態から、最後の最後に前期の2次試験で80%越えの点数を出して、合格の原動力となってくれたのか。振り返りを兼ねてこれから書いていきたいと思います。
1.数学は暗記(文系科目)である
こんなことを書いたら、数学者の先生にぶん殴られますね。
あくまで、「大学受験で合格点を取ること」限定の話だと思っていてください。
何の根拠もなくこんなことを言っているわけではありません。
一般に数学が苦手、という人はこう思っていませんか?
数学はセンスが必要
書いてある意味が何も分からない
これ、僕に言わせれば全部見当はずれです。
センスって何ですか?大学受験にセンスなんてありません。ただ合格点を取れるだけの勉強をしたかどうか、それだけだと思います。
書いてある意味は、分かるまでやれば大概わかります。少なくとも、大学受験レベルの話は、その年代でわかるような話にかなり限定されて出題されています。
ちょっとキツイ言い方になってしまったのですが、これは当時の自分に対しての戒めです。正直今でももう少しできたよなって思うときがあります。
先述のエピソードで心を入れ替えて勉強し始めた僕ですが、他の教科と比較すると依然としてかなり遅れを取っていました。そんな状態で高校3年生の夏を迎えてしまいました。そのときの僕の気持ちです。
時間がない、ヤバい
→基本からまるで分かっていない
→最速で必要な分量をこなさなければ
→過不足ない良問ぞろいの問題集をやりこもう、パターンを暗記しよう
今にして思うと、この判断が結果として正解でした。
パターン暗記なんて本質的じゃない、と正直馬鹿にしていたのですが、気付きました。それぐらいのことも今の自分はできてないんだ、と。
複数の問題集や分厚い参考書だと絶対に終わらないと思ったので、できるだけ最小限の問題集で質の良いものを探し、先生に教えてもらいました。
それが「大学への数学 1対1シリーズ」。
1対1対応の演習/数学1 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ) | 東京出版編集部 |本 | 通販 | Amazon
これは最高です。
最後まで僕はこれで乗り切りました。
取り組み方としては以下の通りです。
例題を自力で解く
途中で絶対に詰まる
詰まったところだけ青ペンで写す、そのあとは自力で解く
あとは2と3の繰り返し。例題しか解きませんでした。例題は解説が目の前にあるので、この取り組み方に適していたからです。言い訳ですが、時間もなかったですし。
詰まったところも計算の部分は必ず自分の手でやるようにしていました。
これはどういう手順で解いていくのか?
どの部分が採点上マストな部分(評価される)なのか?
これをひたすら考えながら、そしてそれを身体に覚えこませるために地道にやっていきました。これのおかげで計算ミスも減りました。
これが結構面白くて、青字が少なく終わった問題っていうのは自力で解けた感じがして自己肯定感が上がるんですよね。
たとえ計算部分の黒字が大部分だったとしても。
かつ、復習するときには青字の部分をベースに抑えておけば、時短で要点を捕まえられるようになります。
基本パターンが徐々にわかってくると、この問題はこれか?違うかとトライアル&エラーで自力でより進められるようになります。
解説を読んでも??って感じの問題(めったにないですが)だけ先生に聞きに行っていました。
こんな良い勉強法してたんなら、大学入ってもアプデして続けろよ…
って書きながらちょっとがっくりしました。笑
いや、でも正解がある問題じゃないとこれはできなかったのか。なるほど。
長くなってしまったのですが、英語のところと一緒ですね。
その教科を理解するためには、まず基本的な概念・考え方を押さえる必要があって。そのために基本パターンの暗記はコスパが大変よろしいのではないかと、思うわけですね。
2.数Ⅲの方が簡単
すいません、これも僕の感想です。
数学が暗記という考えに則ると、数学ⅠAⅡBの方が若い学年で勉強していて、単純に接触してる時間が長いじゃないですか。
なので入試を出す側からすると「多少問題をひねっても受験生解けるんじゃない?というかそうしないと差がつかないし」と思うんじゃないかと。
実際、高3の最後になるとⅠAⅡBムッズ!!!となってた記憶があります。
数Ⅲはその点やってる時間も短くて、本番でも基本的な問題が出ることが多い印象です。合格最低点とるのが目標なわけで、基本的で点数の計算がしやすい方がメンタル的に楽じゃないかなと思ってました。
やってる内容自体はそんなに簡単ではないと思うので、基本的なところをどれだけ暗記でつぶせるかが勝負じゃないかと!思います!!
3.まとめ:センター試験と2次試験の数学の得点率がほぼ同じだった。
正直センター試験の数学って難しくないですか!
時間足りないし!
共通テストは見た感じもっと難しそうなので、きついなあと思います。
ただ、そこでしっかり勝負できるだけの基礎力がついていれば、2次試験もある程度勝負できるんじゃないかなと思います。
個人の経験で言えば、2次試験の方が明らかに感触は良かったので。
あれだけ苦手と思っていた数学が、最後に合格の決め手となってくれたこと。これは僕の大学受験の中で最もセンセーショナルな出来事だったかもしれません。
これから勝負の夏休み。「苦手教科の克服」という若干後ろ向きなワードはやめて、「勝負できる教科を増やす」というのはどうですか?
1か月の間にどの教科にどの時間数をかけて、どのレベルまで持っていくのか、考えて地道にやっていくと良い時間が過ごせると思います。
以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
おまけ、文系の数学が苦手な人へ
国語のできる理系というのが僕の強みだったように、数学ができる文系は間違いなく強みになります。
数学も暗記科目とわかった今、実質文系科目といえませんか?
過不足なく地道にやれば、ある程度相応の成果は出ます。
大学時代や社会人でも数学は絶対必要不可欠なので、先に始めるのがお得だなーと個人的には思います。
フィードバックが励みになります。 少しでもお役に立てますように。
