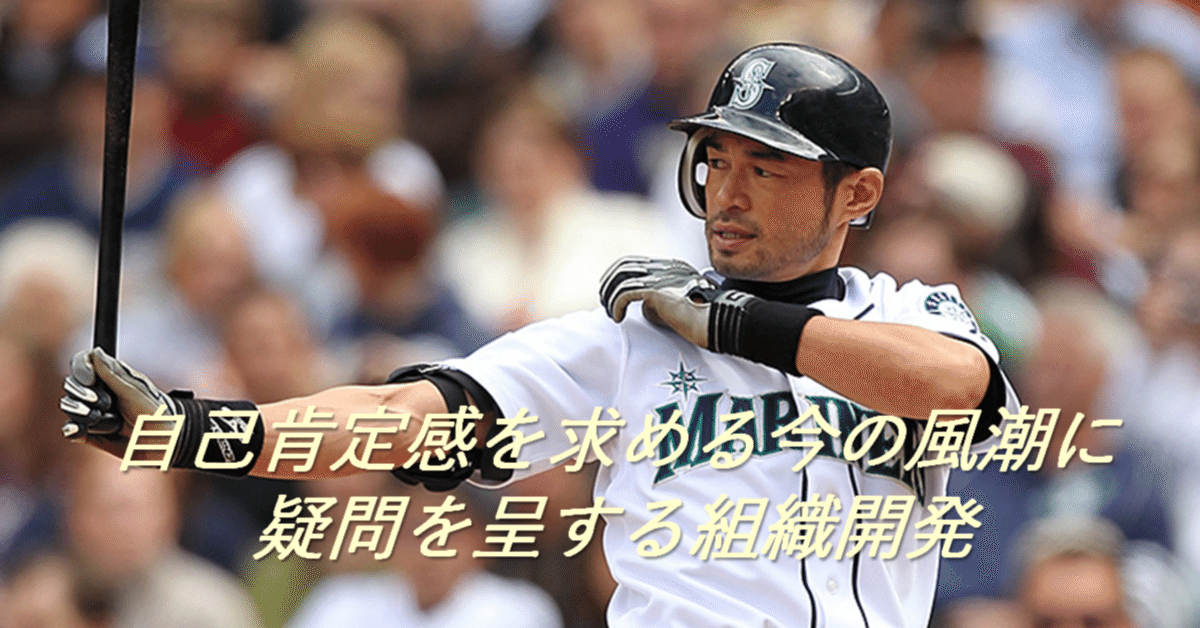
自己肯定感を求める今の風潮に疑問を呈する組織開発
元メジャーリーガー・イチロー氏がインスタライブで、「自分を肯定するのは、僕は凄く抵抗があります。僕の場合は疑問符をつけてます、自分がやったこと、やろうとすることに。これ(自己肯定感)が強い人って、ストレスフリーで楽しそうに仕事(する)みたいな感じですか? それってどうなんですかね。いいなって思うけど、その人たちは人としての厚みが生まれるんだろうか。瞬間瞬間はいい仕事ができるんだろうけど。明らかにダメなのに否定されない。自分でもいいことしか振り返らない。第三者からも指摘されない。僕は堕落すると思いますけどね。人が最悪になるとき(最悪な人)って、自分が偉いって思った人たち。最悪というか魅力的じゃない。それ(最悪というか魅力的ではない状態)が生まれるんじゃないかと。これ(自己肯定感)が強すぎる人は」と、自己肯定感を求める風潮に疑問を呈したそうです。(デイリースポーツ2023/12/22より引用)
これは、フィードバックの必要性を示しているのだと思います。ただ、「自己効力感」を含む概念として「自己肯定感」を捉えているようにも見受けられます。自己肯定感が、自分は役に立っているという自覚であるのに対し、自己効力感は、自分が物事を遂行できると信じる力であり、ある状況下における自身の可能性を認知していることとも言えます。つまり、自己肯定感も自己効力感も、本来、フィードバック(第三者視点あるいは客観性に基づく事実に対する指摘)によって培われるものだと言うことです。
自己紹介で、「私は褒められて伸びるタイプなんです」と言い切る人を見かけることがあります。これは言外に「叱らないで」と表明していることに他なりません。本来「褒める」と「叱る」はセットで用いられ、フィードバックとなります。したがってこの表明は、フィードバックを拒否していることにもなります。もっとも発言者は、叱られることは拒否しないが、「怒らないで」と言っているのかもしれません。確かに“指摘”に怒りの感情が含まれれば、それは同時に“指摘”のニュアンスを失ってしまいます。フィードバックには客観性が求められ、したがって冷静さを失ってはフィードバックにはなりません。その点では、そのように発言する気持ちが、理解できなくもありません。
自己肯定という概念が、自己の心の持ちようであるかのように認識されている風潮を感じます。自己肯定感の弱い者に対するカウンセリングなどでも、そのようにかかわっているのではないでしょうか。しかし自己の在りようとは、周囲との関係性において規定されていくものです。実際、心理療法でも、グループ・セラピーなどで対応しようとする例も見受けられます。この点は、組織開発においても参考になるものではないでしょうか。モチベーション喚起の施策として『1 on 1』などの個別対応がもてはやされていますが、これですべてが解決するわけではないと思います。
組織運営とは、人と人とのかかわりそのものです。正しくフィードバックし、素直にフィードバックを受ける環境が、日常的に担保されている組織であることが重要だと思います。
↓↓↓ 研修・講演・執筆・コンサルティングのご照会 ↓↓↓
https://office-okajima.jimdosite.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
