
AI教育を広げていく原動力のような存在に。【社員インタビュー|Why CLACK編】
こんにちは!認定NPO法人CLACK採用担当の川口です。
CLACKメンバーの想いやジョインのきっかけが分かる【社員インタビュー|Why CLACK編】、今回は2024年1月にCLACKに入職した小浦さんにお話しを伺いました!
教員やIT企業など幅広く経験している小浦さんの変遷を書いていたら少しボリューミーになってしまいましたが、、ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しいです!
インタビュイー・プロフィール
小浦 友梨(こうら ゆり) / 東京都出身
東京大学文学部卒。カナダ・ブリティッシュコロンビア大学院Educational Technology修士課程在学中。中高の教員として学校教育の現場に従事し、校務や授業のデジタル化の必要性を痛感したことから、Microsoft社のCustomer Success Trainerに転身。企業や公共団体、学校向けにDX推進のためのオンライントレーニングを実施し、13,000名以上の受講者のIT スキル向上に貢献。教育×ITを通して、子どもたちの視野や可能性を広げる支援を志し、2023年に認定NPO法人CLACKに入社。デジタル伴走支援部長として、専門高校におけるAI学習の推進プロジェクト「mirAI for Japan」を立ち上げ、高校の先生方へのAI研修を企画・運営。
海外留学を機に価値観が変化。今後の目標を発見

ーこれまでの経歴について教えてください。
はい、大学は東大の文学部の歴史学科に通っていて、その時は歴史の教員になりたいと思っていました。歴史は物語なので、もう出来ているストーリーをただ教科書の内容通りに習うだけじゃなくて、もう少し実証的に生徒が自分で調べたり、自分でストーリーを繋ぎ合わせていくような授業をできるようになりたいなと思っていたんです。
そんな想いを抱きながら、大学時代に3ヶ月程トルコに教育系のインターンに行き、その後、スペインに1年間留学に行きました。そこでとても揺さぶられたといいますか、カルチャーショックを受けました。帰国してすぐ就活だったのですが、就活の軸を何にしようかなと考えた時に、海外に行く体験を通して自分自身、視野が広がり、考え方が変わったりもしたので、自分の中で将来達成したい目標として、手段は何でもいいが、他の人の視野を広げることや可能性を広げるようなお手伝いをしたいなと思うようになっていました。
その時点で、気持ち的にも選択肢的にも教員になりたいという気持ちは変わらずありましたが、いきなり教員の道に進むと世界が狭まってしまうかもしれないと思い、新卒は旅行会社のH.I.S.に就職しました。
海外に行く人を増やすことで、それこそ私と同じようにカルチャーショックをきっかけに視野が広がったり、海外のことを好きになる人が増える機会になるといいなと思ったのがきっかけです。
海外にいる時に、当時は日本のことを知らない外国の人も多くて、日本人と中国人の違いがわからない外国の人も多かったですし、逆に日本人も、フランス人とドイツ人の違いが分かるかと言ったらそうでもなかったり。海外での気づきとして無知が偏見や差別にも繋がっているなと感じました。
H.I.S.は、人種や宗教、国籍を超えて世界平和や相互理解の促進に貢献するという会社として大事にしている理念にも共感したんですよね。
最初の2年は現場の個人営業を経験し、その後社内公募で航空仕入れの部署に異動し、航空会社と交渉して仕入れる座席の数やレートを決めたりするような部署に3年間いました。
その後は、教員になりたいと気持ちが固まっていたので、H.I.S.に在籍している間に英語の教員免許をとってシンガポールの日本人学校の英語教員になりました。
ーなるほど、そのタイミングで教員になられたのですね。働きながらの教員免許の取得、小浦さんのバイタリティーは本当にすごいですよね!教員時代はどうでしたか?
大学を卒業した時には社会科しか取れていなかったので、2年程通信制で日大の就職課程に通い、英語の教員免許を取りました。
2年間、教員の仕事をさせてもらって、国語と社会の授業以外は全部英語で受けるグローバルクラスの担任を任せていただいたり、進学主任として受験の統括をする仕事をやらせてもらうなど、やりがいはとてもあったのですが、とにかくハードで(笑)。
とはいえ、好きな仕事だったので教員の仕事は続けようと思っていましたが、シンガポールにいる間に結婚して、夫がオーストラリアで働いていたので夫がシンガポールに来るか・私がオーストラリアに行くか、半年ぐらい議論を重ねた結果、私がついて行くっていうことになり教員の仕事を一旦辞めました。
2020年の4月にオーストラリアに行く予定だったので、3月にシンガポールの日本人学校を退職し、日本に帰国した途端コロナ禍突入でオーストラリアの国境閉鎖が始まってしまい、、
どうしようかなと思っていた時、たまたま声をかけてもらったのがUber(ウーバー)でした。
初のIT業界、社会のインフラとなるサービスを経験
それまで全然IT業界とは縁がなくて、初めてのIT業界でした。
最初はオーストラリアに行くまでの期間として、派遣の契約で3ヶ月ごとの更新でしたので3ヶ月〜半年ぐらいだろうなと思って始めました。しかし、コロナ禍が全く終息せず、そんな状況の中で、ITが社会インフラとして重要性が増していってるのを実感しました。
当時は、ウーバーイーツもプラットフォームとしてどんどん需要が上がっている時で、レストランに行けない、自分で料理できない、スーパーに行けないという人などにとっては生命線のような感じになっていました。
ITが本当に社会のインフラであり、ITを通してしか人と繋がれない時代を経験して、ITってただの技術手段と思っていたけれども、IT技術があるからこそ人と繋がれたり、必要不可欠なインフラになっているんだと強く思うようになりました。
ーまさにそうですね。ITが人や仕事を繋いで、ひとつのサービス自体が社会のインフラになっている例もありますよね。その後は・・?
1年程、Uber(ウーバー)にいた後は教員に戻りました。オンライン学習の波が来ていて授業内でIT活用する場面も私個人としては多かったんですが、学校としてはまだIT活用をあまり進められていない、学校によっては全くやっていない先生もいる学校もあって、ITの導入どうしようという過渡期のような感じでした。それを見ていて、ITと教育をうまく繋げられたらいいなと徐々に思うようになりました。その頃ようやくオーストラリアの国境が開いたので、教員を1年やった後オーストラリアに引っ越すことになりました。
またそこで仕事を探して出会ったのがマイクロソフトのカスタマーサクセスでした。マイクロソフトのお客様には法人や学校、公共団体、政府などもあり、そうしたお客様にマイクロソフト製品のトレーニングをオンラインでご提供することでIT活用やDXを進めてもらうようなポジションでした。しかし、また1年ほどで夫が日本に戻ることになり、その仕事をやめなければいけなかったので転職活動をしていたところ、代表の平井さんからお声がかけをいただいたことがCLACKに入るきっかけになりました。
教員とIT企業、どちらの経験も活かせる

ーここでやっとCLACKが出てきましたね!(笑)小浦さんの経歴は特殊ですが、ここまでお聞きして、学びを広げていったり格差をなくしていきたいという気持ちが一貫していて素敵です。CLACKとの出会いやきっかけをもう少し教えてください。
Wantedlyのこの先やってみたいことを記載する欄に私が「障害を持ってる方、医療や心理的なケアが必要な方、移民・難民の方などハードルが高い方に対してハードルをなくしていきたい。」「教育とITを融合して授業をより楽しいものに変えたり、受講者のデジタルアップスキリングを支援したい」と書いていておそらくこれを見てCLACKのやりたいことと合うなと思って声かけてもらえたのかな?と思います。
ちょうどお声かけしてもらった時、CLACKがマイクロソフト社と連携して高校の先生方向けにAIトレーニングをするプロジェクトを立ち上げるタイミングで、お話しを聞いてみると私がやりたいなと思っていたことととても近しく、また自分の経験を生かせそうなポジションだと感じて、自分で言うのも変ですけど、適任かなと・・(笑)。そう思ってCLACKへの転職を決めました。
ー今CLACKではどのような仕事を担当されていますか?
転職を決めたきっかけにもなったマイクロソフト社とのプロジェクト「mirAI for Japan」に携わっています。
そもそもの立ち上げの背景としては、マイクロソフト社がAIのリスキリングを推進したいとのことで、デジタルと教育の分野で支援事業を行ってきたCLACKに声をかけてくれました。
私がジョインした時はほぼ何もない状態でしたが、そこから形を作っていって、「学習教材の開発」「先生方への研修」さらにその研修を受けてくださった先生方や生徒さんが継続して学習を続けられるように「継続学習パスの設計」と、主に三本柱でやっています。
プロジェクト始動から半年ほど経過した現段階で、東京と大阪で5校ほどの学校で研修をやらせていただいています。
5月下旬にはAI教育をテーマにしたオンラインシンポジウムに登壇させていただいたのですが、視聴をきっかけにいろんな県の学校や教育委員会からもお問い合わせをいただいているので、夏が明ける頃までには10校以上に学習をお届けできると思います。
高校生たちは卒業後、AIが不可欠な世界、AIと共存せざるを得ない世界に出ていくことになると思うので、高卒で就職したりする生徒もいる中で、このAI学習が生徒に届くことによってAIのリテラシーを身につけたり、AIの課題や仕組みを知れたり、どのように有効活用していけるんだろうと、学びに繋げてほしいです。そして、視野や将来のキャリアの選択を広げることや、AIを活用したスキルアップに繋がっていくといいなと願っています。

ー「mirAI for Japan」の仲間としてどんな人と一緒に働きたいですか?
個人的には「デジタルスキルを提供することを通して、生徒たちの視野や可能性を広げたい」「自分が教える側として、教育のアップデートをしたい」など、熱い想いがある人だと嬉しいです。
ざっくり言うと、日本の教育を変えたいみたいな熱い思いがある人ですね。ちょっと抽象的すぎるかもしれませんが、具体的なスキルももちろん大事ですが、ちゃんと想いがある人の方がマッチすると思います。
AIの授業をやるというとハードル高く感じると思うんです。私も最初AIって聞いたとき自分にできるのかなって思ったんですよ。AIのエキスパートでもなかったですし。
なので、私も自分でAIについて勉強するところから始めて、社内で生成AIのR&Dなども行っていたので、自分で情報を集めたり、社内の人から教えてもらって新しいAIをどんどん試していきながら、知識を少しずつ広げていきました。自分が学んだ中でどの部分を学校の先生方にお伝えできるか、先生方から生徒に授業してもらう時にどんな内容だったら刺さるかなと考えてやってきました。まだまだ始まったばかりのプロジェクトで、高校や先生ごとに合わせて調整していくことも多いので、一緒に学びながらやっていけるような人がいいですね。
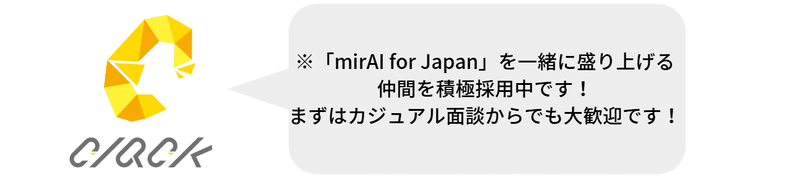
ーCLACKのカルチャーとしては、どんな人が合いそうでしょうか?
CLACKは、草の根をもともと大事にして、一人一人の生徒、一校一校の学校との連携をとても大事にしている組織だと思うので、メタレベルからプロジェクトを動かせます、みたいな人じゃなくても、一つ一つの小さい変化に気づけたり、どのように変化を起こせるかを考え、子どもたちや先生方との関係性を築ける人ですかね。それがインパクトを起こせることに繋がるのではないかと思うので。
変化のきっかけ作りができる人や、人との繋がりを大切にできる人などが合うんじゃないかなと個人的には思います。
AI教育を全国へ広げていく原動力に!

ー最後に、小浦さんの今後の目標・ビジョンについて教えてください!
CLACKの中でいうと、「mirAI for Japan」を立ち上げて半年程経過して、やっと少しずつ軌道に乗ってきたタイミングなので、ここから今やってる教育者の教育という、先生方への研修をもっと広げていきたいです。
また、今後どんどん国単位でもAI教育に対して、ガイドラインなどを策定したり学習指導要領に入れたりと進んでいくと思います。まだ、AI学習の普及に取り組んでいる団体自体がすごく少ないと思うので、AI学習を広げようという動き自体を広げていきたいですね。
今後直接CLACKが生徒にAI学習を提供したり、他の団体にモデル化したものを提供するでも良いですし、「mirAI for Japan」からAI教育を全国へ広げていく原動力のような存在になれたらいいなと思っています。
私個人で言うと、例えば長期入院や事情により登校するのが難しい人や不登校の人、海外にルーツがあって日本語で学ぶのが難しい人など、学びへのハードルが高い人たちにIT活用を通して学びを届けていきたいと思っています。
終わりに
認定NPO法人CLACKでは、一緒に働く仲間を募集しています。
ご興味のある方は、ぜひこちらをご覧ください。
みなさんのご寄付によってCLACKはよりよい機会を経済的・環境的にしんどさを抱える高校生に届けることができます。応援したい!と思った方はご支援いただけると非常に嬉しいです!!
