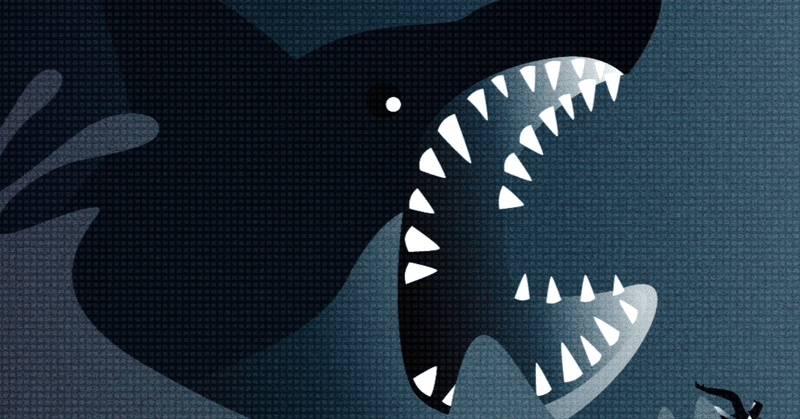
文体の舵をとる─ 『文体の舵をとれ』第七章②
●はじめに
小説のトレーニング本『文体の舵をとれ』を基にした習作です。今回は第七章「視点(POV)と語りの声」の追加問題を。前回までに取り組んだ課題は以下のマガジンにて。
なお今回の課題は、「逆噴射小説大賞2023」の作品に着手する前(七月中旬頃)に取り組みました。本章までに学んだことが、全て作品への血肉と化していれば良いのですが……。
※投稿作品は『文体』マガジン以下の二本です。結果発表を今か今かと待っております。
●問題
第七章 視点(POV)と語りの声
四〇〇〜七〇〇文字の短い語りになりそうな状況を思い描くこと。なんでも好きなものでいいが、〈複数の人間が何かをしている〉ことが必要だ(複数というのは三人以上であり、四人以上だと便利である)。出来事は必ずしも大事でなくてよい(別にそうしてもかまわない)。ただし、スーパーマーケットでカートがぶつかるだけにしても、机を囲んで家族の役割分担について口げんかが起こるにしても、ささいな街なかのアクシデントにしても、なにかしらが起こる必要がある。
今回のPOV用練習問題では、会話文をほとんど(あるいはまったく)使わないようにすること。登場人物が話していると、その会話でPOVが裏に隠れてしまい、練習問題のねらいである声の掘り下げができなくなってしまう。
追加問題
問一※について、三人称限定ではなく一人称で、別の物語を声にしてみよう。もしくは、事件や事故の物語を二回語ってみること。一回目は遠隔型の作者か取材・報道風の声、二回目は事件・事故の当事者の視点から。
あまり好みでない様式や声があって、その苦手な理由を見つけたい気持ちが少しでもあるなら、おそらく再度それに取り組んだほうがいい(ちょっと食べてみたらタピオカが好きになることもあったりするのだから、ね。)
(※問一:ふたつの声)
①単独のPOVでその短い物語を語ること。視点人物は出来事の関係者で──老人、こども、ネコ、なんでもいい。三人称限定視点を用いよう。
②別の関係者ひとりのPOVで、その物語を語り直すこと。用いるのは再び、三人称限定視点だ。
● ①取材・報道風の声(三人称限定視点)
琵琶湖に巨大鮫が現れたのは、丁度800年振りの出来事であった。その史実は鎌倉時代に記された『琵琶湖畔異変記』に認められるのみだが、青春をボート競技に捧げ続けた彼らのほとんどは、そのような歴史を知る由もなかった。地方局の一クルーに過ぎない木島も同様だ。
ダブルスカル部門の最中、事件は突然起こった。
最初の犠牲者は、先頭を独走していた一団だった。中継ヘリから目視できるほどに巨大な背びれが一瞬見えた途端、突然それは姿を現し、船頭の下山に襲い掛かった。船体は大きく姿勢を崩し転覆。足場を失い落下した相方の守川も、水面に顔を出した途端、無数の牙に襲われた。ありえない。木島は我が目を疑った。
一艘、また一艘と異変に気付き、ボートは方々へと散らばっていった。無慈悲にも遅い者から餌食となっていく。普段は静寂に包まれている琵琶湖は地獄の様相を呈していた。試合にあるまじき惨劇の最中、木島は目を背けずカメラを回し続けた。それこそが己の使命。そう自分に言い聞かせながら。
その最中、一艘のボートだけが異なる動きを見せていた。針路を変え、地獄の中心地へと進む二人の選手──槙野と永田に、木島は焦点を合わせた。顎を全開にして向かってくる鮫に対し、彼らが減速する様子はみられなかった。猛烈に回転する四本のオールが車輪のような軌道を描く。非常事態の中とは思えない優雅な動きに、木島は息を呑んだ。
牙を向いた鮫の大口に、船頭の槙野は二本のオールを突き立てた。我が目を疑う暇もなく、オールが上下の顎を抉り、どす黒い血が噴き出した。レースの破壊者は、あっさりと湖底へと沈んでいった。
● ②当事者の視点(三人称限定視点)
槙野の集中力が途切れるのも無理はなかった。
先頭をキープしていた下山が、目の前で息絶えたのだから。しかも、犯人は大きな魚。槇野の目には鮫にしか見えなかったが、琵琶湖に鮫など居る訳がない──いや、いる!確かに、眼前に!
ボートから投げ出された下山のペア──守川が水面に浮き上がった。助けを求める声を発していたのだろう。だが、声は届くことなく、守川は鮫の餌食となった。飛び散った血飛沫は、即座に湖へと溶けていった。
後続を走っていた槙野のライバル達は、一目散に散り散りになった。皆が我先に逃げようとしていた。逃げ遅れた者から餌食となる。速さは命に直結する。敗者たちは次々に沈んでいく。
息絶えるライバル達。最早レースは続行不可能。
槇野は焦った。そして、怒った。
水中で鮫に人間が敵うだろうか?無理だ、と大抵の人は考えるだろう。だが、彼らにその理性的な思考は残されていなかった。
覚悟を決めるしかない。槙野は相棒の永田にサインを送る。
「旋回」。
永田は顔を顰めながら、巧みな方向転換で、船を鮫の正面に位置取らせた。いつだって自分の無茶に付き合う永田に、槙野は心の中で感謝の念を送った。
鮫が迫ってくる。肉体の限界を超える猛スピードで漕ぎ、鮫に向かう。獲物を前にして、鮫は大口を開けて飛び上がった。
この瞬間を待っていた。槙野は雄叫びを上げ、握った二本のオールを顎に突き刺した。一本は上顎、もう一本は下顎。超人的な力が鮫の口を穿ち、巨躯は悶えながら沈んでいった。
●振り返り
「第七章」そのものに対する振り返りは前回行ったため、今回は特になし。強いて言えば……これらの問題に取り組んでから小説を読む際、視点を過剰に気にするようになってしまった気がする。
そして、今更ながらに思う。三人称は難しい……!惰性で書くと絶対にこんがらがる。強く意識しないとまずい。
<つづく>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
