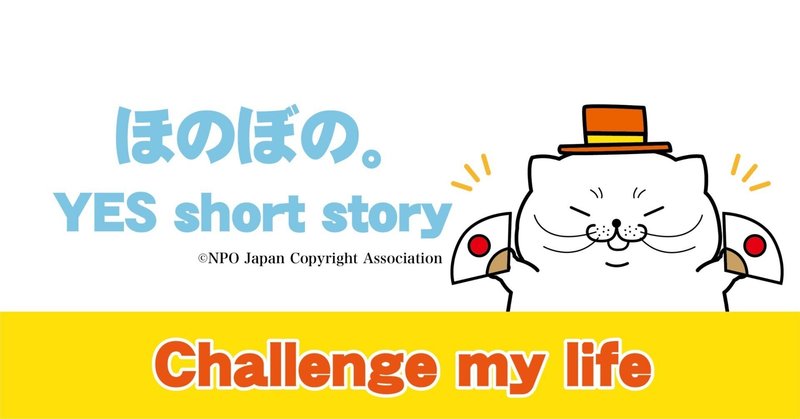
100.2.noteデビュー3か月目、勝手に自分だけの100作品記念・「かなしいおうち」
未亡人たちの村
もしかすると、あれから65年は過ぎたのかもしれない…。
65年前のこの村には約20数件の住宅が並び、ほとんどの入居者は20歳代と若く逞しい人々が住んでいた。まだ、戦争が終結して10年過ぎてはいないのにみな生きるのに必死な時代だった。
もちろん、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどない。あたり一面は畑と山々が見え、まるで大草原の中にポツンと集落が存在していた。何よりも、みな健康でいきいきとして若い。
この村には新築と同時に入居したものばかりで世代も同じくらい、子どもたちも同じくらいだった。子どもたちの楽しい遊びは、広い畑や山に登ること。鳥や虫たち、花たちと語り合うこと。
考えてみたら、この村の人々にとって人生で一番幸せなときだったのかもかもしれない。
毎日の時間は止まり、父や母とも永遠に暮らせる幸せ時間だった気がする。
建物は平屋だが、増築して5DKという広さを誇る。私たち兄弟にしてみれば大豪邸のような天井の高さと広さを感じていた。それだけ小さな身体をしていたのだろう。
私たちには時間がたっぷりあったような気がする。なんといってもテレビはないゲームやインターネット、電話機すらない時代だったからだ。
この村の人々は、異常なくらい仲が良い。醤油や味噌がなければお互いが分け合い。冷蔵庫がないため、近所からのいただきものの交換も多い。まるでおさな友だちの関係のような不思議な村だ。
とにかく、仲が良い。
やがて当時の20歳代の村人は、65年過ぎれば80歳代~90歳~100歳となる。少しずつ当時の若者たちはこの世を去っていく。すると、同時に建物は壊されていき、家の周りは時代とともに建物が建ち始め、駐車場となった。
現在は、たった4棟しかなくなってしまった…。
本当はこのまま家を残したくて闘ってきたが法律上、一代限りという条件のもと、私たち兄弟はなくなく諦めることにした。本当は裁判でもすれば違ったのかもしれないが、天にいる父や母にしてみれば、「もう、いいよ!」という声が聞こえる。
そして、現在も未亡人の村のままそのまま残っている。
世の中、男性が先に旅立ち、残されるのはいつも女性。この村は未亡人だけが最後に支え合い、助け合うわずかな人たちだけが残った…。
父はこの村で94歳まで生きた。母は87歳まで生きた。
私たち兄弟はここで育った…。
3度目のお別れ

©NPО japan copyright association Hiroaki
父が亡くなり、私たち兄弟の心の中に空洞ができた。あれから何年も過ぎたはずなのにその穴を埋めることができない。そして母がなくなり、もうひとつの空洞が生まれた。その空洞にはいつも冷たい風が吹き流れ、風は行き来している。
私たち兄弟の哀しみはいつ癒されて終わるのだろう?もしかすると私たちがこの世を去るまでこの空洞は埋まらないのかもしれない。
そして、さらに追い打ちをかけるかのように3度目の空洞、お別れが来た。私たち兄弟は約3か月間かけて父や母の遺品、家具やすべてのものを処分した。膨大な処分品で大型トラックにしたら2台か3台分あるかもしれない。しかし、すべて業者に任せず弟が最後の供養だといって少しずつ自分で処分した。なんといっても約65年分の荷物である。
布団や家具ひとつひとつに想い出が残る。天井や床のシミ、柱の傷跡、ペンキや壁紙の剝がれ、古くなった畳や床、壊れかけた扉、使われなくなった風呂場、照明など一つひとつに魂を感じる。
何もない部屋に横になる。子どもの頃にあれほど高いと思っていた天井が低く感じる。
この部屋で父や母、弟と生活し一緒に寝ていた。何もない部屋だが風の音が聞こえる。電気もなくなった部屋だがわずかな光が注ぐ、床や壁からはぎしぎしとしなる音がする。
目をつぶると様々な音があることに気づく。部屋にそそぐわずかな光が移動する。まるで時間が止まってしまったような感がした。
そばには、不思議に、笑顔の父や母の気配を感じる。風の音や光の動きで私に何かを伝えようとしているのだろうか。
小さな庭に出ると、母が好きな花々がまだ咲き誇っている。弟の妻が植えてくれた苺や菫、松葉ぼたんやゴーヤの花もまだ咲いている。何もなくなった家なのに花畑に囲まれているような…。もしかすると、わざと母が咲かし続けているのだろうか?
この家には本当に誰もいないのだろうか?
この家はまだ生きているように思える…。
どうして?
何か声が聞こえるから…
何か語りかけているように思えるから…
かなしいおうち
私は何度も家を買い、売り、処分してきた。引っ越しに引っ越しを重ね続けた。一戸建の家もあればマンション生活などもしてきたが、特段家に対する愛着や執着など残ってはいないが、この父や母がいた、私たち兄弟が育ったこの家には異常な愛着が残った…。

©NPО japan copyright association Hiroaki
家って触れると声が聞こえる
こんなにも古くぼろぼろの家だが
人の想いが刻み込まれている
家にも魂、心がある
家だって泣くときがある
家だって笑うときもある
家だって幸せだった時がある
家は私たちに何を思うのだろう
家が、ありがとう、さよならといった。
私たちには還る故郷がありません
しかし、どうしてこんなに悲しいのでしょう?
父の生前の言葉がよみがえる。
「家族というものはお互いに近くに住んでいつでも会えるようにしてほしい!」「家族は離れ離れになってはいけない」「支え合えることが本当の幸せだ」「だから、お前たち兄弟もそばで暮らしてほしい…」
大正11年12月10日に生まれ育った父は、樺太開拓団としてこの地で生まれ育った。当時の写真を見ると驚くほど街は整備され、映画館や散髪屋、喫茶店やスナック、などがあり都会の暮らしのような街並みだった。
やがて、父が11歳のときに祖父が亡くなり、実母と病気の兄、幼い妹と4人で過酷な生活をしていた。そして、戦争がはじまり、父は軍隊に入隊、実母は満州で亡くなり、兄と妹と、弟と離れ離れとなる。
私たちの本家の故郷は樺太にある。
その深い悲しみが、私たち兄弟に父が語り続けていた唯一の遺言となった。
父は、年老いてからもその故郷の記憶に残る家の絵を一枚残した。私は幼きながら意味も分からず父がクレヨンで描くその絵を不思議そうに眺めていたことを想い出す。

本年度の9月30日に実家の引き渡しとなった。何もない家の中で私はふと気づいた。家には想い出(たましい)があるということを。今まで家に対する執着や情などないと思っていたが、自分たちが育ったこの場所には言葉にならないほどの無限の想い出が残っていることを…。
最後の日、弟と、弟の妻と3人で残された最後の村人2人に挨拶に出向いた。年老いた村人は二人とも涙して、別れを惜しんだ…。
もしかすると二度と会えないかもしれない、今が最後になるのかもしれない。私たちの父や母と仲の良かった最後の親友たちである。
私たちも涙が止まりません。
こんなにも悲しいことなのでしょうか?
父が一生懸命になって、家の絵を描いていたことを今更ながら想い出した。それは、もしかすると二度と戻れない故郷の自分の家を描いてそばに置いときたかったのかもしれない。
(昭和の終わりにようやく、父は許可が下りて樺太に出向くことになった。せめて祖父のお骨だけでも日本に持ち帰りたかったが、真と鼻の先でソ連兵から入ることを禁じられ目的はかなわなかった…)
父は、家には想い出(たましい)があることを知っていた。故郷を失った父がせめて残せるものは記憶の中の一枚の絵だった。
そう、家が故郷だったのですね。
終戦となり、それから長男はなくなり、その後、私と弟が生まれた。
父や母にとって、生まれて初めての幸せのとき、私たち兄弟が父や母の幸せ。あとは何もいらない。家族が一緒に暮らせるのですから。私たち兄弟が父や母の幸せかもしれないが、私たち自身がそのような父や母のもとに生まれ平和に育てられたこと、何よりも私たちの一番の幸せだったと今更ながら思う。
私たち兄弟の故郷もここに在る…。
私は父のように絵が描けませんが、父から写真技術を教わった弟が最後の写真を撮りました。
そして、よくこの写真と絵を見るとあまりにも似ていることがわかりました。父はこの平屋が気に入っていたのでしょう。また、この街に住む理由も感じます。山々に囲まれた広大な盆地、雪が降るとまるで樺太と同じような風景となります。ここを父は最後の棲家、安住の地として選んだのでした。それがこの一枚の写真と父の描いた絵で感じるのです。
そう、ここが第2の樺太、第2の故郷だったのですね。
私たち兄弟の3度目のお別れです…。
こんなにも心が痛むなんて、思ってもいませんでした。
この街は、冬の時期は天気のよい日が多く、空気も澄んでいるため、遠くの景色がよく望めます。近くの山からは、丹沢山塊、南アルプス、日光方面などの山々が眺望できます。数多くの山々に囲まれていてまるで大自然の宝庫のようです。
まさに、樺太(現サハリン)にある、鈴谷岳(すずやだけ)は、樺太島の南部鈴谷山脈にあり、同山脈で一番高い山である。 ロシア連邦では、1890年に樺太島に訪れた文豪アントン・チェーホフにちなみ、チェーホフ山 (пик Чехова) と名付けられている。よく似ている地形と風景でした。
祖父のお墓は樺太に在り、祖母は満州のどこかに埋められたままお墓がない。私たち兄弟で父と母が眠るお墓に祖父母の名前を彫り込むことにした。新しいcoucou家の本家となる。

3つの空洞とともに生きる
ごきげんよう!coucouです。長い長い文章におつきあいしていただいて心から感謝申し上げます。
あっという間の3か月、note90日を超えました。タイトル通り、自分だけの勝手な「100作品記念」100.2です。このYES short storyのほとんどが実話の物語です。登場人物や背景など動物や自然などに例えて表現していますが、すべてリアルな物語です。
今回はcoucou一族のお話ですが、私の父の代で初めてのお墓を建てました。この地が第2のcoucou一族の故郷となります。
今、私たち兄弟は父の言われた通り、いつでも会える場所に住んでいます。家族兄弟は離れ離れになってはいけない、当時の父の残念さ、無念さがよくわかります。
私たち兄弟は言葉にならないくらいの深い愛情で育てられ、人が信じられないほど、命がけで守られてきました。
人は誰もが「94歳まで生きたのだから十分だった」「往生したね」と褒めたたえますが、私たち兄弟はその誉め言葉が嫌いです。
なぜかというと、人には誰もに深い、深い物語があって、その物語を知る人はいない。あまりにも、辛く苦しい人生を送った父や母のことを考えると残念で仕方がありません。よく、生きてきたと思います。
ですから、私は父と同じくらいにこの世を去った家族の方々には「とても、残念です」とお伝えしています。
なぜなら、家族にとってとても残念なことだからです。
私たち兄弟はこの3つの空洞を抱えながら、塞ぐことなくいつまでも大切に生きて行こうと考えています。
私たちがこの世を去るときに、また父や母ともう一度物語を作ろうと考えています。だから、逢いに行くことをとても楽しみにしているのです。
さよなら、わがふるさと、わがおうち。
※私の弟からラインが入りました。
我が家よ。
僕らの永遠の棲家、我が家よ。
雨の日も風の日も僕らをいつも一生懸命支え、守ってくれた。
未だ幼く辛く泣いて帰った時もいつも優しく迎えて入れてくれた。
思い出が沢山あり過ぎて語れない。
父が死に母が死に、我が家よ、貴方とは三回目のとても辛いお別れだ。
父、母をいつも優しく包み、僕ら兄弟をずっと力強く助けてくれた。
今頃になってその事が良くわかる。
そして、最近思うが、我が家は僕らをどんな風に見ていてくれたんだろう?
果たして僕らは良き家族でしたか?
幸せに暮らしましたか?
少し聞きたい。
我が家よ、貴方は僕らのとても大切な家族でした。
有難う。
またしても、涙がとまりません…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
