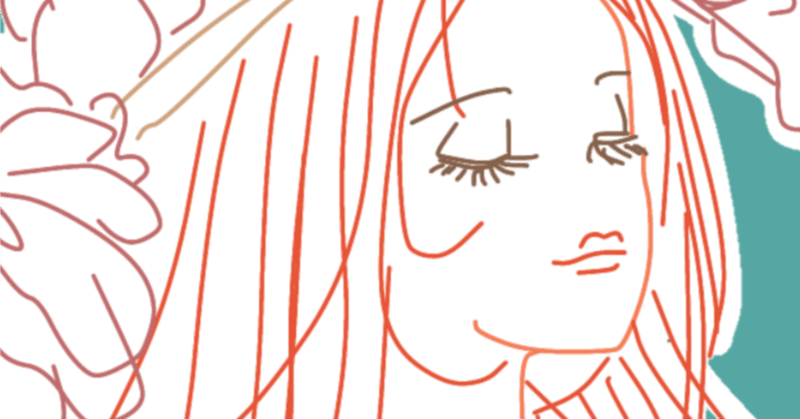
まちづくりはスーパーヒーローがいたから成功するのではなく、まちづくりが成功する地域は制度的にスーパーヒーローを作り出すのかも仮説〜木村隆之. (2015). 「まちづくり研究およびソーシャル・イノベーション研究の理論的課題に関する一考察」.
従来のソーシャルエンタープライズ論は「社会起業家」の特異な能力に偏っていた
木村隆之. (2015). 「まちづくり研究およびソーシャル・イノベーション研究の理論的課題に関する一考察」.『経営学論集』第26巻第1号を読みました。
日本でもゼロ年代から盛んになったまちづくりにおける社会的企業、ソーシャル・エンタープライズの研究だが、本論文は、まちづくりの成立プロセスの説明が社会起業家という特異な能力者の存在に依存しがちであった点を指摘する。
まちづくり研究によって行われてきた事例蓄積と,ソーシャル・イノベーション研究において提示される,社会企業家によるプロセスモデルが持つ理論的限界を指摘する。それは、「まちづくり」というものを社会企業家という特異な能力を有する主体に還元する形で説明する「スーパーヒーロー仮説』にあった(2節)。そこでは,予定調和な記述の再生産が行われており、類い稀なる社会企業家が、社会問題を掲げその解決に向けてイノベーションを創出し彼もしくは彼女の情熱や価値観に共感するアクターを巻き込むことで地域再生が実現するというストーリーが繰り返される。この、まちづくりを成功させる「スーパーヒーロー仮説」は、ヒロイックな表現故に読み手に感動を与える
代表的なまちづくり事例研究には共通して,類い希なる社会企業家(スーパーヒーロー)が現れ、地域課題を掲げ、その問題解決に力的な運動を展開し。「情熱」や「価値観」を共有することによってステイクホルダーを味方につけ、まちづくりを成功させるという「スーパーヒーロー仮説」が背後に存在している。「スーパーヒーロー仮説」を背景に持つ研究は、社会企業家という卓越した存在を前提として据え、彼もしくは彼女らが価値観を共有させて人を動員し、まちづくりに成功するという物語構造に基づいて事例を分析する(eg.Steyaert, 2007;高橋・松嶋,2009)。そのため、社会企業家は如何に「社会企業家」となるのか、未利用の資源としてのステイクホルダーは如何に発見され動員されるのか、「まちづくり」のメカニズムとは何なのかを説明することが出来ない。
この理論的限界を超えるべく、経営学において,この「まちづくり」という現象の理論化を検討する研究が「ソーシャル・イノベーション」である。ソーシャル・イノベーションとは「社会的ニーズ・課題への新規の解決策を創造し、実行するプロセス」と定義付けされる(PhilsJr.et al, 2008)。
類い稀なる社会企業家を出発点に据え,彼もしくは彼女が、価値共有を下に正当性を獲得し,地域資源である協力的なステイクホルダーを再結合もしくは新結合することが強調され、それらが価値共有を遂げる、つまり社会企業家の理念に染め上げられたとき制度変革が生じるという説明となる。この様に、素朴な事例記述を超えるべく、理論的体系化を目指したソーシャル・イノベーション・プロセスも,最終的には既存のまちづくり研究に見られる「スーパーヒーロー仮説」に回帰する。(略)例えば,谷本・大室・土肥(2006)は、特定非営利活動法人北海道グリーンファンドが日本で初めて市民による風力発電事業を立ち上げた事例を基に企業家とステイクホルダーの相互作用という具体的行為からまちづくりの現象を捉えようとしている。そして,市民の反原発への意識と初の市民風力発電事業への賛同を背景に,ステイクホルダーが協働し合う関係を「ソーシャル・イノベーション・クラスター」という構図で説明する。大室は,この「ソーシャル・イノベーション・クラスター」の成熱に,社会的課題に反発するステイクホルダーの参加を指摘しているが、その動機付けとして「社会的課題を解決したいという想い」を強調する(谷本他,2006,p.52)。
社会企業家(もしくは社会的企業)がステイクホルダーに社会的価値を「わかりやすく提示する」ことによって,ステイクホルダーの意識が変化し,共購し、自ら係り合いを持つとされる(前述,p.145)。しかし,これら具体的記述においても,社会企業家がステイクホルダーの協力を獲得する根拠に「社会的課題を解決したいという想い」を据えることで「スーパーヒーロー仮説」に回帰している。つまり、「ソーシャル・イノベーション・クラスター」において重要だとされるステイクホルダーの巻き込みプロセスにおいて認知的正当性を重視するために,実践レベルにおいて地域内に存在する非協力的なステイクホルダーに如何なる対応行動がなされているのかを説明できていない。この理論的課題は,谷本自身も認めており、松嶋・高橋 (2007)を引き合いに出し,「制度的企業家が多様な主体の利害との関係的なルールを結んでいく動的なプロセスを読み解いていく視点」が不十分だと述べている(谷本,2009,p.34)。このように,既存研究では予定調和的に企業家とステイクホルダーが用意された「スーパーヒーロー仮説」の下で説明するため,企業家とステイクホルダーの行為を隠してしまう
それゆえの限界もあったと指摘する。
この理論的限界について,谷本(2009)はソーシャル・イノベーション研究における理論的課題として,「社会企業家が多様なステイクホルダーとの関係性のなかから、どのようにイノベーションを生み出し,社会変革の可能性をもたらしていくのかに関するプロセスを説明することができない
その上で本論文では、ソーシャル・イノベーションの独自性とは、単なる資源の新結合による価値創出ではなく、ソーシャル性、つまり社会性、公共性の達成にこそあるのだとみなすことで、スーパーヒーロー仮説に回収されない理論化が可能であると主張する(P2)。
スーパーヒーロー仮説に頼らないソーシャル・イノベーション論
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

