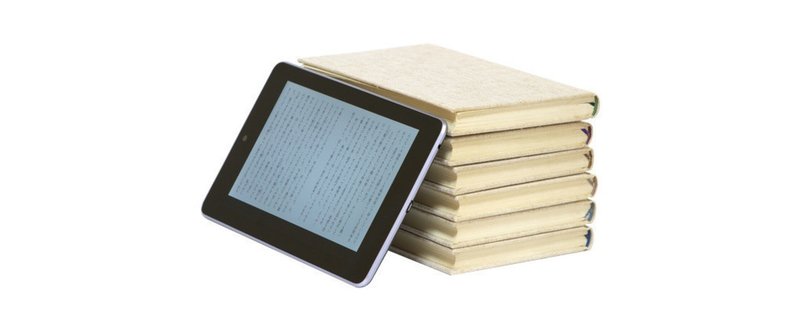- 運営しているクリエイター
2014年12月の記事一覧
未(ひつじ)年をむかえるにあたってもう一度読み直ししてみませんか──村上春樹『羊をめぐる冒険』他
「羊の性は死を聞いて懼れざるものなり」
「孔子曰く、土の精は羊となる」
という説を紹介したのは南方熊楠(『十二支考』)ですが、村上さんの作品に登場する羊男たちもまた、土や地下(地下室)が似合っているように思えます。
大きく村上さんの作品に描かれた羊男さんは二つのグループの分けられそうです。ひるつは以前紹介した『羊男のクリスマス』に登場した羊男さん(たち)です。作品名ではこの『羊男のクリ
夜中にふと目覚めた時に感じるなにかの気配のように、すぐれた童話の言葉は私たちの心の奥にそっと棲みつくのです──ジャンニ・ロダーリ『兵士のハーモニカ』
とても多面的な世界を私たちに見せてくれるロダーリさんの作品です。心に残る言葉がたくさんあります。
たとえば
「おそらくそれは、アウレリオ王子が生まれてはじめて使った「考える」という言葉でした。もしかすると、いまさっき流した大量の涙が王子の脳を洗ってくれたのかもしれません。あるいは、深い悲しみと愛が、これまでの〈頭の悪い王子〉というあだながぴったりだっためんどうくさがりの王子に、新たな人生の
美しい心とはなにか……幸福とはなにか……そして神とは何か……根源的な問いがここにはあります──オスカー・ワイルド『幸福な王子』
「生きて人間の心をもっていたころは、ぼく涙の味などしらなかった。(略)廷臣たちからは幸福の王子さまと呼ばれていたし、ほんとうに、ぼくは幸福だった。もし快楽が幸福であるとすればね。そんなふうにぼくは生きて、そんなふうに死んでいったの。ところが死んだ今となって、みんなにこんな高いところにのせられたものだから、ぼくは自分の町の醜さやみじめさがすっかりみえてしまうのだ。そしてぼくの心臓は鉛でできてるく
「羊男世界がいつまでも平和で幸せでありますように」という最後の言葉がジーンと心に響いてきます──村上春樹・佐々木マキ『羊男のクリスマス』
暑い暑い真夏の盛りに、羊男さんがクリスマス用の音楽の作曲を頼まれたところからこの物語は始まります。
(暑い中の羊男のコスチュームはとてもつらそうです……エアコンもないようです)
けれど、音楽はなかなかできません。羊男さんは、それは夜にピアノを弾くと大家さんに怒られるのでうまく進まないからだと思っていました。
(大家のおばさんの怒った姿は迫力満点です)
でも、時間は飛ぶように過ぎ、もうす
イエスの誕生日はどのようにして祝われるようになったのか、そして今のクリスマスの姿は……これはクリスマス大百科です──嶺重淑・波部雄一郎『よくわかるクリスマス』
「誕生日を祝う習慣は古代オリエントやギリシア、ローマの世界では存在していた。しかし、これはキリスト教の習慣ではなく、異なった宗教を信仰していた人びとの習慣であった。むしろ、初期のキリスト教徒たちは誕生日を祝う習慣を批判的な目で見ていたようである」
キリストの誕生日が12月25日になったのは、ユリウス歴で冬至の日であり、「不敗の太陽神の祝日」であったことが大きな理由だったそうです。またこの日と
判断をしないですむという安易な判断停止・思考停止をメディアにもたらす自己規制という罠……──森達也『放送禁止歌』
一九九九年五月二三日午前三時過ぎに1本のTVドキュメントが放送されました。著者の森さんが制作した『放送禁止歌~唄っているのは誰? 規制するのは誰?』です。放送禁止歌を放送するというなんとも奇妙な番組はどうやって誕生したのしょうか。この本はTVディレクターとしてこのテーマに取り組み、放送へといたった道のりと放送後の反応までをふくめてまとめ上げたノンフィクションです。
ところで「放送禁止歌」
人と人が向き合うときに生じる感情のすべてが、凝縮されて描かれているのです──太宰治『駆け込み訴え』
息せき切って一人の男が飛び込んでくる。
「申し上げます。申し上げます。旦那さま。あの人は、酷い。酷い。はい。厭な奴です。悪い人です。ああ。我慢ならない。生かしておけねえ」
と始まる、独白体の短編小説です。
訴え出たのはユダ、訴えられたのはイエスです。ユダは思っていました、ほかの弟子に負けずに、いえそれ以上に献身的に主に仕えていたのに、少しも自分のことを考えてくれないと……。
「私はあ
読むたびに物語のその姿、意味をなんどでも変えてくるようなファンタジーです──フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』
トムにはつまらない夏休みになりそうでした。大好きな裏庭で思いっきり遊ぼうと思っていたのに弟がハシカになってしまったのです……。トムへの感染を心配した両親はトムをおじさんのところへ預けることにしました。でもおじさんのアパートには庭なんてありません。トムは庭で遊ぶのが大好きだったのに……。
気が進まないトムがおじさんのアパートを訪ねた時にすぐに眼にはいったのが大きな古時計でした。でもこの古時計
古き日本を知るということではなく、今の私たちの位置を映し出す助けになるものなのです──柳田國男『明治大正史 世相篇』
歴史の綴り方というものにこういう方法があるということを今さらながら感じさせるものでした。ここには(変ないいかたですが)柳田さんが見て、生きた事実しかありません。それが生活史というものだということに改めて気づかされました。
ある節の書き出しに何気なく
「明治三十四年の六月に、東京では跣足(はだし)を禁止した」
と書き出されていますが、それまで跣足は一般的だったのでしょうか。柳田さんはそれ
なんのための経済(成長)であるのか、どのような世界を求めているのかを私たちは忘れてはいけないのです──宇沢弘文・内橋克人『始まっている未来』
本年9月に鬼籍に入られた経済学者・宇沢弘文さんと経済評論家・内橋克人さんの対談を中心にして編まれた本です。
宇沢さんは環境問題にも積極的な発言をされていた人ですが、この本でも市場原理主義のもたらす荒廃を激しく論難しています。ミルトン・フリードマンをリーダーとする市場原理主義者、規制緩和を中心とする構造改革のシナリオ作りをした竹中平蔵さん、中谷巌さん、島田晴雄さんなどを徹底的に断罪しています
読み手のほうにも本との出会いの運命がある。そして自分たちの運命であっても、それには時が経ってからしか知ることができない部分があることも確かなように思うのです──木田元『なにもかも小林秀雄に教わった』
木田さんの思想遍歴、哲学者になるまでの道のりを、読んだ本(読書)という視点で綴ったこの本です。以前に紹介した自伝『闇屋になりそこねた哲学者』とあわせて読むと、今年の8月に鬼籍に入られた哲学者の歩まれた道がよりわかるようになるのではないかと思います。
闇屋時代(?)にむさぼるように読んだ芥川龍之介、夏目漱石に始まり、生涯の格闘の相手となった哲学者マルティン・ハイデガーの読解にいたるまで木田
間違えた政治はなぜ行われてしまったのか。なぜそれを正すことはできなかったのかを考えてみる必要がある──保坂正康・姜尚中・雨宮処凜『「ポスト戦後」を生きる』
歴史家・保坂正康さん、社会学者・姜尚中さんそして作家・雨宮処凜さんを迎えての、2013年11月14日に開催された道新フォーラム「現代への視点~歴史から学び、伝えるもの」(同フォーラムは2009年から毎年開催されています)の内容を収録したものです。
毎年といってもいいくらい問題になる首相・閣僚の靖国参拝問題について、日本側が靖国とアーリントン墓地を同一視していることの「無神経とも言える歴史
時流に流されることなく自らを鍛え抜いた叡智であり、良識(コモンセンス)というものがここにはあります。そしてこのような人を持ったことを私たちはもっと誇っていいのではないでしょうか──石橋湛山『湛山回想』
この人が病に倒れずに首相を続けていたら現在の日本は大きく変わっていたのではないでしょうか。少なくとも岸信介さんが首相になるのはもっと遅れたでしょうしたでしょうし、60年安保もずいぶんと様相が変わっていたでしょう。(石橋さんは安保採決に議決欠席をしました)池田勇人さん、佐藤栄作さんの政権もどうなっていたかわかりません。
歴史にイフは禁物ですがこの人の下で日本の進路が決まっていたらと思う人
“社会を作るには”私たちはどのようにすればよいのか、またそれ以前にどのような社会が望ましいのかを考える必要がある──小熊英二『社会を変えるには』
いろいろな読み方ができる本なのではないかと思います。民主主義とりわけ代議制民主主義が生まれてくるまでの思想史をコンパクトに紹介しているところは、民主主義を考え直そうという時には的確な入門になっていると思います。
また、小熊さんの実践活動に裏づけられたデモ等の意味付けもとても説得力があります。
「「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作れる」と答えた人がいました