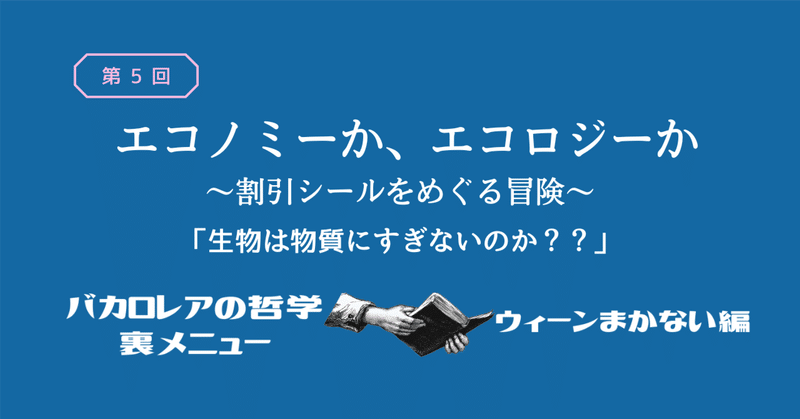
エコノミーか、エコロジーか ~割引シールをめぐる冒険~|『バカロレアの哲学』裏メニュー|ウィーンまかない編
今回の哲学問題「生物は物質にすぎないのか?」
『バカロレアの哲学』の裏メニュー「ウィーンまかない編」。本連載では、著者・坂本尚志さんのウィーンでの生活と、実際に出題されたバカロレアの哲学問題を引き合わせて記録していきます。
今回は、毎日の食卓に欠かせないスーパーの安売りと割引シールについて。

農業大国オーストリア
安くておいしいものが食べたい。体にいいものであればなおよい…。図々しい願望かもしれませんが、食事担当としてはどれも気になります。オーストリアは農業国でもあり、野菜や肉(そしてワインやビール)の多くを自国で生産しています。穀物自給率は88%(2018年、農林水産省調べ)です。完全ではありませんが、自給自足に近い状況にあります。
ウィーンから郊外へ行くと、すぐに田園地帯が広がり、麦や野菜、そしてワイン用のブドウ畑がひろがっています。小さな農業大国としての姿を身近に感じることができます。
オーストリアは有機農業の先進国でもあります。EU諸国からの安い農産物に対抗するために、有機農業へのシフトが進んでいます。スーパーのプライベートブランドでも有機農業によって生産された野菜や肉、加工食品が並び、消費者にとっては多くの選択肢があります。ウィーンに来て特に驚いたのが、加工食品にも自国産が多いことでした。オーストリア産の食品にはそれを示すマークがついています。冷凍食品も同様に、オーストリア産の野菜や肉を使用しているものが大半です。冷凍食品にも「地産地消」が徹底されていることがうかがえます。
複数買いと割引シール
そしてもうひとつ、オーストリアのスーパーで目につくのが、割引方法の多様さです。日本なら目玉商品が日替わり、週替わりで値下げされますが、その多くは一品あたりの値段です。しかしこちらでは(フランスでもそうでしたが)、2つ買うと半額、3つ買うと半額、といった複数個の購入で値下げする安売り方法をよく見ます。ビールなどは500ml缶を24缶買うと半額、といった売り方をします。

私は値札を見て「安い!」と思い、しかし安売りの条件を確認してやめる、ということがよくあるのですが、賞味期限が長い食品や、消費のスピードが速い食品については、このような売り方は合理的でしょう。
別の割引方法として、割引シールというものがあります。路上で配られている無料の新聞にスーパーの割引シールがついていることがあるのです。好きな商品に自分で貼ると、25%引きになります。セール品などは割引シールの対象外ですが、ここぞとばかりに高めの商品に貼り付けて買ってしまいます。普段買わないものを買っているという意味では、思うつぼなのかもしれません。主体的に選んでいるつもりでも、店に来て普段買わないものを買ってしまうというのは、まさに割引シールの戦略なのでしょう。しかしそれでもなお、このシールはなかなか面白いアイデアだと思います。

圧がすごい!冷蔵庫の鶏
もう一つの割引が、日本でもおなじみの、食品ロス防止の観点からの賞味期限の近づいた商品の割引です。肉や魚といった生鮮食品の場合は、消費期限前日が25%引き、当日が50%引きのことが多いようです。イースターの直後には、カラフルに色づけられたイースターエッグが半額になっていて、クリスマス直後のケーキの安売りを思い出しました。
つい最近買い物にいったときには、鶏一羽が半額になっていました。その日の献立の予定もすべて白紙に戻し、半額の鶏を買いました。賞味期限は多少過ぎても問題はありませんが、冷蔵庫に鶏がいるというプレッシャーから解放されるためにローストチキンを作りました。詰め物もせず、耐熱皿に下ゆでした野菜と下味をつけた鶏を入れて45分程度焼けばできあがりです。家族4人でおなかいっぱい食べて、残った骨を水洗いしてから水を張った鍋に入れます。ショウガ、ニンニク、ニンジン、タマネギ、セロリなども一緒に入れて数時間コトコト炊くと鶏ガラスープができあがります。鶏ガラスープは週末のお昼に、塩こしょうと醤油で味をととのえて、ラーメンのスープにします。
麺はオーストリアでよく食べられるヌードル入りスープに使われる細いパスタです。長さが5センチぐらいのこのパスタは、5分弱でゆであがり、パスタっぽさがそれほどなく、鶏ガラスープにもよく合います。乾麺やフライ麺の中華麺も試してみましたが、入手しやすさや価格の面から、この細くて短いパスタがラーメンのかわりにわが家では活躍しています。ネギ(若タマネギという名前で売っています)と残ったローストチキンを乗せると、おいしいラーメンになります。

こうして一羽の鶏を最後まで活用していますが、食品ロスを減らすだけでなく、おいしいものを食べられるのも楽しいことです。昨今食料価格がじわじわと上昇していく中で、節約しつつも豊かな食生活を送るために、今日も私は割引シールを探し求めているのです。
生物は物質にすぎないのか?
人間が、そしてあらゆる生物が生き続けるためには、その外部からエネルギーを取り入れることが必要です。動物の場合、そのエネルギーは他の動植物を摂取し、それを消化することによって取り出されます。生物が栄養をとり、生きていくこと、そして生殖によって増えていくことは、物理学、化学、そして生物学によって、物質のふるまいとして理解可能であり、記述可能です。その意味では、生物は物質にすぎません。デカルトにならえば、それは部品が集まって作られた機械のようなものであると言えるでしょう。
しかし、生物は単なる物質の集合ではないようにも見えます。たとえば一匹の猫を構成する物質をそっくりそのまま集めたとしても、それは猫ではありません。ニャーと鳴かない物質の集まりにすぎないのです。
ということは、物質の集まりと生物には差異があるのでしょうか。生物を生物にさせるもの、それを魂や活力という言葉で表現した哲学者もいます。一般にこの立場は生気論と呼ばれます。生物には固有の原理があり、物質とは同一視できないというのがその主張です。
問題に戻ると、「すぎない」という言葉が重要です。賛成と反対の二つの立場はそれぞれ「生物は物質にすぎない」と「生物は単なる物質ではない」と言い表すことができるでしょう。「生物は物質にすぎない」と主張することは、機械論の観点から見ると妥当です。しかし、遠い将来に、そのメカニズムが完全に明らかにされるかもしれないものの、生物の謎はいまだにすべて解明されたとは言えません。「生物は単なる物質ではない」という主張は、生物に物質を超えるなにものかを見出しています。生物は物質であるだけでなく、世界の他のモノとは異なる存在なのです。生気論の立場をとった哲学者たちによって、この主張は支持されるでしょう。
さらに言えば、生物の中でも人間に着目すると、反対の立場は異なる意味合いを帯びます。生物としての人間を理解するためには、その物質的なメカニズムだけでなく、人間に固有の概念や思想、制度や歴史まで考察を広げなければなりません。
生物を物質の集まりと同一視することは正当なのでしょうか。もしそれが不可能なら、生物は物質の集まりとどのように異なっているのでしょうか。言い換えれば、生物固有の原理とは何なのでしょうか。あるいは、生物固有の価値とはどのようなもので、どのようにして生まれてくるのでしょうか。
結局のところ、生物は物質にすぎないのでしょうか、それとも物質を超えるなにかなのでしょうか。
人間の根幹を支える食もまた、こうした哲学的考察の中で重要な位置にあるはずです。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
