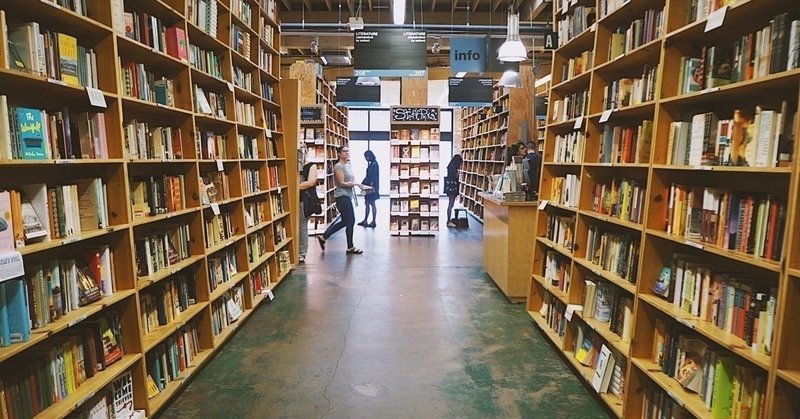
書店がいずれ必ず終わる理由
ぼくが出版社の社長をしていたとき、感じていた最大の欺瞞が「大量のムダを出す」ということだった。今の本は、例えば5000部刷ったとしたら、割合は色々あるものの、だいたい3000部——60%売れたら採算が取れるようになっていた。つまり、後の40%は廃棄されてもいいようになっているのだ。
なぜそうなっているかというと、そもそも本は、売れるか売れないか分からない状態で作り、本屋さんに卸さなければならない。そうして読者に買っていただく。もしそこで売れなかったら、本は出版社に戻ってくるので、あとは捨てるしかない。
これが本当にムダである。出版社にとってもムダなのだが、それ以上に読者にとってムダなのだ。なぜかといえば、余った40%を捨てても採算が取れるようになっているということは、その分が価格に上乗せされているということだからだ。つまり、ムダになった分のお金は他ならぬ読者が払っているのだ。
これは、全ての本においてそうだ。皆さんが持っている全ての本の裏には、捨てられていった大量のムダがある。そして、その捨てられていった大量のムダの代金は、皆さんが支払った。つまり、そういうムダがなければ、皆さんはもっと安く本を買えたのである。
ぼくは絵本を作っていたのだが、このムダが特に大きかった。なぜなら、印刷代や紙代、製本代が字だけの本よりかかるからだ。一冊当たりのコストが大きく、捨てることのムダもそれに伴って大きくなっていた。
絵本にとって、これはムダであるのと同時に大いなる欺瞞であった。なぜかといえば、絵本の出版社というのは子供のために本を作っている関係上、普段から「資源のムダをなくそう」と声高に訴えていたからだ。環境問題を憂い、子供たちにもムダを出さないよう呼びかけていた。
そういう態度を取りながら、他ならぬ自分たちが資源をムダ遣いし、環境を汚染していた。ぼくは、これほどの欺瞞はないと、ずっと居心地の悪さをぬぐえなかったのだ。
そこでいつからか、「これををなんとか止めることはできないか」と考え始めた。しかしながら、「じゃあ電子書籍で出せばいい」とはならなかった。なぜかというと、これは多くの人がいうことでもあるが、紙の本にはいまだに電子書籍には敵わないさまざまな利点があるからだ。特に絵本については、紙の本の方が断然魅力的だ。
ぼくは、必ずしも電子書籍を否定しているわけではない。実際、ぼく自身が著者として活動するときは、必ず電子書籍を出すようにしている。また最近では、紙の媒体よりこうしてネットで活動することの方が多くなった。このnoteも、紙のムダを出さずにテキストの収益化ができるので、ぼくとしてはとても気に入っている。近い将来、ほとんどのテキストは、こうした電子媒体で発表されるのではないかと考えている。
それでも、紙の本の魅力は今なお大きい。絵本は、単に目で見て——つまり視覚だけで楽しむわけではない。紙やインクの匂いを嗅ぐときの嗅覚、本を持ったときの触覚、読み聞かせをしてもらったときの聴覚など、文字通り五感で体験するものだ。だから、できれば紙で読んでもらいたい。
そのため、「余った本を廃棄する」というムダをなくした上で、なんとか紙の絵本を出すことはできないかと、ずっと考えていた。そして、そうなるともう「デマンド出版」しかないのである。つまり受注生産だ。
デマンド出版では、まず読者に注文してもらう。それから、注文があった分だけ本を作る。そうして、読者に届ける。そうすれば、原則的にはムダな本が一冊も出ない。それで、環境破壊も大いに抑止できる。
ただ、紙の本というのはこれまで、大量に作るからこそコストが下がり、それなりに安価で提供できていた。これが一冊一冊注文のたびに作っていたのでは、コストがかかってしょうがない。これまで1500円で済んでいたのが、その数倍、もしくは10倍以上かかってしまうこともありうる。
それでも、デマンド出版も今はだいぶん進化していて、いろんなことができるようになってきた。文字の本については、判型などが制限されるという条件でなら、すでにデマンド出版は可能だ。注文してからほんの数分で、一冊の本ができあがるようなシステムが存在している。
しかし、絵本についてはこれがまだない。それでもぼくは、今の技術でなるべく安価にデマンド出版ができないかと、児童書の出版社の社長だったときにずっとその方法を模索していた。
そうしたときに思いついたのは、思い切って全ての絵本の判型やページ数、紙やデザインを統一する——ということだった。そうして、タイトルごとに内容だけを変えるのである。そんなふうに本の外枠を統一すると、デザインのコストや紙のコスト、印刷のコストなどが大幅にを抑えられるのだ。
これを思いついたのは、あるレストランに行ったときだった。そのレストランでは、メニューがなかった。つまり、お店の指定した料理しかサーブされないのだ。その上完全予約制で、しかもスタート時間まで指定されていた。20時スタートで、客が全員揃ってから同時にお店がサーブするコース料理を食べるのである。
なぜそうしているかといえば、メニューや客の人数があらかじめ分かっていると、仕入れる食材のムダや時間のムダ、人件費のムダもなくすことができるからである。その分、値段を安くしたり、料理に手間をかけられたりと、客が受ける恩恵も大きい。そこでは、メニューを選んだり好きな時間に行ったりできる利便性は失われるが、それよりも、より美味しいものをより安く食べられた方がいいという考え方なのである。
これと一緒で、本もその内容に合わせた紙質やデザイン、判型を選ぶという利便性は失われるものの、その分、安価でムダがない本を読者に届けられれば、それは読者にとっても恩恵が大きいのではないだろうか——そんなふうに考えた。
そうしてぼくは、デマンド出版で絵本を作れないか、可能性を模索した。そうしたときに出版社を辞めることになったので、結局これは計画だけで終わってしまった。しかし今後は、そういう形態にならざるをえないだろうと考えている。
なぜなら、今後さらにテクノロジーが発達すれば、デマンド出版は当たり前になるだろうからだ。違ったデザインや違った紙質の本も、それほどコストがかからず、ものの数分で製本できる機械がそのうち現れるだろう。
そして、もしそういう機械が現れたなら、そのときこそ本屋さんが本当に終わるときだ。そうなるともう、出版社もいらない。著者と、編集者と、プリントする機械さえあればいい。それを、著者か編集者がネットで受注し、その都度本を作って、あとは宅配するだけである。内容は、絵本だったらネットで簡単に確認できるから、買う方としても不便はない。
そういう時代が、いずれ来る。なぜならそれによって、余った本を大量に廃棄するという大いなるムダが省けるからだ。これからのどこまでも効率化が求められる時代に、我々はもうそうした道を選ばざるを得ない。それが、書店がいずれ必ず終わることの理由である。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
