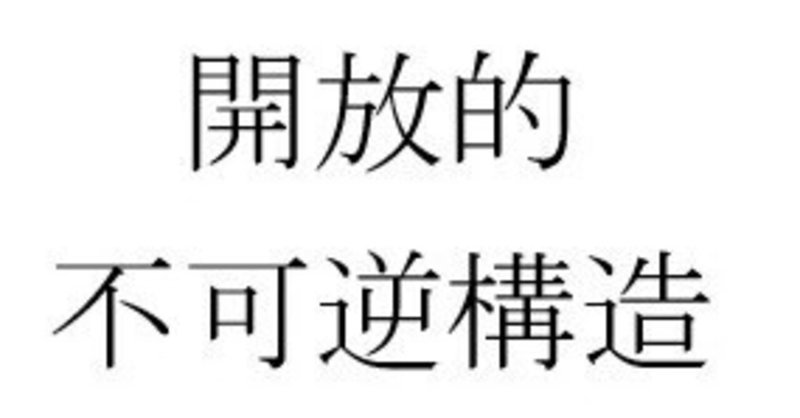
今までを振り返る#2
前回の記事の続きです。前回の記事は、次のリンクからご覧になれます。
この#2は、途中、やや暗い内容が書かれているので、お読みになった後、すこし心を休ませることをお勧めします。
5.社会を知る
興味を持ったことをLaTeXでまとめて楽しんでいたねこっちでしたが、受験勉強を始めるようになったころ、それまで見えなかったものが見えるようになってきました。それは「社会」についての漠然としたイメージです。
きっかけは、とある「Yahoo!知恵袋」の投稿でした。学校の先生が「君たちも社会の荒波にもまれていくだろう」と言っていたのを聞き、「社会の荒波とは何だろう?」と気になって調べた時にヒットしたものでした。そこには、「社会に出て自分の甘さを知ることが人の成長の一歩だ」と書かれており、「そんなことで弱音を吐く奴は愚か者だ」と書かれていました。
ねこっちはその投稿を見て、急に胸が締め付けられる風を感じたのでした。ねこっち自身、社会に出たことはないものの、新たな環境に入った際の苦しみはよく知っていたからです。そう、中1不安定です。
社会に出た時、きっと様々な経験をすることでしょう。その投稿にも、「上司に怒られて勉強になる」「自分の甘い部分がどんどん露見する」と書いてありました。しかし、そうしたことを連想すればするほど、出てくるのは中1不安定の時のつらい記憶ばかりでした。確かに、4月の宿泊研修の際、布団のたたみ方が悪いと先生にこっぴどく叱られたことがありました。それは布団のたたみ方を覚えたという意味では勉強になったのかもしれませんが、同時にねこっちは先生の強い語気に深く傷つきました。そうした「心」の部分の傷つきは、大人になるとすべて押し込んで、全部「勉強になった」と感謝し、自己研鑽しなければいけないのでしょうか。中1不安定でさえ、ねこっちが夏休み明けに倒れてしまったことで周囲が気を遣ってくれるようになり、やっと自分なりに中学という環境に適応できたのでした。しかし、もうそんなことも通用せず、自分の心という心を無視、抑圧して「大人」にならなければ社会には出られないのでしょうか。
投稿の最後にはこうありました。
「苦労をしない/知らない人間は、社会では邪魔者以外の何物でもありません。」
社会には、自分の居場所なんてないんだ。そう思い、ねこっちはひどく落ち込みました。そして、この日から社会をそうした目で見るようになっていきました。
6.天才になってやる
ねこっちが社会をそうした目で見るようになったころ、日曜劇場で『IQ246』というドラマが放送されていました。ねこっち一家は、ねこっちが中学生のころから日曜劇場をよく見ていたので、その延長でこのドラマも見ていました。最初のうちはただ楽しかっただけのそのドラマでしたが、それを見るにつれて、ねこっちの中である考えが起こるようになりました。
「社会の荒波を乗り越えるには、方法は一つしかない。それは、天才になることだ。」
そのドラマに描かれていた天才のように華麗に生きなければ、多くの「凡人」と同じように苦しい経験をし、その中で心を圧して生きていかねばならなくなってしまう。大人になっても心をもち続けるには、天才になるしかない、そう思ってしまったのでした。
このころから、ねこっちの心のバランスは再び崩れていきました。好きだったLaTeXでのレポート作成も、天才のやることではないからとやめてしまい、ただ好きだった物理学についても、「これは自分が天才になるうえでどういう意味があるのか?」と逐一考えてしまったりし、ねこっちはどんどん荒んでいきました。「天才になってやる。」そう思えば思うほど、不思議と物理は楽しくなくなり、何のためにやっているのかもわからなくなっていったのでした。
社会の荒波の一件に始まった、この「天才になる」という思考は、ねこっちの「ただやってみたい」という好奇心や探求心を奪っていきました。その後受けた、現役の時の東工大受験は失敗に終わったのでした。
7.大学入学と深まる不安定
ねこっちは浪人生活をはじめ、この時はどういう訳か「天才になってやる」という考えに強く襲われなかったので、途中で自分に合った勉強法を見つけ、1年間の宅浪の末に東工大合格を果たせたのでした。ここの詳細は、以前の別記事に譲ります。なお、以下の記事が「簡易Ver.」となっているのは、いつかもっと本格的に浪人史を書きたいと当時思ったからです。これと言って深い意味はありません。
晴れて東工大に合格し、それまでの天才至上主義を捨てて物理学に励もう、と思っていた矢先のことでした。ねこっちは、大学の構造の複雑さに戸惑っていました。
教務課、履修申告、学修、・・・様々な漢字が並ぶ手続きの数々に、ねこっちは戸惑っていたのです。「大学生は、ただ勉強ばかりやっていてはだめなのか・・・」そう思ったのでした。
しかし、それらの手続きや仕組みも、ねこっちのサポーターである母が手伝ってくれたため、自分のペースを失わずにできました。しかし、大学の学生支援課の先生に、ねこっちはある日次のようなことを言われました。
「あなたも、もう大学生ですからいつまでも親御さんと一緒にいてはいけませんよ。」
ねこっちはそれを聞いてショックを受けました。ただでさえ新しい環境に恐怖を抱いてしまうような中で、母がサポートしてくれなければ、ねこっちは何もできません。それを、「大学生だから」という理由で自立のようなことをしなければいけないのは、あまりにも酷でした。
確かに、大学生の中には、一人で(親の助けなしに)履修申告も手続きもできてしまう人はいます。それは事実です。しかし、大半の学生がそうだからと言って、ねこっちにまでそれを押し付けるこの先生は筋違いだと思いました。よく冷静になって考えてみれば、大学生のそうした人々も、最初から一人で何もかもできたわけではないはずです。いつかの年齢のときに、初めて発語できるようになったことでしょう。いつかの年齢の時に、初めての友達ができたことでしょう。いつかの年齢の時に、漢字が書けるようになったことでしょう。そしていつかの年齢の時に、親元から離れるだけの自立心が育ったのでしょう。ねこっちも、ゆっくりながらも成長してきました。大勢の方の支援の下、大学受験もできたのです。確かに、成長のペースは人より遅いかもしれません。しかし、これがねこっちの(私の)歩みなのです。それを「大学生ですから、いつまでも親御さんと一緒にいてはいけませんよ」と言われてしまっては、せっかくゆっくりながら懸命に作ってきた『ねこっちの人生』という作品を、いきなり急ピッチで作らなければだめだと言われたように感じ、ねこっちはショックを受けたのでした。
ねこっちはその後、精神状態を崩して授業どころではなくなってしまったのでした。そのため1年間休学し、学校への復帰を目指して療養することにしたのでした。
8.開放的不可逆構造
休学する中で、ねこっちは自分を見つめる時間を得ました。そこでは様々なことを感じ、考えたのでした。
ねこっちの精神不安定を作っていたのは、大学生活を通して見えた巨大な社会の構造でした。今までは、不安定になった時に巻き込む人々は、母、学校の先生で済んでいました。それでもつらかったことには変わりないのですが、ねこっちがこの時見たものは、その上、「社会とかかわるようになると、自分という存在が広く社会に開かれるようになり、関わる人が増える」という現実でした。つまり、自分の存在が社会に開放されるので、問題が自分のことだけで済まされなくなります。例えば、ねこっちの年齢では、公共の場でパニックになると、たとえそれが些細なことだとしても、最悪、警察沙汰になってしまうかもしれません。もう子どもが道端で駄々をこねるような様子とは違うとみなされてしまうのです。このように自分の存在が社会に開かれることを、ねこっちは大変怖がっていました。そして、そのようにして開かれた自分の存在は、たいてい、有無を言わせずに公的な人格をもちます。つまり、第三者が見たとき、ねこっちはあくまでも「一大人」であり、何か年齢にそぐわない行動を起こすと「いい年して」「大の大人が」とバッシングを受けるのです。このような圧力には逆らえないのです。
以上のように、社会には①「自分の存在が開放され」、②「その開放された自分は公的な人格を帯びておりそれには逆らえない」という2つの要素からなる構造があることが分かります。当時のねこっちは、この構造のことを「開放的不可逆構造」と名付けました。この開放的不可逆構造こそ、自分が生き生きと生きることを邪魔している、そう思っていたのでした。
9.濁る心
その後、ねこっちは復学し、再び勉学に励む日常を送るようになりました。しかし、あれだけ好きだった物理を心から楽しめない自分がそこにいました。「こんな高度なことをしたって、どうせあの社会に出ていくのだ」「自分はもう大人であって、子どもではないのだから、どんなに楽しもうとしたって無駄だ」・・・そのようなことを考えてばかりいました。面白いと思える自然現象もなく、ただ言われたことをやっているだけの勉強をしていました。
中学のころの先生に子どもの心を奪い去られ、そのように怒られても「勉強だ」と考えなければならず、さらには「大人だから、大学生だから」という理由で母といることも否定された自分には、生きる意味があるのだろうか?そのような問いを何度も繰り返し立てました。そして、答えが出ない時や、自分なりの答えが明らかに道徳と矛盾していると思った時、ねこっちは深く絶望し、自分を傷つけるなどしていたのでした。
「勉強など、いくらやっても無駄だ。どうせ天才ではないのだから。」「結局、心から笑えるのは子どもだけだ。大人の笑顔なんか作り笑いだ。」どうしようもない考えばかり浮かび、ねこっちの心はどんどん濁っていきました。
勉学にも本腰が入らないまま、再び休学もする中で、ねこっちはどうして自分はこうなったのだ、と自分を悔いていました。「人生やられっぱなしだ。」そう考えており、「人生」という言葉も嫌いになってしまっていたのでした。今年の初夏ごろまでは、このような情動を繰り返しており、ねこっちは、最愛の母にもあたってしまうなどしていました。
こうして苦しい日々が過ぎていき、休学も繰り返す中で、4年が経ちました。
(後編に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
