悲しみよこんにちは
初めて、フランソワーズ・サガンの小説を読みました。
18歳の頃に書いたというデビュー作
「悲しみよこんにちは」
*
17歳の女の子が過ごした、ひと夏の物語。
ヴァカンスの話です。
ヴァカンスって、日本人にはなかなか馴染みのない習慣。ヌーヴェル・ヴァーグの映画なんかを見て、それがどんなものかというのは、何となくわかりましたが。
それは、「旅行」というより「別の場所で暮らす」という感じ。
夏のあいだ別荘を借りて、都会から離れ、日常から離れ、人付き合いから離れ、自然の中で、恋人や家族といった親しい人たちだけで過ごす。
気楽で、孤独で、解放的で、閉塞的。
相反する性質も含んだ、不思議な生活。
(……もちろんこれは私のイメージに過ぎず、本当のところはわかりません。)
*
回想的に、物語は始まります。
舞台は、とある海辺の別荘。
強い陽射し、目前に広がる海、熱い砂浜、風が抜ける松林……夏の盛りの自然の中で、17歳の主人公セシルが、生き生きしているかと言えば、そうでもないのです。無邪気な明るさやみずみずしさはなくて、どちらかというと、気怠さと虚無感がある。
セシルは、享楽的な父親との奔放な生活を楽しんではいますが、父親と全く性質の違う、上品で慎み深いアンヌ(父親の恋人)に憧れを抱きます。しかし、そうかと思えば、次の瞬間には、自分の価値観を否定し、自分たちの生活に介入するアンヌを憎むのです。
セシルの胸のうちで燻る、親の価値観から抜け出したいという欲求。ただ、自分の今までの人生を形作った価値観から抜け出すには、大きな変化を覚悟しなくてはなりません。変化を夢みながら同時にその変化を恐れるセシルの心は、常に不安定で、危うい。
その危うさは、周りの人間をも巻き込んでいきますが、そうかといって大事件が起こるわけでもなく、破滅もせず好転もしない日々がじわじわと続きます。
ところが、このヴァカンスは、ある日思わぬ形で終わりを迎えます。
最後に彼女の心に残ったものは、「悲しみ」。
*
タイトルにもなっている「悲しみよこんにちは」というフレーズは、ポール・エリュアールの詩の一節です。この「悲しみ」という言葉がどういう意味合いを持つか、小説の冒頭で主人公が語ります。
ものうさと甘さが胸から離れないこの見知らぬ感情に、悲しみという重々しくも美しい名前をつけるのを、わたしはためらう。その感情はあまりに完全、あまりにエゴイスティックで、恥じたくなるほどだが、悲しみというのは、わたしには敬うべきものに思われるからだ。
(河野万里子訳、新潮文庫、2009年)
*
出版当時(1954年)の若者は、この小説をどう読んだのでしょう。
今と変わらないのかな。
気になるところです。
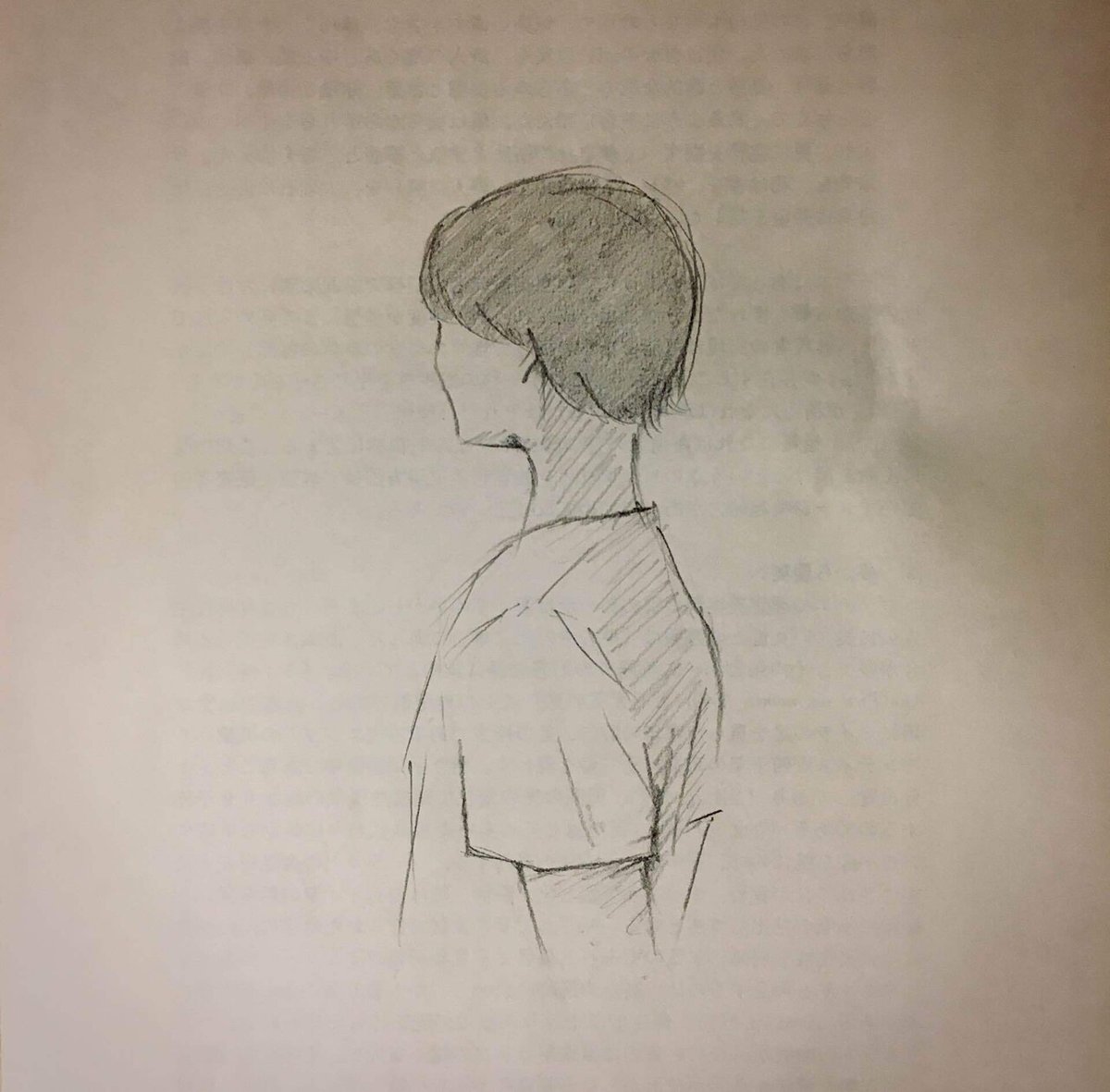
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
