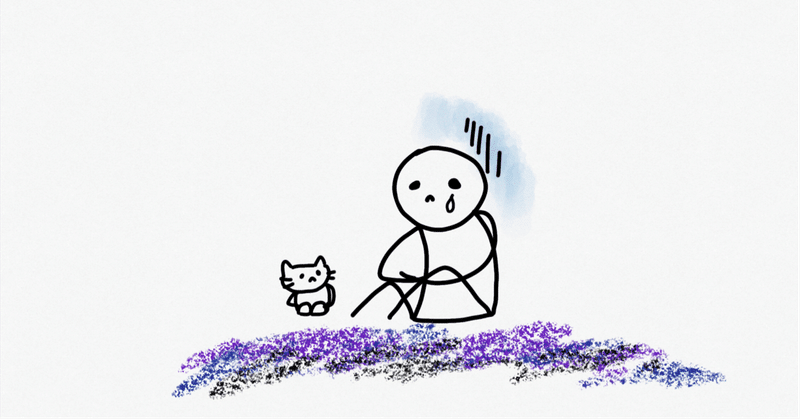
AIで自殺予防はできる?【メンタルヘルスにおける新たなブレークスルー】
こんにちは、田原です。
数年前まで無気力な中卒フリーターで、アニメ&ゲームが世界の中心だった僕ですが、EAに出会ったことで金持ち世界に突入しました。
今は、いろんな案件を検証しながら月230〜300万くらいの利益が出てるので、経済的にはかなり余裕になりました。(上を見たらキリないけどねw)
まぁ、こうやって自由にやれてるのも、当時の僕が「投資」「自分で稼ぐ」という一歩を踏み出したのが全てなんですよね。
詳しくはこっちで書いてます、どうぞ↓
ということで、本題に入ります。
今回は、、
AIで自殺予防はできる?【メンタルヘルスにおける新たなブレークスルー】
というテーマで書いていきます。
自殺は海外でも話題になることが多いテーマですが、日本の自殺率の高さは異常なので特に重視して考えるべきものです。
現状のAIは、ワークフローの自動化やコンテンツ生成、顧客対応という分野が主戦場となっていますが、人類の最も静かな危機に対する味方になる可能性を秘めています。
『もし、スマホをポチポチするだけで、自殺念慮(自殺したい気持ち)を最大92%の精度で予測し、必要な支援を提供することで、命を救える可能性があるとしたら?』
メンタルヘルスへの意識は高まっているが、十分な速さではない
社会的孤立と現代生活のストレスは、毎年自殺率を上昇させており、この傾向はCOVID-19パンデミックによってさらに悪化しました。
参考までにデータを載せておきます↓
2020年:パンデミックの最初の波(2〜6月)では、過去3年間の同時期と比較して自殺率は14%程度減少しました。
2020年後半〜2021年:特に2020年8月から11月にかけて10代〜19歳の若年層の自殺率が増加し、2020年11月には前年同月比で1.86倍となりました。
2021年以降:2021年は2020年と比較して自殺者数が増加。特に女性の増加率が高く、15.3%増でした。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺の動向 (https://www.mhlw.go.jp/content/r4h-2-2.pdf)
統計数理研究所:日本におけるCOVID-19パンデミック後の 自殺率上昇の地域差及び性差に関する分析 (https://www.ism.ac.jp/editsec/toukei/pdf/70-1-115.pdf)
という感じで、数字を見るだけでも改善すべき領域、ブレイクスルーが必要なことは自明ですよね?
悲劇的な問題だが主観的な臨床評価に依存する現状..
自殺は悲劇的な問題であり、自殺リスクの評価は、患者の本当の緊急性や精神状態の微妙な兆候を見逃してしまう可能性のある臨床評価に依存しています。
自殺を効果的に予防する方法を見つける必要がありますが、従来の評価の問題は、患者と医療提供者との会話への依存に起因していることです。これが大きな障害になっています。
例えば、
①:苦しみの表現は千差万別
まず、これらの評価は主観的なものであり、早期の警告サインを見逃しやすいです。なぜなら、一人ひとりの個人はユニークであり、苦しみを経験する方法も、それを表現する方法も異なるからです。
②:評価者が制限され、スケールアップできない
対象者が多いにも関わらず相対が求められるということは、スケールアップするのが難しいということです。リスクのあるすべての人にリーチすることができないため、多くの人が必要な支援や介入を受けられないままになっています。
③:セラピーに対する固定観念
メンタルケアを受けることができる人にとっても、セラピーを取り巻く社会的な印象のために、助けを求めることを避ける人は多いです。特に男性に当てはまり、数値的にもメンタルヘルスの治療を求める可能性が圧倒的に低いです。
従来のセラピーでは対応できない部分をAIが補う
メンタルヘルスケアをより利用しやすくすることは、誰もが一人で問題に対処する必要がなく、すべての静かな助けを求める声が気づかれ、答えられる未来を築くことを意味します。
特にAIは、メンタルヘルスケア、特に自殺予防において大きな可能性を示しています。
その一例が、Nature Mental Health誌に掲載された研究です。この研究では、AIの一分野である機械学習を用いて、大量のデータをふるいにかけ、臨床医には明らかでないパターンを見つけ出します。
具体的には、、
ユーザーが入力した簡単な情報に基づいて、最大92%の精度で自殺念慮や行動のさまざまなレベルを予測することができると報告されています。
この研究では、参加者はスマホアプリを使って、様々な刺激に対する反応をテストするタスクを行いました。これらのタスクは、通常の臨床面接では容易に発見できないような微妙な好き嫌いを拾い上げるように作られています。
AIシステムは、これらの入力(簡単なアンケートの回答から複雑な行動データまで)を分析し、自殺念慮や傾向を持つ可能性を推定します。
この手法が注目されるのは、個人の病歴や詳細な情報を必要としない点です。プライバシーへの配慮とともに、AIの処理能力を生かしたスケーラビリティの高さが、精神医療の課題を解決する可能性を秘めています。
リソースが限られた中で自殺予防の力強い味方となり得るでしょう。実際、論文の著者は、
「人間の行動を定量化して自殺傾向を予測することで、精神衛生をこれまでにない定量的な視点から理解できるようになり、行動経済学などの他分野とも関連が生まれます」
と、指摘しています。
注意しないとAIが間違った方向に進む可能性
一方で、AIの自殺予防への活用には倫理的な課題も存在します。プライバシーやデータセキュリティの確保は必須です。
AIにバイアスが生じれば、一部の人々を見落とすなど重大な過誤が起こりかねません。そのためAIシステムの公平性と公正さを常に追求する必要があります。
加えて、AIに過度に依存し、専門家による人的介入が不十分になれば、危険な事態に陥る可能性があります。
AIは人的支援を補完するツールとすべきであり、決して代替となってはなりません。AIとヒューマンタッチをバランス良く組み合わせることが不可欠です。
このように、精神医療分野でAIを活用するには、倫理、技術、臨床、規制など様々な専門家が連携する必要があります。人権と尊厳を損なうことなく、AI技術の恩恵を受けられる体制を整備しなければなりません。
AIの自殺予防への今後の展望
今後、AIはメンタルヘルス、特に自殺予防において、有望かつ複雑な役割を担うと考えられます。技術が進歩するにつれて、この技術が僕たちの日常生活にさらに統合されていくことが予想されます。
①:予測モデルの強化
将来のAIシステムは、予測の精度とニュアンスが向上する可能性があります。機械学習の進歩により、これらのツールは、現在見落とされている微妙な行動や感情パターンを検出し、早期の介入を可能にするかもしれません。
ちなみに、この予測モデルは「犯罪の可能性がある行動」などを追跡するために使用される可能性も考えられます。PSYCHO-PASSの世界観が現実化しそうですね..

犯罪しそうな奴が分かれば安全かもしれませんが、国家の暴力装置が強くなりすぎてディストピアですw
②:ウェアラブル技術との統合
AIは、メンタルヘルスに関連する身体的兆候を継続的に監視するために、ウェアラブルデバイスと統合されるかもしれません。ストレスレベル、睡眠パターン、心拍変動は、人間の心理状態を示す一般的な手がかりとしてよく使われます。
これらの手がかりのパターンを学習することで、スマートウォッチがアドバイスをくれたり、サポートネットワークに警告を発してタイムリーな介入を行うことができるかもしれません。
IoTデバイスが進化し、それらの身体データをAIに食わせることで、より自殺リスクを減らせる可能性は十分に考えられます。
③:公衆衛生戦略
より大きな規模では、AIがさまざまな集団における傾向を分析し、自殺率を予測することで、公衆衛生当局や政策立案者が、地域社会におけるメンタルヘルス危機の根本原因に取り組む集中的な予防戦略を策定するのに役立つ可能性があります。
大規模なデータを食わせることは、AIが人間のプライバシーを過度に侵害することなく補助を受けられる分野の一つです。
人と人とのつながりを尊重しよう
個人的には、AIが人間の精神衛生を完全に代替することはディストピアに繋がりそうな気配しかしませんw
結局のところは、大昔から言われているように、感情を自然に共有し、思いやりの心を持ち合うことがカギとなります。世界的な宗教もこれを複数のアングルから主張してるよね。
例えば、学校教育の場から、精神衛生をこれまで以上に重視し、算数や理科と同様に丁寧な指導を心がける必要があるのかもしれませんし..
思いやりの心を育むことで、寛容な大人を育て、自然と他者の苦しみに気づく社会が実現する可能性だって否定はできません。
「まぁ、SNSでストレス発散してる奴がいる限り、そんな社会を実現するのは相当な難易度だけどねw」
とは言っても、AIは精神医療を強力にサポートしてくれる存在です。
せっかくテクノロジーが発展してるんだから使わないのは論外ではありますが、AIによる監視社会に陥ることなく、人と人との絆を大切にしながら、適切な役割分担を行うべきでしょう。
テクノロジーと人的支援を賢く組み合わせることで、誰もが必要な精神的ケアを受けられる社会を創り上げましょう。
AIについて全然知らん人は、時代に置き去りにされます。
僕らの知らないところで、基盤にAIが導入されていくのは自然な流れだし、普段から使うような場面でも導入されていくでしょう。
今後は、AIを使いこなす側とAIに使われてる側、この2つに分かれるのは自明です。
まだAIについて知らないのであれば、AIの可能性についてAIツールを使いながら理解しておくべきです。
ってことで、まずはAIトレンドに波乗りしながら稼いでみてください。
正しい方法でツールを使えば、ビビるほど簡単に成果出るので↓
ではでは!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
