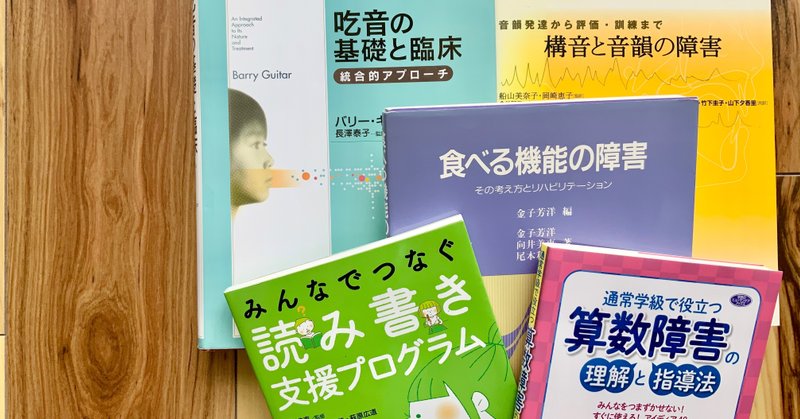
ギリギリまで準備して舞台に立つ(言語臨床関連専門書籍紹介)
※この記事は本の紹介。
小児発達障害領域は本がとにかく多い・わりにジェネラルな内容が多いので、「これが知りたい」にピンポイントで答えてくれる本がすくない。ある程度正しければどんな本でもざっくりとためにはなるのだが、「明日から使える」という意味で一発目からアタリを引くのが意外とむずい。
しかしいろいろ調べていくとここ数年(2016〜)、良書がめちゃくちゃ増え領域横断の動きも広がっている&紙面の見やすさ的な意味でもデザインのよい本が増えた。お値段もお手頃(1,000円台後半〜)だ。読者層の広がりを感じる。
知りたい人が増えることで役に立つ情報が手に入るようになる循環が、とても喜ばしい。
小児言語臨床、THEこれ持っとけばマップ的に進んでいける5冊+写真に載っている以外にもこれまで勉強してきた歴代の本のリスト計12冊、プラス、自分的アタリ本の見つけ方を置いていくので、参考にしてください。 後半が有料部分です。
ちなみに一般の本の読書は👇に読書リストを掲載しています。
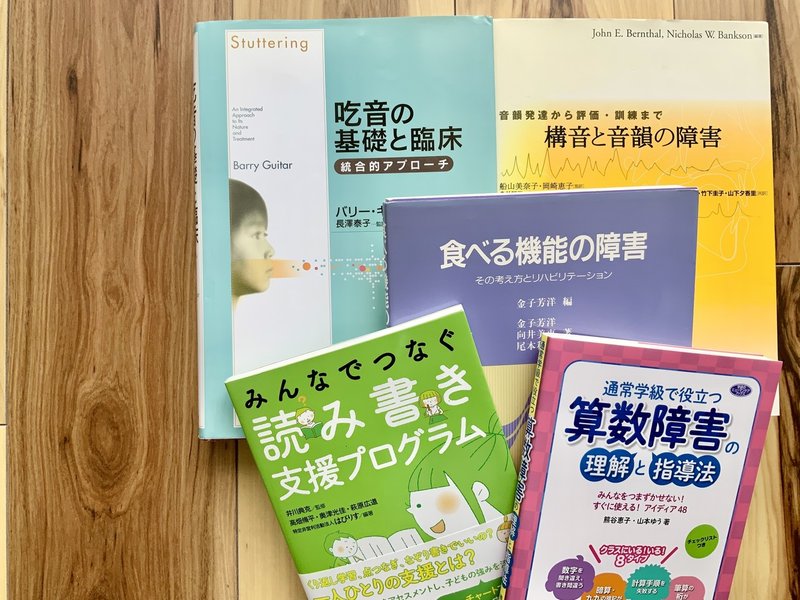
吃音の本
これ持っとけば…というか、吃音の具体的な臨床手順について網羅的に書かれてある本が暫定これしかない。
そのほかの本は、古いか、サポート的な内容が主だったり介入の詳細が省かれていたりするので、まあまあのお値段しますが吃音臨床やるならこの本読んどかないとお話にならん感じです。翻訳してくださり本当にありがとう、、、。ちなみに訳はとても読みやすく、書いてある内容も決して敷居が高いものではないので、本の重量に驚きますが難しいわけではありません。コツコツ読めば必ず読めます。ただ、吃音臨床は特殊っちゃ特殊なので臨床心理学系の科目を放送大学等で単科でよいので学んでいくとよりいいでしょう。
構音と音韻の本
これもガチ本の1冊。一度に読み切る体力は無く、普段は積読エリアに燦然と鎮座しています。いや…はやく全部読まなきゃ(汗)『ことばの発達を支えることばドリル』という音韻教材を作ったときに、音韻の発達について詳しく学びたくて買いました。以後も必要な箇所をつまみ読みしていますね。
構音や音韻領域の臨床のいいところって機能水準の話で完結するので評価がそのまま訓練を兼ねるところだと思っていて、質のよい評価ができれば、訓練プログラム立案の部分が要らない。そして適切な機能訓練を十分な量やってあげれば着実に伸ばせます。
あとは、結局トレーニングを代行してくれるのは日々一緒に過ごしている周囲の人(たいていは親御さん)なので、教える人が背景のリクツまで分かっているかどうかが訓練効果にかなり影響を与える。この辺が心理系・言語系の臨床の限界というか、受け手のリテラシー/バックグラウンドに支えられている部分だなあと。わかりやすく説明する技術を磨いていきたい。
摂食嚥下の本
これ、あちらこちらで言語聴覚士さんが推薦していて手にとることができました。ありがたや。自分で見つけたわけではありません。
しかし、内容よくまとまっているんだこれが。必要なのはこういう本ですよね。情報がぎゅっとまとまっていて、本文の難易度が一定でテーマが行ったり来たりしない。あたまから順番に読んでいけば必ず理解できる。
摂食嚥下療法を医療外で提供することは法律で禁じられているので、わたしがエンゲを見ることはしばらくなさそうだが、この本を読んで摂食嚥下療法も明快だなーと思った。機能レベルのみで考えることができるので評価が訓練に直結している。
口腔顔面周囲筋と協調運動の発達について困ったときに参照できる本がマジでこれ以外に見当たらないので、小児の摂食嚥下をやらない&言語発達や構音指導をする人には必須だと思います。これまで想像で補っていた部分がテキストに落とし込まれているのがほんとありがたい。
発達性読み書き障害(ディスレクシアの本)
いただいたサポートは、ことばの相談室ことりの教材・教具の購入に充てさせていただきます。

