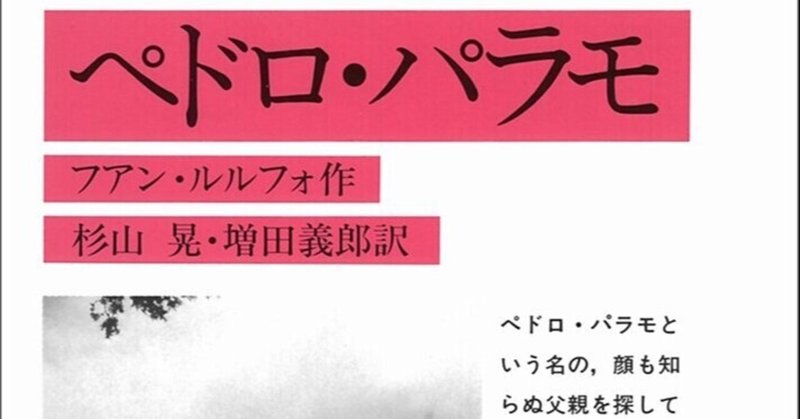
ときにはわからない本を読む愉しみ『ペドロ・パラモ』
『ペドロ・パラモ』この薄い本を読むのに1ヶ月以上かかりました。今まで読んできたどの小説にも似てなくて、難解で、途中でもうやめようかな…と思ったのも事実。
まず登場人物が多く、名前が覚えられない。名字で呼んだり名前で呼んだり時々変わるのにも混乱。
そして何より前ぶれなく次々に語り手が代わっていく大胆さ。"○○は言った"みたいな分かりやすい地の文もないので、読み進めないと語り手が誰に取って代わったのかわからない。
語り手が代わると同時に時代も前後します。現代と過去、そして過去の回想が自由に入り混じる構成。
さらに死者が町を彷徨い、喋り出す。一体誰が生きてて誰が死んでいるのか。主人公だと思ってた"おれ"もいつの間にか死んで墓の中で他者の会話を聞いている不思議。
過去も現在も、生も死もシームレス。主に会話文が続き、説明的な文章は極めて少ない。決して親切な小説ではないし、私は全然わかりませんでした。巻末の解説で、永遠にぐるぐる回りつづける円環構造になっていると言われて、ようやく少しだけ何か理解できたような気になれただけです。

『ペドロ・パラモ』フアン・ルルフォ
あらすじ
母の死を機に、顔も知らない父親を探してコマラへたどり着いた"おれ"。しかしそこは死者たちの彷徨う町だった。
この時代のメキシコにおけるキリスト教についての素養があると精読する一助になるかもしれません。
私は特定の宗教を信仰していないので、信仰心というと何かとても純粋で神聖な感情をイメージしてしまうのですが、この本の中での宗教は生活の根幹でとても大事なものだけど、同時にすごく俗世間的。高いお金を払うほど良いお葬式が挙げられて死後も安泰だとか、友だちが死ぬ時には私が死ぬ時にもよく計らってもらえるようにあっちに着いたら頼んだおいてねとお願いしたり。懺悔というのも興味深い制度だなと思います。罪を犯すことを恐れる割には懺悔して赦しを得られたら大丈夫という、良い意味での大雑把さ。海外文学を本当に理解するにはもうちょっと宗教について勉強しないとなと思いました。
なかなか読み進めるのに苦労した一冊ですが、時にはわからないながら必死に背伸びして読むのも大切なこと。背伸びするのってかっこ悪い感じがして、自然体が人気の今の時代には流行らない気がするけれど、私は大事なことだと思います。今はわからなくてもいい。いつかわかるようになるかも知れないし、もしかしたらずっとわからないままかも知れない。それでもよい。
わからないものを、わからない=ツマラナイとカテゴライズして他所へやってしまうのはもったいない。そうじゃなくて、わからないことをわからないまま自分の中に置いておける、わからなさへの耐性を鍛えておくことには意味があると思うのです。なにせ実際の人生は、わからないことばかりじゃないですか?
わからないからツマラナイのではない。わからないこともわからないまま、まるごと愉しみたいです。
面白くても本を閉じて5分でもう内容を忘れてしまう小説もあれば、読んだ後もなぜかずっとその本について考えてしまう小説もあります。『ペドロ・パラモ』は全然わからなかったのに、読み終わった今も何かがひっかかり、考えてしまいます。良い本は頭の中に心地良い残響を残していくようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
