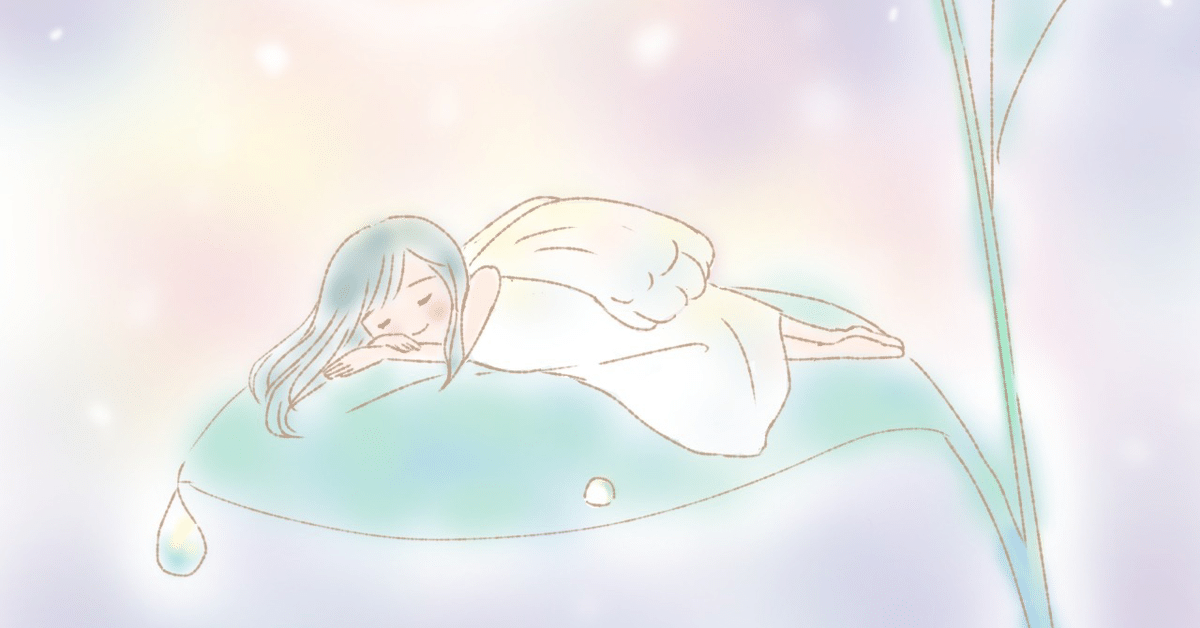
『はてしない物語』考察② 幼ごころの君の存在と善悪
前回の記事では 「誤りの名前」が「虚偽」を生み出し、それにあやつられた人間の意識から「虚無」が生まれることについて考察しました。
今回はファンタージエン国における幼ごころの君の存在と、ファンタージエン国における善悪の区別について考えていきたいと思います。
ファンタージエン国の女王、という書き方は誤解を生みやすいですが、幼ごころの君は一般的な生きものではありません。作中で「それ」は、自然界の法則のように只そこに存在しているだけの、主観的な感情を持たない「法則そのもの」であることが暗に説明されています。
女王幼ごころの君には、支配するということがなかった。圧力を加えたり、権力を使ったり、したこともなければ、命令を発したり、裁いたりということも一度もなく、また、攻めることも、守ることもなかった。……幼ごころの君はただ存在するだけだった。けれども、それが特別なことだった。―幼ごころの君は、ファンタージエン国のあらゆる命の中心だった。すべての生きもの、善なるものも悪なるものも、美しいものも、醜いものも、おどけものもまじめなものも、おろかなものも賢いものも、すべてみな、この幼ごころの君が存在してこその命だった 。
上記の通り、幼ごころの君は「善なるものも悪なるものも」一切の区別はなく平等に扱っていることがわかります。事実、幼ごころの君は、バスチアンが望んだものを、正しいものも、正しくないものも区別することなく、全て与えていました。正しくないものを与えることによってバスチアンが身を滅ぼすかもしれないという助言を一切与えず、ただバスチアンに望まれたものを平等に与えました。それは、幼ごころの君が無慈悲で残酷だからではなく、幼ごころの君という存在そのものが「筋の通った法則」であることを裏付けています。
「愛したい」という最後の望み以外、バスチアンが幼ごころの君に求めた望みは、「与えてもらいたい」という受動的な願いです。一方的に「何かをしてもらいたい」という受動的な行為には、必ず同等対価が伴うという法則。バスチアンはエゴの望みを叶えてもらう度、彼の記憶がその対価として奪われていきました。
対してアイゥオーラおばさまのもとで気がついた最後の望みは、自分から「愛を差し出したい」という能動的な衝動であり、今までバスチアンが抱いていた受動的欲求とは全く異なる性質の感情です。そしてその「差し出す」という感情、行為の同等の対価として巡り巡って「与えられた」のが、最後の記憶を失ってしまったバスチアンに差し伸べられたアトレーユの救いです。物事や感情を「与え続けるだけ」も「受け取り続けるだけ」も絶対に不可能だということ。良きことも悪きことも何らかの形で必ず対価は支払われるという法則がそこには存在します。
しかしながら、これは物語なのだから、少しくらいは幼ごころの君が「バスチアン、このままいけば、危険ですよ」と教えるくらい良いではないか、そう思う人もいるかもしれません。だけれどもそれでは意味がないのです。
何を考えるか、何を望むか、それは誰に支配されるものでもなく、自分自身が決定し、自分自身がその対価をおわなくてはいけない。仮に、本来人が真に欲するべきことは、「自分から愛すること」だと教えてもらったとしても、それは他人の言葉を受動的に受け入れて従っただけで、本当の意味で「気づいた」とはいえない。この普遍的な法則によって、幼ごころの君はバスチアンを含む、ファンタージエン国の全ての存在を善悪の区別なく平等に扱っています。ある者を善き者にするも、悪き者にするも、実際はその者自身の意志決定によるという原理がそこにはあるということ。そして善き者の精神軸には「能動的な愛」があり、悪き者の精神軸には「受動的な欲望と虚無感」があることをこの『はてしない物語』は教えてくれます。
幼ごころの君がバスチアンに行動や感情を強制しなかったように、
我々は本来何物にも己の感情や行為を強制されないはず。
何かを欲しがるのも、差し出したいと思うのも、感情と行動の選択は自分に託されている。己を幸せに出来るのも不幸に出来るのも本当は自分だけであるという普遍の原理を、世間の目や、教育やメディアといった外的要因にがんじがらめになって忘れかけている読者にこの物語はとても良いヒントになると思います。
次回の記事では『はてしない物語』の中で虚無から世界が救われる鍵となる「ファンタジー」の役割について考えていきたいと思います。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
