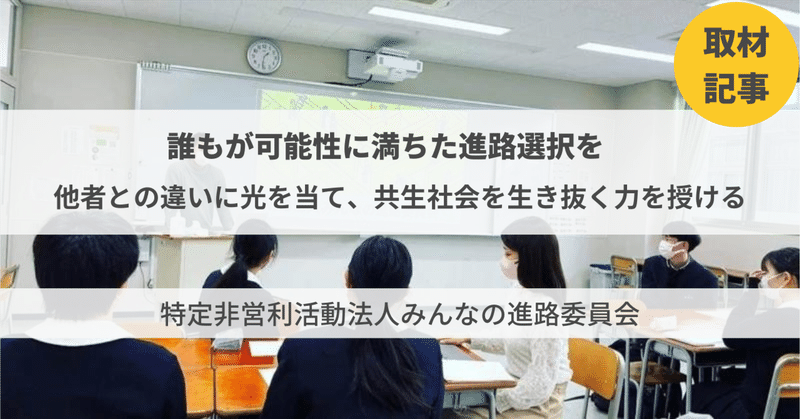
【取材記事】誰もが可能性に満ちた進路選択を 他者との違いに光を当て、共生社会を生き抜く力を授ける
正解のない予測不可能な時代ともいわれる現代。未来を担う子どもたちを取り巻く状況も日々変化しています。彼らの目の前に立ちはだかる経済格差の壁、問われる多様な価値観との付き合い方。教育現場では先行き不透明な課題が山積し、社会全体がチャレンジしにくい閉塞感に覆われています。そんな中、特定非営利活動法人「みんなの進路委員会」が発信するのは、“普通”を忖度し合わず、他者とは違う自分らしさを自由に愉しむこと。その取り組みは非常にユニークで、多様な価値観を育てる「変人学部事業」、異文化への越境をサポートする「ボーダレスキャリア事業」といった斬新な活動を通して、中高生が自らの進路に対して勇気ある一歩を踏み出す後押しをしています。今回は、「みんなの進路委員会」代表理事・谷村一成さんに活動の原点や具体的な事業内容についてお話を伺いました。
【お話を伺った方】

1994年香川県高松市生まれ。高松高-中央大-フォースバレー・コンシェルジュ株式会社-DAYS BLG! はちおうじ。日本人海外大生の就職支援に3年間従事。NPO法人green bird高円寺チームリーダー。行政書士。ライターほか
■身近なロールモデルを可視化し進路選択の可能性を知ってもらう

mySDG編集部:まずは「みんなの進路委員会」の活動内容について教えてください。
谷村さん:「みんなの進路委員会」では、「ボーダレスキャリア」事業と「変人学部」事業の2本柱で活動を行っています。「ボーダレスキャリア事業」は、いわゆる海外大学への進学という選択肢を知ってもらう活動です。経済格差や家庭環境などの障壁を乗り越えて道を切り開いた同世代のロールモデルに出会うことで、本人が持つ進路選択の可能性の広さを知ってもらうことを目的としています
一方、「変人学部事業」では、身の回りのズレや「変」の定義をそれぞれ話し合い、その上で他者と自分との違いをポジティブに理解し、価値観が異なる人間同士の相互理解を深めるワークショップを開催しています。いわゆる「変人」という存在を通して、世の中の常識を見つめ直し、“他者との違い”がもつ価値や可能性を生徒たち自身で考え、学び、気づいていく作業を実践しています。
mySDG編集部:設立にはどんな背景があったのでしょうか?
谷村さん:「みんなの進路委員会」の母体は、2016年、私が中央大学の3年生のときに立ち上げたサークルが母体となっています。当時は「中央大学変人学部」というサークル名でスタートしました。サークルを立ち上げた背景には、私が上京後に感じた「生まれた環境による格差」があります。四国地方の県立高校を卒業後、東京に出てきた私はこれまで出会ったことのないような同世代の存在にかなりの衝撃を受けました。「小学生で起業した人」「大学生で本を出版した人」「高校生でテレビのレギュラー番組を持っていた人」。彼らの周りには同じような活動する人たちが身近にいて、自分のやっていることが特別だという感覚がない人さえいました。当たり前の違いに驚き、次第にこれらの差は生まれた環境によって生じるものだと気づくようになります。
特に地域の限られたロールモデルしか見えない若者たちにとっては、自らの可能性さえ閉ざしてしまうことも少なくありません。そんな若者の現状を変えたいという思いから、多様な選択肢を示し、身近なロールモデルを可視化する活動として「中央大学変人学部」の設立に至ります。当初は大学生向けのキャリア教育の一環として、自ら考え行動している同じ中央大学の学生を講師に迎え、自らの活動のきっかけや想いなどを話す授業を開催していました。2021年に「みんなの進路委員会」と名称変更したのち、2022年には中高向けのキャリア形成事業を開始し、NPO法人としてあらたなスタートをきったばかりです。
mySDG編集部:ちなみに「変人」というキーワードがものすごくインパクトがありますが……。
谷村さん:確かに「変人」という言葉には、ネガティブな響きを感じる人も少なくないかもしれません。しかし「変人」はある意味、そのユニークな思考と行動力で世の中を作り、変えてきた存在でもあります。サークルを立ち上げた当時、学生の間では自ら考え行動する学生を変人扱いされるような風潮がありました。だからこそ、あえて自ら変人と名乗り、自ら考え行動することの何が悪いのかと開き直る意図を込めて「変人」という言葉を選びました。
■「海外大学への進学はお金がかかる」はある意味、偏見…!?

mySDG編集部:社会全体で格差が広がる中で、家庭環境によっては海外大学への進学はかなり厳しいものになります。「ボーダレスキャリア」事業ではどのように海外進学への突破口を提示されていらっしゃるのでしょうか?
谷村さん:海外大学の進学にお金がかかるというのは、ある意味、偏見だと私は思っています。その偏見をなくしていくことが、まずは私たちがやるべき最初の活動でもあります。例えば海外大学と聞くとアメリカやオーストラリアの大学を思い浮かべる方が大半だと思うのですが、一方で台湾やマレーシア、ヨーロッパ諸国といった選択肢もあるわけです。その場合、日本の大学に比べ、断然学費が安かったりもします。実際に僕らの活動の中で、家庭の事情で日本国内での大学進学を諦めた学生が海外大学への道を知って、進学できたという人が何人かいます。世界は広いので色んな壁を打ち破る可能性があるんです。そういった体験談を海外大学に進学した学生さんに話してもらい、枠にとらわれない進路の選択肢に触れてもらうことが私たちの大きな狙いです。
mySDG編集部:経済的な事情が進学を阻んでしまうことは以前からの課題ではありますが、それ以外に今の子どもたちの壁になり得るものとしてどんなものがあるのでしょうか?
谷村さん:「ボーダレスキャリア」事業に関しては、主に地方の中学校・高校をメインに活動を行っていますが、都内で授業を開催した場合には、地方の学生たちとは違う課題があるように感じています。地方の学生にとっては海外大学への進学は身近なロールモデルが少ないこともあって、現実的な選択肢として落とし込んでいくことが求められます。一方で都内の学生からよく聞くのは、とにかく周りに帰国子女が多いということです。だから海外大学に進学できるのは、彼らのようにすでに英語が堪能な人物でないと進学は無理だろうと、はなから諦めている学生が多いですね。興味はあっても、身近にいる帰国子女の存在に圧倒されて、もういいや……となってしまう。つまり、都内の場合は海外大学に進学しているロールモデルはいても、周りにいる同級生のレベルの高さから、海外進学に関心を持つことへのハードルが上がっている印象ですね。
mySDG編集部:確かに都内はその分野の際立った人たちが集まりやすいので、ある意味、子どもたちにとってはチャレンジするハードルが上がってしまう側面があるのかもしれませんね。
谷村さん:そうですね。特に進学校の場合だと、その地域のナンバーワンの実力者たちが集まっているわけですよね。競争原理の中で自分の居場所を獲得し、より選抜された人たちが集まってきているので、常にヒエラルキーを意識せざるを得ない。生徒の中には、「私は数学が好きだと思ってたけど、数学オリンピックに出てるようなすごい人が隣にいるから、私なんかが数学好きなんて思っちゃ駄目なんだ」と話す子もいたりして。だからこそ、彼らには自分たちを取り巻く競争原理から一度抜け出して、広い世界から自分の可能性を探ってみてほしいと思います。
■誰もがちょっぴり変であって、他者との違いは不正解ではない
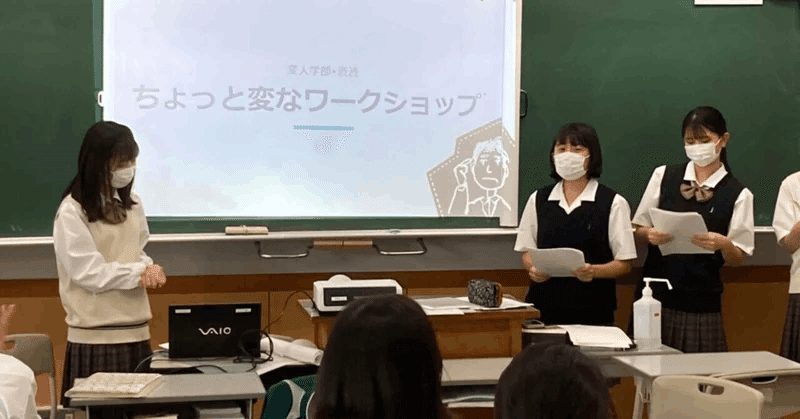
mySDG編集部:特に今の時代はSNSの普及によって住む地域や年齢に関わらず、才能のある人たちがどんどん世の中に出る社会になりました。しかし一方で、周りからの厳しい目にさらされやすく、目立つことを恐れる風潮もあります。そういった中で、「変人」に光を当てる活動をされているのはどのような理由からなのでしょうか?
谷村さん:そもそも「変人」というものに対して、世の中の期待値が高すぎるような気がするんです。「変人学部」を名乗って活動を始めたときも、SNSでは「変人を名乗っていいのは孫正義かスティーブ・ジョブズのレベルじゃないと駄目なんだ」みたいなコメントがきたりして。つまりは変人とは外れ値を極めた天才であるという考えを持っている人が多い。一方で、変人を奇人として捉える人たちもいて。とにかく変人に対する考えがものすごく極端だなと感じています。
mySDG編集部:確かに変人と天才は紙一重というか、人として欠落したものを補うのが能力や才能として捉える人は少なくないかもしれませんね。

谷村さん:当法人のアドバイザーであり、「京大変人講座」を主宰する京都大学の酒井教授は「地味変(じみへん)」という概念を提唱しています。つまり、人はみんな地味に違っていて、それぞれが「ちょっと変」であると。個人個人が異なる考えやバックグランドを有しているからこそ、他者との違いを不正解と捉える必要もないわけです。自分はズレた存在かもしれないけれど、だからといって多数決で多い方が正解とは限らない。いろんな人のズレを知ることで結果的に“当たり前”なんてものはないんだと理解してもらえたらいいですね。それに、他者のズレや自分の変人性を受け入れて楽しめれば、正解のないこれからの世の中でも活躍できる人材になれるんじゃないかと思います。
■がんじがらめの子どもたちが好き勝手楽しめる世の中に

mySDG編集部:今後の展望を教えてください。
谷村さん:「ボーダレスキャリア」事業としては、授業を開催できている学校数がまだまだ少ないので、まずは私の出身地である四国を中心に関われる学校を増やしていきたいですね。さらに7月からは試験的に四国地方で海外進学を目指す中高生のコミュニティを立ち上げるため、ますます多くの学生たちの目標をサポートできればいいなと考えています。一方「変人学部」事業に関しては、やはり教育現場において「変人」というワードがなかなか受け入れられづらいこともあり、まずは世の中からアプローチしていくために、今年の秋に「変人學会」を立ち上げる予定です。さまざまな大学教授の方々に参加していただきながら、多くの企業とも協働していくので、遊びと学びを結びつけながら、「変人」こそ世の中に必要な遊びであることを発信しつつ、正しさばかりが過度に追求されてしまっている今の社会の風潮を変えていきたいですね。
mySDG編集部:最後に子どもたちに対して、活動を通して伝えたいメッセージがあれば教えてください。
谷村さん:正直なところ、子どもたちには自分たちの思うまま、自由にやってほしいですね。とはいえ、今の時代は勝手にやれる環境がなかなかなくて、子どもたちががんじがらめになっているというのが問題ですよね。本人たちも知らず知らずのうちに諦めてしまっていることもあるので、その壁をとっぱらっていくことが私たちの活動の最大の目的です。とにかく子どもたちには、勝手に好きなことをして楽しんでほしいし、もっと勝手なことができる世の中をともに作っていくことがこれからの目標でもあります。
この取り組みが参考になりましたら、ぜひいいね・シェア拡散で応援をお願いいたします🙌
mySDGへの取材依頼・お問い合わせは mysdg.media@bajji.life までお気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
