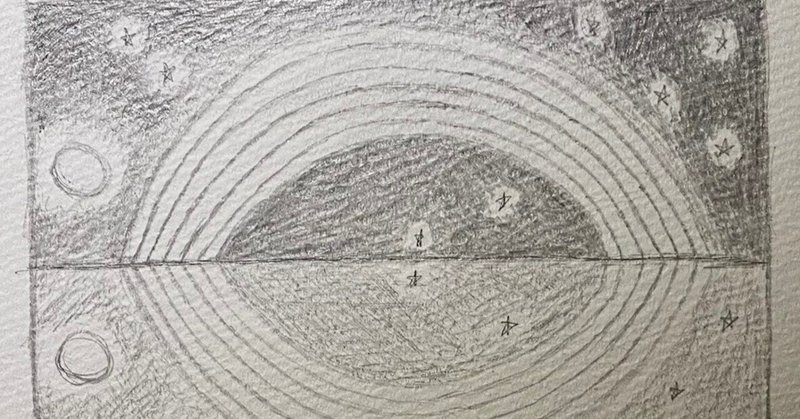
[小説] リーラシエ ~月齢9~
「おはようございます。ディアナさん。」
「おはようございます。リーラシエさん。」
ここに来て10日目。
ようやくリーラシエと滑らかに言葉を交わせるようになった。最初は目も合わせず俯いていたリーラシエだが、今ではディアナに笑顔を見せるまでになった。
「では、行きましょうか。」
「はい。」
初めて早朝の食料調達に連れていってもらって以来、ディアナもリーラシエの食料調達に随伴している。
猫は家から一緒に行ったり、途中で合流したり、姿を現さなかったりと日によってまちまちだ。
「それで、リーラシエさん。昨夜夢を見たんですよね?どんな夢だったんですか?」
「それは、私の過去だったような気がします。」
過去という言葉にディアナは胸が高鳴るのを感じた。
過去について思いを巡らせたことに触発され、出生に関する記憶を思い出したのかもしれない。
「ふと気づくと、私はここではないどこかの村に立っていました。周りには質素な小屋が立ち並んでいて、辺り一面に緑が広がっていました。」
リーラシエは昨夜の夢を思い出すように天を仰いだ。
「周りには私よりも幼い子どもたちが駆け回っていて、楽しそうでした。」
リーラシエの表情がさっと曇った。
「子どもたちはみんなで鬼ごっこをしたり、ボール遊びをしたり、誰かの家に集まってお菓子を食べたりしていました。みんな、笑顔で。」
リーラシエが俯き、下唇を噛んだ。
「私はずっと独りでした。みんなが鬼ごっこをしている時も、ボール遊びをしている時も、家に集まってお菓子を食べている時も。それが、無性に寂しかった。」
リーラシエの頬を一筋の光が流れた。
「ごめんなさい。無理に話させてしまって。」
ディアナは慌ててリーラシエの話を遮り、直角に腰を折った。
リーラシエは涙を拭いながら首を横に振った。
「いいんです。ディアナさん。私がお願いしたことですから。」
リーラシエは柔らかな口調で言った。それでも顔を上げないディアナに痺れを切らして猫がディアナに擦り寄った。
「確かではありません。しかし、あれは私の出身の村だったような気がします。簡素な家々や生い茂る緑は私の故郷を想起させました。」
「つまり、リーラシエさんはここの出身ではないということですか?」
リーラシエは静かに首肯した。
「はい。私の故郷はここではなく、夢に出てきた村だと思います。」
その情報はリーラシエの故郷を知るための手掛かりになる。しかし、素朴な村落地帯などこの地球上に無数に存在する。残念だがこれだけではリーラシエの故郷を特定できない。
「他に何か特徴はありましたか?景色とか食べ物とか。」
リーラシエは夢の詳細を思い出そうとじっと思案した。
「村の周りを山に囲まれていたような気がします。それと、川が流れる音が聞こえたような。ディアナさん?」
リーラシエの話を聞いた途端、ディアナは硬直した。質素な村で周りを山に囲まれている。そして川が流れている。
その情報を照らし合わせると、ある一つの村が思い浮かんだ。もちろん、これだけでは断定できない。
しかし、ディアナは確信していた。旅人の勘というやつだ。
「そうですか。話してくれてありがとうございます。少し考えてみます。」
ディアナはリーラシエに本当のことを告げなかった。
そう、ディアナはリーラシエの故郷を特定していた。素朴な家、拡がる緑、川と山。ディアナもよく知っているあの村だ。
「ミャ?」
顔を歪め、俯いていたディアナの側にいつの間にか猫がいた。深刻な面持ちでいるディアナを不思議に思ったのだろう。
「なんでもない。」
ディアナは猫に笑いかけたが、その笑顔は何とも言えず哀愁を帯びていた。ディアナはリーラシエに本当のことを言わなかったことに後ろめたさを感じていた。
リーラシエは自分の故郷を知りたがっている。ならば、一刻も早くリーラシエに真実を伝えるべきだ。
だが、ディアナはまだ時期尚早だと思った。リーラシエはまだ故郷のことをほとんど思い出していない。夢で記憶のほんの一片を垣間見ただけだ。今真実を伝えたらリーラシエは混乱するだろう。何より、沈痛で暗然とした記憶が一気になだれ込み、大きなショックを受けるかもしれない。
それでは意味がない。ディアナはただ純粋に『あの子』の幸せを願っているだけだ。『あの子』を困惑させ、精神的に疲弊させるために真実を告げるのではない。
「ディアナさん?」
野で食料を採り終えたリーラシエがディアナを覗き込んだ。じっと俯くディアナを不思議そうに見ている。
「もう食料調達は終わりました。帰りましょう。」
「…リーラシエさん。もし、故郷が分かったらどうしますか?」
「え?」
ディアナからの思いもよらない問いかけにリーラシエは当惑した。
もし故郷が分かったら。
考えてもみなかった。今はただ自分の故郷を知りたいと思っていた。でも、もし故郷が分かったら。
「行ってみたい気もします。自分の故郷がどんなだったか、今はあまり思い出せませんが。でも、見たくない気もします。故郷は私にとっていい思い出がある場所ではありませんから。」
リーラシエは歯を食いしばった。
「どっちなのでしょう。自分でもわかりません。でも、私はここを離れたくない。」
今度は強い口調だった。ここを離れたくない。それは紛れもないリーラシエの本心だろう。
ディアナはリーラシエの本心を聞いたことに安堵しつつ、暗闇に紛れたこの先を思い遣った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
