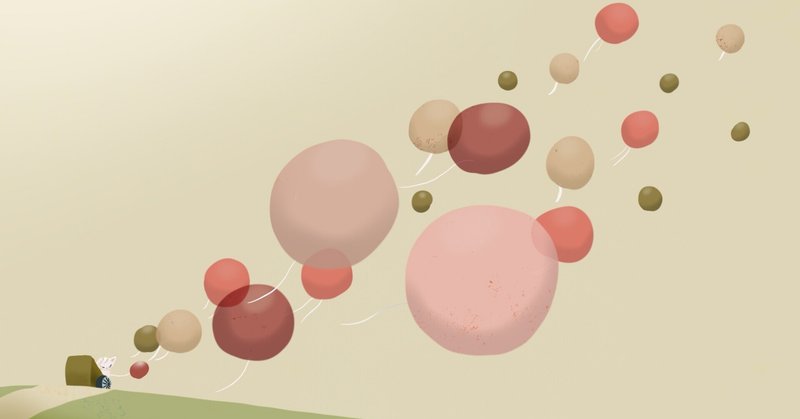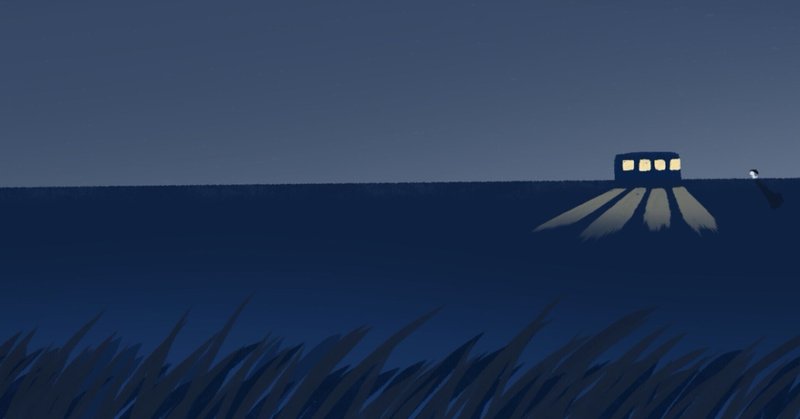2021年2月の記事一覧
そして、わたしはバスを降りた
盗み聞き、と言えば人聞きが悪いが、そう言われてもしかたあるまい。乗り合いバスに乗っていた時、わたしの後ろで話していた若い娘二人の話である。
普段であれば乗り合いバスになど乗らないのだが、その時はどうしたことかタクシーが捕まらず、仕方なくバスに乗ることにした。座席は埋まるくらいの混雑ではあった。わたしの腰を下ろした後ろには若い娘二人が座っていた。わたしは文庫本を取りだし、それを読もうとしたのだが
サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ
「ええっ!?」と、少年を思わずその席から立ちあがらせたのは少女の一言だった。
「引っ越すことになりました」と、少女は教壇の上、教師に付き添われながら言ったのだった。
少年が急に大声を上げたものだから、教室中が彼を見た。
「どうした?」教師が尋ねた。おそらく、その教室にいた誰もが思ったことだろう。クラスメイトたちの視線もそれを尋ねている。
「あの、ええと」と、少年は言いよどんだ。「ちょっと、寝てて
ほんの、ささいな、プロポーズ
その頃のぼくは、まだほんの子どもだったので、自分の前方には見渡す限りの地平が広がっているものと思っていた。無限の可能性。なんて月並みな表現。そんな月並みな表現が似合うくらい月並みな感覚。なろうと思えば、宇宙飛行士にだって、大統領にだってなれる気がしていた。もしもそうならなかったとしたら、そうなろうと思わなかっただけ、そんな気がしていた。遅刻ばかりで、叱られてばかりの落第生が何を言うか、と、ぼくが
もっとみるタネも仕掛けもございません
凄腕のマジシャンがいた。シルクハットからウサギを出すとか、アシスタントの体を真っ二つにするとか、そういうありきたりなものは当然のことながらお手の物。高層ビルを消して見せたり、橋を消す。タキシードの懐から象を出す。金魚をクジラに変えて見せる。そのスケールは桁外れ、他の同業者たちは自分の影が薄くなると結託し、殺し屋を雇ってそのマジシャンを抹殺しようとしたが、その殺し屋はマジシャンの手で猫に変えられ、
もっとみる