
(会期終了)とうきょうげんだいまとめ C01~14
23年7月あたまにあった東京現代についてのまとめその3
前回はギャラリーのBぜんぶを眺めたので今回からCを眺めてく
ブラム&ポー、セイディ・コールズといったド本命もようやく登場するで
ちなどういうフェアなのかとかそういうのは1個目でやったので以下参照
C02:亞洲藝術中心 | Asia Art Center
Taipei, Beijing

正面左 "Plum Blossoms in Courtyard - I" , 2023 / "Plum Blossoms in Courtyard - II", 2023
正面 "A Sunny Day - Red Camellia", 2021
正面右 "A Peaceful Day - Pink Camellia", 2023
右端の立体造形物 Ju Ming 朱銘 Living World Series – Ballet, 2012
なんでC02から? 01はどこいったん?
みたいに思ったと思うが、俺もそう思ってんので聞かないで
なんかしらんけどCは02からスタートしてた
ASIA ART CENTERは1982年に設立され、現在は台北と北京798アートゾーンに2つのギャラリースペースを持つビジネスグループに成長し、総面積2500平方メートルの美術館レベルのアート展示を提供しています。ギャラリーは東西の現代アートを展示し、インクと油絵、彫刻、インスタレーション、ビデオ、写真、音響、タペストリーなど多様なスタイルを含みます。また、Art Basel、JINGART(北京)、ART021(上海)、台北当代藝術博覽會に定期的に参加しています。戦後のアートムーブメントや現代インクアートを専門に扱い、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ本土、ラテンアメリカのアーティストを紹介しています。
引用元: ASIA ART CENTER
「現代美術」より「当代藝術」の方が、なんか「おまえらの代の責任」感があっていいんじゃね? さすが漢字の本場
ここもちゃんとホムペにがっちり出品作出してる「いいギャラリー」だ
展示風景もばっちりなので正直、公式みてくれって気持ちだわ
Asia Art Centerは、東京現代の初版に参加を発表しました。ギャラリーは、台湾の彫刻家である朱銘と李真の作品をはじめ、世界各国のアーティストの作品を展示しています。アーティストたちは、自分たちの生活や環境を反映した作品を通じて、観客に対して自由な解釈と想像を促しています。また、彼らの作品は、彼らがアートを通じてどのように聖域を求めているかを反映しています。各ブラシストロークと彫刻は、彼らの物語の構成を作り出し、労働集約的な行動は、アーティストが自分の生活と環境を思索するのを可能にします。
引用元: Asia Art Center
まとめから作家リスト削られたので以下
台湾の巨匠彫刻家である朱銘 Ju Ming(1938-2023)と李真 Li Chen(1963-)の作品、台湾の画家董小蕙 Dong Shaw-hwei(1962-)、アメリカのセス・アームストロング Seth Armstrong(1983-)、ミシェル・ブレード Michelle Blade(1981-)、クレア・コレット Claire Colette(1980-)、ハワード・フォンダ Howard Fonda(1974-)、イギリスのフローレンス・ハッチングス Florence Hutchings(1996-)とシャーロット・キーツ Charlotte Keates(1990-)、日本の松谷武判 Takesada Matsutani(1937-)と田中敦子 Atsuko Tanaka(1932-2005)、ニューヨークを拠点とする日本人アーティストの山口めぐる Meguru Yamaguchi(1984-)の絵画を展示しています。
引用元: Asia Art Center
董小蕙、松谷武判の漢字違ってたので執筆者が修正 あとピンイン、スペリングも同左が挿入
GPT4君、有名人ならけっこう漢字当てれんじゃん すげえ・・・
かなり実績のある作家が中心なブースだった
となると日本(の現代美術文脈)からピックされるのがともに具体(GUTAI)の松谷武判と田中敦子になってくるのは妥当か
表通りのおたく的には「田中のあっちゃん」といえば攻殻機動隊のメスゴリラこと少佐のCV:田中敦子だが、裏通りのギャラリーをめぐってるおたく界隈では「電気服の田中敦子」である
C03:Yavuz Gallery
Singapore, Sydney

左の壁面の絵画も同作家(だったと思う・・・)
正面 Saskia Pintelon "VIP", 2000
正面右 Saskia Pintelon "Don’t fall asleep while sunbathing", 2018
その右の立体造形物は たぶんIsabel and Alfredo Aquilizan の作品
シンガポール(2010年)とシドニー(2019年)に設立されたYavuz Galleryは、コンテンポラリーアートを通じて異文化間の対話を促進することに専念している。当ギャラリーは、世界各国から多様なアーティストを紹介しています。私たちは、現代の問題に挑戦するアート作品の社会的意義を原動力とする強力なキュレーション・プログラムを称賛しています。
ヤヴズ・ギャラリーは、アーティストにグローバルなプラットフォームを提供するために、意欲的な展覧会と国際的なアートフェア・プログラムに支えられている、アジア太平洋地域を代表する現代ギャラリーのひとつです。
訳:Deepl
読みだが「ヤヴズ・ギャラリー」とDeepl君は言ってる 信じろ
なんかトルコっぽい響きだがなんでかよくわからんかった
東京現代についてのステートメントは以下
Yavuz Galleryは、東京現代の初版に参加し、アジア太平洋地域の評価の高いアーティスト、Isabel and Alfredo Aquilizan、Karen Black、Saskia Pintelon、Caroline Rothwell、Pinaree Sanpitakによるグループプレゼンテーションを行います。展示作品は、重要な歴史的な作品と新たに委託された作品を、ドローイング、ペインティング、彫刻の形で紹介します。フィリピン/オーストラリアのアーティストデュオ、Isabel and Alfredo Aquilizanは、彼らの象徴的な「Left Wing Project」シリーズからの作品を展示します。オーストラリアのアーティスト、Karen Blackは、人物描写と抽象表現の間を揺れ動く新たに委託された絵画を初めてYavuz Galleryでデビューします。ベルギー出身でスリランカを拠点とするアーティスト、Saskia Pintelonは、大胆にレイヤーを重ねた絵画とコラージュを展示します。オーストラリアの多分野アーティスト、Caroline Rothwellは、自然環境とアートのサブセットを探求します。タイの著名なアーティスト、Pinaree Sanpitakは、自然な桑の紙を使った手作りのミニチュア彫刻を展示します。
引用元: Yavuz Gallery
「アジア太平洋地域の評価の高いアーティスト」と書いてある通り、他とはなんか違う空気出してた
Pinaree Sanpitak、Isabel and Alfredo Aquilizanの作品なんか興味深い
作品性がありながら(本当にあるのかはわからんけど)素人目にも造形としてキレイ!とかスゴイ!とかカワイイ!とかと思わせる所もしっかりあって人気出そう
派手じゃないから人はまばらだったがポリシーは感じた
C04:GALLERY SIDE 2
Tokyo

GALLERY SIDE 2は、1997年に設立され、2018年に西麻布に移転したギャラリーです。国内外のアーティスト、ムラタ有子、田附勝、ピーター・マクドナルド、占部史人、ミケランジェロ・コンサーニ、花澤武夫、三井淑香、佐藤姿子の作品を展示しています。オーナーの島田淳子は90年代にニューヨークで出会ったリクリット・ティラヴァニとウドムサック・クリサナミスとともに、美術(アート)と日常(ポップカルチャー)、個(プライベート)と公(パブリック)といった境界線を押し広げ、美術史を考察しながら、現在を切り開く試みに重きを置いています。
引用元: 美術手帖
かんぜんに死語だが「ミーハー」なこといえば、ティラヴァニと初個展からやってる、っていのはすげえな
特にステートメントもないが、全体的な方向性っていうか、何を目指してるんだな、みたいな特徴があんまりわからんかった
(直前にヤブズギャラリーとか見てるせいだが
これは所在地に「tokyo」って書いてあるギャラリーの多くでそうだった印象ある
C05:313 Art Project
Seoul

めっちゃ小さい立体造形物は Xavier Veilhan "Manfredi", 2018
"313 ART PROJECT"は、韓国ソウルに位置する現代美術ギャラリーで、国際的なアートシーンと韓国のアートシーンとの間で意義深い交流を促進しています。ギャラリーは、国際的に評価されつつも韓国ではまだあまり知られていないアーティストを紹介し、新進の韓国アーティストを国際的に紹介することに焦点を当てています。また、韓国の伝統的な価値観に根ざした個人的な哲学を独自の芸術的ビジョンに翻訳するアーティストを国際的なプラットフォームで紹介しています。2019年にはパリに新たな展示スペースを開設し、韓国のアートシーンの多面的な側面を世界に紹介しています。
引用元: 313 ART PROJECT
というギャラリーらしい
「韓国の伝統的な価値観に根ざした個人的な哲学」というのはよくわからんかったが、非常に現代美術らしい展示風景だったように思う
C06:A Lighthouse called Kanata
Tokyo

右の絵 三鑰彩音 "Flowers in the Mist", 2020
左の立体造形物 横山修 "waves", 2023
右の立体造形物 尾崎悟 "can you see me", 2023
「A Lighthouse called Kanata」は、青山和平によって設立されたギャラリーで、その名は「カナタという名の灯台」という意味です。このギャラリーの目指すものは、一隅を照らし、埋もれた存在に光を当て、遠く彼方へその想いを伝えること。有名無名、男女、年齢を問わず、固定の価値観に捉われず、信じる美を広めることです。また、日本の美を世界に広め、その美が日本へ帰ってくることを願っています。そして、100年後、200年後の日本人のために、そして世界のために何が残せるのかを考えています。このギャラリーは、芸術家が夢を託し、お客様がその夢に包まれ、私たち自身も夢が叶う場所となることを願っています。過去と未来は一つとなり、光はやがて希望と成すという想いが込められています。
GPT4君がうまくまとめてくれているが、このギャラリーのホムペに載ってんのはガチのポエムなんで、ぜひ本物を!!!!
このブースはめちゃくちゃ記憶に残ってるんだが、なんでかっていうとここだけ猛烈に「デパートの美術品コーナー」っぽかったからだ
調べてみたらここは「酉福ギャラリー」(Yufuku Gallery)という場所だったのが、2020年6月に現在の屋号にかわったってことらしい
で、その酉福ギャラリーは陶芸とか金工などの工芸美術作品を売ってたっぽいので、デパートっぽいのはむしろ当然な気がする
東京青山にある酉福ギャラリーの公式サイト。陶芸、金工、漆、ガラスなど幅広い作品を取り扱っています
ぜんぜん関係ない(わけでもないが)現オーナーの父君が興味深い名前だ

という歴史をふまえると工芸的な作品が多いのは納得ではあるし、むしろそこ強いぜ感あっていいんじゃないかと
なんで逆に現代美術っぽい絵画の方がこのブースだと中途半端な感じだ(作家はどっちもT美出身
サイトが独特の感性でみやすいとはお世辞にも言えないが、作品リストもあったのでやばい人に見えて実は話すといい人系なんかも
C07:Blum & Poe
Los Angeles, New York, Tokyo

真ん中の壁の奥に見えてるのはもしや・・・ 岡崎乾二郎アゲイン!!
ほかはわからんです
"Blum & Poe"は、ティム・ブラムとジェフ・ポーによって1994年にサンタモニカで設立された現代美術ギャラリーで、現在ではロサンゼルス、ニューヨーク、東京に拠点を持つ国際的なギャラリーです。ブラムの日本のアート界に対する深い知識と、ポーのロサンゼルスの新進アーティストに対する鋭い洞察力を組み合わせ、影響力のあるアーティストの国際的なプログラムを展開しています。現在、Blum & Poeは16カ国からの60以上のアーティストとエステートを代表しています。また、ギャラリーは、環境とコミュニティの管理を全ての運営に優先しており、2015年にはアメリカで最初のグリーン認証ギャラリーの一つとなりました。
引用元: Blum & Poe
ここはめっちゃブース広い!
広すぎて上田勇児の陶芸作品があったことしか覚えてない(うそ、岡崎けんじろう再びもおぼえてる
Blum & Poeは16カ国からの60以上のアーティストとエステートを代表とか書いてある通り、ここはすげえギャラリーらしい(しらんけど)
まあそもそもこのフェアのセレクションする人(Selection Committee)がこのギャラリーの人なんで当然えらいんだろう

日本側でこのプレスリリースに名前出てくるのは以下の人々
「コレクティブカウンシル」って何するのかわかんないが、文面読む限りは「コネとかパイプで何とかしてくれる顔の広い人」のようだ


なんで、そんなショッカーの基地みたいな場所で知ってる作家の、しかも陶芸作品とか見つけるとやたら安心する(っていうかした)
全体的には日本マーケットを意識したラインナップ(陶芸、岡崎けんじろ、奈良など)なんだと思うが、ちょっとおもろかったのが(薄塗りの)岡崎作品のすぐ横にめっちゃ厚塗りのZhu Jinshiの作品が展示されてて、「あれ、これも岡崎けんじろ?」みたいになってしまうところ
(じっさいZhuの作品はずっとパワー系でぜんぜん似てないが
以下、ステートメントと作家リスト
ブラム&ポーは、約30年前のギャラリー設立以来、日本美術界との強い結びつきを築いてきました。1995年にサンタモニカで初めてブルーム&ポーの個展を開催した著名な日本人アーティスト、奈良美智の作品と、今年初めに東京で初めて個展を開催した大井戸猩猩のペインティングを展示します。新旧の提携を祝うことで、ブラム&ポーはその豊かな歴史と、世界中のアーティストのキャリアのあらゆる段階を支援するという継続的なコミットメントをさらに示している。
https://www.blumandpoe.com/fairs/tokyo_gendai_2023
ちなみにこのページ、サイト内からは行き方わからんかった
C08:Sadie Coles HQ
London

奥の壁面左から順に Kati Heck Jungs "VII ( im Spiegel)", 2023
Nicola Tyson "Portrait of Isabel Rawsthorne", 2021
Nicola Tyson "Virgin and Child", 2020
Nicola Tyson "Dance Floor", 2023
一個とばして Isabella Ducrot "Vaso II", 2022
飛ばしたやつも Nicola Tyson なんじゃないかと思う
どいつもこいつも凄い&よい・・・
ショッカーの大幹部みたいなブースその2
何しろHQ(司令部)ってついてるぐらいだから大物であることを隠す気はなさそう
「Sadie Coles HQ」は、ロンドンを拠点とする現代美術ギャラリーで、約50人の国際的なアーティストを代表しています。1997年に開設され、その初回展示ではアメリカの画家ジョン・カリンの新作と、イギリスのアーティストサラ・ルーカスの「The Law」を並行して展示しました。これにより、ギャラリーの国際的なプログラムの幅広さが確立され、その後の20年間でさらに拡大しました。Sadie Coles HQは、その設立以来、多くの展示や国際的なアートフェアプログラムを通じてアーティストにグローバルなプラットフォームを提供しています。
引用元: Art Basel
「初回展示でジョン・カリンとサラ・ルーカス」
どんな作家なのかは以下
で、さすがに戦闘力は激高い
そんな特別なことはやってない(ように見える)んだが、あきらかに全員なにかしらの毒手というか、これで刺してやるって武器を持ってて殺意が高い
美大出たままふわっとしたきれいな画面で内面のテーマの表象をやってるみたいなの(誰とは言ってない)はこのセイディ・コールズというジャングルでは生き残れないんだろう
あんまほめたくないんだけど(なんでだよ)Paloma Varga Weiszを筆頭にまじよかったので東京現代のチケ代はここで1/4くらい回収できたと思う(あと3/4はシゲオ・トヤ、元永定正、PARCEL、そうきょギャラリーその他
出品作品は以下で見れる! 正直おすすめ! 東京現代に行きたくなる!(終わってっけど)
C09:MISA SHIN GALLERY
Tokyo

前田紗希 Saki Maeda "i19_9", 2019 / "21_23", 2021 / "23_13", 2023
篠田太郎 Taro Shinoda "Katsura 03", 2020
川俣正 Kawamata Tadash "P.S.1 Installation Plan", 1984 / "People's garden plan documenta 9", 1992
MISA SHIN GALLERYは、2010年に東京の白金に開設され、2018年に南麻布に移転したギャラリーです。コンセプチュアルなアプローチを持つ国内外のアーティストを紹介し、世界的に著名なアーティストの展覧会を開催するとともに、中堅アーティストに美術史における正当な位置を与えることを目指しています。また、1960年代から1970年代の日本のコンセプチュアリズムに焦点を当て、戦後日本の美術史に新しい洞察と分析を提供しています。さらに、建築、演劇、音楽など他の分野と美術との関係を模索することも目的としています。企業のアートコレクションやアートプログラムへのコンサルティングも行っています。
引用元: MISA SHIN GALLERY
東京現代についてのステートメントは以下
MISA SHIN GALLERYは、パシフィコ横浜で開催される7月7日(金)から9日(日)にパシフィコ横浜にて開催されるアートフェア、第一回Tokyo Gendaiに参加いたします。
フランシス真悟のモノクロームシリーズとInterferenceシリーズの油彩作品、篠田太郎のペインティング、前田紗希の油彩作品、川俣正のレリーフ作品、東松照明のビンテージ写真を展示をいたします。
原文には問い合わせ先メアドもあったが記事執筆者が削除
作家リストには彦坂尚嘉、松澤宥なども並んでおり、日本現代美術の王道って感じではあった
なんかいいこと言おうとして頑張ったが、特に思いつかなったので次へ
C10:Gallery Baton
Seoul

右 Suzanne Song "Cast IV", 2023
Gallery Batonは2011年に設立され、現代美術のパラダイムに基づいた洗練されたプログラムを一貫して提供することで、主要な現代美術ギャラリーの一つとして認知されています。アートバーゼルやフリーズなどの国際的なアートフェアに参加し、主要なアート機関との共同プロジェクトを進行する一方で、アーティストとの共成長を優先した持続可能なアートエコシステムの創造にも取り組んでいます。また、ビデオや新メディア作品のための会場としてObservation Deckを運営し、スタジオスペース、キュレーションサポート、展示の機会を提供する非営利プログラムであるChapter IIも運営しています。
引用元: Gallery Baton
完全なリストはみつかんなかったんだけど、Bae Yoon Hwan、Suzanne Song、Hoh Woo Jung、Rinus Van de Velde、Song Burnsoo、David O’Kaneらの作品があった模様
写真とってるBae Yoon Hwanは国内の作家と言われてもあんまり違和感のないような作風のペインターで、今回の作品も「Acrylic on basketball」なので絵画である
その他の作品も(韓国の作家のものは)けっこう日本と同じような傾向が感じられたので、やっぱ近くにあるって影響は互いに大きいと思った
C11:ANOMALY
Tokyo

左の壁面 柳 幸典 "Wandering Position - Formica japonica 3 -", 1995
ちらっとCADANのチラシ映ってるのもポイントたかし先生
アノマリー!!(とりあえずでかいところには「!」をつけていく
ANOMALYは、2018年にHashimoto Art Office、Urano、Yamamoto Gendaiギャラリーが統合して設立されました。モダンアートから現代アートまで幅広いアーティストを擁しています。そのウェブサイトでは、「ヨーロッパやアメリカから持ち込まれた“アートギャラリー”のシステム」からの独立を宣言し、「極東の日本、東京」(具体的にはTerrada Art Complex)に位置づけています。また、単なる白いキューブ以上の存在を目指しています。2019年のアートバーゼル香港での初出展では、ギャラリーのブースは特に闘志溢れる反逆的なエッジを持って目立ちました。ANOMALYの他のアーティストには、伝統的な日本建築の精巧な木製モデルで2017年のヴェネツィア・ビエンナーレの日本代表となった岩崎貴宏や、イラク侵攻について米国を批判し、福島の災害や「クールジャパン」の陳腐さについて日本政府を批判した高峰忠士などがいます。
「2018年にHashimoto Art Office、Urano、Yamamoto Gendaiギャラリーが統合して設立」っていう出自なんですって
銀行かよ
それはともかくめっちゃ目を引く長門の鋳造作品がある
沈船風なのであきらかにビキニ環礁で標的艦になって沈んだ長門だってわかんだけど、「なんか長門っぽくねえな」みたいな違和感あった
よくみると、てっぺんに「電探」(レーダーのこと、昭和生まれは誰でも知ってた)が残ってる
これビキニに引っ張ってこられる前にとっくにぶっ飛ばされてね?と思ったんだけどやっぱりそうだと思う
沈む直前の長門の絵とか写真は昭和世代なら脳裏に焼き付いてるのでそれが違和感の原因だろう
(地味に艦橋構造物の形とかも違う気がするんだけどそれはまあいい
クロスロード作戦時の「長門」 pic.twitter.com/5uKFfzSBff
— GUMDROP@いいこと言おうとすると誤字るマン (@GUMDROPap9) July 30, 2019
でも作者はわざわざ沈んでる長門の写真とか撮って制作してるようなので、そんな人が間違うかいなって気分だったんだが、以下の記事を読む限り「プラモ」を資料にしてるようなので、ならあるわ
戦艦長門のプラモデルのパーツを70倍に拡大し、鉄の鋳物として制作した立体作品《Nagato70・Ⅰ-Ⅱ》とその設計図が展示されている。プラモデルはアメリカで普及し始めた1950年代初頭、在日の米軍関係者によって持ち込まれたと言う説もある。
↑のように作家は(もちろん)意図的にあえてプラモの型を使っているはずなので、コンセプトはわかんだけど、沈んでる船の姿に寄せてるくせにめっちゃわかりやすいとこを(ありし日のまま)残してる意図はわからん
どうしても日本人にとって物語性が強くなってしまう長門を物質というか事実として突き放すがための作品、なんじゃろう
この作品の占めるわりあいが高杉なためブースに対する感想はとくになし
C12:Ceysson & Bénétière
New York, Koerich, Paris, Lyon, Geneva, Saint-Étienne, Pouzilhac

久々に読めねえ・・・
GPT4君の意見
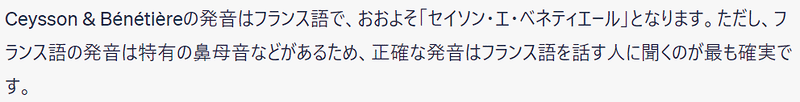
ほーん、なるほどね
なら「セイソン&ベネティエール」でいくか(「&」を「et」と読むかどうかは任せた
からのこの激短ステートメント(対訳でお送りします)
La galerie est heureuse d'annoncer sa participation à Tokyo Gendai avec Claude Viallat.
当ギャラリーはクロード・ヴィアラとともに東京現代に参加することを発表いたします。
https://www.ceyssonbenetiere.com/fr/fairs/tokyo-gendai-tokyo-2023-127/
生産性高すぎだろ
さすが年中打ちこわし&焼き討ちやってる国は違うな
日本人が全員この仕事の仕方だったらGDP3倍くらい増えそう
そんだけかい!
C13:当代唐人艺术中心 | Tang Contemporary Art
Beijing, Hong Kong, Bangkok, Seoul

唐コンテンポラリーアートについて
タン・コンテンポラリー・アートは1997年にバンコクで設立され、現在ではバンコク、北京、香港、ソウルに7つのギャラリースペースを構えています。
当ギャラリーは、重要なプロジェクトや展覧会のキュレーション、他の美術館や機関とのコラボレーションに全力を注ぎ、国際的に高い評価を得ています。
https://www.tangcontemporary.com/contact-en
資本こそパワー
日本には「成金=センス悪」みたいな幻想があるが、金余ればすなわちセンス高まっていくが現実っぽい
いまこのギャラリーが北京でやってるJoana Vasconcelosの個展とか超みてえ!!!
お客とギャラリーの人がめっちゃ大声で値段の話してたり(「ワンハンドレッド・サウザンダラー!?」「HK$」「オウ、HK$」)しててとにかく活気があった
まあ、核心がいろいろ変なことしてくれやがったので、すべては短い夢で終わっちまうわけだが・・・
ぜんぜん関係ない話だが、なんでこう中国人は「唐人」と言いたがるんだろうという疑問があったのでGPT4君に聞いてみた
「唐人」は、中国語で「中国人」を指す言葉です。唐は中国の唐朝(618年 - 907年)を指し、その時代は中国文化が非常に繁栄し、その影響力が広範囲に及んだため、中国文化を象徴する言葉として使われます。したがって、「唐人」は「中国人」または「中国文化を持つ人々」を指す言葉として使われます。
「唐人TV」や「当代唐人艺术中心」などの名前に使われるときは、中国文化を伝える、または中国人のコミュニティを象徴する意味合いがあります。
なんで漢人はだめなん?
「漢人」は確かに中国の主要な民族である「漢族」を指す言葉であり、中国の人口の大多数を占めています。しかし、「唐人」の言葉が使われる理由は、その歴史的な背景と文化的な意味合いにあります。
唐朝は中国の歴史の中で特に繁栄した時代であり、その時代の中国文化は広範囲に及び、多くの国々に影響を与えました。そのため、唐朝は中国文化の象徴として広く認識されています。また、唐朝は多民族国家であり、その開放性と包容性も評価されています。
つまり逆にいうと「漢」のイメージは
・文化的じゃない
・開放的じゃない
・包容的じゃない
ってことらしい
だいたい俺の印象と一緒だわ
(おまけに割ってんのも漢代のツボだったよな、という・・・
C14:Vito Schnabel Gallery
New York, St. Moritz, Santa Monica

Vito Schnabel Galleryは、現代美術の展示を行うギャラリーで、ニューヨークとスイスに拠点を持っています。創設者のVito Schnabelは16歳で最初の現代美術展をニューヨークで開催し、以来、多くのアーティストと関係を築いてきました。スイスのギャラリーは、アルプス東部のEngadin地域に位置し、ハイキングトレイルのネットワークの中にあります。2015年に設立されたこのギャラリーは、St. Moritzのリゾートタウンに囲まれた白いキューブの建物で、公共スペースでのキュレーションも行っています。現在は、Spencer Lewisの新作大型絵画が展示されています。彼の作品は、鮮やかな色彩と強烈な物理性を特徴とし、視覚的な力を引き出すために画面を過剰に作業することで知られています。
引用元: The Aficionados
ここも壁サー(ぺろたんの横)
美女にモテることでも有名なヴィト・シュナーベルだが、「16歳で最初の現代美術展をニューヨークで開催」とかやっぱそういう「人生3周目」感なんだなという印象
フランチェスコ・クレメンテのたぶん新作っぽい(2023だから)水彩を展示していた
くぅ~~疲れました! 以上でCは終了!!!
だいたい半分くらい来た気がする・・・
次はDからだで
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
