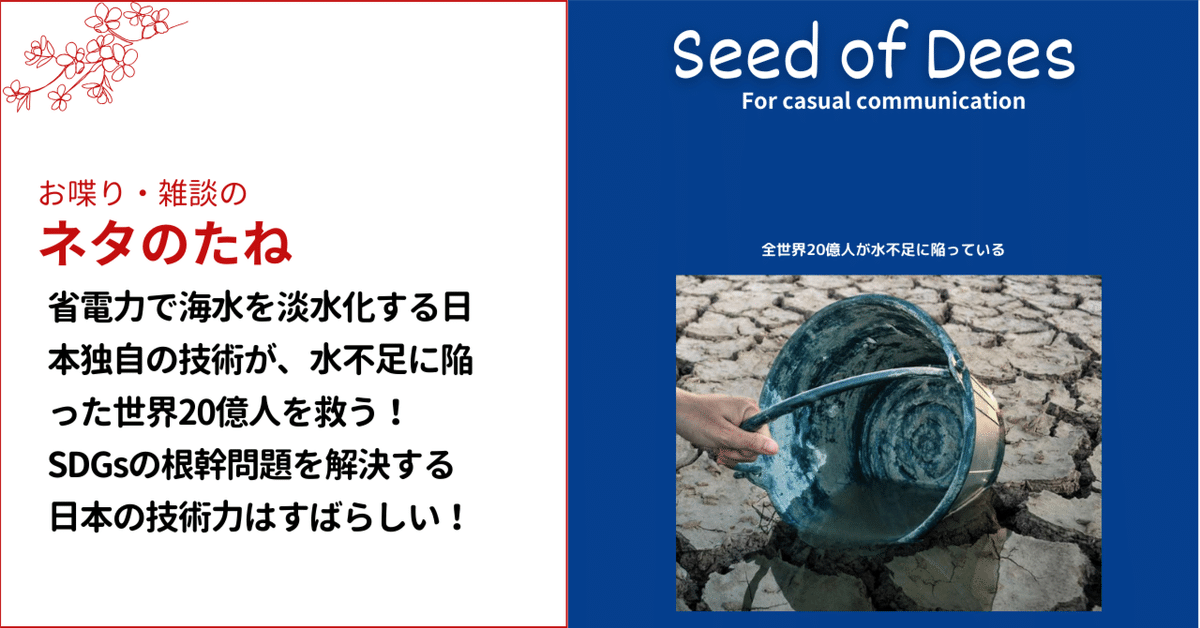
省電力で海水を淡水化する日本の技術が、水不足に陥った世界20億人を救う!SDGsの根幹問題を解決できる日本の技術力は捨てたもんじゃない!
こんにちは、今日の「ワイドナショー」のテーマが僕の記事と2つもダブっていてご機嫌なDJムッチーです。
水資源に恵まれていて、衛生的な水がいつでも気軽に使える日本にいると気付かないことですが、世界20億人の人が安全な飲み水がない状態なのです。
そして、世界の約7億人が、水不足の状況で生活しています。不衛生な水しか得ることが出来ないことによって、毎日4900人、年間では約180万人の子どもたちが亡くなっているのです。
単純な人は、水を送ってあげないといけないと考えてしまいますが、そう簡単な問題ではないから、このような様態なのです。
ではお金を寄付しようと言い出す人もいますが、水不足の国ではお金でお水は買えないのです。

海水を飲み水に
地球上にある水の98%は海水で、淡水は2%でし。淡水の内、飲み水として利用できる水は全体の0.01%にも満たない量です。
海水を淡水に変えればいいじゃないかと考える人は多いでしょう。
海水から真水を作るには熱を利用するか、濾過膜を利用するかの、2つの方法があります。 以前は海水を熱して水蒸気を集めて淡水にする方式が主流でしたが、これでは燃料費がかさんで、中東のお金持ちの国でしか実現できていませんでした。近年は熱利用はCO2を大量に発生してしまうので、問題視されていて減少傾向にあります。
そこで、最近では海水に高い圧力をかけ、濾過膜を通過させて塩分や不純物を除去する方式が優勢になっていますが、高圧を作り出すのには大量の電飾が必要ですから、やはり中東のお金持ちの国でしか実現していません。
日本の技術力
熱を利用する方法
電力を使わずに海水から真水を得る技術が東京工業大学と大阪のベンチャーエクスフュージョン社によって基礎技術が開発されました。
真水を作る基本構造は、従来の熱を利用する方法に近いのですが、電力を使わずに熱を作り出す点が比類を見ない技術で、日本の環境技術が世界の水不足の解決につながると高い評価を得ています。

開発した基礎技術の最大の特徴は、電力がほぼ不要だということです。液体金属のなかでも錫(すず)に着目したことが、ブレークスルーの始まりでした。錫は融点が約230度と比較的低く、熱が伝わりやすい。これを太陽の光を集めて温め、300度ほどまでの熱い液体になったところに海水を吹き付けて水蒸気を発生させます。この水蒸気を集めて、真水を得る仕組みです。
液体の錫はその後冷えても、太陽熱で温めることで再利用が可能で、新技術はほぼ電力は必要ないのです。
錫が冷える過程で、副産物として海水に含まれるリチウムやマグネシウム、モリブデンなどが固まって出てきます。リチウムは核融合発電の燃料として、エクスフュージョン社が目指すレーザー型核融合炉での活用が期待されます。
このシステムは、現在実験室内の小さな装置で水の生成に成功した段階。2025年にも規模を大きくした実証装置が稼働します。
大きなプラントを作る資金が乏しい国への政府支援として日本から造水プラントを提供することで、世界における日本の価値を獲得できますね。
能登半島地震では、水道復旧に時間がかかりましたが、このシステムが実用化されれば、災害時の水対策にも使用できるようになるはずです。
この開発は、留学生の一言から始まったそうです。
東工大ゼロカーボンエネルギー研究所の近藤正聡准教授は、核融合炉を冷やすのに必要な液体金属などを研究してきたそうです。ところがエジプトから来た留学生の「まずは水です」との一言で、海水淡水化への応用研究が始まったそうなんです。切実な思いは人を動かすという事が良く分るエピソードですね。
近藤淳教授は「実用化へと踏み出せる段階にきている。徐々に水の生産量を大きくしたい。」と胸を張っておられます。
濾過膜を利用する方法
日本触媒と東洋紡エムシーは、既存のろ過技術に比べて電力を3分の1に抑える手法を開発しました。大幅に電力を抑えた濾過膜による淡水化装置で真水の量産に既に動きだしています。

プラントには東洋紡エムシーが開発・製造する濾過膜「FO膜」と日本触媒が開発した、液状の浸透圧発生剤とを組み合わせて真水生産を行います。
浸透圧発生剤が溶け込んだ液と、海水の間にFO膜を置くと、海水側から水分子が膜を通って溶液側に集まってきます。溶液は加熱すると発生剤と分離して真水のみを得られるしくみです。
従来は浸透圧を発生させるために電力を用いていましたが、この仕組みにより省電力が実現したのです。
(水は浸透圧の低い方から高い方へと動く性質があります。)
日本触媒が独自技術で発生剤の性能を上げたことで、他社が用いた従来の発生剤とFO膜を組み合わせた場合より造水能力が30%高まりました。海水からどのぐらい水を得られるかを示す回収率は65%で、既存技術の「ろ過膜」システムより高い水準を確保しているそうです。「大量な電力の確保が難しい島しょ部など現行のROシステムでは経済的に造水が難しい地域に水を届けられる」と日本触媒は期待しています。
このプロジェクトは2023年に1日500立方メートルの水を海水からつくる実証に成功しています。次の目標は米企業トレビ・システムズとの共同でハワイに大規模プラントを建設することです。大規模プラントでは1日6000立方メートル規模の真水を海水からつくる計画なのだそうです。
真水生成の現状
現在の真水生成施設では、水不足の地域での需要もまだ十分にまかなえていません。実用化済みの海水淡水化技術で生成されている水は1日あたり1億立方メートルで、単純計算でまだ4億人分ほどの量しかない状況です。
ウガンダやインドなどでは、水不足に伴って水の使用量が減ってきているという調査があります。地域によっては水不足が引き金となって、GDPを押し下げる影響があるという試算も出ています。
世界的な水不足は、人口の急増により食物確保のために灌漑農業が進んだことが原因とされています。これら農産物を輸入に頼る日本も、実は間接的に水不足の国といえるかもしれません。
中国人が日本の水源の土地を買っているのも、本能的に水不足の不安を感じているからでしょうね。
すぐ成果が出るAIの研究もいいですが、人間の生活の根幹にかかわる基礎研究にもっとみんなで真剣に取り組みましょう。
使命を感じてくれる若い人の背中を押して揚げてください!
それでは、今日はこの辺で失礼します。
話のネタに困ったら使ってくださいね。
皆さんからのサポート心よりお待ちしています。。。
よろしくお願いします、
スキとフォロー、コメント、とてもうれしいです。
じゃあまたこの次
本好きのDJムッチーでした。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
