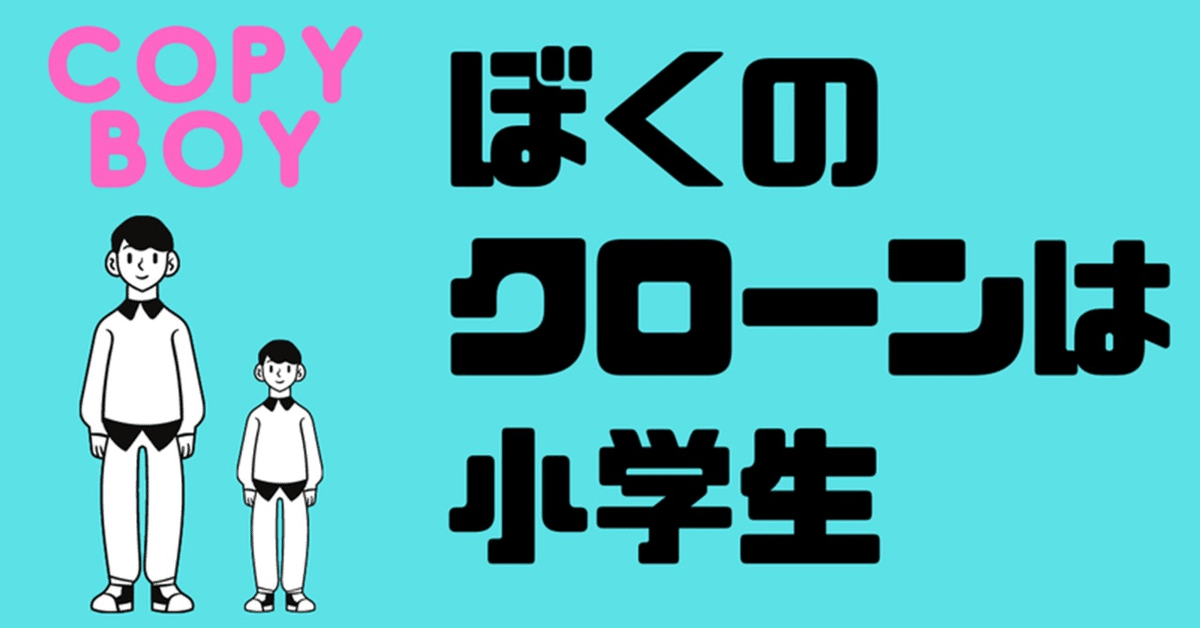
"COPY BOY" ぼくのクローンは小学生【おはなし】
【★おはなし本文の前に…】
ダメなパパが娘のために書いた”おはなし”。
どんな”おはなし”かを、
noteやtwitterの皆様が温かく紹介して、
なぐさめてくださっています。


あれ? 目から水が…。 https://t.co/Y93ZcuKWF4
— strawberrymoon 何か書いている人🤫 (@strawbe70580821) November 10, 2021
ありがとうございます。
そもそも”COPY BOY”というおはなしは、
ダメなパパが思春期の娘をビックリさせようと書いてみたら、
「あーあ」と情けない結果になってしまったモノです。
↓↓↓ こーんな風に…
【★おはなし本文です】

本文のみをまとめました。全33話。
読みやすい挿絵画像ありのオリジナル版の方はリンクからどうぞ。
■第1話 はじめに
ワケあって、
僕はクローンと暮らしている。
そいつは「チビ」。小学2年生。8歳のまだ子どもだ。
顔は、幼い頃の僕と全く同じ。姿も同じ。ホクロもすべて同じ位置にある。
21歳大学生の僕と、好きな食べ物も同じ、爪をかむクセも同じ。
生意気にも、同じ相手に恋をする。
僕たちは、とっさの言葉や行動が同時にシンクロすることがある。テレビの双子タレントみたいに。
ジャンケンするとなかなか決着がつかないことも。
この世にクローンがいる。
…なんて、もちろん信じていなかった。
だからアマゾソでDNA鑑定キットを買った。
綿棒で頬の内側をなぞって僕とチビの細胞を送ってみたら、業者から返ってきた報告書には、まるであきれたかのように簡単な一文だけがあった。
「一致。同一人物のDNAです。」
なんで、こんなことになっちゃったのか。
よかったら、そのワケを聞いてほしい。

■春、第2話 出会い!
「あなたはタイムマシンで過去へ行きました。
そこで出会ったのは、子どもの頃の自分。
未来から来たあなたは、一体何を伝えますか?」
こんなのどう答えりゃいいんだろ。正解のない質問をして、対応力をみる。入社面接はまるで禅問答だ。
「子どもの頃の自分に…ですか?」
面接官に質問返ししてしまった。
「そうです。どんな未来を伝えますか?」
「えーっと…」苦し紛れに「…えっと…『就活大変だよ』…とか?」
たっぷりの愛想笑い。でも面接官に能面みたいな顔で、
「あー、なるほど…。以上です。ありがとうございました。」とぶった切られた。
グールグル、アッパレ…流行りの企業名ばかりを選んで、かたっばしから受けまくり。どうせなら高望みしたい。だけど連敗記録50社を更新する、大学4年の春。
不合格のたび「あなたには価値がない」と切り捨てられる恐怖。社会に放り出される日はひたひたと近づいてくる。
でも、本当は何をやりたいのかわからない。一体ぼくは何者なのか。何のために生まれてきたのか。ただ、ただ、あせる。
スタパのテーブルで一人、僕はさっきの面接の反省会をしていた。タイムマシンの模範解答は一体何だったんだろう?子どもの頃の自分に何を伝えれば良かったんだろう。
後悔の沼に、ずぶずぶずぶずぶ。
「はぁー」
コーヒーの水面に映る自分を見つめた。つまらないリクルートスーツ姿。僕って何者なんだろ。ローストされた豆の香ばしい香りが立ち込める店内。まだ一口も飲んでいないのに、苦い。
しかし…
どうも集中できないなぁ。
さっきから店内に響いている甲高い声のせいだ。ママ友グループと小さな子どもたち。店内にバラまかれたように大勢居座って騒いでいる。近くに住宅街でもあるのだろうか。
ん?何かが膝に当たる。小さな汚れた運動靴。隣の席の男の子だ。寝ころびながら遊びに夢中になって、僕の深い紺のズボンに泥を擦りつけていた。だから子どもは嫌いだ。ママたちはおしゃべりで気づきもしない。無邪気な侵略はどんどんエスカレートしていく。テーブルのコーヒーが揺れてるよ。いつかこぼすぞ。
テーブルのスマホがバイブで小さく滑りながら鳴った。
面接の結果か?と期待したが、知らない番号。エントリーしている企業ではなさそうだ。
隣の子どもたちがキャーと叫ぶ。
うるさいなあ。喧噪に負けないよう大きめの声で出た。
「はい。」
「もしもし?」
と電話の奥で、若い女性の声がかすかにした。
「もしもし?」
「もしもし?聞こえますか?」
「はい、なんとか。」
「しおつま…、汐妻ユタカさまの携帯でしょうか。」
勧誘かな。
「すみません、聞こえづらくて…。」
きっと面倒な電話だろ、そんな気持ちも手伝って、ちょっとぶっきらぼうに答えた。
「…ちょっと騒がしいですね。」
「そうなんです。では…(また今度に)」切り上げようとした尻尾を掴まれ、
「では、会って直接お話しを…。」
ん?気配に見上げると、
「…させていただいてよろしいでしょうか?」
スマホを耳に当てた女性が肉声で僕に尋ねた。
少しばかり年上だろうか、まあるい眼鏡の奥の大きな瞳で僕をのぞきこんでいる。
「え?え?」
頭が追い付かないうちに、彼女はするりと正面に腰掛け、
「突然、申し訳ありません。何度かメールもお送りしたんですが…」人懐っこい笑顔になった。
彼女は、「わんわんほけん」と、名乗った。スーツ姿。やっぱ勧誘か。
「知らないメールは開かないことにしてまして…。あの、どな…?」
僕の言葉をさえぎって、
「実は、汐妻ユタカさんにお伝えしたいことが。」
「なんで僕の名前を?」
「ご家族のことです。」
「家族?」
「ええ、ご家族。」
「ばあちゃんと二人暮らしなんですけど…。」
なに真面目に答えてるんだよ。相手のペースに乗せられんなよ。保険なら入らないよ。
「ああ、やっぱり。」
「やっぱりって?」
「何もご存知ないんですね。」
「何も?」
「あの…。」急に神妙な面持ちになり、周囲をうかがいながら「いきなりで、大変失礼なんですが…。」
「はい?」
「こんなところで、誠に申し上げにくいのですが…。」
小声で、ぐんと顔を寄せた。近いし。
なに?なに?
「ねえねえ!!」
突然叫ぶ子ども「おねえちゃん、ほらこれ面白いよ!」下からだ。
メガネの女性は、やれやれとため息をつくと体ごとテーブル下に潜り、やさしい声で、
「今ね、お兄さんと大切なお話し中だから、おとなしくしててね。」
ほんとだよ。さっきから気が散る。チビめ。
気にせず、床でミニカーのドライブを続けているチビ。てか、誰がママなの?外で遊ばせたら?
彼女はテーブルの下から這い出て僕の方へ居直り、あらためて静かに言った。
「誠に申し上げにくいのですが…」
「はい」
「…お父様が、先月亡くなられました。」
「……へ?」
「はい。」
神妙に告げられたはずなのに、全く現実感がなかった。
「胃がんでした。謹んでお悔やみ申し上げます。」
こんな話、スタパでする?言葉が入ってこない。あたりまえだ。なぜなら、
「あのぉ、両親はとっくに他界してまして。」この世にいませんけど。
「どのようにお聞ききになっています?」
「父は私が中学生の時に事故で。母は私を生んですぐ。」
彼女はやはりという顔で、
「そうでしょう。ですが実は、お父様は…」
「え?」
「ええ、そうです。生きていらっしゃいました。先月まで、あなたの知らない所で。」
「まさか。」
「…で、」業務的な口調になり「今日は、お父様が生前残された"ある案件"について、ご子息であるあなた様、汐妻ユタカさんにお譲りしたく…」
「父が残したあんけん?保険の?僕に?」
話が見えない。
「こちら…。」
メガネの瞳が落とした視線をたどってみると…テーブルの下。
「…こちらのお子さんのことです。」
「……?」
「お父様がお育てになっていました。…あなたの弟さんになります。」
子どもいたんすか!!
ドン!!
と突然テーブルが揺れ、コーヒーがこぼれた!
チビが勢いよく立ち上がろうとテーブルに頭を打ったらしい。
「あー!ふくもの!ティッシュでもいいから!」
周りの大人は慌てたが、運動靴のチビは頭をさすりながらオモチャをいじっている。
くそ、エントリーシートがびちゃびちゃ。
うそでしょ。
父が生きていて、子どもがいた?養子とか?
えっ、まさか…
「血は…?」
「つながっています。」
再婚してた?子どもがいた?
いきなり、知らない弟と感動の初対面?
「この子は8才。小学2年生です。あなたと同じユタカという名前です。」
「は?僕と同じ名前をつけた?」
「はい、弟さんにも。」
「父が?」
「いきなりなので理解しづらいかもしれませんが…。」
「はあ。」
「このお子さんは…。」
「はあ。」
「あなたの…。」メガネちゃんは深く息を吸って、言った。
「あなたの、クローンです。」
「はい?」
チビが顔を上げて僕を見つめた。
■春、第3話 これが僕!?
永田町にほど近い、外堀通りを見下ろすようにそびえる高層ビル。
長いエレベーターを降りると、真っ白い壁が立ちはだかっている。どこから入ればいいのだろう。
「わんわん保険」という野暮ったい呼び名に似合わず、「ONE ONE INSURANCE」とモダンなロゴが間接照明で浮かび上がっていた。
真新しい建材のいい匂いと、かすかなお香の香り。一本足の小さなカウンターにちょこんと置かれたタブレット。「お約束の方」という表示を選んでタップすると、「顔を写してください」と指示。シャッター音とともに、画面がフリーズされ、光が下から上へ…スキャンだろうか。やがて音もなく壁が開いた。
ロビーは思ったより広かった。天井が高く、一面の窓を生かして、無機質だが白を基調にした開放的で上品な空間が広がっていた。別世界。こんなオフィスで働ける人間もいるんだな。
奥に誰かがぽつんと座る。あのメガネの女性だ。片手にコーヒーカップ、片手にスマホ姿で不意を突かれて固まっている。グミみたいな緑のソファーの上、油断そのままで丸いメガネの瞳を丸くして。
「………。」
「あのう…。」
「はぁっっっ。」我に返り、グミから飛び起きた彼女は「あ、すみません、お早かったですね。」とカップを置くと、「こちらです。」と案内してくれた。
「この人、存在してたんだ」
今日は柔らかな私服ということも手伝ったのだろう、妙な安心感があった。
スタバでの一件は夢だったんじゃないか…と心配だった。就活が辛すぎて僕は頭がおかしくなったのか?いもしない女性のまぼろしを見たのか?確かめないと通常の生活に戻れない気がして。しばらく気が気ではなかった。だから訪れたのだった。
真っ白な廊下を進む彼女の背中に、
「あの…」
「はい」
振り向いたのは、あまりに無垢な表情だった。言いづらくなった。
「先日のお話…」
「はい。」
すれ違う白衣の人々が、僕の顔を見るたび振り返ってコソコソ話している。なんだよ。
「正直、あまり覚えていなくって…。そもそもおっしゃった意味も理解できていませんでしたから」
「大変失礼しました。そうですよね。いきなり過ぎましたから。気分を害されたのは当然ですよね。」
「すみません。あの時は、なんだかよく分からなくて。エイプリルフールだったし。怒っていきなり帰ってしまって、ほんとすみません。でも、なんていうか…わざわざあんな妙な冗談を言いに来られた理由が気になって。こちらをググってみて。とにかく、お話を聞くだけでもと…。」
気恥ずかしさでしゃべりすぎ。
「ありがとうございます。よかったぁ。」
メガネちゃんはあの人懐っこい笑顔になった。
◆
待たされた会議室は、4面を覆ったガラスに化学式のような白い記号が美しく幾何学的にプリントされていた。洗練されたデザインに似つかわしくない、ガヤガヤ声とともにおじさんおばさん3人組が入ってきた。
「いゃぁ、わざわざお越しいただいて。」
僕を見るなり、なぜか互いにほくそ笑み合う。
なんだなんだ?
「すみませんね、先日は驚かせてしまって。少々荒っぽかったですが、おかげでお目にかかることができました。犬巻と申します。」駄菓子屋のおばちゃんみたいな顔に、厚化粧で高級そうなスーツがどうも不似合いだ。馴れ馴れしくも妙に慇懃無礼な口調で名刺を差し出した。
そうだ、名刺の受け取り方とかも練習しとかなきゃな。シューカツ的には。そんなことを考えていた、まだその時は。
犬巻渕子の名刺にはCEOとあり、その隣には、「ないかくふ?」
「内閣府の者です。保険会社なんですけどね、私は出向みたいなもので。」
おじさん二人は、ただ黙ってニコニコしている。東京大学医学研究科の遺伝子工学やらなんやらの権威という教授と顧問弁護士。一度に紹介されても覚えきれない。
「すっかり暖かくなりましたね。朝晩は冷えますけど。さっきも四谷の桜がすっかり満開でしたよ。これ、赤坂青野の栗大福です。日本茶でよろしいですかね。」
犬巻がよっこいしょと座った。
「まずは、わが社についてね。こちらを観てくださる?」
大きなモニターでビデオを見させられた。可愛い犬と飼い主の楽しそうに遊ぶスロー映像がゆっくりフラッシュする。小田知正風の泣けるBGM。テロップが入る。
”愛するペット、もしも早すぎる別れが訪れたら、あなたはどうしますか?”
どうやらペット保険を扱っているらしい。
わかったところだけ、かいつまんでいうと…、
例えば、ペットの犬が死んだとする。保険で支払われるのはお金ではなく、犬そのもの。しかも、愛犬と全く同じクローン犬。
”愛するペットの死を受け入れられない飼い主が、もう一度一緒に暮らしたい…”
そんな想いに応えるため、愛犬をDNAから培養して、全く同じクローン犬を飼い主の元に帰す保険だった。
そういえば、そんなニュースを見た気もする。
「わが社のクローン技術は、あなたの亡きお父様、汐妻教授のご尽力によって、世界に類を見ないほどの高いクオリティーを実現しました」
「はあ」
「と、いうわけで、あらためてご紹介します…」犬巻が誇らしそうにドアを指し、
「あなたのクローンです。」
部屋に入ってきた汚れた運動靴。
メガネちゃんの手にぶら下がりながら後ろに見え隠れする影。彼女の腰に隠れて、恐る恐る覗く目。場に不似合いな小さな男の子。
小学生も下の方だろうか。目深に被った野球帽の下に愛想のない表情。爪を噛みながら一重まぶたで僕ををチラリと見た。知らない大人に緊張しているのか、そっぽを向きワザと気にせぬフリをしている。
今日あらためて見てみたが、やっぱり可愛くない。
「こちらのお子さん、8歳のあなた自身です。」
「8歳…。」
アニメの巨匠、宮崎腹男に似た山羊教授。白髪交じりのヒゲに埋まった口を開いた。
「汐妻さん。いやぁ、すっかり大人になられて。お父様とは旧生物工学研究所の悪友でしてね。」僕を嬉しそうに見つめ恍惚の表情で「クローンって聞いたことありますよね 。」
「はあ。映画とかで。」
「あなたと全く同じ遺伝子配列を持っている同一個体とでも申しましょうか。この子、あなたより9年遅れて生まれたクローン人間なんです。」
「あのう…」
「9年前。当時12歳のあなたから細胞を摘出し、核から培養を始めました。10ヶ月経過するとヘソの緒のチューブを外して、溶液プールから出たところを分娩と見なします。そこから8年。だから8歳的な。」
「的な…?ちょっと待っ…」
「我々は年齢を、そう数えています。」
何を言ってるのだ、このヒゲのおじさんは。
…あの、よくわかんない話すぎて…。理解できないんで、もう少し分かるように説明してもらえませんか。現実ばなれ。だいたい、どう見たって、こんなクソ可愛いげのない子どもが、僕のはずが。
犬巻がタブレットの写真を見せた。
「これ、あなたですよね。お父さんがお持ちでした。」
当時の父と僕が写っている。
「ああ、父と住んでいるころに後楽園ゆうえんちに行きました。僕も持ってます。この写真。」
「子どものころのあなたの顔、よくご覧になって。」
「はい見てます……」
犬巻が指で大きく引き延ばした。覗き込むと、画像が少し荒いが、やや眩しそうにしかめっ面をした、おせじにも可愛いと言えない僕の一重の目と低い鼻。への字に結んだ薄めの唇。
「くらべてくださいな。」
目を移すと、今、目の前に、そっくりそのまま寸分たがわぬ姿で遊んでいる子ども。なぜかTシャツも写真と同じだ。
「ほらね。」
に、似て……る。
「似てます、かねえ…」
動揺を悟られないためには、他人事みたくつぶやくしかない。
ヒゲのヤギ教授は嬉しそうに、うんうんとうなづく。
「ほんとうに、そっくり!まるで芸術品よね。ほら、帽子をおとりなさい。よーく、顔を見せて差し上げて。」
嬉しそうに、犬巻がそいつのシャツをめくると、小さなおへその横にホクロが申し訳なさそうについている。子供用のスニーカーを脱いで、小さな靴下を引っ張ると、左足小指がエビのように曲がっている。
「あなたも同じですよね。」
家のばあちゃんしか知らないはずなのに。
「あなたさっき、受付でどうやって中に入りました?」
「エレベーター降りたとこのタブレットで」
「こうさいにんしょうです。眼球の虹彩認証。」
「ええ、撮りました。」
「我々はあなたのデータは入力していません。しかしあなたは中に入れた。事前に別の虹彩を登録していたんです。」チビを顎で指し「…その子のね。」
少年が、その瞳で僕を見あげた。
「確かめて。指紋もすべて同じはずですよ。」
ちょ、ちょ、ちょ。ちょっと待ってくださいよ。そんな話、信じろって言ったって無理です。
人間はまずいっす。人間は。倫理的にアリなのこれ?突っ込みどころが渋滞しています。どこから手をつければいいのか。
そうだ、これは趣味の悪いドッキリかもしれない。
そもそもなんで?本当の話なら、なんで僕にクローンなんて??
「ええ、ええ、ご乱心はごもっともです。いろいろ聞きたいこともおありでしょう。そのへんはまたゆっくりお話ししてまいります。」犬巻は日本茶をすすって、
「で、本日は2つ、素敵なお話があります。」
ひとつ目は、
「この子と一緒に暮らしてください。」
「は?」
「この子はあなた自身です。お父様が亡き今、残された忘れ形見のこの子をあなたが引き取るんです。残された子どもたち同士で手を取り合って生きる。素敵でしょ。ね。」
いやいやいやいやいや。
「素敵ではないです。」
子供を預かるなんてムリっしょ。僕は就活中の身で、僕のバイト代とばあちゃんの年金で細々と暮らしているんです。
「その点はご心配なく。ふたつ目の素敵なお話。お給金が出ます。」
「おきゅうきん?」
「汐妻さん、就職活動をされているとか。」
なんで知ってんの?
「急すぎて…。何をするのかもわかってませんし。」
「この子と一緒に暮らす、ただそれだけです。行動を共にし、ひとつ屋根の下で生活してください。時々、レポートしてもらえればOK。ウチに就職したと思えばいいじゃないですか。」
内定がこんな形で目の前に…。
いや、いや、いや、グールグルとかオシャンティな企業でなくていいの?こんな訳の分からない仕事でいいのか?僕が人生を捧げたいライフワークはまだ見つかっていないのに?
「報酬は月30万円。養育実費としてさらに20万。併せて50。臨時で必要な経費があればその都度ご相談できます。ね。素敵でしょ。」
ご、50万…。
一緒に暮らすだけで月50まんえん?
話だけでも聞いてみるか。あとから断れるし…就活しながらできるかも。
「決まりね。これからは内閣府付特別研究員の猫塚がいろいろケアさせていただきます。」メガネちゃんは猫塚というらしい。「LIMEでも交換してください。」
「QRコードでいいですか?」互いにスマホを重ねる。なんだか照れ臭い。とか、こっそり思ってみたりする。
「その代わり」
今度は、弁護士が口を開いた。
こっちは俳優の温水洋ニ似の鶴田。テカった頭の上にふんわり産毛が申し訳なさそうに乗っている。だからツル田は覚えやすい。
「この子がクローンだという事は、決して口外しないでいただきたい。高度に厳しい機密になりますので御注意を。契約書と守秘義務誓約書と保険の約款にサインをお願いします。ちょっと多いですが…。」
目の前に分厚いファイルが「どん」と積まれた。
「Tvvitterで『クローン人間なう』とかつぶやいちゃダメですよ」と、にやりと笑った。
家で待つばあちゃんに、なんて話せばよいのだろう。
僕は栗大福をかじった。
■春、第4話 家に来た!
今日、クローンが家に来る。
心の準備もできず迎えた朝。昨夜は寝れず、眠気が覚めない。まだ夢うつつのような気分で爪を噛む。
「おはようございまぁす!」
丸メガネの猫塚キナコの張り切った声と、ガラガラ引き戸の音でふと我に返る。
チビは猫塚に小さな手を引かれ、古いランドセルを背負って玄関にたたずんでいる。なぜだか僕が子どものころに着ていたのと全く同じ犬のイラストのシャツ。少し汚れた運動グツの足をモジモジさせながら爪を噛んで突っ立っていた。
こっちは大人だ。「こんにちは」と言ってやる心の余裕は持っている。ヤツはペコリともせず、もじもじ郵便受けをイジっている。
猫塚が「こんにちはって」と促すとようやく小さな声で「…こんにちは」という言葉をやっとこさひねり出した。
可愛くない子どもだなぁ。確かに僕もこうだったかもな。似ちゃってなんだか悪いね、と少し思った。
「ゆーちゃん、お客さん来たんかえ?」
奥からばあちゃんが声を上げた。
ばあちゃんには、知り合いの子どもを預かるとだけ話していた。守秘義務があって良かったかも。「クローンの孫がいたよ。」なんて、さすがに体に毒だ。
ばあちゃんは、小さな子どもが家に来るのが余程楽しみだったのか、古臭い一軒家の中をまるまる一週間掃除していた。
ぞうきん片手に玄関の縄暖簾から顔を出し、ドアの前に佇むちいさなユタカを見つけて、「あら」と顔を見つめた。
「‥‥‥」
目を大きく見開いたばあちゃんは、言葉も出ず凝視した。やばい、バレるか…。
と思いきや、ほっとした笑みをこぼし、
「ゆーちゃん。」
僕の名で呼んだ。
「ばあちゃん、僕じゃないよ」
「ゆーちゃんやろ。ゆーちゃんや。」
僕にそっくりだと言いたいのか、頭が混乱しているのかはっきりしなかった。ただ、たいそう喜んで、小さな手を引っ張って奥へ連れていった。
実は、先週チビと会ってから、僕は熱を出して寝込んでいた。考えるほど、このトラえもんみたいな話、ありえない。
クローンどころか”子どもと暮らす”、こんなことには慣れていない。なにを用意すればいいのか、ググってみた。
「クローン 子ども 一緒に住む 準備」…キーワードで検索しても、「検索条件と十分に一致する結果が見つかりません」と出るばかり。
とりあえず、近くのイヨートーカドーで新しい布団や、子ども用の歯ブラシ、下着や本、お菓子などを買っておくしか僕にできることはなかった。
「これ、どこへ運びます?」
ダンボール箱を抱えながら猫塚キナコが言った。着替えの服や身の回りの物。続いて、アニメの巨匠似のヤギヒゲ教授がニコニコ嬉しそうに助手たちを引き連れ入ってきた。いくつものジュラルミンケースを運び入れ、慣れた段取りで居間に小型カメラを設置し始める。昭和40年代建造のくたびれた日本家屋の柱やらんまに最新鋭のデバイスが似合わない。しばらく僕たちの生活を記録したいらしい。これも給料の一部だ。
ばあちゃんには、チビの健康管理のためとか、YouTofuで配信するとか言っておこう。
チビはテーブルでモナカをくんくん嗅いでおいしそうに食べた。
「おいしいおすか?」ばあちゃんが聞くと、こくりと頷いた。「そうかいな、そうかいな」
食べる前に匂いを嗅ぐのは僕のクセでもある。チビの顔をじっと見てみた。
「よう、うまいか?」
話してみる。食べる手を止め、僕の目を見て…知らん顔をした。
なんだよ。可愛くないなあ。
これが僕か…。一週間ぶりに見たけど、まだ半信半疑。顔を見ていると、畏れと近親憎悪のようななんとも言えない気持ちになる。こいつも、そう感じているのか。
「ねえ、ユタカくん!」猫塚の声がしたとき、
「ん?」
「ん?」
僕と「小さな僕」は揃って同時に振り向いた。
ヤギヒゲ教授たちは「シンクロニシティ!」となぜか嬉しそうにざわめいた。一緒に笑う猫塚。「ははは。ですね。ややこしいですよね。」
当然名前が同じ。並んで振り向く大小2つの同じ顔がマヌケに見えたらしい。
教授は「二人がこんな近くにいるなんて。たまらないです」と恍惚の表情。
僕ら二人は、どう見えてるんだろう。
ふとスマホでツーショット自撮りしてみた。同じような顔が並んでる。気持ち悪い。アプリで自分の顔を移したみたい。小さな僕がモナカをくわえている。
こいつの部屋を作らなきゃな。
机も本棚も二階の僕の部屋にしかないから、仕方なく荷物を運び入れた。僕は他の部屋に寝ればいい。
「ここに置けばいいですか」猫塚が荷物を置いていく。「へぇ、もう少し散らかってると思ってました。」と笑った。
「ばあちゃんが片付けたんです。今日のために。」
「やっぱり。小さなユタカくんも全然片付けられなかったみたいです。お父様との家も、竜巻に遭ったみたいにおもちゃが散乱してましたよ。ふふふ。」猫塚さんはよく笑う人らしい。よく見るとメガネの奥はどことなくガッキーに似てるかな。いや、ガッキーだと思うことにする。せっかくだから。
ダンボールの中を開けてみて驚いた。全部、僕の子どもの頃と全く同じデザインの服だ。
「父はなんのために服まで似たものを用意してたんですか?」
「それはコピーではありません。ユタカさんが着ていた服そのものですよ。お父様は、あなたの子どもの頃の服をすべて残していたんです。この子に着せるために。」
「どういうつもりで?」
「それは…わかりません」ふと、寂しそうな目をし、「あの子、お父様がなくなってから、周りの大人にはしゃいでみせるんです。なんだか、それが余計に可哀想で。」
「そのくせ僕とはまだ一言も話してませんよ。」
ヤギヒゲ教授が階段からひょっこり顔を伸ばした。
「戸惑ってるんですよ。子供心にわかるんじゃないですか。やっぱりあなたに対して、他の人と違う何かを感じているんでしょう。」
「そうなんでしょうか」そう言われても、まだ半信半疑。
「私たちはそろそろこのへんで失礼します。家の前にバス停があって便利ですねぇ。それじゃ、わからないことがあったら、なんでも”猫ちゃん”に聞いてください」トントントンと降りていった。
へぇ、猫ちゃんって言うのか。
絵本の間から、1枚の写真がひらひら落ちて、足の親指に優しく当たった。拾って見ると、父ちゃんが幸せそうに笑っていた。その横にちょこんと幼い僕が肩を抱かれて笑っている。いや違う、僕じゃない…、チビだ。父が少しだけ歳をとっていた。自撮りしたのだろうか。腕を伸ばす父。その後ろに遊具が見えた。公園かな。仲良かったんだな。僕の知らない、父とチビの重ねた年月がそこにあった。うらやましいような不思議な気持ちになった。
父が亡くなってから、チビはひとりでこの写真を眺めているのだろうか。
その夜は、僕とチビと猫ちゃんとで、ばあちゃんのカレーライスを食べた。コンコンとスプーンを鳴らし、カレーのルーとご飯をぐちゃぐちゃに混ぜるチビ。そういや、僕もこんな食べ方してたっけな。
「ユタカ君、得意な科目は図工なんですよ。ね。」
猫ちゃんが水を向けるとチビはカレーを突きながら「うん」とうなずいた。
「ユタカさんも…」二人が振り向くもんだから言い直す。「えっと、大人の方のユタカさんも、図工お得意なんですか?」
「ええまぁ。子どもの頃ですけど。」
「…呼び方決めた方がいいかもですね。」
「名前が同じだしなあ…。」
猫ちゃんがチビに聞いた。「ユタカお兄さんって呼べる?」
「イヤ。」
「じゃ、なんて呼ぶ?」
何も言わず、ぷい。
なんだよこいつ。なんか肌が合わないな、クローンだけど。
これから一緒に住むんだぞ。僕の不満顔を見て、猫ちゃんは可笑しそうに笑いをこらえた。
ばあちゃんが
「お風呂入りや。ゆーちゃん二人で入ったらよろし。」
と言ったその瞬間、
「えー!」
「えー!」
「やだ!」
「やだ!」
また揃った。
猫ちゃんは笑いながら「気が合いますねー。教授によると、とっさの反応ほど揃うようですよ。一緒に暮らしていると、よりシンクロ度が増していく可能性が高まるそうですよ。」
「なんだか双子タレントみたいだな。」
「そうそう。でも、むしろ双子より近い存在…二人は同じ人間ですからね。」
その言葉でつい…
「同じじゃない!」
「同じじゃない!」
また揃った。
チビは爪を噛んで、猫ちゃんと一緒に入りたいとグズった。父が亡くなってからは、少しの間身の回りの世話をしてもらっていたらしい。慣れない環境だからか、余計に甘えている。
ばあちゃんに「入ってやって」とうながされ、猫ちゃんは遠慮気味に「じゃあ、お言葉に甘えてお先にいただきます」と手を引いた。 猫ちゃんの黒いスーツから伸びた白く細い右足にまとわりついたチビ。そのまま脱衣場へと消えていった。
お風呂からケラケラと二人の笑い声が響く。
なんだよこれ。へんなシチュエーション。きゃっきゃ騒ぐ声を聞きながら、荷物を整理した。
「こらっ待って」お風呂から、はしゃいで裸で飛び出したチビ。ばあちゃんのうしろに楽しそうに隠れた。その小さな腹のへその横にやっぱり確かにホクロはあった。洗っても消えないなら本物なのだろう。
◆
夜も更け、ぼくは例の分厚い契約書を読んでいた。
布団で寝息をたてるチビ僕を起こさないよう、小さな声で猫ちゃんに尋ねた。
「こいつは、クローンの意味を分かってるんですか?」
チビの寝顔をやさしい瞳で眺めながら、
「わかってるような、わかってないような…。ただ、お兄さんみたいな、双子みたいな、あなたより先に生まれた…生まれ変わりみたいな人だよということは話してあります。」
「余計ややこしくないすか。」
「ま、子供のうちの方が、抵抗なく現実を受け入れるかもしれませんね。常識が邪魔しないので。」
「ふーん」
「今日は余程疲れたんでしょうね。いつもは本を読んであげないと寝られないんですけど。」
「え、それも、これからぼくがやるんですか。」
「そういうことになりますね。ごはんはおばあさまが作ってくださるっておっしゃってましたけど、朝の支度やお風呂などはお願いします。」
「キツイなあ。」
「新入社員。お仕事のひとつです。」といたずらっぽく笑った。「じゃ、私は失礼します。起きちゃうとぐずるので。また明日。」
まだクローンなんてすべては信じていない。
目の前に横たわっているこれはなんだ?子どもの頃の僕の姿で寝息をたてるこれは?
もしもタイムマシンで子供の頃の自分に会いに行ったら、こんな感じなんだろうか。
本棚に飾った写真を見つめた。父が何も言わず笑っている。
いやいや、なによりも大きな疑問が解消されていない。
父はなぜこの子を誕生させたのだろう?
■春、第5話 検査で…
「父ちゃん、トイレ…」
次の朝早く、チビのすすり泣く声で、僕は起こされた。
目を覚ましたチビは、亡き父を探して泣いていた。見慣れない部屋に、状況を把握しきれず悲しくなったそうな。
「あらあら、ゆーちゃん、どしたの。」ばあちゃんも起きてきて、「まだ早いから眠たいねぇ。はい眠たい眠たい。」よしよしと”小さな僕”をなだめつつ、古い階段をミシミシ降りて行った。
子ども番組を観せると、少し機嫌が良くなった。なるほど、これは使えるな。
ばあちゃんの味噌汁の匂いで目を覚ましていく。テーブルには目玉焼きとトースト。和洋統一感がないけど絶妙に合うのがばあちゃん特製。
”ちーん”
仏壇の鐘をリン棒ではじく。父と母の写真。僕にとっても、チビにとっても同じ父と母。ばあちゃんが、一口サイズのご飯を金の器でお供えする。毎朝の小さな日課。チビが興味深そうに眺める。
珍妙なお客様を迎えてから、初めての朝食。
チビはテレビに取りつかれたように凝視している。なんか話してやるか。「なあ」と声を掛けてみた。
「…………。」
なのにテレビに夢中。僕もよくばあちゃんに叱られたっけ。キンキン騒がしい子供番組の「間違い探し」に心奪われている。簡単だろこんなの。
ふぅん、確かにけっこう難しいな…。
「あった!」
「あった!」
同時に見つけてシンクロした。
機嫌が良さそうだぞ。今だ。
「なあ」
こっちを向く。
「お前は、僕。僕はお前。同じ人。わかってる?」
「…………。」
小さな僕は、僕の顔をじっと見た。ちゃんと目を合わすのは初めてかも。
テレビの音だけが響く。やがて、”うん”と小さく頷くと、またテレビに心を奪われた。
ちゃんとコミュニケーションとらなきゃな。なんでこんなに難しいんだろ。”自分自身”なのに。
確かに僕も人見知りだったかもな。思いだそう。あの頃、なにに興味があったか。
「ほら、あとでさ…なんか…オモチャとか買いにいくか」懐柔してみる。
”いらない”、と小さく横に首をふる。そういうことでもないらしい。
ほんと可愛げがないチビだな。我ながら。自らの子供時代ながら情けない。
「こんにちはぁ」玄関から猫ちゃんの声がした。
チビは、箸をテーブルに放り出して玄関に走って行った。
「ちゃんと寝れた?夜中おしっこ自分で行けた?」と聞く猫ちゃんにまとわりついて、すっかり元気になったチビ。心に余裕ができて、古い家にあるものが珍しいのか、キョロキョロ見回しはしゃぎ始めた。
「おねえちゃん、ほらみて。ほらみて。」すっかり「この家慣れたよ。ぼく、おにいちゃんだもん。」的なカッコつけをしている。
ばあちゃんの寝室で古い鏡台を見つけると、
「これなに?」
「鏡台や。三面鏡ゆうてな。ばあちゃんも昔はお化粧したりしたんよ。」嬉しそうにばあちゃんが布をめくり上げ「嫁入りしたときに持ってきたもんや」
「へぇ」とチビは、いないないばあみたく三面鏡を開いたり閉じたり。閉じた中に頭を突っ込んだ。「うわぁ」大声をあげて何やら感動している。
僕ものぞく。と、そこには合わせ鏡に無数のチビの顔が果てしない空間に広がっていた。その上からのぞく僕の顔。同じ顔と同じ顔。混ざりあって遠い彼方へと無限に広がっていく…。
少し、ぞっとした。
「さあ、ユタカさんたち」
「ん?」
「ん?」
猫ちゃんに呼ばれ2人の顔が振り向いた。
「今日は一日、とってもとっても退屈な"検査デー"です。」
「えー」
「えー」
「まあまあ、シンクロでそんな顔しないで」猫ちゃんは笑いながら僕たちの背中を両手でポンとたたき。「これもお仕事ですよー 。」
◆
僕たちが京王線に揺られて向かったのは、奥多摩のニュータウンを過ぎたあたり。
整然と並んだ団地をタクシーで横目に過ぎると、やがて真新しい道路が山の中のトンネルに吸い込まれていくように延びている。
真っ暗な中、壁にきらめくオレンジ色のLEDライトの群れを抜け出た先に、まぶしい太陽の光とともに忽然と現れた前衛的な現代建築。斜めに空を切り裂きそうなガラスの破片のようなデザイン。日に照らされた真っ白なコンクリートと美しい芝生の緑が手前の人工的な堀の水面に映えて、ディズミーの白亜の城をも思わせる。”東京大学遺伝子工学臨床実験研究所”という銀のプレートがきらりと光った。
驚いた。僕がここに来たのは初めてではない。その理由は、のちほど。
犬巻渕子とヤギヒゲ教授、たくさんの助手たちが「きたきた」と玄関で待ち受けた。
「ここって…」思わずこぼれた。「もしかしてあなたたちの…?」
「わかっちゃいました?」と教授がおどけて笑う。
「さ、今日は盛りだくさんですよ。」猫ちゃんから、ビニールに包まれた検査着をポンと渡され「午前はメディカルチェックです。」
検査室は、無駄に天井の高い真っ白な廊下を進んだ先にあった。
「採血しますね」
猫ちゃんがおもむろに僕の腕に黒いゴムチューブを巻く。「親指を中に入れて握ってください。」肘の裏の青筋を叩きながら血管を探している。傍らには注射器。
「ちょ、ちょ」思わず腕を引っ込めた。
「いや、あの、もしかして、猫ちゃんさんが?」
「ああ」そういえば、という表情で、「医師免もってますから。」僕の手を引っ張り、消毒液でひんやり拭いた。「言ってませんでしたっけ?」
言ってません。
「てか、猫ちゃん”さん”、ってなんですか」クスッと微笑ながら、注射を細い指でつまんだ。
「いえ、なんとなく」
「あれ、肩に力入ってますね。もしかして…小学生のユタカくんと同じですか、注射がぁ…」いたずらっぽい微笑で僕の気をそらし、プスリ。
「うっ」
「…苦手なとこも。」ふふっと笑った。
チビと2人して上半身裸で台に横になると、ヤギヒゲ教授は楽しそうに、へそのほくろや、曲がった足の小指、とがった軟骨の左耳などを比べた。
僕たち2人だけの共通点を、なぜか彼らは既にリストで持っていた。
「目を閉じてくださいね」
MRIにゆっくり頭が入っていく。グオングオンと激しい機械音。真っ暗な世界で、ぼーっと考えてみた。
僕は毎年ここで健康診断を受けていた。以前、交通事故をしたことがあって、病院から勧められ、後遺症がないか調べるためにと聞かされて。少なくとも、今日まではそう信じていた。
…もしかして、僕は被験者だったのか?じゃあ、何を調べていたのだろう。こうやって健康チェックするのも実は利用するため?
この手の映画だと、クローンは臓器提供のためにつくられるっていうのがお決まりのパターンだ。まさか、チビが僕のために臓器を提供?それとも逆に、僕の臓器が…?疑念が湧いてくる。
人間のクローンなんか造っちまう彼らならやりかねない。油断できない。てか、そもそも人間のクローンなんて作っちゃダメでしょ。モラル的に。よし、いつか問いただしてやろう。
午後は、奇妙なテストをたくさんさせられた。
紙の上にインクをこぼしたような模様をみせられ、「これは何の絵に見えますか?」とか、会話する男女のイラストを見せられ、「この人々はなんと言っていますか?」とか。
そうそう、真っ白なジグソーパズルもさせられた。犬巻とヤギヒゲ教授たちがずっとそばで眺め、助手がパソコンに何かの数値を打ちこんでいる。なぜか時折、なにやら感嘆の声を漏らしながら。僕たちは何も大したことをしていないのに。
お互いにフワフワした大きなゴムボールの投げ合いをさせられたりもした。なんのためかはわからない。チビがちょっと強く投げてきたので、これまたもっと強く投げ返したらチビの顔にぱんと当たった。すると真っ赤になってムキになって投げ返し、僕に突き指をお見舞いした。互いにキーッと投げ合う様を、教授たちは淡々と数値化していた。
そして、最後の実験。
ついに”あの現象”は起こった…。
僕とチビの生活が、これからその”現象”に激しく振り回されることになることを、まだ僕たちは知らなかった。
猫ちゃんがチビの手を引いて「ここからは別々の部屋に別れてください」 と、どこかへ連れていった。
厚いドアがレバーで閉められると、プシュッという空気音とともにそれまでのノイズがピタっと無くなった。気圧の変化を耳の鼓膜に感じる。いわゆる”シーン”という静寂の音さえも聞こえないのは、部屋の壁一面に、何百ものスポンジ突起が一面にデコボコと張り巡らされているせいだろう。無音室だ。心理的にヤバくなりそうな部屋だな。ずっといたくないな。頭に電極みたいなのをいっぱいつけられ、妙なカードテストが開始した。
5枚のカードに、〇▢☆十のマークや波形など、簡単な図形が描かれている。
…うーん疲れた。嫌だなあ。おかしくなりそうだよ。だんだんそんな気分。
ヤギヒゲ教授に「この中で1枚選んでください。どれでもいいですよ」と言われても、
「はあ」考える気力もわかない。まあいいか。疲れてるし。
うーんと…なんでもいいや。
「☆」を指さしてみた「これで」
「では、目を閉じて、今選んだカードを頭の中でよーく思い浮かべてください。この形をはっきりね」
「はあ」うーん、と思い浮かべた。
なんのことかさっぱりわからない。一体何をさせたいのか?
うーん。うーん。と、やってみる。
教授が、助手に「どう?」という目線を送る。助手はインカムでどこかとコソコソやりとりし、「まあまあですかねぇ」と囁いている。僕の何かが、彼らの期待を上回っていない失望のような声だ。
「まあまあ」だと?悪かったな。なんだかわかんないけど。うーん。うーん。頑張ってるんですけど。
まさか…もしかして、僕のイメージしたカードの絵を、離れたチビに当てさせようとしてるのか?んなこと起こるわけないじゃん。この人たち大丈夫?
はあ、つかれる。早く終わらないかな。もうどっか行きたいなあ。
そんな時、インカム助手が教授に耳打ちをした。
「うん?」教授は一瞬表情を曇らせたが、僕には優しい笑顔で「ちょっと待っててね」と言うなり、プシュっとドアを開け、出て行った。さっきまでの静寂から、世間のノイズが一気に戻ってくる。いや、もっと騒がしいぞ。廊下中に「さっきまでここに!」とか言い合う声が響く。
なんだなんだ?一人だけ事態からのけ者にされて余計に気になった。電極をそっと脱ぎ廊下に出てみると、犬巻や研究員たちがバタバタ館内を走り回っている。
「なんで目を離したんだ!」「トイレかと」「エレベーターは!?」「非常口は!?」
あいつだ。チビだ。いなくなったんだ。
目を離したすきに姿が消えたらしい。チビ、逃げやがったな。無理もない。僕でさえ、午前中からかなり飽き始めてたからな。
ふと見ると、隣の部屋のドアが開いている。なんとなく中を覗いてみるが誰もいない。僕のいた部屋と同じく、一面デコボコのスポンジが張り巡らされている。テーブルの上には、同じく電極と例のカードが置きっぱなしだ。「なんだ。隣でやっていたのか」
なぜだか…騒ぎをよそに、ぼんやりと僕の頭をある思いが支配しはじめた。
初めて来た場所なのに懐かしいような、ざわざわ胸騒ぎがするような不思議な感覚だ。
「なんだろう。この感覚」
思いに誘われるままに、隣部屋に入ってしまう…。
隅のソファーへ歩み寄り、腰をおろしてみる。遠くに皆の騒ぎ声がかすかに響く。あいつなにやってんだよ…でもまあいいか。チビの行方より、”ここにいたい”ことに興味が勝(まさ)った。
なんでだろう。なんとなく”ソファーの下を覗いてみたい”という願望がムクムク沸き起こり始めた。人間の行動なんて、ほとんど深く考えず選択しているものだ。息をするのも、踏み出す足をどちらにするかも。そう、直感的に。
だからなんとなく、ゆっくり股の間に頭を突っ込み、床におでこを近づけてみた。
ソファー下の薄暗い隙間には、特に何もない。…2つの黒い玉が見えただけだ。さあ、戻るか。
…ん?黒い玉?
もう一回、股の間から見た。
…目だ。
目が合った。薄暗い中、”小さな僕”がうずくまってこちらを見ている。刹那だが、その瞳と何か気持ちを交わした気がした。
なにかに怯えるように胸の前で小さくたたんだその手に握りしめていたのは、”☆”のカード。
目を離すと見失ってしまいそうな気がして、僕は凝視したまま叫んだ。
「いましたぁ!」
その後、
僕がチビを見つけたことを犬巻や教授たちは大袈裟に喜んだ。なぜだか学術的にとても価値があるとのことだった。「どうして分かった?」「何を感じた?」としつこく聞かれたが、「たまたまです」自分でも言葉ではうまく説明できなかった。とても不思議な感覚だった。
教授たちは大興奮。結局さらに長時間、体中を調べられるはめになった。
◆
「なぁ、なんで隠れたの?」
ばあちゃんの夕食のコロッケを箸で突っつながら尋ねたが、チビはなにも答えなかった。
あまりに疲れたのか、僕と馴染めないのか、今夜もチビは絵本の読み聞かせをするまでもなく寝てしまった。
今日は一体なんだったんだろう。
一日中行われた検査。チビを見つけたこと。僕の頭で何が起こったのだろう…。
明日から通う新しい学校の上履きや体操服などにサインペンで僕と同じ名前を書きながら、考えた。
これぞという答えは何も浮かばなかった。
■春、第6話 学校で…
"小さな僕" が学校から泣いて帰って来た。
転入生としての初日なのに。
どうしてそうなってしまったのか。
◆
…そもそも今日は、朝から大変だった
午前7時、起こしてもなかなか起きない。
いい加減にしてくれよ。これから毎日これかよ。面倒だな。僕の気持ちも分かってよ、お前も僕だろ。
まだ半分寝ているチビに朝ごはんを食べさせ、ランドセルを背負わせて、「忘れものない!?道具箱と体操服と。遅れちゃうよ、早く!」引きずるように学校へ連れてった。
担任は、若めの男性の先生だ。ジャージ生地のズボンとポロシャツ。着任してまだ年数を重ねていないのだろう。一文字の太い眉毛がやる気に満ちた生真面目さに溢れていた。だからだろうか、先生は転入届を見て、たいそう不思議がった。
「あれ?」
「え?」
「ここ保護者の欄ですよ。弟さんの名前になってます。」
生徒の欄に「汐妻ユタカ」と書いてある。保護者名の欄にも「汐妻ユタカ」と書いてある。
しまった。うっかりしてた。でも、一応、正しいんだけど。
…そういえば、犬巻が言ってたっけ。
「学校には、表向き腹違いの義兄弟ということにしてますから、そのつもりで。」
戸籍では、兄弟で同じ名前をつけることは原則認められてはいない。だけど特別にチビは別の戸籍を持たせてもらっていた。
学校の転入手続は犬巻たちが事前に済ませており、教育委員会を通じて校長まではなんとなく丸め込んでいたのだが、現場の担任までは手が回らなかったようだ。
そのまんま説明するとややこしくなりそう。
「あー、えー、あのー、こ、これ、『ユ』じゃなくて『コ』なんです。そうそう。これ字が汚いですけど『コ』。カキクケコのコ。この子が『ユタカ』で、兄の僕が『コタカ』。ややこしくて、すみませんね。ははは。」
とペンで『ユ』を上から何度も『コ』と書きなぐったが、
「不確かですと、何かあった時に困りますので。」
「す、すみません」手ごわいな。「書き直します。」
「今回は結構です。」納得できない様子のまま、目を皿のようにしている。「それにしてもご兄弟、似てますねえ。まるで双子のようだ。いや、それ以上…。」
ドキ。
「そこそこだと思いますけど。」はぐらかすしかない。
先生は、腑に落ちないけどまあいいや、的な肩のすくめ方をした。
「では、そろそろ授業ですので」
連れられて進む廊下。
小学校、と呼ばれる場所は久しぶりだ。何年も足を踏み入れたことはなかった。
授業前のひっそりとした校舎。春の柔らかな朝の光が斜めに射す。下駄箱があって、建物のほこりの匂いと子供たちの気配をかすかに感じさせる匂い…。初めて来た場所なのに、なぜか懐かしい。記憶が呼び覚まされるような気分。あの頃の小さな僕が、もう一度人生をやり直しているかのような不思議な気持ちになった。なんだか、いいね。
ひとり勝手に感傷に浸っていたら、…ん?
ふと、胸のあたりがモヤモヤしてきた。なぜだか心の奥底がざわつきはじめたのだ。あれ?なんだこれ?
まるで何かのプレッシャーのような、妙な感じ。なんだろう。
突然、「汐妻くん!」と先生に呼ばれて、
「はい」
「はい」
また二人で返事。
先生は怪訝な顔で「コタカさんじゃありません。ユタカ君の方です」
「し、失礼しました」この先生は要注意だな…。
「ではお兄さん、こちらで失礼します。汐妻くん、2年生の教室はこっちですよ。」
「あ、では、よろしくおねがいします。」チビに「ほら、行きな。」と背中を押すと、すっと僕の背後に回った。
「どうしたのさ、授業始まるぞ。」
小動物のようにこわばって固まるチビ。お前、ビビりだな。と軽口を叩こうとしたその時…、
あれ?
またきた。さっき感じた心のプレッシャーが…今、僕の背後にあるのを感じる。チビの狼狽が背中越しにヒリヒリ伝わってくる。新しいクラスに向かう不安なのか。なんだろう?この感覚…。研究所でチビを見つけた時の、あの不思議な感覚に似ている。
いや、待って。なぜか僕までドキドキしてきた。
なんだ?なんだ?チビの感情の乱れが僕にも移るというのか?
困った先生は時計を見ながら息をつき、指先を刻みながら待っている。
ヤバイ、急がなきゃ。しゃがんでチビの目を見たが、「うーん、うーん…」言葉になっていない。
おどおどして、とても悲しい目の色をしている。なんとかしなきゃ。安心させよう。大丈夫だよと言い聞かせなきゃ。
いや、むしろ僕自身の気持ちを落ち着かせなきゃ。僕の動揺まで伝わってしまう気がして。まず僕が落ち着こう。深呼吸して「大丈夫…大丈夫…。」そうそう。それを彼の目に伝えた。
「大丈夫だよ。大丈夫だよ…。」
「‥‥‥‥」
「な、大丈夫だろ」
「‥‥‥‥」
やがて、ほとばしるチビの感情は静まり、わずかな安堵へと変わった。
チビは、コクリとうなずくと、先生の傍らへ歩み寄った。なんだったんだ?この感覚。
変な兄弟だな、と言いたげそうな先生も、時間がないので「じゃ、教室へ」と歩み出す。先生の後ろにくっついて爪を噛みながら渡り廊下を連れられて行くチビ。
とぼとぼ歩いていく後ろ姿を眺めながら、何かが心に引っ掛かった。でも心配しても仕方ない、慣れてもらわないと、と自分に言い聞かせた。
◆
昼過ぎ。嫌な予感は的中した。
チビの洗濯物を干していたら、スマホが鳴った。
「ちょっとご報告が…」担任の先生だ。もしかしてクローンがバレた?
だが、そうではなかった。先生の声色は、疑り深かった今朝とは違って少し申し訳なさそうだった。「そのぅ…トラブルというわけではないんですが…汐妻君が昼休みにクラスメイトとちょっとありまして。いえ、いじめとは言い切れないんですが…。」
いじめだ。
給食の時間、筆箱にパンを詰め込まれたという。挙動不審にビクビクしてたからか。クラスメイトの子ども特有の残忍さなのか。
近ごろの学校は、そういうのを真っ先に保護者に報告するのだという。やたらと先生に謝られた。「ユタカ君が帰ったら問いただしたりせず、なにも聞かずにやさしくしてあげてください」とアフターケアまでレクチャーされた。
難しいな。こういうとき、親ならどうするんだろう。どう迎えてやればいいんだろう。正解が分かんない。あとでググってみるか。
「でも…汐妻くんは、いじめられたんじゃない、皆でふざけて遊んだだけだって言い張ってまして…。」
チビは、筆箱からパンを見つけたのを周囲の友だちが笑う中、自分も笑っていたらしい。でも、楽しいわけはない。苦々しくも愛想笑いをして。「食べろよ」と、はやし立てられ、鉛筆の刺さったパンを食べたのだという。
その光景を思い浮かべたら、なんでだよ!と無性に怒りが込み上げた。立派なイジメじゃないか!なんで、ヘラヘラ笑ってるんだよ!嫌ならハッキリ言えばいいのに。たかが子ども同士の話だろ。学校のクラスなんてちっぽけな空間だ。大人になったらもっと大きな世界がある。いろんなことに遭う。教室の小さな人間関係なんて、いつか大したことないって思えるようになる。
「‥‥‥‥いや、待てよ。」
自分の中の記憶が、僕を呼び止めた。
この悔しさ、どっかで…。
ああ、そういえば…。意図せず、記憶の奥からある光景が蘇ってきた。
ぼくは幼い頃、保育園に途中から転入した。初日にズラリと並ぶ園児たちの前で挨拶をさせられた。たくさんの子どもたちに会うことは初めてだった。彼らだって新参者が珍しかったのだろう。見知らぬエイリアンに対する子どもたちの好奇の目にさらされた。生まれて初めてだから、緊張という感情を知らなかった。恐怖なのかなんだか意味の分からない感情がピークに達したとき、僕はその場から飛び出していた。
そして、チビと同じように洗礼を受けた。給食の中に積み木を入れられたのだ。保育園児のやること。でも、された本人にしたら、初日に死刑宣告されたようなものだ。
そうだ、その時、僕も笑っていたような気がする。幼心にそうすることで、苛められてないよ、僕は一緒に遊んでるんだよ、という設定にしておきたかったのだろう。いじめをされていないと思うことで、いじめそのものがなかったことになる気がして。歯向かうと怪我をする。ささやかな防衛だった。
そのせいなのか今でも、大人になったぼくは他人の目が怖い。人前に出ると異常に緊張し、話そうとするとお腹の下の方がキュッと縮む。就活面接でも愛想笑いが関の山だ。あの経験のせいなのか、それとも生まれつきの性格なのかわからない。ただ、いつの日からか、クツの奥で転がる小石みたいに、小さなコンプレックスになってしまった。
そうか。僕とチビは同じだ。
現役小学生のチビにとっては、たとえ小さなクラスでも全世界なんだ。毎日毎日その社会で生きていくしかないんだ。永遠に続く地獄に思えたのかもしれない。そう思うと、僕の姿をしたアイツが、筆箱にパンを詰め込まれながらも愛想笑いをしている姿が思い浮かんだ。
…切なくなった。
廊下でチビが僕の背後に隠れた時、どうしてすぐに教室に行かせてしまったんだろう。もっとゆっくり話を聞いてやるべきだったんじゃないか。時間をかけてやるべきだったんじゃないか。後悔した。
可愛げなくて、小憎たらしいガキだけど。僕が過ごした人生をもう一度やり直している小さな自分。毎日一生懸命生きているチビ。そんな辛い思いはさせたくない。
そう思うと、チビの話を聞きたくなった。
チビに伝えておきたい事が、いろいろあるような気がしてきた。
夕方、学校から帰ってきたら話しを聞いてやろう。
今夜こそ、寝床でやさしく本を読んでやろう。
その夜、僕は夢を見た。
ここは小学校だ。自分の体が小さい。
教壇に立たされた僕を、生徒たちがじっと見つめる夢だった。
■春、第7話 シンクロ!?
『緊張を感じとった?』
ポンと軽い音で現れたLIMEのメッセージ。
可愛い猫のアイコン。猫ちゃんからだ。
『おもしろい現象ですね』 と猫のアイコンは言った。
『おもしろいですか?ちょっと戸惑ってます』
『お話、聞かせてください』
『お願いします』
『のちほど行っていいですか』
あ、また家に来るんだ。横のチビに教えると、ぴょんぴょん飛び跳ねて喜んだ。
『ええ、いいですよ』 抑えめの返事にしておいた。
◆
猫ちゃんが家に来る目的は、もっぱら僕とチビの生活のチェックだった。
オカズで残った最後のハンバーグに、僕とチビの2人で箸を突き刺して取り合いになってるのを、ケタケタ笑って眺めなら、スマホに何かを入力していた。
「何を書いてるんですか?」
「同時にお箸を突き刺したのが、すごくシンクロしているので、記録してるんです。」
「は?」
「アプリを使って、柱のカメラの映像データに時間と内容を記録するんです。”12時34分・同時に箸を突き刺す”って。それがリアルタイムで研究室のクラウドに飛んで、教授たちが分析します。」
残り少なくなったハミガキチューブから空気に押されてペーストがポンッと飛び出した。それが鏡に貼りついたとき、僕たちは声を上げて笑った。面白がるツボも似ているのだろう。
猫ちゃんも笑った。笑いながら、スマホでメモをとっている。
テレビで何を観るかでチビと揉めたとき、
「よーし、じゃんけんで決めよう」
最初はグー、じゃんけんホイ!
…どちらもチョキ
あいこでしょ!
…どちらもグー
あいこでしょ!
…どちらもパー
…どちらもチョキ
…どちらもグー
…どちらも……
「はあ、はあ、はあ、はあ」
「はあ、はあ、はあ、はあ」
あいこでしょ!
…またあいこ。
何回やっても、あいこばかりが続く。
猫ちゃんは「すごい!連続16回!これは報告しなきゃ」興奮して舞い上がっていた。
「こんなことを記録して何がわかるんですか?」
「クローンとオリジナルが一緒にいるとどんな現象が起こるのかを調べているんです」とスマホに記録しながら言った。ぼくのことは”オリジナル”と呼ぶらしい。ときおり、行動がシンクロしたり、相手の考えていることをなんとなく感じたり、そのメカニズムをヤギヒゲ教授たちは研究しているんだそうだ。
「だから、双子も研究していますよ。」
クローンと双子は似ているらしい。犬塚は東大教育学部の付属中学校に双生児を生徒として毎年数多く入学させている。ふだんの学校生活を送る彼らの行動データをもとに、クローン研究をすすめているのだという。
そこで分かっていることは、
双子もクローンも、リスクに対する姿勢が似るらしい。例えば、レストランは行き慣れた店に行くタイプか、知らない店に入るタイプなのか…。さまざまなチョイスが似てくるという。つまり、一日に何千回もある行動の選択、”次の角を曲がる?”、”どの本を手にとる?”と、何を選ぶかが同じであれば、その後の運命さえ似てくる。
「双子よりクローンの方がはるかに似る精度が高いようですよ。リスクに対しても。」彼女は言った。
「リスク…ですか。」
「そうです。おチビちゃんが教室に行けなかったのも。」
「リスクを感じた?」
「はい。」ばあちゃんの麦茶を飲み干しながら、「大人のユタカさんと似て。」
「僕と似て?」
「はい。人見知りでしょう?」グラスの水滴を指先でなぞりながら僕を見た。すべて見透かされているようでちょっと恥ずかしい気がした。チビも僕と似て人見知り…、いや似てるっていうより本人同士だけど。
彼女は続ける。
「検査の時に逃げたのも同じ。リスクを感じたんだと思います」
「それも?」
「検査を面倒だと思ってたでしょう?」いじわるそうに僕を見た。
「思ってました。」バレてました?と愛想笑い。
「きっとその気持ちが通じた。」
「そんなことが…。」
「あるんです。」
猫ちゃんが言うには、チビと僕は知らず知らず互いに”怖い”感情を交換して共鳴し、どんどん増幅してしまったのだという。生活を共にしていれば、さらにそのシンクロ度は特に増すのだという。
「どういうこと?」
「今はまだ研究中です。」
「なんのためにこんなことを調べてるんですか?」僕はそこが気になった。
「クローンと一緒に暮らすとどんな現象が起こるのか、まだよく解明できていないんですよね。クローンが社会に進出した時、どんな影響を与えるのか?その先の未来にはなにが待っているのか?予測しておきたいんです。」
「社会に進出?…これからクローンが増えるってことですか?」
「それは…」
「それは?」
「あの…」
「あの?」
「…また、おいおいお話しますね。」といたずらっぽくはぐらかした。
「えーっ!?ずるい」
「ここから先は、また秘密保持契約書にサインしてもらわないと。どっさりとね。」フフフとおどける。
そう言われたら余計気になります。
「では、別の質問いいですか?」
「はい?」
「どうして父は僕のクローンを作ったんですか?」
「え?」
単刀直入すぎたのか、少しの驚きを見せ、やがてぽつりと、
「…それは、亡くなった汐妻教授しか分からないんです。」
話は、そこでなんとなくうやむやになってしまった。
◆
夕食のあと、チビとトランプでババ抜きをした。
でも、2人とも互いのババを引かなくて勝負にならない。”引いて”と願えば願うほど、なぜか位置を察してしまうから。最初にジョーカーを持ったほうがずっと持ち続けるだけの、つまらない作業に終わってしまう。
「おもしろくない」
チビが嫌になって、カードを放り出した。
遠くのささやき声にふと目を移すと、猫ちゃんの後ろ姿。縁側に腰掛けスマホで話している。
「…ですが…どうしても気になってしまって…」
表情はうかがえないが、何かを強く訴えているように聞こえる。本社の犬巻だろうか。夜も更けた隣近所を気遣ってかコソコソ声。しかし確かな意志の固さを感じるトーンで。
だが、うまくいかなかったのか、やがてあきらめたように肩を落とす。いつも笑顔を振りまいているのに、あんな背中を見るのは初めてかも。
「大丈夫ですか?」
「ええ」と振り向いた猫ちゃんは変わらぬ笑顔だった。
気になった。
けど、なんとなくそれ以上は尋ねることはやめておいた。
それは、今じゃないような気がして。
■春、第8話 秘密基地
チビのすることは、なぜかいちいち懐かしいと感じるものだった。
幼い頃、僕もやっていたことばかり。そりゃそうだ。本人だから。
例えば…、
道を歩けば、高いところを歩く。
路肩の少し上がった段とか白線でもいい。渡り歩きながら家まで帰る。そこから落ちたら、はるか断崖絶壁から落下、という幼稚な空想いっぱいの大冒険。子どもがやりがちな、あれだ。
また例えば、学校からの帰り道に、石ころを蹴って家まで帰る。石がどこにも落っこちたりしないで、無事に家に帰れたら成功。宝物として大事にしまって置くのが楽しみだったり…。
そこには合理的な理由も価値もない。なんてことのない遊びに、意味を見つけてこだわるところがそっくり同じだった。嬉しいような、残念なような。
◆
そして、今日も。チビが懐かしい”アレ”を作っていた。
僕がそれに気づいたのは、猫ちゃんから来たLIMEでだった。ポンと軽い音で現れた可愛い猫のイラストのアイコンが言った。
『おチビのユタカくん、今なにしてるんですか?』
一緒に画像も送られてきた。チビが部屋で何やらシーツらしきものをカメラに覆いかぶせようとしている。
『柱のカメラを隠そうとしているようなんですが』
猫ちゃんは、我が家のLIVE映像をオフィスで見ていて疑問に思ったらしい。
二階では、チビがシーツの端をもって「うーん、うーん」と背伸びをしている。
「なにやってんだ?」
返事もせず、柱の高い位置に取り付けられたカメラにシーツを洗濯ばさみで留めようとしていた。
「なあ、なにやってんの?」
こっちをチラッと一瞥したが、無視。夢中で続ける。
「ゆうちゃん、いいねえ。」覗きに来たばあちゃんの声。「また作っとんの。久しぶりやね」階段から顔を出して嬉しそうに言った。
「こんなの作ったことないよ。」僕が正そうとすると、
「ゆうちゃん作っとったよ。」よっこらしょと階段をミシミシ鳴らしながら降りていった。
「だから作ってないって…」言いかけて気づいた。
…あ、もしかして…シーツを掛けて、テントのような形…。
そうだ、秘密基地だ。
確かに。これ、覚えてるぞ。子どもの頃だ。よく作ったっけ。懐かしいな。
イメージは分かるが、しかし上手く出来ないようだ。そうそう、シーツの重みで崩れてしまう。あーでもないこーでもないと苦労している。
「ちょいと貸しな、洗濯ばさみじゃ重さに耐えられないよ。何かヒモとかで縛って…。」
「いいの、自分でやるの!」
ああ、そうじゃないのに…もどかしいが手を出せない。
猫ちゃんにLIMEを送った。
『秘密基地を作っているみたいです』
『なんですか、それ』
『僕も子どもの頃によく作ったんです。さすが僕のクローン。』
『何をするものなんですか?』
『中に入るんです。』
『入ってどうするんですか?』
『なにをするわけでもないんですが、オモチャで遊んだり、おやつを食べたり』
『はあ…』 あんまり響いてない。女子は、やらないものなのだろうか。
バサッ
落ちてきたシーツをチビが頭からかぶった。シーツのオバケがキーッと怒っている。
「上手く作れないみたい。イライラしてます。」
しょうがないので、僕はイスと棚を使って、骨組みを作った。昔、父が作り方を教えてくれたっけ。
そこへフワっと華麗にシーツをかけて見せたら、驚きとともに僕を見た。初めて僕に向けた尊敬のまなざし。どうだ、大人の力を見たか。
ところどころヒモで縛っていく。ひさしぶりだな、なんだか楽しくなってきた。
チビは一気に僕の偉業に興味を示した。シーツをめくり入口に誘われるようにそろそろと身を忍び込ませていく。中に消えると、ひゃーと声が聞こえた。しばらくして上気した顔を出したり隠れたりを繰り返して、大いにはしゃいだ。
俄然やる気が出たようで、眉間にしわを寄せ、画用紙に計器やレバーなどを描いては、テントに貼っていった。見事にぼくが子どものころ作った秘密基地そのまま。小2にしてはクオリティーが高い。我ながら。
中に入って懐中電灯をつけると、三角錐の内側の空間を照らし、そこは無限に広がる宇宙となった。
「わあっ。」
声を上げたチビが僕を見て、笑った。僕も笑った。
あれ、なんか気持ちいいぞ。なんだろ。今、こいつ笑った。いや、心通じた?なんなんだろ、よくわかんないが、なんだか嬉しい。ポジティブな感情もシンクロするのだろうか。
小さな段ボールをテーブルにして、オモチャとマンガをいっぱい持ち込んだ。
基地内では、チビに「隊長」と呼ばされた。
「隊長、食料をもって参りました」
「こ、これは…」
「そうです!”うまか棒”です!ばあちゃんに戸棚に閉じ込められていたのを救出しました!」
「よくやった!」
狭い中、大好きなオモチャをいじり、二人でスナックのうまか棒を齧ってカケラをポロポロ落としながら笑い合った。
チビはいたく気に入って、夕食もここで食べ、寝るのもここにしたいとせがんだ。布団を狭い基地に敷き、絵本の読み聞かせをさせられた。
ヤツが持ってきた本は、すべて昔、僕が父に読んでもらったものばかり。
『ジャングル探検隊』 や 『宇宙に浮かぶスペースコロニー』など…。
懐かしくて、全く同じだ。
幼い頃の僕が破ってしまったページがテープで貼られているのも、同じ。
父はわざと同じものを残しておいたのか。だとしたらなぜだろう?
特にチビのお気に入りは、「バス」の絵本だ。
家族揃ってバスに乗ってお出かけするおはなし。
動物園や遊園地、ショッピングモールにスケート場…
次々止まるバス停ごとに、「ここなの?」と子どもたちが尋ねるが、
パパは「もっといいところ」と秘密にする。
最後に到着するのは森にぽつんとある小さなレストラン。
庭に光あふれる大きなモミの木のクリスマスツリーが美しい。
そこで家族揃って温かな食事をするというストーリー。
父と母。そして兄弟。こんな温かさに満ちた体験をしたことがない。
チビだって、僕だってそうだ。
この本、好きだったな。読んでいる間だけでも、小さな幸福を疑似体験できた。それが嬉しくて何度も読んだ。クリスマスには季節外れだとしても。
「兄ィ、もう一回読んで」
なに?誰?兄ィ?
…ああ、僕のことか。
「い、いいよ」自分同士なのに「兄ィ」って…。
「兄ィ」か…。
ちょっと、しみじみ。
好きな絵本も遊びも同じ。やることなすこと似ている。小憎たらしいところも。
やっぱり、こいつ13年前の僕なんだな。
だから僕にはわかる。きっと不安だろうな。こんな見知らぬ兄ちゃんと一緒に住んで。
どうして父は、チビを誕生させ、同じ本や服を使わせ、同じ人生を過ごさせているのだろうか?
「兄ィ、あの歌やって」
「歌?」
なんだ急に…
「父ちゃん、ピーってお口でやってくれたよ」
「ああ、口笛ね。なんの歌?」
すると、チビが
♪ふんふふん~♪
と鼻歌で歌いはじめた。
子どもらしく下手なのもあって、最初は音の羅列をなかなか僕の頭が捕らえられなかった。
やがて迷子になっていた僕の頭に、突然、メロディが舞い降りた。
「聴いたことあるぞ。」
懐かしくて切なくて美しいメロディ。なんだっけこれ?
続きが僕自身の中から沸き起こってきた。リズムに乗せて、唇を震わせてみる。自然とメロディが重なる。チビと目でリズムを合わせる。
「そうだ。父ちゃんだ。」
よく口笛で聴かせてくれた。父と離れてすっかり忘れ去られていた。曲名も知らないけれど。好きだった。懐かしくて、懐かしくて、涙が出そうになった。
亡き父と過ごした時間を、この子に重ねて感じた。吹くのをやめると、この気持ちが消えてしまいそうで、いつまでも奏でた。
なんていう曲だったんだろう。アプリで旋律から曲名を検索することはできるが、やめておいた。曲名を知ってしまうと、いつでも取り出して聴ける。流行りの歌みたいに、色褪せて擦りきれてしまいそうで。なんだかもったいなくて。だから、そっとしておくことにした。
…ん?寝息をたててる。
まどろみながらだろうか、手を繋いできた。
初めて触れる、”小さな僕”の手。プニプニして小さく丸っこい。掌で包むと温かい。ちょっと照れ臭い。
一生懸命、秘密基地を作っていたその指先をのぞくと、僕の指紋とやはり同じだった。こいつ、本当に僕自身なんだな。しみじみ思った。
一重のまぶたを閉じ、低い鼻で小さな唇の先っぽを尖らせて眠っている。
眺めていると、初めてこいつを、
「思ったほど憎たらしいやつじゃないかも。」と感じた。
いや、むしろ、
「そこそこかわいいかも、我ながら。」なんて思えた。
その甘美なメロディは、夜の秘密基地に、いつまでも響いた。
「意外と、いいかもな。この生活。」

■夏、第9話 夏休み!
気が付いたら、小学校は夏休み。
長い梅雨が夏の訪れに気づかなかったらしく、2,3日憂鬱な雨を居座わらせたが、やがて夏が慌てたように、猛烈な暑さで街を襲った。
空の青がまぶしい。チビの元々まぶしそうな顔も、一層くしゃくしゃになった。
”小さな僕”と、奇妙な同居が始まって3か月。
自分同士のくせに極端に人見知りだった2人。いつの間にかおしゃべりが増え、家の中はにぎやかになっていた。
好奇心旺盛なお年頃らしく、
「なんで空は青いの?」
「なんでパンダは白黒なの?」
とずっと聞いてくる。
なかなかうまく説明できない。テキトーな言葉でおさめても、腑に落ちてくれない。それはそれでいい。自分から話すようになれたのなら。
チビとの夏休みは、とにかく遊んだ。大学も休み、フットサルサークルも就活がうまくいかなくて疎遠になった。なので時間はある。
父ちゃんに遊んでもらったように、チビにもできるだけ同じように接してみようと思った。僕がしてもらって嬉しかったことは、コイツも嬉しいに違いない。なにせ僕自身だから。
思えば、チビのためのつもりだったのに、僕にとっても良かったのかもしれない。しばらく忘れていた子供っぽい遊びが、僕のオトナの硬い殻をほぐしてくれる気がした。あとで思えば、人生で一番楽しい時間だったと言ってもいい。
時には、
ばあちゃんの物干しざおの先に虫取り網を括りつけて、近くの神社で蝉捕りをした。
父がよく連れてきてくれた境内。石畳を踏むと、頭上の木々から一斉に蝉の声が降り注ぐ。ひんやりとした空気に深い緑葉の匂いが溶けている。
一番高いところ、木漏れ日に透かしてブローチのような黒いシルエットを見つけた。茶褐色の羽が透ける…アブラゼミだ。
チビといたずらな目線を交わし、身を屈めて忍び足で木の根元へ。獲物は油断して樹液を味わっている。狙いをつけて高みに網で忍び寄る。竿の重みに腕が小刻みに震え、先端の網が大きく揺れる。うっかり葉に触れた振動で気づかれてしまわないよう、迷路のような枝の隙間をすり抜け、上へ、上へ…。気づくなよ、気づくなよ。
あ…鼻がムズムズする。太陽が目に飛び込んでクシャミがでそう。チビも鼻をムズムズさせている。こんな時にシンクロしないでよ。ダメ。今はダメ。目で制すると、うん、と鼻をつまむ。
息をひそめ、蝉の高さまで忍び寄る。獲物の背後で、網が無言でぱっくり大きな口を開けている。いよいよだ。チビを目を合わせ、息を合わせて、せーの、と素早く幹に叩きつけようとしたその瞬間、鼻がムズムズ…
「へえっくしょん!」
「へえっくしょん!」
網を叩きつけた時には手遅れ。
ジジッジッと飛んでいく蝉の声が空へ吸い込まれる。
「あーあ。」
「あーあ。」
顔を見合わせ。「……」
「チビが悪い!」
「兄ィが悪い!」
言い合う言葉さえもシンクロする僕ら。
あざ笑うかのように大勢の蝉の声が降り注いだ。
◆
また時には、
街を秘境に見立てて大冒険した。
見知らぬ路地の古い民家の間。塀の隙間に体を這わせながら、どんどん中へ。
時には庭を抜け、塀の上を渡り何軒も越えて、まるで巨大迷路。命の危険も顧みず危険な密林を進む、われわれ探検隊。路地裏というジャングルの奥へ。
挟まった僕をチビが引っ張り、チビを僕が塀に押し上げ、2人は助け合いながら進んだ。黙々と進む小さな隊長を、追いかけ進んでいく。すばしっこいチビに置いて行かれないよう食らいついていく。右へ曲がるか、左へ抜けるか…前を行く小さな背中に意識を寄せるうち、次の動きがなんとなく分かるような気がしてきた。
「もしかしたら心が読めたりして…?」調子に乗った好奇心で、試しに目をつむってみたら、がんっ!とブロック塀の出っ張りにスネをしこたまぶつけた。
「んぐぐぐぐ」
ただの住宅街だ、何かがあるはずもない。でも、僕たちには違った。
塀の隙間のその先には一体何が待ち受けているのか?想像すると胸の鼓動が高まってきた。何だろこの気持ちは?ワクワクで大きな声を出したくなる。高揚した顔のチビが「わかる?」と誘うように、こちらを振り向く。感情がシンクロする。子どもだましの探検ごっこが、こんなにも心を揺さぶるなんて。大人になって忘れていた。
やがて、暗い隙間の遠い先に、逆光さし込む出口が見えてきた。
長い長い通路を抜け、茂みのような植木をかき分けたその先に広がっていたのは…
…まるで見たことのない奇妙な場所だった。
巨大な敷地に、幾何学的なデザインの建物たち。磨き上げられたようなツルツルのビルが並ぶ。
美しく揃えられた芝生の緑。その上に白いローラーで自由に曲線を描いたみたいな遊歩道。歩道橋やビルをつなぐ通路の立体交差に未来を感じた。
人が誰もいない。信号はまだ灯らず、道路に車の姿もない。新しい車道の白線の白さがいやに目立つばかり。燦燦と日光が降り注ぎ、植栽は生命力に満ちあふれている…にもかかわらず、誰もいない。
隅には、土嚢や建設資材が寄せられていた。そういえば駅前に再開発エリアができるらしい。ショッピングモールでも建設途中なのだろう。でもそんなあたりまえの現実なんて今の僕たちにはカンケイない。われわれ探検隊には全く違う景色に見えた。
そう、これは絵本で見たスペースコロニーだ。宇宙人が密かに作った未来都市。夜中に人知れず空から舞い降り、静かに横たわっているのだ…。そんな幼稚な空想も、”同じ自分”のチビとイメージを分かち合うのに言葉は要らなかった。
われわれ探検隊の世紀の大発見だ。街を支配したかのように大興奮した。感情がシンクロして奇声を上げながら思わず同時に走り出す。芝生の上を飛び跳ねるように転げまわった。芝の柔らかなチクチクした感触と微かな草の匂いが心地いい。
そうだ、ここには小学校のいじめも夏休みの宿題もない。就活や卒論の悩みもない。僕たちだけだ。僕たちの新天地だ。ユートピアだ。チビの笑顔がはちきれそう。良かった。
気持ちが高ぶって2人の口からあふれたのは、あのメロディ。僕らそれぞれ違う時代に、同じ父から子守歌として聴かされていた口笛。2人おどけた鼻歌で歌いあった。
「♬ら~ら~らら~」
「おい、誰だ!!」
警備員だ。遠くから走ってくる姿が目に飛び込んだ。
やばい。僕たちは一目散に逃げながら、なぜか笑いが止まらなかった。怖いけど、スリルと興奮を2人で共有していることが、おかしくておかしくてたまらなかった。
その時、もはや僕の心は8歳の男の子。
追いかける警備員の目に映ったのは、もしかしたら笑いながら裏路地を駆け抜ける2人の同じ顔した子どもたちだったのかもしれない。
それは、僕と小さな僕が”ともだち”になった日だった。
■夏、第10話 ふたご語
「あんたら、汗だらだらやんか。風呂場行きぃ」
うだるような暑い午後。ばあちゃんがソーメンを用意する間、僕とチビは水風呂に入った。
水中メガネに海パン。バスタブに体を沈めると一度は息が止まるほどの冷たさに、
「ひょー」
「ひょー」
と2人して声をあげたが、あとから次第に馴れが追いついてきた。最高の気持ち良さ。今度は味わうように抑え気味に、
「ひょー」
「ひょー」
と息をもらした。
潜るとそこは、窓から差し込んだ光がゆらめく美しさ。秘境の洞窟の地下水路だ。
水の中でチビと顔を合わせる。昆布のように揺れる前髪。水中メガネのゴムで横に引っ張られた目。シュノーケルを咥えたゴリラのような口元。互いの変わり果てた姿を見て、思わず噴き出して笑ってしまう。
水上のシュノーケルの先から、
「ホホホヘヘヘ」
「ホホホヘヘヘ」
と笑い声が風呂場の壁で反響し、頭上から他人の声のように水中に降ってくる。
水から上がると、腰にまとわりつく海水パンツを引きはがし、バスタオルで体をぐるりと巻く。
すっかり冷えた体で畳に転がると、頬にあたるイグサがほんのり温かくて気持ち良かった。
庭で揺れる洗濯物。午後の柔らかな光の筋。蚊取り線香のくゆる煙の匂い。ぼぉっと眺めて美しさにのめり込んでいる。
チビとたわいもない話をしていた。
「今、なんて言いました?」
白い足が覗き込んだ。猫ちゃんが知らない間に来ていたのだ。
「え?」
「今、2人変なことばで話していましたよ」と不思議そうにチビの髪をタオルで拭く。
「変なことば?」
「自覚ないですか?」メガネに当たりそうな長いまつ毛で瞬きをする。
「全然。」
「”べーなー”とかなんとか。逆再生みたいな変なことばでした」
そんなふうに言われても、
「そうかなあ。普通に話してたと思うんですけど。」
チビに「なんか変なこと言った?」と聞いても「ううん、なんにも」と気持ちよさそうに頭を拭かれている。
「じゃあ」と、猫ちゃんが、壁のカメラを見上げた。
◆
慣れた手つきでタブレットを操り、カメラの映像をピックアップして、再生すると、ザラついた映像には、僕とチビが2人で寝転びコソコソ話している姿が。
”にぃーぼーぬまぼーれーたーろー”
”べーてなー”
「これ…、フタゴゴ、ですね。」
猫ちゃんは医師の診断のようにさらりと告げた。
ソーメンのガラスの器をばあちゃんがテーブルに運ぶ。僕はつゆに茗荷を散りばめながら尋ねた。
「なにゴゴ?」
「ふたごごです。双子語。双子同士が話す、特別な言葉です。」
「特別な言葉って?」
僕ら普通に話しているつもりだけど。
チビは興味なさそうに、ソーメンの上の氷を箸でつついている。腑に落ちていない僕を見て、猫ちゃんは、聞きます?とばかりにソーメンをすすって咳払いした。
「双子って、生まれてから言葉を覚える前なんですけど、2人だけの言語を作って話すことがあるんです。双子をもつ親御さんには”あるあるネタ”なんですけどね」と細い小指でなにやら検索する。
くるくると回るサーチ表示を待つと画像がポンと現れた。外国人の女の子2人。可愛らしいが、ずいぶんと古い写真のようだ。
「有名なのはポトとカベンゴです。1970年代のアメリカ、ジョージア州で、8歳の双子が自分たちだけの言葉を話していたのが発見されたんです。」
「自分たちだけの言葉…」
「ええ、いくつか複数の単語を崩してつなげ、新しい一つの単語に変化させる。スタッカートみたいなリズムを持っていて…。まさに、さっきのユタカさんたちと同じですね。」
そう言われても、自覚なんてない。「僕たちが?ちゃんと普通に話してましたよ」
「無意識なんですね。」
「コワイなぁ。気づかないうちに、言葉が変化していったってこと?」怯えながらソーメンをすする僕が滑稽に見えたのか、フフと笑って、
「でしょうね。それほど自然に。これも貴重な学術的資料になりますね。」内閣府付特別研究員としての探求心がのぞく。「で、コソコソなんて言ってたんですか?」
”にぃーぼーぬまぼーれーたーろー”
”べーなー”
「チビが『兄イ、ぼくのうまか棒、食べただろ』って疑うから、僕が、『食べてない』って答えただけですよ。」
「食べてない?」
「はい。べーなー。」
「べーなー…べーてなーぃ…たべーてなーぃ…食べてない。ああ、なるほど」猫ちゃんが空で繰り返す。
「絶対食べた!」チビが蒸し返した。
「箸で指すなよ」
「1つ足りないもん」
「そうかなぁ」
「数えたもん」
「算数弱いくせに」
「返せ!」
「はいはい、うるさいな」
「返せ!」
「はいはいはいはい」
「いつ?なんじなんぷんなんびょう!?」
そんな僕たちを眺めながら、
「貴重な学術的発見が、うまか棒って...」
猫ちゃんはあきれたように笑った。
■夏、第11話 夢も同じ!?
夜中、目が覚めた。
夢を見ていた。
時々見る夢だ。空を飛べる能力を身に着けている。
でもビューンと鳥のようには飛べず、平泳ぎのように手足を搔くと、少しずつ体が浮くのだ。まるで水の中のような不自由さで、急いで空気を掻かないと沈む。頑張れば5メートルくらいは空中に浮遊する。簡単に飛べないところが妙にリアルなのだ。リアルだから夢とは気づかない。
「空を飛べた」と、人類初の超能力獲得にいつも歓喜するのだが、毎度のごとく風に煽られて墜落し、ビクンと足を突っ張って起きる。
シーツで作った秘密基地で、チビも同じように目を覚ましていた。
「落ちた」チビが枕に顔を押し付けたまま言う。
「落ちたって?」どういうこと?
「風が吹いて」
「風?空を飛んでた?」
「こうか?」布団の上で仰向けに平泳ぎをしてみた。
「そうそう」
なんだ?なんだ?もしかして、僕とチビは同時に同じ夢を見たのか…?
「夢…ですか。面白いですね。そんなことあるかもとは言われていましたが…」
猫ちゃんはスタパのカウンターでアイスカフェモカを注文しながら言った。
「あるかも?」同じ夢は想定内なの?
店員に「あ、氷少なめに。ユタカさんは?」
「アイスコーヒーで。」
「あれから調べていくうち、すこしづつ分かってきたんです。」
「また怖いことじゃないですよね…。」
「ふふふ。大丈夫ですよ。」打ち消しながらも、また研究者の顔になる。「クローンと一緒に暮らしていると、互いの脳の細胞組織が共鳴しあうようです。」猫ちゃんと僕の頭を指差す。
「きょうめい?」
「で、だんだん脳波のパルスが合ってくるんです。だからシンクロも起こりやすい。」
脳のパルスはよく分からないが、要するに考えが似てくるってことか。「一緒に暮らしているだけで?」
「同じ夢まで見るなんて。本当にあるんですね。」
「こわい。こわい。」
「逆に、夢を見ている間は、おチビちゃんとユタカさん、2人の脳がつながりやすいのかもしれません」
脳がつながる?「どうやって?」
「どう言えばいいのかな、2人で『意識の粒』みたいなものをやり取りしているんです」
「意識?粒?」頭がついて行かない。
「量子学ってわかります?」
「でた。また難しいやつだ。」大げさに嫌がってみせると、猫ちゃんはカードゲームの駆け引きのように「知りたくないですか?」いたずらな笑みで僕を試す。
「うーん、すみません…サルでもわかるように教えてください。」
ドリンクを運びながらテーブルに座ると、猫ちゃんはボールペンで紙ナプキンに歪んだ丸を描き始めた。
「なんすかこれ。そら豆?」
完璧な彼女も絵は苦手みたい。
「脳です。見えません?」不満そうにふくれる。ちょっと可愛いけどこれ以上ツッコまず、
「脳。脳。脳。見えてきました。続けてください。」
「人の『意識』って、ただの脳内の電気信号なんです。人は『考えている』と思ってるけど、実は、脳内の神経細胞で小さな電気の粒が行き来しているだけ。その粒が、夢を通じて…」
「夢を通じて、2人の脳を行ったり来たりする?」
「そう。2人とも同じ人間。細胞分裂した1人の体みたいなもの。だから、そばで生活することで、細胞が1つの脳だと勘違いして、情報の粒をやりとりし始めるんです。わかりやすく言うと、同じラジオが同じ周波数を受けちゃう、みたいな。」2つの脳の間に矢印を何本も引っ張る。
「僕たちの脳がラジオ…。」
「そう。細胞というのは元々情報を交換し合うんです。脳に限らないですよ。細胞はすべて。体中、隣合ったひとつひとつの細胞だって、自分がどの位置の細胞か教え合っているんです。細胞みんながお隣さんに耳打ちしてる感じ。だからちゃんとすべての部位が正しい位置にできる。足に耳が生えたり、手のひらに目ができたりしないのはそのおかげ。もし、怪我をして欠損してもちゃんと元通りに再生する。」
「へぇー」僕が大げさに感心すると、小指でショートの髪を耳にかける。これが猫ちゃんのどや顔だ。こういう時は先生感が出て、年上だったことを思い出す。
「じゃ、同じ夢を見るっていうのも、ラジオみたいに受信し合っているってこと?」
「おそらく。ユタカさんの夢か、おチビちゃんの夢か、どちらかを一緒に見ている。時には、2人共同作業で夢をつくりあげているのかも。まだよくわかっていませんが。とにかく、夢を見るレム睡眠の間が、最も意識の粒を交換しやすい状態なのかもしれませんね。」ストローでアイスカフェモカを混ぜている。
「寝てるときくらい、1人にしてほしいな」
溶けた氷で薄くなったコーヒーの味が、申し訳なさそうに広がった。
クローンは同じ夢を見る?
■夏、第12話 猫ちゃん
それからというもの、猫ちゃんは僕らを観察するため、よく家に訪れた。
専用のお箸やお茶碗までばあちゃんが用意してくれるほど。
ばあちゃんと僕だけだった辛気臭い家に、他人が、ましてやこんな若い女性が足を踏み入れるなんて不思議な気分。ふすま戸の貧乏臭いすきま風でさえ、ショートヘアを揺らした香りで爽やかな風に変える。
それにしてもこの人、よく笑うな。チビと猫ちゃんがいると賑やかになるな。
子どもと一緒に住むのなんて面倒くさいな、って最初そう思ってたけど、これはこれで悪くないかもな。
”小さな僕”が猫ちゃんにキャッキャと甘える様子がなんか気になった。
けど、じろじろ見るのは良くないよな。バレると恥ずかしいから、点いていないテレビの画面ガラスに反射して映る姿をチラ見する。
チビがくらいついて離れない。お前、僕自身のくせに。誤解されるだろ。
いくら子どもだからって、猫ちゃんに甘えすぎだろ。こら、もうちょっと離れろって。くそ、ガラスの反射だと見えにくいな…。
「ゆうちゃん、テレビ点いとらへんのに、なんで見とんの」
ばあちゃんの声で皆は笑った。
猫ちゃんと目が合って、バツが悪くて愛想笑い。
だけど、皆で笑っているこの時間、好きだなって思った。
猫ちゃんも、そう思ってくれるかな。
◆
昼食をすませトイレに行こうとしたら、庭の下駄をひっかけた猫ちゃんが植木の葉を指先でいじりながら電話をしているのに気が付いた。
相手は上司の犬巻だろうか。感情的に何かを訴えているようで、
「このままでいいんでしょうか。私にはそう思えません。話をさせてください…。」
この前と一緒だ。一体なにがあるというのだろう。
通話を終える気配に誘われて、
「大丈夫ですか?」と思わず言葉が口をついて出ていた。
振り向く彼女。その真っ直ぐな瞳に、ひるんで後ろめたくなった。いえ、こっそり聞いていたわけじゃないんです。すみません。
「ええ」
メガネの涙をぬぐいつつも、自然に振舞おうとする猫ちゃん。いつものような柔らかい微笑がちょっぴり寂しそうだった。
なにか良くないことのような気がして、
「よかったら…」
「はい?」
「…あの、聞かせてもらえませんか。」
「え?」
「よかったらで…ですよ、よかったらで…あ、いやならいいんです…でも、よかったら。」
モジモジする僕の姿が可笑しかったのか、少し表情が和らいだ。
「もう、だいじょうぶです。ごめんなさい。それにしても…」
話題を変えられた。
「それにしても?」
「よかったですね」
「え?」
「…ユタカさんと、おチビちゃん、すっかり仲良くなりましたね。」
「そうですかね。」
「本物の兄弟みたい。」
「本人同士ですけどね。」
「あは、そうでした。」
「時々、小憎たらしいですけどね。それなりに楽しくやってます。」
「ですね。私も楽しいです。」かみしめるように言った。
「ですね。」
「ずっとこうしていたいなぁ。」空へ向かって無邪気に背伸びをした。
ずっとこうしていたい…。
ちょっと引っ掛かった。深い意味はないのかもしれないけど。
踏み込むのもいけない気がして、僕が精一杯絞り出した言葉は、情けない相槌だった。
「…ですね。」
気まぐれに吹いた風が肩までの髪を揺らし、振り向いた猫ちゃんは僕に優しく微笑んだ。
■夏、第13話 好き!工作
”小さな僕”は、僕の人生のあわせ鏡だ。
見ていると、自分自身についてよく気づかされる。
蒸し暑い昼下がり、チビがじんわり汗をかきながら、秘密基地の中でなにやら黙々と作っていた。
ああ、夏休みの工作ね。
割りばしと輪ゴム、タコ糸を使って…。何を作ろうとしているのだろう。厚紙で小さな箱を作り、切れ目を入れて。まるでくす玉を真っ二つに割るように開く。どこかで見たような…。
…あ、これ、僕も作ったことあるぞ。クレーンゲームだ。
タコ糸を引っ張ると、箱が開き、離すと輪ゴムの力で元に戻る。全く同じ形だ。
教えていないのに自然発生的に同じ行動をしている。恐ろしいなクローンって。
イメージは分かるが上手く出来ないようだ。
そうそう、タコ糸の仕掛けは難しかったな。あーでもないこーでもないと苦労している。かつて作った僕には正解が分かっているから、
「ちょいと貸しな、糸を引っ張る方向を変えればいいんだよ。厚紙で小さなわっかを作って糸をこう通すと…。」
「いいの、自分でやるの!」
ああ、そうじゃないのに…もどかしいが手を出せない。
このチビは、もくもくと何かを作ることが好きらしい。
秘密基地はもちろん、時にはペットボトル万華鏡、時にはゴミ袋を膨らませた巨大な象、紐をひっぱると自動で開く筆箱…。
チビは熱中しすぎると他に何も手がつかなくなる傾向があると、ヤギヒゲ教授が解説していた。
「子どもの頃のユタカさんもそうだったらしいですよ。その分、2人とも底知れぬクリエイティブな才能があるんじゃないですか。きっと。」と気楽に評していた。
子どもの頃の僕も…、か。
確かに工作が好きだった。
時間さえあれば…、いや、時間がないときほど無性に作りたくて、妖気が乗り移ったようにごはんも食べずに手を動かし続けた。何も聞こえなくなって父ちゃんに叱られたっけ。
モノを作っていると、世界を創造しているような興奮に出会えた。
だけどあれほど大好きだった工作も、大人になった今の僕は紙ヒコーキひとつさえ作ることもなくなった。あんなに楽しかったことが、大人になったらどうして忘れてしまうのだろう。
「クリエイティブな才能」かぁ…。
僕は就活もせず、これから将来どうなっていくんだろう?
一体なにをすればいいんだろう。僕が本当に好きなことってなんだろう。あの頃のお絵描きや工作のような、魂を揺さぶるような興奮を味わえる仕事って、なんだろう。
好きなことを一生の仕事に選ぶことはできないのかな?どうせ自分には才能なんてありゃしない。選ばれた一握りの人だけの特権なのかな、どうせ。
いや、誰がそう決めたんだ?自分で最初から限界を決めていないか?
自分がしたかったこと、自分の内側から涌き出る興味から、なぜ僕は目をそらすようになったのだろう。
大人は嘘をついて生きている。たくさんの嘘。でも一番の罪は自分に対しての嘘。
「将来なにになりたい?」
チビに聞いてみた。
”小さな僕”は僕の人生の合わせ鏡。
原点回帰。なにかヒントがあるかもしれない。
「ね、なにになりたい?」
「わかんない。」
興味なさそうに、なんともつれない回答。
過去の自分から未来のヒントを引き出すため、粘る。
「夢とかないの?」
「寝てるとき見るよ」
「その夢じゃなくて、大きくなったらこうなりたいなぁ、っていう夢」
「あるよ」
「なに?」
「ぼくね」
「うん、うん」
はちきれそうな満面の笑顔で、
「大きくなったらね、兄ィと、猫ちゃんと、ばあちゃんと、ずっとずっと夏休みするんだ。それが夢。」
■夏、第14話 倒れた僕
僕は救急車で運ばれた。
それは、チビと公園の砂場で遊んだ日のことだった。
◆
砂場に足を踏み入れるのは久しぶり。久しく忘れていた沈む感覚は、ふわふわ雲の上を歩いているよう。炎天下でも、砂に手を差し込むとひんやり気持ち良い。
砂山を作り、2人両側からトンネルを掘り進める。山が崩れないように注意深く、指先で少しずつ削るように。
やがてベコッと柔らかくなったその瞬間、向こう側のチビと手が繋がった。湿ってざらざらした冷たい土から突如現れた、柔らかく温かいまるで何かの生き物のような感触だった。
その瞬間、ビビっと指先から意識が繋がったような気がした。チビも感じているであろうシンクロ感。一瞬だったが、鏡に映った僕のように、砂山の向こう側で手を突っ込んでいる僕自身の姿を見た気がした。少し頭がフラついた気もしたが、気に留めなかった。
お次は、泥だんごづくり。
水で泥をこね、掌でいたわるように包んで丸める。砂をかけながら表面の水分を抜いて、だんだんと手の中で固くしていく。何度も砂を振りかけ振りかけ、つるつるに磨いていった。
つい今しがたまでジャリジャリしていた獰猛な泥が、こんなにも洗練された人工物になるのかと今さらながら感動し、その滑らかな球体を愛でながら磨き続けた。
集中すると言葉少なくなる。黙々と繰り返すその行ないは、まるで山奥の寺院で何百年も脈々と受け継がれる写経のように、精神の落ち着く、尊い営みのようだった。
沈黙を破ったのはチビ。
砂をいじりながらなぞなぞを出題してきた。学校で流行ってるらしい。
「9つの色がある食べ物は?」挑戦的な笑み。
「なんだって?」
「9つの色の食べ物」
「9つ…」
「9つの色」
「ここのつ…んー…あっ、ココナッツ!」
「ブー」
「9…きゅう…キュウリだ!」
「ブー」
「ヒントは?」
「ヒントなし」
「ケチ。えっと、9つの色の食べ物だろ…?」
シンキングの時間稼ぎに、もっと乾いた砂を探そうと立ち上がった瞬間のことだった…。
覚えているのはそこが最後。そこからあまり記憶がない。
白昼、巨大な夜のカーテンが閉められたかのように、暗闇が急に押し寄せたような感覚。こういうのってドラマだとバタッといくものなんだろうが、自分の身に起こるとよくわからないものだ。
◆
たっぷり寝すぎたようなけだるさを感じながら、気が付いた。
瞼が開けられないほど重く、頭も混乱していたが、固いシーツのクリーニングの匂いで、ここが知らない部屋であることが分かった。
少しずつ思い出されるのは、誰かに何度も名前を呼ばれたこと、見上げた天井が流れていく光景…。
ところどころ断片的に蘇ってきた。
病室、なのかな。ここ。
つい今しがたまで見ていた夢を思い返した。
泥だんごをいっぱい作らなきゃと焦っている夢。丸めても丸めても崩れていく…。
…そうだ。そういえば、チビと公園にいたんだっけ。
コソコソ響く聞き覚えのある声。
外の廊下で犬塚とヤギヒゲ教授がなにやら議論しているようだ。
猫ちゃんが報告する。
「MRIの結果を待ってですが、前回の検査より10ミリほど移動したようです。」
「たった数ヶ月で…。」
「あらあら、9年間おとなしくしてたのに。」
「クローンと会わせた途端に動き始めた、か。」
「不思議な縁を感じますわね。」
なんのことだろう。
目をやると、ばあちゃんがテレビのワイドショーをイヤホンで観ていた。
「目ぇ覚めたんか。」
「うん。」
「もうちょっと寝とき。寝るんが一番や。」
寝返りを打つと、チビと目が合った。
隣のベッドで同じく横たわりながら、僕を見ている。
「おう。」
「おう。」
「何があった?」
「兄ィ、バタッてなった。」
泥だんごを作っている途中で倒れたらしい。そして、なぜかチビも頭が痛くなったそうだ。倒れたのは僕なのに、なんでチビまで?
猫ちゃんによると、互いが生活を共にすることでシンクロ度合が高まってきているらしい。相手が体調を悪くすると、少しだけど影響を受けるのだという。
僕に似て極度の人見知りなのに、道行く人に「兄ィを助けて」と、泣いてすがりついたそうだ。無理してくれたんだな。
「ありがとな。」
「うん。もうすぐだったのに。」
「何が?」
シーツの中から腕を引っ張り出した。その手に握っていたのは、半分に割れた泥ダンゴだった。
僕らは声を殺して笑った。
犬巻が、心配しているかのようなわざとらしい表情をぶら下げて、部屋に入ってきた。体調を気遣うねぎらいの言葉を並べ、"貧血"というワードで理由めいたことを説明する。でも、僕がたまたま倒れたわけじゃないのは、さっきのコソコソでなんとなく察する。
「廊下で何の話してたんですか?」
「何も。」
「9年おとなしくしてたとか、なんとか」
「ああ…」(聞いてたのね、だけど)「別の案件ですわ。」
僕に何か隠しているのか。僕になにがあったというのか。
僕の生活にチビが現れたことと関係あるのだろうか。
病院のベッドってのは、いけないな。心が弱る電波でも出てるのだろうか。疑心暗鬼になってしまう。
「給食。」
いきなりチビが言った。
「給食?なにが?」
「9つの色がある食べ物」
「なにが?」
「9色。きゅうしょく。給食。」
なんか、ありがとなチビ。
気持ちが楽になったよ。面倒な話は今度にするよ。
それより、また作ろうな、泥だんご。
■夏、第15話 命の宣告
猫ちゃんからLIMEが来た。
『今日、お時間あります?』
『ありますよ。午後なら』
『何時ごろですか?』
『3時すぎには。小学校の保護者面談が終われば。』
『その時、おチビちゃんいます?』
『いた方がいいですか?』
『いない方がいいかもです』
なんだかいつもと違う。
『なにかありました?』
質問には答えず、
『3時、うかがいます』
なんだろ。チビがいない方がいい。あれ、もしかして、二人で会いたかったりして。なーんて。
そんな浮ついた邪念を手のひらで転がしながら、猫ちゃんが家に来るのを待った。
◆
「保護者面談はどうでした?」
おっと、そんな当たり障りない会話から始めるのね、冷たい麦茶に手もつけず。はいはい。
ばあちゃんは買い物。家には僕ら2人。
「成績はそんなに良くはないですね。僕に似て。」
「ああ、そうなんですね。」猫ちゃんは乾いた返事だった。
向かい合うテーブルは、まるで卓球台。本題に入るまで、さながら牽制のラリー。
「友だちもできたみたいです。」
「お友だち?」
「それなりに仲良くしてるようですよ。」
「よかったですね。」
「そうなんです。羊太君と言って…」
「ようたくん。」
「ええ、おとなしめの子らしいです。」
「気が合いそうですね。」
「僕の小学生のときの親友にどことなくタイプが似てましてね。そんなとこまで同じなのぉって。ははは……は…」
誘い笑いを向けてみたが、いつもの屈託のないケラケラは返ってこなかった。
もう一球、返してみよう。
「成績はそんなでもないんですが、図工はクラスで一番得意だそうです。」
「…あの、ユタカさん…」いきなり空気を変える球。
「はい。」
「あの…なんていうか…よく聞いてください。」自分からラリーを断ち切ったのに、モジモジしている。
「聞いてますよ。」
「あ、やっぱ、いいです。」メガネを外して、拭き始める。
「ちょっと、話しかけてやめるのは反則ですよ。」
もしかしてだけど告白ぅ?…ああ、僕は馬鹿です。
「そうですよね…」とあきらめたように「はぁ」と息を吐き、意を決して、
「あの、ユタカさん!」
「はい」きた!
「そんなに…」
「そんなに?」
「そんなに長く…ないかも…」
「へ?」
長く…ない…?期待していたワードじゃないから入ってこない。「長くないって、何が?」
「ユタカさんが」
「僕が?僕の何が?」
「この…先…」
「この先って…?」
「……」
どんなに僕がバカでもさすがに察する。
「え?…いや…でも、え?」聞きたいような聞きたくないような。「ちゃんと言って。医師免許持ってるんでしょ。まさか…」
答えを引き出そうと訴えると、彼女はとても言いにくそうに、
(…はい)
と唇だけ動かした。
「いやいやいやいや」さすがに何を言いたいのか、理解はできた。でも、そんなことを言われる理由がわからない。
「なんでですか?救急車で運ばれたのと関係あります?」
(はい)
とても良くない話っぽい。逆に詳しく知りたい。
「倒れたのと関係あるんですよね?」
覚悟を決めるようにメガネを戻した猫ちゃんは、
「詳しいこと、お話していいですか。」
「はい。」
「嫌だと思ったら言ってください。やめます。」
「嫌です。」
「えっ」
「でも、聞きます。」
椅子の上で互いに姿勢を正す。
「ユタカさんは…」
「はい。」
「脳に爆弾を抱えています」
「爆弾?」
「9年前の事故を覚えてますよね」
中1のことだ。あの朝、寝坊した僕を父が車で送ってくれた。
なかなか起きなかったのは僕のくせに、なんで起こさなかったと父を助手席で責めたてた。日頃慎重な運転だった父も、焦りと、交差点で小さな子供が飛び出してきたことに動転して、一瞬ハンドルを切った。
父が亡くなった事を知らされたのは、病院で目を覚ましてからだった。事故から何日も経っていた。僕は長い長い手術のあと、眠り続けたらしい。
猫ちゃんから聞かされたのは、その後の、僕が知らなかった新しい事実だった。
車が突っ込んだのは、よく立ち寄っていた雑貨店。怪我口から、細かいガラスの破片が血管にたくさん侵入しており、ほとんどは手術で取り除いたが、血管をギリギリ通る0.5mm程度の欠片はたくさん残ってしまった。それらは何年も体中を循環しているのだという。
しかも、1年ほど前から数個が脳内に留まっていることが分かった。メスを入れられない場所。もし血管を突き破って脳内で出血したり、詰まって脳梗塞を起こしたら、命の保証はない。今回倒れたのは、久しぶりに破片が動いて、ついに脳内の血管壁に刺さってしまったのだ。その影響によって公園でめまいを起こしたらしい。
今も血液の流れに揺れている状態。もし血管が破れたら?何かの拍子で抜けたとき穴は?
脳内にいつ爆発するかわからない爆弾を抱えている。それは数か月後なのか?明日なのか?わからない。
9年前の事故。9年前…、
チビが生まれたのも、その年だ。
合点がいった。
「僕は死ぬんですか?」
「……」
「その代わりにチビを作ったんですか?」
「……」
医師免許を持ってるくらいだから、こんな告知なんてわけもないはず。だけど猫ちゃんは、テーブルの縁を触りながら返事をしなかった。猫ちゃんの気遣いは、今の僕にとってはムダだった。
いつ死んでもおかしくない僕のバックアップとして、チビは作られた?
そう思うと、父や皆に対して失望に似た怒りの感情が込み上げた。
「…なんだよ。」
「……」
「実験用のモルモットじゃん、僕の人生。父ちゃんが選んだのは僕じゃなかったんだ。死にかけの僕は捨てたんだよな。壊れてない新品を選ぶよね、そりゃ。そんな無責任な。なんで隠していたんですか。ひどすぎる。」
「それは違うと思います…」
取り繕ってくれても、僕には救いにならなかった。
「じゃあ、どうしてチビをつくったって言うんですか?」
「それだけはどうしてもわからないんです。」
猫ちゃんがひとつひとつ慎重に言葉を選ぶのを感じる。気を遣ってくれているのか、本当のことが言えないのか。
「私が…聞いているのは…」
父はクローンのチビを育てるために、僕から離れて生きることを選んだという。
「何故かは…わかりません。でも、ユタカさんを捨てたんじゃないと思います。きっと…、うん、これしか方法がなかったんじゃ…ないでしょうか」
オリジナルとコピーが互いの存在を知ったり、一緒にいることは、固く禁止されていた。同じ人間が2人同時に存在すべきではないという倫理的な問題はもちろん、そばにいることで、互いの心身にどのような悪影響をもたらすかもわからなかったためだ。
「誕生させたおチビちゃんの命を放っておくことはできなかったんじゃ…。お父様としては、自分が死んだことにしてチビちゃんを引き取る唯一のチャンスだった。事故を体験して、突然の別れは起こり得るということを実感したんでしょう。2人を守るためにお父さまの苦渋の決断だったんじゃないでしょうか。」
そんな風に言ってくれる優しさは充分理解できた。でも、今の僕には響かなかった。死を宣告されたこと、今まで黙っていたこと、僕たちが実験材料だったこと。すべてがショックだった。
「そりゃ、新品の方がいいだろうさ。壊れた欠陥品じゃなく」
「そんなことは…」
ばあちゃんは、何も知らされず、事故後の経過検診として毎年僕を研究所に連れて来てくれていた。孫の命について知らされないなんて。いくらなんでも可哀想すぎる。
「あなたたちは知ってたんでしょ、僕の寿命を。最近急に進行したことも。だからチビを連れて僕の前に現れた。もうすぐ死ぬ僕とチビの人生を入れ替えさせるために。」
「それは…」
猫ちゃんが口ごもった。核心を突いてしまったのか、今まで見せたことのない悲しい表情で目をそむけた。言い過ぎた僕も後悔に気まずくなった。
「兄ィ?」
チビが二階から目を擦りこすり降りてきた。
学校から帰って疲れて眠っていたのだが、ただならぬ声に目を覚ましたのだろう。
「あ、猫ちゃん」
嬉しそうに声を上げた。彼女は無理に笑顔で、
「おチビちゃん、いたんだね。起こしちゃった?」と楽しい雰囲気を取り繕う。
チビは僕の表情を察したのか、
「どうしたの?」
「一人にしてくれ」
つい強い口調に。チビに当たってしまう感じもなんか嫌だ。自己嫌悪。
死への恐怖。
怖くて、悲しくて、悔しくて、喪失感。なんとも表現できない感情でもあり、一方でどこか他人事のような現実感のなさもあった。どう受け止めていいのか。整理できない。
次の日もしばらく布団から出られなかった。いや、ちゃんと寝られさえもしない。夢と現実のはざまで行ったり来たりしていた。
3日間はどう過ごしたか覚えていない。
僕はこれからどうすればいいのだろう?
■夏、第16話 理由教えて!
”小さな僕”に強く当たってしまう。
チビはなんのことか分かっていない。が、ただならぬ何かを感じ、僕から遠ざかって、ばあちゃんにまとわりついた。ばあちゃんは、よしよしとなだめる。その眼差しは僕に向けるそれと同じ愛情に満ちたものだ。
ばあちゃんにとって、僕が死んでもこいつがいるってことか。
僕、死ぬの?ほんとに?
僕は消えていなくなるというのに、チビはずっと生きていける。”新しい僕”として。何とも言えぬ嫉妬心が芽生えた。神様は僕じゃなくて、こいつを選んだのか。
◆
今日は、月1回の検査デーだ。
またはるばる多摩の奥、遺伝子工学臨床実験研究所に足どり重くやってきた。
「ちょっとチクっとしますよ」
猫ちゃんに採血されていても、ちょっと気まずい。直視できなくて横を向くのは、針が怖いせいだけではない。あれ以来初めて会うから何を話していいのか、よそよそしくなってしまう。
「こないだは…」
勝手に言葉が出てしまった。
「え?」
猫ちゃんは少し驚きながら針を抜く。
なんて言えばいいんだろ。次に続く言葉を探さなきゃ。なにか言わなきゃ…。
「なんか…えっと、すみません。」
「あ、いえ…、どういたしまして。」
ぎこちない返事で、丸い絆創膏を貼る。
今日はゼナーカードテストにも集中できなかった。
〇▢☆、十形や波形などのマークを頭の中でイメージして、隣部屋のチビに伝える。初日にチビが嫌がって逃げた例のテストだ。
最近はなかなかの上達ぶりだった。先月は調子が良くて、5回のうち3回は、僕のイメージする図形をチビが当てるようになっていた。徐々に成果が出始めている。逆に怖いけど。
ところが、今日はさっぱり当たらない。ヤギヒゲ教授たちはさらなる成長を期待していたようで、ガッカリしている。
わかってるよ。でもね、あなたたちの実験に素直に加担する気分になれない。
◆
休憩中、オフィスフロアのデスクでキーボードを叩く犬巻に「ちょっといいですか」と切り出した。
犬巻に問いただしても、僕の命についてはなにも解決しないだろう。
そんなことはわかってる。でも、知らないことが多すぎる。少しでも知っておきたい。
小気味よくリズムを刻むタイピング音が止んだ。鼻に乗せた老眼鏡のフレーム越しに僕を覗く。
「検査に集中できていないようですわね。先月の方が数字が良かったと記憶してますけど。」
僕が話しかけることなど予想してたようにサラリと言った。マウントをとって、ペースを引き寄せるのはいつものとおりだ。
「あんなこと聞いてしまったんで。」
「もう協力したくなくなった、とかおっしゃる?」とメガネを置く。
「秘密が多すぎて」
「教えないわけじゃございません。あなたには適正なタイミングで適正な真実を知らせる。設計されたスケジュール通りよ。」
あくまで友好的な笑み。
「教えてください。なんでもいいから」
「すべてをお答えできるかどうかはわかりませんが…」
思い切って核心を突く。
「あとどれくらい生きられますか?」
「残念ながら、そんなに時間は無さそうです。」
さらっと言うなあ。
自分で尋ねておきながら、答えを受け入れたくない。でも、怖いもの見たさで、知りたくないことをさらに聞く。
「チビは、僕のバックアップとして生まれたんですか?」
「わかりません。お父上が勝手にされたこと。正直困惑しています。私たちは、あなたじゃなくて、もっと優秀な遺伝子でクローンをつくりたかったのに。」
失礼な。言い方あるでしょ。死を宣告されたばかりの人間に。
「じゃあ、どうして?」
「日本初のクローン人間の実験対象に誰を選定すればいいのか、当初は、政府としても苦慮しました。人権問題にもなる。
これが映画だと、人体実験は名もなき死刑囚にしたりするのがお決まりのセオリーなんですけどね。凶悪犯罪者なんてもう一人増やすわけにもいかないでしょ。
そうこうするうち、お父様、汐妻教授の事故があって…」
「僕が実験台になった」
「汐妻教授の独断でした。
どうして突然、ご自身の息子さんに決めたのか?その理由だけは、最後まで教えてくださいませんでした。しかし、事故の直後おチビちゃんが生まれたことを考えると、先の無い…いや失礼、あなたの代わりと考えるのが自然でしょうね。お父様は、クローンでもどんな形でもいいからあなたを生かしたかったのかもしれません。」
パタンと薄いノートPCを閉じ、「さ、そろそろ再開しましょ」小脇に抱え、「よっこらしょ」と立ち去る。
父を信じたい。
でも信じられる事実が出てこない。死への不安。何かにすがりたい。
知りたい。材料が欲しい。
余計に事情を探りたくなって、
「犬巻さん」
銀色のエレベーターに乗り込むぽっちゃり丸い背中に問いかける。
「あなたたちはどうしてクローンを作りたいんですか?」
「これ以上は、またいつか。」
つれない言葉とともにドアがゆっくりと閉じる。
だから思わず言葉を投げつけた。
「じゃあ、もう協力はできません。死ぬ人間に怖いものなんてありませんから。」
ガツッ、ネイルの素手でドアをつかむ金属音がした。
犬巻の満面の笑みが現れる。
「まあまあ、穏やかに。」
濃い口紅の口角を無理に引き上げている。
「どうしてクローンを作るんですか?」
「しょうがないですわねぇ。」
ふうっとため息をついてガラス窓のもとへ。
下のフロアが見渡せ、検査室が並んでいるのがわかる。ヤギヒゲ教授や白衣を着た助手たちが準備を行うため行き交う姿が見下ろせた。チビ用に設けられたキッズエリアの遊具でチビと猫ちゃんが楽しそうに遊んでいる。
「国民の未来のためです」
「はぁ?未来?クローンなんて人を不幸にするだけじゃないんですか?」
「どう考えるかは見方によるんじゃないでしょうか。
この国にはもう人が足りません。このままじゃ経済活動が破綻してしまう。深刻な少子化問題を克服する打ち手が必要なんです。
そこで国が行きついたのが…クローンなんです。」
犬巻は、僕を別のフロアに連れて行った。
液体の入った大きなガラスの水槽チューブが並ぶ。そばには小さな子犬が数匹ケージの中でじゃれ合っている。皆、同じ姿だ。
彼女によると、ONEONE保険は、表向きはただのベンチャー保険会社。実は政府が、人間のクローンを社会に導入するために、政府系金融機関と東京大学に作らせた実験的な合弁会社だという。
ペットの保険はあくまで隠れミノ。人間のクローンを作るための土壌づくり。最初は動物のクローンで世論を慣れさせ、やがて人間にスムーズに移行するプランだ。
いよいよヒトに導入するときは、例えば悲しい事故で我が子を失ったご夫婦などを対象にスタートする。ニュースで話題になったそのお気の毒な境遇に世論の同情の声が高まったところで、人道的な特別処置として初めて公式にクローン人間作成に乗り出す。社会的な意義。そうやって徐々に世論を慣らしていきたいらしい。
「こんなことしていいんですか?」
「むしろ日本は遅い方です。」
「他の国でも?」
「ええ。まあ…。あんまり言えませんけど。」
やるせなくて子犬に手を差し伸べるとペロペロなめた。
なんてことだ。クローン実験がここまで進んでいるとは。
「そりゃそうですわ。技術的にはとっくに可能でしたから。クローン羊のドリーちゃんだって1996年ですからね。すっかり前世紀です。」と笑い「ヒトのクローンは、移民に頼らず国力を増強できますからね。世界的ビッグビジネスになります。」
「そんなに…」
「でもね、倫理的な問題がありますでしょ。」
「だから、チビのことは秘密にし、普通の子供として育てている。」
「そんなところです。」
オリジナルの人間とクローン人間が互いに与える影響についてはまだ何もわかっていない。とんでもなく悪いことだって起こるかも…。
だが慎重だった政府も、チビの誕生から9年経ってようやく動き出した。2人を一緒に暮らさせることで、何が起こるのか?確認すべきというフェーズにきたのだと犬巻は説明する。
そう、僕がもうすぐいなくなるかもしれないから。
だからって、なぜ僕なんだ?
僕のクローンを作る必要があったのか?
「お父様はあなたで実験がしたかったのか、あなたの代わりが欲しかったのか、本当の理由は、もう誰にもわかりません。」
犬巻に尋ねても、
今一つ納得できる答えは得られなかった。
■夏、第17話 残りの人生
僕、やってないことばっかり。
生い先が短い、なんて知らなかった。
勝手に将来を夢見ていた。これからどんな人生を歩んで、どんな人と出会って、どんな家族を作るんだろうと。
さすがに大リーガーやノーベル賞なんてことはないにしても、自分で起業して結構お金持ちになったりして、と夢想くらいしていた。
「いつかできるでしょ」とタカをくくって、今まで何もしてこなかった。
いつも、
「明日始めよう。」
「僕は本気出してないだけ。」
「やる気になればすごいことができちゃうかもね。」
なんて、根拠のないうぬぼれに逃避していた。
ただ高速で過ぎて行く時間に振り落とされないようしがみついていた。
でも、現実は違った。もう時間がない。
残された時間をどう使うか?考えた。
今までできなかったことをやらなきゃな。そんな映画あったっけな。スカイダイビングするとか?ピラミッドを見るとか?
エンディングノートでも書くかな。
…考えた。
いろいろ考えた。
なにかやらなきゃ。なにをすればいい?
なにかを始める時間なんてあるの?悠長なこと言っている時間はない。途中で人生終わり。突然カットアウトってことになるかもしれない。
気持ちだけが焦る。
とにかく、いつ死んでもいいと満足できるほどのことをやらなきゃ。
なんなの、それ?どこにあるの?そんなこと。
◆
夜、ばあちゃんが背を向けお茶をすすっている。
コツコツと古い振り子時計の音が響く。
ぽつりと、
「ばあちゃんが先に死のうか。」
小さな背中が言う。
「え?」
「死んだらゆうちゃんに命あげられるか?」
「なに言って…」
「ええねん。どこに頼んだらできるん?あの犬巻さんとかいう人らか?それやったら、なんぼでも…。」
「そんなこと言わないでよ。」
振り向く顔に、涙がしわを伝う。
「そやかて、おかしいやん。年寄りがのうのうと生きてて、こんな若い、これからのもんを…おかしいやん…」
くしゃくしゃの泣き顔。
胸が詰まった。
「心配させてごめん」
そう言うしかなかった。
ばあちゃんの肩をそっと手のひらで包んで、はっとした。こんなに肩の骨が小さくて華奢だったなんて。壊れてしまいそうな繊細な飴細工のようで、畏れながら柔らかく抱きしめた。
「息子だけやのうて、孫まで亡くすんは殺生や。いやや。もういやや。」
ちくしょう。情けない。
この小さな年寄りにそんな残酷なことを言わせる自分が悔しい。
僕が死んだあとは、どうするんだろう。
ばあちゃんだって、いつまでも元気じゃないだろうし。
チビは一人ぼっちになってしまう。幼い頃の僕と同じ、いや、小さな僕そのものが、たった一人でどうやって生きていけばいいのだろう。
もちろん、ONEONE保険の犬巻や教授たちの庇護下で生きていくかもしれない。でも、いったい誰がチビの将来を心配してくれるだろう?誰がチビに愛情を注いでくれるのだろう。
いや、いない。誰もいない。”実験用モルモット”になんて。
”チビに愛情を注ぐ” か…。
そんなことを考えたら、父が生きていた頃を思い出した。
父は、確かに僕を大切にしてくれていた。
幼い頃、僕はお腹が痛くなって、泣きながらトイレに入っていた。
狭い壁に囲まれたトイレで、体温が上昇し汗が吹き出て身体中びっしょり濡れていた。この痛みが一生続くんじゃないかと恐怖にさいなまれていたとき、温かくて柔らかい手が僕のお腹に伸びてきてそっと添えられた。父がドアの隙間から手を差し伸べ、うんちする僕のお腹を擦ってくれたのだ。優しさが下腹に染み込むように伝わって、心が少しずつやわらぐ気がした。
それから痛みが収まるまでずっと父は擦ってくれた。ずっと、ずっと。
それなのに、身勝手を父にぶつけたこともあった。
朝起こされて不機嫌な僕はヒドイ言葉を父に投げ掛けた。
「掃除機をかける音がうるさい。」「皿洗いする音がうるさい。」「テレビが聴こえない。」
全部僕のためにしてくれてたのに。
父は、はいはいと収め、僕のワガママを包み込んでくれた。
やってくれるのは当たり前。親だから当然。と、気にも止めていなかった。惜しみなく愛情を注いでいてくれたのに、それを僕はほったらかしにしていた。その無償の贈り物に僕は甘えていた。
親ってものは、どうしてそこまでできるのだろう。親ってすげえな。僕にはきっとできないな。できるわけないな。
だとしたら、僕にできることってなんだろう。死ぬまでにすべきことってなんだろう。
…そんなことを考えた。
そして、僕は、ある決心をする。
■夏、第18話 決心した!
僕は、ある決心をする。
残りわずかな僕の人生、これから一体どうすればいいかを。
◆
決め手となったのは、チビがまたいじめられて帰ってきたからだ。
クラスに一人、まだしつこくちょっかいを出すヤツがいるという。
チビは僕の分身だ。僕自身をいじめられた気がして、無性に腹が立った。やられっぱなしではいけない。なんとかしてやらなければ。
チビに、
「嫌なものは嫌と言えばいいじゃん」
そう言いかけて、はっとした。
大人になった僕は偉そうなこと言ってるけど、子ども頃の僕だって歯向かう勇気なんてなかった。
もし当時立ち向かえていたら、いじめっ子に一目置かれたかもな。自分に自信が持てただろうな。スクールカースト、ちょっとは違った景色だったかも。大人になってまでいつまでも人見知りで、自分のやりたい事も満足に貫けない、そんな情けない人生じゃなかったかもな。
今の僕の頭で、小学生の頃の自分に戻れたらな。きっと大人の知識でうまく乗り越えられるだろう。
すると頭の中で、ある光景がフラッシュバックした。
就活の面接官のあの質問だ。
「あなたはタイムマシンで過去へ行きました。
そこで出会ったのは、子どもの頃の自分。
未来から来たあなたは、一体何を伝えますか?」
何を伝えますか…?
伝える…
はっと、した。
そうか…そうだ、これだ!
答えが出たかも。
時間がかかったが、ようやく今、分かったような気がする。
僕の命はあとわずか。
明日か明後日か、いつ死がおとずれるかわからない。
そんな自分が今、何をすべきか?
自分なりに残された時間を一番有効に使うにはどうしたらいいか?
僕は気がついた。
そして、決心した。
「インストールしよう。」
僕の人生を、この”小さな僕”に伝えよう。インストールしよう。
地味で値打ち無いかもしれないけど、僕の人生をこのチビにインストールして人生を託そう。
僕の知ってること、役に立ちそうなこと、全部教えてやろう。僕がいなくなっても、チビが困らないように。
チビはクローン。僕と同じような人生を送る可能性は高い。これから似たようなトラブルや悩みに出会うに違いない。そういう時、自分の力で乗り越えてほしい。
残されている時間がわずかなら、チビにすべてを託すことが、最も意味のあることに違いない。ぜんぶチビに伝えきって、悔いのない人生の閉じ方としよう。
僕の意思をチビが持って生き続けてくれたら、たとえ僕の肉体が滅ぼうとも、その意思は次の世代へつながっていくかもしれない。
いや、なんならぼくの気持ちはどうでもいい。
このチビが無事に生き続けてくれたら、それだけでいい。
それだけで、未来の途切れた僕でも、未来を感じられる気がする。
ただただ、未来を感じられる気が。
それまでは、僕自身、恥ずかしくない生き方をしよう。
心を入れ替えた僕の姿を見て、生き方を学んでほしい。
「なんで空は青いの?」
「なんでパンダはしろくろなの?」
今度から面倒くさがらず、教えてやろう。
ちゃんと向き合おう。
チビと。つまりは僕自身と。

■秋、第19話 インストール!
気がつくと、さらさらした心地よい風の季節になっていた。キンモクセイの甘い香りが頬をすべり鼻をくすぐると、ちょっぴり寂し気な秋が顔を出した。
そうそう、この感じ。結構好きなのだ。
「インストールしよう。」
そう決めて以来、”小さな僕”ともっと一緒に過ごすことにした。話もした。なんでも教えた。
僕が知る限りの知識、生き方、考え方…
好きな音楽、感動した本、忘れられない絵、影響を受けた映画、テレビ、
逆上がりのコツ、サッカーの上手くなる方法、
過去にした失敗、どんな人生を送ったか。
伝えられることはなんでも”インストール”しよう。
放っておいたら、同じようなつまらない人生を送ってしまいそうな僕の分身に。
説教めいた "人生にとって大切なこと" を教えたいけど、僕なんて聖人でもないし、そんなのわからない。
たとえくだらないこと、ささいなことでもいい、知ってることはなんでも教えてみた。
『いじめられっ子は助けてあげて。やられちゃったら、いじめられた子の友だちになって。』
『いつかクラスで好きな子ができる。気を引こうと、ちょっかいを出しすぎては逆効果。』
『中2は人生で大切な時。最もこじらすけど、最も感覚が研ぎ澄まされる魔法の時間。その時に感じたことは、一生忘れない。』
『嫌いなトマトとマヨネーズ、大人になったら好きになるよ』
『太陽を直接見たときと、苦いチョコを食べたときは、クシャミが出るよ。』
『タートルネックのセーターを着ると首がチクチクするよ。』
もはや、どーでもいいことだっていい、何でも教えた。同じ"本人"である僕しか教えられないことを。
今までの人生で学んだことをあらためて思い返していると、人生の終わりに向けてゆったり静かにアルバムを整理しているような、そんな安堵感を味わえた。
「空はどうして青いの?」
「パンダはなんで白黒なの?」
そう聞かれる度、図書館に通って調べまくった。
チビが納得してくれる回答を見つけるため、棚から棚まであらゆる本を引っ張り出して読みあさった。
ググったら何かしら出てくるが、「空が青いのはね、光に含まれる青色の波長が短く大気の散乱で…」などと説明したってわかるはずもない。幼いチビでも納得できるような、噛み砕いた答えはなかなか見つからない。ちょうどいい答えを探して深夜まで勉強した。
幼いけど純粋なその探究心を大切にしてやりたかった。疑問をもつ心を持ち続けてほしかった。
一番やっかいだったのは、「お空のむこうには何があるの?」だ。
これには困った。
「お空のむこうにはなにがあるの?」
「宇宙だよ。星がいっぱいある。」と、答えてみる。
「うちゅうのむこうにはなにがあるの?」
「向こうは…ん、えーっと…んーーー」
「ねえ、なにがあるの?かべ?」
「んんんーーーーーーーーーーーーーーー」
ごめん、宿題にさせて。人類にとっても宿題だから。
もちろん勉強も教えた。
近頃の小学生の勉強は難しい。教えられるほど自分が理解できていないことに気づいた。
だから、もう一度小学一年生の教科書から勉強をしなおした。先の五年、六年生までも、今後の流れを掴むため全部勉強しなおした。
思い出したら、ちょっと勉強が面白くなってきた。気がついたらチビより勉強してるかも。僕が子どもの頃こうだったらな。神童って呼ばれてたかもな。
あまりに宿題をやらないから、うるさく言った。
僕自身が子どものころに勉強しなかったくせに、堂々と「やれ」と言うのは、どうも気が引ける。どこの親もそうなのか。気乗りしない態度を隠しながらしつこく言わなければいけない。自分の心の後ろめたさの不協和音が伝わったのだろうか、余計にチビは嫌がった。
「なんで勉強しなきゃいけないの」と逆ギレ。
「子どもは勉強が仕事なの!」
「大人になって役に立ってるの?」
うーん、そりゃそうだよな。
傍で雑巾がけしていたばあちゃんが諭すようにポツリとチビにささやいた。
「昔の人が苦労して見つけてくれはったことを、簡単に教えてもらえるんやから、もうけもんやろ。」
もうけもん…
なるほど。そう。そうだよ、チビ。そういうことだよ。
ばあちゃんがくれたヒント。僕なりに時間をかけて図書館へ通って再構築してみた。
「チビ、ここに座りな、いいか…」
例えばだ。
もしも石器時代に行ったら、現代人の君は、火を起こし、食物の種を植える術を披露できるだろう。
江戸時代に行ったら、ペストにかからないように熱湯で茶碗を煮沸するかもしれない。
それってなんでできるか、わかるかい?
誰かが見つけたことを教えてもらったからだ。
九九や三角の面積の求め方だって。誰か天才が人生をかけて発見した人類の宝。
勉強は、それを簡単に教えてくれる。
次の世代に伝えたから、子供たちはその上のレベルを知ることができる。伝え忘れたら、人類はそのレベルで足踏みをしていただろう。人類の進化はそうやってきたのかもよ。
「だから勉強は必要なんだよ。」
「う、うーん…。」
チビはうなった。
おっ、これイケるかな。
「…うーん。でもやだ」
鉛筆をポイと投げてゲームをイジり始めた。
なかなか難しい。8歳だしな。
自分だって勉強きらいだったしな。押し付けるのだけは気をつけなきゃ。ぼくの経験や知識をチビに押し付けて、自己満足で自分のコピーを作るのは避けよう。
◆
ご機嫌取りに、チビの好きな工作を一緒に作った。絵も描いた。
面白半分にイラストアプリの使い方をチビに教えてみたら、すごい勢いで食いついた。ずっといじったりしている。すぐに僕なんかより上手になりそうだ。
そりゃそうだよな。チビには素養があるはず。その芽を活かしきれなかった失敗者が言うのだから、間違いない。
恥ずかしい事を告白するよ。
僕は本当は芸術系の学校に行ってみたかった。デザイナーとか、モノを創る仕事がしてみたかった。
でも高校や大学受験の時には、そんなことを口にすることさえはばかられた。
そうだ。自信がなかったのだ。学校の先生にこう言われるのがオチだ。
「食べていけるのは一握り。もっと潰しの利く道にしなさい」
抗う勇気もなく、常識に流されて普通の大学を選んだ。どちらの道が正解だったかは今でもわからない。
僕がそうだったということは、チビもいつか同じ気持ちになる日が来るだろう。将来、進路に迷う時が訪れる運命だろう。
夢を押し付けるつもりはない。どんな夢を選んでもいい。自信をもって堂々とやりたいことを”やりたい”と胸を張って言える、そんな人間になって欲しいだけだ。後悔はしてほしくない。
いい機会だから、2人で絵を書いてみようと思った。
せっかくなので、公募サイトに載っているデザイン募集に、なんでもかんでも応募してみた。地方の小さな町役場のロゴマークから、物産展イベントのシンボルマーク。かまぼこメーカーのかまぼこ板アートコンクールまで。
チビとチラシの裏にアイデアをシコシコと描きためては、アプリでちゃんとしたデザインに起こして送った。
これって合作っていうのかな。それとも同じ人間だから一人で考えたってことか?いずれにしても名前は同じだから、一人ってことになる。
毎回、当選者発表の日までは2人密かな楽しみができた。優秀作に選ばれた時のありがとうコメントを勝手に妄想するだけで幸せだった。
だけど、山のように応募したのに、残念ながらホームページで僕たちの名前を見つけることは、結局一度もなかったけど。
◆
僕がいなくなってからの先のことも考えた。
塾に通わせるべきかな。
学資保険とかよくわかんないけどやっとかなきゃいけないかな。
お金はどれくらい残してやればいいのかな。
僕が死んでしまっても暮らせるお金は残しておこう。
シンプルだけど、ごはんを腹一杯食べさせてやりたいと思うようになった。
ある時、チビがお腹を壊して「痛い痛い」とトイレで泣いていた。
苦しみから救ってやりたいという感情が自然と沸き起こり、気がつくと手を伸ばしていた。汗でびっしょり濡れたTシャツのお腹を、手のひらで優しくさすってやる。「大丈夫、だんだん痛くなくなる、痛くなくなる…」
そう、いつかの思い出。父ちゃんが僕にしてくれた事だ。父は、どんな気持ちだったんだろう。思いをはせながら、チビに対する僕自身の感情を見直してみた。
親は子供に対して見返りを求めない。無償の愛情を持つというが、父はこういう感情だったのだろうか。
甘ったれた大学生の僕には、親というものの本質なんて、もちろんわかるはずもない。
でも、ほんの少し、ほんのさわりだけでも、
”家族”という気持ちを、一日一日、チビに教えてもらっている気がする。
いろいろ教えてやっているつもりだったのにな。
おあいこだな。
■秋、第20話 記憶の図書館
「兄ィ、ぼくサルノスケきらい。」
2Bの鉛筆でイカの頭の尖った部分を描きながら、唇を尖らせチビが言った。
日本海の幸に恵まれた山陰のとある港の町役場が、観光誘致のため行ったゆるキャラデザイン募集に応募しようと2人で考えていた時のことだ。港の名産のイカをモチーフにキャラクターを作ろうとこだわった。軟体動物なんてあんまり可愛くないから採用率を下げるようなもんだと何度忠告しても、言い出したら聞かないのは”同じ僕”だからよくわかる。この偏狭的なこだわりは他に役に立てればいいのに。
とにかく作業に集中してたから、”サルノスケきらい”という聞き慣れない言葉が唐突に出てきても、僕の耳がついていけなかった。どうやら、今描いてるゆるキャラの話ではないらしい。
「何がきらいだって?なんのスケ?」
「サルノスケ。あいつ、やなヤツ」今度はイカの10本脚を描いていく。
「誰が?チビのクラスにいるの?」
「違うよ。兄ィの学校」
「僕の学校?大学に?」
「小学校だよ」
「なに言ってんの?」
「サルノスケだよ。サルノスケ」
「サルノスケ?...」いたっけ、そんなやつ。
「やなヤツ。兄ィの消しゴムとった」
…あれ、そういえば…昔、そんな名前のやついたっけかな。
ああ、猿之介だ。ぼくにちょっかいを出したがるやつだった。小学一年生の頃だからすっかり忘れていた。大掃除で昔なくしたオモチャを見つけたような懐かしい感覚。
「なんで知ってんの?サルノスケの話したっけ?」
「ううん、会ったの」
おかしい。15年前の話だぞ。
「会ったって、いつ?」
「昨日。」
「昨日?なんでよ。どこで?」
「夢で。」
夢?そんな夢見てないぞ。
クローンの特性で僕ら本人同士の夢がシンクロするとは聞いたが、そもそも僕が見ていない夢をチビが見るはずがない。
「見たよ。兄ィの小学生のときの夢。」
昨日の夢…たしか小学校は出てきたかもしれないけど、
「猿之介なんて出てこなかったぞ」
「いたよ。消しゴムとった。」
どういうことだ?
僕が忘れていた友だちを?
「あとね、アゲハちゃんも知ってるよ。」
僕の初恋の女の子だ。
「おお懐かしい…、てか、なんで名前知ってんの?」
「ときどき遊ぶから。」
え?そんなこと知らないぞ。
チビが僕の夢で勝手に15年前の初恋の子と遊んでいる?教えてもいない名前を知ってる?いくら好みが同じだからって…そんなことある?
どういうこと?どうしてこんなことが?
◆
「こういうことかもしれません。」
猫ちゃんの声が勢い良すぎて、図書館の大理石の天井にぶつかって響いた。
係員がチラリと見たので、僕と猫ちゃんは声を落として本棚の陰にそそくさと隠れる。
大学の図書館に通うようになったのは、チビの疑問に答えるためだ。
今日の質問は「なんでヒコーキは飛べるの?」というこれまた難問。ググったら何かしら出てくるが、「翼の上下面の空気の圧力差を利用して…」とか航空力学を説明してもわかるわけない。チビの頭でも納得できるちょうどいい答えが見つからなかった。
そうこうするうち、猫ちゃんが約束の午後3時にやってきた。
サルノスケの一件があまりに腑に落ちない僕に、研究所の分析の結果を教えてくれるという。
棚に身を寄せた猫ちゃんは、新たな発見に興奮気味で、
「こういうことかもしれません。おチビちゃんはユタカさんの記憶を覗いたのかも。」
「どういうことです?」
「ユタカさんとおチビちゃんは夢がシンクロする。そこまではいいですね」
先生のような口調。図書館だと雰囲気が出るから、つい生徒みたく答えてしまう。
「はい。毎晩一緒に同じ夢を見るようになりました。」
「寝ている間の脳波を調べたら、記憶がメモリーされる部分、大脳皮質が2人とも活発になっていたんです。」
「それがなにか問題でも?」
「問題ではないです。むしろすごいことが起こってたんです。実は、ユタカさんの夢が入口となって記憶の奥底まで、おチビちゃんがたどり着いたのかもしれません。」
なんすか、それ。もしかして、
「チビが僕の頭の中をのぞいてる?」
「はい。のぞける可能性があります。」
「えー、気持ち悪い」
「ユタカさんも、おチビちゃんの頭の中を…」
「のぞける?」
「はい。お互いに。」
「プライバシー的に問題ないですか。」
「変な事、考えなければいいんです。」とニコリ。
「考えません。」
でも、変だ。なんで僕が覚えていないことをチビは知ることができたのか?
「僕、忘れていたんですよ。サルノスケのこと。」
「おチビちゃんは、ユタカさんの脳の中、記憶の奥底にまで深くダイブしたんでしょう。」
「どーゆーことですか?」
「聞きます?」
「また難しい説明?」
「ぼちぼち」
「うーーん。やさしくお願いします」
おどけると、猫ちゃんは笑った。そんな軽い冗談を言い合える関係に戻れて嬉しかった。係員がまたギロリ。二人して肩をすくめ、人差し指を唇に当てる。
「例えるなら…脳には、巨大な記憶の図書館のようなものがあります。」両手を広げて歩き出し、「ここみたいに。」くるりと回る。
「おっ、そーゆーの分かりやすいですね」後を追う。
「脳の図書館には、すぐ取り出せる新しい記憶と…」
手前にあるマガジンラックの雑誌をするりと手にとって、先へ進む。
「それから、奥の倉庫に収納されて取り出しにくい記憶があるんです。」
ずらりと並ぶ棚を指す。膨大な本がぎっしり詰め込まれていた。
「すごい量だなぁ」
「人生で体験したことはすべて、記憶の棚に入っているんです。」本を一冊ずつ手に取って次々僕の胸に渡す。「これが生まれたとき。これが初めて歩いたとき、それからこれが…」
「いやいや、さすがにそんなに覚えてらんないでしょ。」
「それが覚えてるんです。”人は脳の10%しか使っていない”、とかよく言いますよね。まあ、都市伝説的なもので正確にはちょっと違うんですけど。本当は脳をもっと使っているのに、ただ気づいていないだけ。」
「もっと使ってる?誰でも?」
「聞いたことありませんか?例えば、サバン症候群の方が、目で見た風景を写真のように細部まで記憶したり、膨大な数字を一瞬で覚えたり、特殊な記憶力があるって。」
「特別な人だけでしょ。」
「誰でも、脳にはすべて記憶されているんです。」
「僕覚えてないですよ。全部なんて。」
「全部思い出せないのは、取り出せないだけ。脳の安全装置です。
辛いことをすべて覚えていたら大変でしょう?いじめられたり、つらい失恋をしたり、病気の苦しみ、大きな怪我の痛みなど…、全部覚えていたらストレスで耐えられないかもしれませんよね。ユタカさんも9年前の自動車事故の痛み、覚えていたら…?」ポンと渡してくれた医学書には、人体の臓器の生々しい写真がどーんとあった。
「死んじゃいます。」
「ね、都合よく忘れるのは、人間の防衛本能みたいなものです。」と棚に戻す。
「確かに、忘れないと先に進めないことってあるもんな。」
「でしょ。人間の安全のために、記憶の大部分は、図書館のロッカーの奥にあって取り出せないようになっている。」
係員の座る貸出カウンターの奥に、厳重なロッカーが立ち並ぶ。
「記憶力がすごい人は、棚が整理されていて、記憶を選んで取り出すのが上手い人なんでしょう。」
不思議そうな顔で僕らをうかがう貸出係。こんな係員が探してくれるのかもね。
「それと僕たちの夢と、どんな関係があるんです?」
「『夢』は、記憶のロッカーを開ける鍵のようなものかも。」
「夢が鍵?」
「『夢』を見ている『レム催眠』の状態。熟睡でもなく目覚めでもない。浅い眠りの間に思考の電気信号が活発にやり取りされている…だから記憶を遡るのに適しているんじゃないかと。そう研究所は考えています。」
「じゃあ、僕の夢にチビが入ってきて、埋もれたサルノスケを偶然見つけた?」
僕は、棚の裏側の見えない所から絵本を引っこ抜いて見せた。いたずらな子ザルが騒動を起こす話だ。
「記憶の奥底から、サルノスケ君を見つけ出したんでしょうね。同い年くらいの子だから、気になったんでしょう」
「でも、夢って起きたら忘れるもんでしょう?覚えてましたよ、チビ。」
「きっと、チビちゃん自身の脳に持って帰って棚に入れた…」
僕は想像してみた。
チビの姿が陽炎のように現れ、棚をウロウロ、何かを探しているようだ。
ふと僕の手元を見つけて、嬉しそうに子ザルの絵本をとり、胸に抱えてはしゃぎながら出口の方へ走っていった。
「僕の記憶がチビの記憶になったってこと?」
「ええ。一緒に暮らすだけで。特に夢の中では、記憶や経験までもよりコピーされやすいってことでしょうね。」
「記憶がコピーされる…。」
「昔、お父さまの汐妻教授が犬のクローンを作った時、オリジナル犬とクローン犬を一緒に研究所で飼っていたことがありました。するとなぜか、オリジナル犬しか知らないはずの芸を、突然クローン犬が始めたそうです。」
「教えてもいないのに?」
「ええ。知らないはずの元飼い主になついたり、行ったことのない家までひとりで帰ったり。」
「犬も一緒に暮らして、記憶がコピーされた…」
「同じ夢を見たのか?どうしてなのか?解明されなかったんですが…これは、とんでもなく大きな発見かもしれませんね。」
なんだか知らないがすごいな。
少し喜んでいたら、猫ちゃんは嬉しそうではなかった。
「でも…」
「でも?」
「全部の記憶を取り出せるということは、とても危険なんです。とてつもなく悲しく辛い記憶を取り出してしまうかもしれないんです。」
「悲しく辛い記憶…」
「それが引き金になってロッカーがあふれ出し、人生すべての激痛や苦悩が洪水になって押し寄せてしまう」
「そうなると?」
「そうなると…ユタカさんと、おチビちゃんは…」
「2人は…?」
「人間の体じゃ耐えきれなくて、脳神経が崩壊するかもしれません。」
眼の前の棚がすべてドミノのように倒れ、本が散乱し、大理石の天井が崩れて行くような気がした。
「……」
「……」
「やっぱコワイじゃん‥‥。猫ちゃん、やめて、その怖い感じ。」
猫ちゃんは笑った。
■秋、第21話 夢地図
チビと僕は、どんどん同じ夢を見始めた。
夢を入口にして、相手の記憶に入り込んで互いを知り合った。
僕の小学校はもちろん、中高時代。父との思い出…。
チビが父と2人で暮らした思い出。前の学校のこと…。
同じ夢を一緒に見るだけで、互いの知識と経験がコピーされていく。
人生を2人分経験しているようだ。
これ、使えるかも。
毎日一生懸命チビに勉強を教えてるけど、この睡眠学習を上手く使えばイイんじゃない?今まで勉強してきた記憶が寝てる間にチビの脳にコピーされる。トラえもんの暗記パンみたい。苦労しなくていい。ずっと寝てりゃいいし、楽だ。
勉強の知識をコピーしたいなら、”教室の夢”を見る。
友だちとの経験をコピーしたいなら、”友だちと遊んだ夢”を見ればいい。
だけど、気を付けなければ。
猫ちゃんが忠告するように、記憶の底から、痛みや悲しみまでもうっかり引っ張り出してしまうかも。
夢をコントロールできればいいのに。見たい夢を選べるし、互いの記憶を安全に探せるに違いない。
だったら『夢』の構造をもっと知っておかないとな。
見た夢を記録しておくべきだよな。夢で ”どこで誰と出会ったか”、忘れないようにメモしなきゃ。
というわけで、早速、朝起きてすぐ見たことを忘れないうちに枕元のノートに書きなぐってみた。でも、起きてすぐだとぼんやりうろ覚えで、なかなか全部を思い出せない。
もっといい方法ないかな。夢の中で迷子にならないように。例えば、地図みたいな…
そうだ、「夢地図」を書こう。
どんな場所があって、道があって、誰が登場して何をしたか…。
夢の中の世界で、舞台となった場所をベースにストーリーや登場人物を思い出したら、格段に記録しやすくなった。
そうするうち少しずつ、夢にはいろんなルールがあることが分かってきた。
夢の中の世界は、日常生活のリアルな風景がもとになっている。僕の家や近所、日常の風景から、昔の僕の育った記憶と、チビの記憶。
そこに、かつて観たテレビや映画、自分の空想などがスパイスとなってアレンジするもんだから、どこか少しだけ現実と違うパラレルワールドのような世界。
だから懐かしいような、初めて見るような、とても不思議な場所だけど、とても居心地がいい。
しかも、現実の場所の配置と違って、家も学校も近所もお店も路地も、ごちゃごちゃにつながっているからややこしい。家にいて押し入れを開けたら公園に出たり、学校の廊下を歩いていたら、路地に出たり…。
朝思い返すと、こんな場所とつながってたっけとなる。どうやら、現実世界がパッチワークのようにごちゃまぜに切り貼りされた世界のようだ。
そこには、いろんな人が出てくる。ばあちゃんも、学校の友だちも。いろんな人が混ざり合って登場する。時間軸がむちゃくちゃで、チビのクラスメートと僕の大学の友だちが同い年で登場したりした。
でもなぜか、夢の中ではそれらの”違和感”には気づかない。どんなあり得ない出来事だって、さらっと受け入れてしまう。不思議だけど。
毎朝のメモがたまってきたら、ごちゃまぜの世界を、パソコンの図形ソフトで一枚のつながった夢地図にしていく。根気のいる作業。
だけど、”意識して夢を見る”ことを始めたら、毎晩、布団に入るとき夢を見るのが楽しみになった。
「今夜はどんな夢だろうね」チビと僕は枕を抱いてささやき合った。
どんなことが起こるだろう?ラブコメかな?SFアドベンチャーかな?全米が泣くような感動巨編かな?まるでシネコンの席にチビと並んで座って待つワクワクに似ている。しかも普通の映画じゃない。3Dや4DXなんて目じゃない。バーチャルリアリティーの超体感アトラクションだ。
そういえば、ひとつ気になることがある。
おめでたい映画気分に水を差す、ちょっと奇妙で、不可解な出来事。
”ヒトカゲ”だ。
ある夜、夢の世界でチビが、「兄ィ、あの人だれ?」と指をさした。振り向いた時には一瞬姿が見えたが、すぐいなくなってしまった。
それ以来チビと僕は、夢の中で誰かがこっちを覗いているのをしばしば目撃するようになった。どこにいても、誰と一緒でも、離れた場所からこちらをうかがうような影。陽炎のようにユラユラ揺れ、顔はハッキリ分からない。誰なのかも分からない。曲がり角の向こうや木の陰から、いつもこちらを見ている。そんな気配をいつも感じ、夢の中でも腕に鳥肌が立つ。
僕らは朝起きると、「見た?」「またいたね」と話し合い、そいつに『ヒトカゲ』とアダ名をつけて呼んだ。ちょっとしたホラーとして楽しんでもいた。
しかし、やがてその”ヒトカゲ”が、
僕たち2人の関係に大きな影響を与えることになろうとは、
その時、僕とチビはまだ知らなかった。
■秋、第22話 ハロウィーン!
ちょっとやっかいな問題が起こってしまった。
小学校のハロウィンパーティーのこと。ほんの遊び心で、僕とチビは仮装をしてみた。
腹話術の人形の仮装だ。
揃って同じ青い半ズボンにサスペンダーと蝶ネクタイ。口の両端から顎にかけて縦に2本の線を書き、ほっぺを赤くメイクしただけ。元々同じ顔だ。僕がチビの背中に手を添え、まるで同じ顔をした腹話術の人形が2体。大きな人形が小さな人形を操っているように見せた。
2人揃って…、
「こんにちは」
「こんにちは」
「マネすんな」
「マネすんな」
「お前こそ」
「お前こそ」
頭を叩く”パコン!”
頭を叩く”パコン!”
首が伸びて「ヒャー」
首が伸びて「ヒャー」
ただそれだけ。それだけなのに、小学生にはウケた。子供騙し、とはよく言ったもんだ。
なにせ同じ顔で見事なまでの同じ動きと同じ言葉のシンクロ。初めてのペアルックもそれらを際立たせた。おかげでチビっ子たちに”キモカワ”と絶賛された。人によっては同じ顔に驚いて「特殊メイクですか?」と本気で尋ねられることもあった。何度も繰り返し披露するうち、どんどん人が集まり、一気に人気者になった。
しかし、問題はこれから。
注目を集めてしまったために、誰かが動画を撮っていたらしく、SNSにアップされたばかりか、ネットで話題になってしまったのだ。
2人揃って、
「こんにちは」
「こんにちは」
「マネすんな」
「マネすんな」
「お前こそ」
「お前こそ」
頭を叩く”パコン!”
頭を叩く”パコン!”
首が伸びて「ヒャー」
首が伸びて「ヒャー」
ここからは偶然のアクシデントが重なってしまった。
たまたま友達に「ユタカくん」と呼ばれて…、
「ん?」と振り向く。「なに?」
「ん?」と振り向く。「なに?」
たまたま居合わせた犬に「ワン!」と吠えられ…
「ヒャー!」とビックリ
「ヒャー!」とビックリ
揃って気まずくて…、
頭をポリポリ掻く。
頭をポリポリ掻く。
と思ったら…、
「へえっくしょん!」と大くしゃみ
「へえっくしょん!」と大くしゃみ
これをあまりに揃って同じ顔でやったもんだから、「面白い」と動画で投稿されてしまった。
ネットの世界で一気に拡散され、学校や近所でちょっとした有名人だ。チビは人気者になった。
こうなると、いつもいじめてくる子でさえも、「俺は”ユタカくん”と友達だよ」と周囲に自慢してへんなアピールをしてきた。「くん」付けして、急に優しくなって…。あきれたけど、まあ、これはこれでよかったかもね。
テレビの取材の申し込みがあったり、人気が出るのは嬉しいが、
犬巻から軽率な行動するな、目立つとバレてしまう、とこっぴどく叱られた。「契約書に書いてあります」とぴしゃり。
人の興味なんてそれほど続かない。やがて話題も収束していった。
しかし、ほっとするのも束の間…。
そのあと、さらに事態は大きく動く。
■秋、第23話 世界でも!
アジアの若い女性が赤ちゃんを抱いている。
一見微笑ましい画像が、なぜか世界中のニュースを騒がせた。
インドでクローン人間を作ったというニュースだ。
13億以上も人口であふれているのに、これ以上増やすなんて…、「なんなのそれ」と世界から非難された。
首都ニューデリーで人権保護団体のデモが起き、糾弾されたインド政府は、クローン人間研究を真っ向から否定した。
米国や西ヨーロッパ諸国、ロシア、中国もみんなズルかった。各国は自分たちも研究を進めているくせに、国内世論を気にして、表向き批判するコメントを発表。
逆ギレしたインド政府は、「各国やってるよ」と国名を名指しで挙げて矛先を向けさせた。
おかげで、どの国でもクローン研究をしているという疑惑が世界中を席巻する始末。
ニューヨーク、パリ、モスクワ、香港、イスラム国でもクローン反対のデモが起きた。どの文化でもクローン人間はご法度らしい。有識者、宗教家、芸術家、そろってクローン研究を批判した。
大物アーティストのなんたらガガが『SAVE CLONES』という曲をアカペラで配信したら、世界中のアーティストが次々ウェブ上でアレンジしてまたたく間に広がった。
国連では持続可能な開発目標の18個めに、クローンの人権を加えるかどうか大真面目に検討し始めたという。
ローマ教皇は、
「人は神ではない。神の業を真似てはいけない。」
との声明を発表。クローン人間実験は、愚かな行為。神への冒涜だと宣言した。
日本でも、まことしやかウワサが湧いてきた。厚生労働省でクローンの臨床実験が行われている、というモノ。野党からの追及に、政府はそのような事実はないと真っ向から否定した。遺伝子研究に関する文書はすべて残っていないと内閣官房長官は無表情で言い放った。
僕とチビがいるのにね。
◆
そんな中、
例の僕たちのハロウィンの腹話術動画が、じわじわ時間差で今ごろ世界中に拡散された。シンクロ具合の見事さに、海外のオモシロ動画番組でも取り上げられたらしい。
ネットに勝手にアップした人がつけたタイトルが "クローンボーイズ" だったため、「これって本当にクローンだったりして」と冗談交じりでささやかれ始めた。挙げ句には、似ている2人を見つけては晒す"クローン狩り"というネット民に目をつけられるまでに。
犬巻にこっぴどく怒られた。
「危険です。すごく危険。こんなに世界でクローン問題が取りざたされている時なのに軽率すぎます。」
「すみませんって。」
「あなたたちの身も、危険なんです。」
「そんな大げさな。似たようなフェイク動画、星の数ほどありますよ。」
「世界中の当局を侮ってはいけません。素性なんてすぐバレてしまいます。強制的に拉致されてしまう危険性だってあります。」
「大丈夫でしょう。ははは」
「真面目に話してます。」と、バッサリ。
「すみません。」勢いに思わず謝った「…でも、どーゆーことですか?なんで外国が僕たちを?」
「こうなったらお話しますがね…。」
わんわん保険のオフィスの椅子にどさっと腰を下ろし、憮然とした諦めの表情で説明し始めた。
「クローン技術の開発は、世界中で競争が激化しています。ここ2年はスウェーデンが一番トレンドなんですが、アメリカ、中国、インドなど、水面下で密かに開発競争が加速しています。なんだったら以前、あなたたちの存在を嗅ぎつけた某国から秘密裏に外務省を通じて申し入れがありましたわ。2人を調べたいから一時提供してほしい。どこにいるんだって。」煩わしそうに言い捨てた。
「なんで僕たちを?」
「おチビちゃんは、世界的に見ても極めて…」咳払いをはさんで繰り返す「き、わ、め、て、高いクオリティのクローンなんです。お父様の汐妻教授の技術は世界的にも唯一無二。9年前、一気に日本がトップレベルに躍り出たんです。…まあ、それも彼が亡くなって、ちゃんとした形で継承されなかったんですけどね。あーあ、もったいない。」と口紅を塗りたくった唇をへの字にした。
それは、世界に類を見ないほど精度の高いコピー。…いや、”2つともオリジナル”とさえ言える最高級の芸術品なのである。シオツマ法という独自の製法。父が開発した。
たとえば双子。一卵性双生児だとしても、指紋まではさすがに違う。母親の胎内での位置や栄養の吸収など微妙な環境のわずかな違いで変わってしまうという。
ところがシオツマ法は、両親の遺伝子情報まで計算して成長を予測する。そして指紋まで同じ完全なクローンを作る技術なのだ。
しかし、その詳しい方法を誰にも伝えることなく父は亡くなった。
「ちゃんとした警備をつけなきゃ。」
犬巻が溜息まじりにつぶやいた。
■秋、第24話 バレた!
チビはスーパーマーケットが好きだ。ついて行きたいとよくせがむ。
僕も小さい頃そうだったからムリもない。
グレープ味のうすっぺらいグミ、イチゴのチョコレート、コーンスープ味のうまか棒…、色とりどりの棚はまさに夢の世界。
今日も、狩猟本能に目覚めた様子で興奮気味に物色している。ふと、チビが棚の上の方に目を奪われた。最近CMで見かけたシリアルだ。小さなオモチャのオマケが本当の目的だけど。自分で取りたくて背伸びしている。
僕がとってやろうと手を出そうとした時、耳の端に何かがコソコソ聞こえてきた。
買い物のおばちゃんたちだ。こっちを盗み見ながら囁き合っている。
目が合うと、そそくさとワゴンセールを選ぶフリをしてごまかされた。
YouTofeの腹話術映像が海外のネットでざわつき始めてから、どうやら顔が知られてしまったようだ。いよいよ本物のクローンではないかと疑われ始めたらしい。
家の周りもざわつきはじめた。表にメディアの取材やYouToferらしき姿をちらほら見かけるようになった。カーテンの隙間から覗くと、脚立に座ったカメラマンたちがスマホで時間つぶしをしている。中には外国人の姿も。海外の取材チームだろうか。
見出しが躍る。
「人体実験された子どもたち!? 倫理を無視した政府!?」
記事が出た裏には、政権をひっくり返したい野党の思惑があるという。大手広告代理店を使ってこっそり仕掛けたそうだ。「政治屋の泥仕合ね。」皮肉たっぷりに犬巻がボヤいていた。
もちろん僕たちが本物のクローンなんて確信はない。フェイクかどうかなんて彼らには関係ない。"!?"を見出しの最後につけておきさえすれば、何でも書ける。断定はしてないから、訴えられても心配はないんだと。
世間は、物見遊山な同情をした。退屈な国民には、”いたいけな子どもVS政府”という構図が、ちょうどよかったようだ。週刊誌、ワイドショー、ネット…、格好のエンターテイメントとして人々に消費された。
◆
チビが不安になっているのが、手にとるようにわかる。
感情のシンクロ度合いが強すぎて、少しこめかみ辺りがピリピリする。何が何だかわからないだろうね。小学生にしては負担が大きすぎる。精神的に不安定になっているのだろうか、小2のクセにおねしょをして泣いていた。
お昼過ぎ僕が洗濯物を干していると、学校の先生から興奮気味に電話があった。
”またいじめられた?”
そんな不安が頭をよぎったが、戸惑っているような喜んでいるような浮ついた声で、
「汐妻君が大変なことに…」と言うばかり。
どうしたのか問うと、
「授業中、寝てばかりいて。」
「え、それはすみません。帰ったら厳しく…。」
「いえ、そうじゃないんです。」
「は?」
先生が放った言葉は、予想を裏切るものだった。
「成績が上がったんです。」
「はぁ?」
「それが、普通じゃない上がり方で。なんというか、急激すぎるんです。」
最近、授業中に寝てばかりいるのに、何を当てられても完璧に解いてしまい、すべて非の打ち所のない正解なのだという。
職員室で試しに、中学の参考書を見せたら、因数分解をやってのけ、英語の過去完了形を訳し、古文のラ行変格活用をそらで暗唱したのだという。
「ありおりはべりいまそかり…。」小2で習うわけない。
また、いじめっ子を言い負かして、けちょんけちょんに泣かしてしまったそうな。それはまるで大人が子どもを諭し問い詰めるような言葉遣いだったそうだ。
もしかして僕のせい?
僕でさえ忘れた予備校時代の勉強の記憶や、大人の僕の言いまわしが、ここにきてチビの脳に加速してコピーされ始めたのか。パワーアップしちゃったな。このペースでいくと、とてつもない天才少年を作ってしまうかも。おねしょは治らないけど。
「ご家庭内で何かあったんですか?」
またもや疑り深い口調になってきた。むしろわかっているクセにわざと聞いていると言った方が正しいかも。「もしかして、最近騒ぎになっている噂に関係あるんじゃないでしょうか?」
特ダネを掴んだ週刊誌記者のような口ぶりだ。こりゃ先生、ワイドショーの見過ぎだ。下世話な好奇心で教師という立場を忘れてしまっている。電話の向こうできっとあの一文字の眉毛を疑わしくクネらせているのだろう。
困ったな。
いよいよ隠しきれなくなってきた。
■秋、第25話 ステージ4
騒ぎが静まるまで、おとなしくしているよう犬巻に釘を刺された。
学校以外、あまり外に出かけられない日が続き、僕とチビは2人で過ごす時間が増えた。
ずっと家で、朝から晩までそばにい続けた。そのせいで、発言や動作のシンクロが多くなり、僕たちは知らずのうち同じ行動をし、まるで一心同体のような錯覚さえ起こし始めるほどだった。
◆
そして、ついにその時がやってきた。
きっかけとなったのは、夢を見たことだった。
お祭りの夢だ。
縁日の屋台がひしめく夜の境内。たこ焼き、お面、りんご飴、金魚すくい。ぶら下がった電球が人の波に揺れて、うす橙色の光に染まった風景もゆっくり揺れている。
僕の記憶がベースになって作られた夢なのだろう。チビは初めて見るお祭りに大興奮した。あれもこれもと、せがんだ。
「兄ィ、これやりたい!」
ヨーヨー風船釣りだ。
錨状に曲がった針を紙のこよりで吊るし、水風船についたゴムの輪をひっかけて捕るのだ。
「いっぺんに水につけちゃダメだよ。濡れたらすぐ切れちゃうから。」
「わかってる。」
「狙いをつけてから、水に浸ける。狙いをつけてから、浸ける。」
「わかってるって!」
”ボチャン”
言ったそばから、水中に手を突っ込んだ。紙こよりをどっぷり濡らしてから、輪っかを探すもんだから、えいやっとひっかけたとたんに切れてしまった。
「はははは。ほらね」
「うるさい。もう一回。」
「はいはい。おじさん、もう一回。」
その時、背後に何か感じた。
急いで振り向いたら、視界の端に何かを一瞬だけとらえた。行き交う人々の隙間だったけど、確かに見え隠れした黒い影。明らかに誰かがこっちを覗いていた。
あの”ヒトカゲ”だ。
間違いない。
チビと僕の夢に出てくる怪しいヤツ。また出てきやがった。一体なんだよ、何者なんだ?
いつもは恐れの感情だけが僕を支配してしまうのだが、今日は違った。むくむくと好奇心が持ち上がり、僕の弱虫を押さえつけ始めた。今なら正体を突き止められそう?そんな思いがよぎる。気がつくと、えいやっと走り出していた。
「チビ、そこにいろよ!」
僕は人混みをかき分け、ヒトカゲを追った。人にぶつかりなかなか前に進めない。夢の中ってのは両足に力が入らなくて、いつも思うように走れないのはなぜだろう。
まごまごする僕を置いて、やがて、ヒトカゲはどこか雑踏へ消えてしまった。
あきらめを引きずりながらヨーヨー釣りに戻ると、なにか変だ。
チビの姿が見当たらない。
どうせそのあたりにいるだろうとタカをくくって見回したが…、いない。
「おじさん、ここにいた子は?」
「さあね。」
行き交う浴衣と浴衣の隙間に、チビのあのボロくて黄色いTシャツが通り過ぎるのを期待した。あっちの方角か?それともこっちか?…わからない。はるか向こう、きらめく縁日の雑踏の先っぽまで見渡しても、いない。
どんなに探しても、いつまでたっても見つからない。
…しまった。見失った。ヒトカゲの仕業か?
今まで夢の中で、チビがいなくなったことはない。僕とチビで同じ夢を見る時は、必ず2人でいた。だって2人の夢だから。
だけど、今ここにいるのは僕の意識だけ。チビの意識は?どこへ行ってしまったのか?
たまらない焦燥感で途方に暮れたところで…、眠りが覚めた。
目を覚ましてあわてて横を見たら、チビが小さな寝息をたてていた。
良かった。夢だ。そりゃそうだよな、ほっと息をついてチビを揺り起こした。
「おい、チビ、もう7時半だよ」
起きない。いつものことだ。
「おい、チビ。起きろって」
なんだかいつもと違う。
何度揺り動かしても、目を開けない。チビが全く目覚めなくなっていた。息はしてる。脈もある。
これは夢か?いや違う、なんとかしなければ。
急いで猫ちゃんに電話し、リモートの遠隔操作で診てもらった。
「心配しないで。ユタカさんはシンクロしていませんか。気分は?」
「だいじょうぶです。」
画面に映る彼女から指示されたとおり、脈拍計や心電図の吸盤をチビの小さな体に設置すると、データが遠く離れたリモート先でもわかるらしい。あわてるから手が震える。
数値を確認した猫ちゃんは、
「健康ですね。寝ているだけのはずなんですが…」言いながらも首を傾げた。「とにかく念のため、救急車を呼びますね。」
手際よく連絡をしながら、問診する医師のような口ぶりで僕に尋ねた。
「最近、変わったことはありましたか?」
「学校でも寝てばかりいるようです。」
「寝てばかり…。今日はどんな夢を見ましたか?」
「お祭りの縁日です。屋台がずらっと。チビ初めてだったらくて、すごいはしゃぎっぷりでした。」
「もしかしたら、楽しすぎて一度にものすごい量の記憶を、自分の脳内に持って帰ってしまったのかも。」
思わず想像した。
図書館の本をしこたまカートに積み上げ、山からポロポロ落としながら、重そうによろけて運ぶチビの姿。
「持って帰ったけど、データ量が多すぎて、脳内で処理しきれていない可能性があります。」そこまで言って、猫ちゃんは自分の言葉を確かめるように、「…データ量が多すぎる…」ひとりつぶやく。
気になって、
「多すぎると、なにかあるんですか?」
「もしかして…」
画面の中でも、思いを巡らす様子が見て取れる。
「もしかしてって、なにが?」
「あとで説明しますね。だとしたら、眠ってるだけですので安心してください。」
「そう言われても。」
「他に変わったことありませんでした?」
「あ、そういえば、ヒトカゲがいました。」
「ヒトカゲ?」
「いつも夢に現れるんです。顔は見えない影のような人間。」
「記憶データのバグのようなものでしょうか。」
と首を傾げた。
10分後救急車が来て、チビは奥多摩にあるいつもの遺伝子工学研究所へ運ばれた。
◆
やがて1時間もしたころ、猫ちゃんの言った通り、チビはなにごともなかったかのように目を覚ました。
「うーん」
「だいじょうぶかい?」
大きなあくびをして、シャツの下から手を入れてお腹を掻いたチビは、「あれ、なんで猫ちゃんいるの?ここどこ?」と眠たそうに言った。
「のんきなもんだな。」思わずホッとして笑ってしまった。
「よかった…。」猫ちゃんは柔らかそうな指先で、寝ぐせのついた小さな頭を撫でる。
心配して損しましたよね、と軽口を言おうとしたけど、なぜか陰のある横顔に見えて何も言えなくなった。彼女はずっと頭を撫でていた。
「私にも年の離れた妹がいるんです。」
猫ちゃんがまるで独り言のようにつぶやいた。
「へぇ、妹さんが。」
プライベートを話すなんて珍しいなと、嬉しくて踏み込んでみた。「仲はいいんですか?」
「…長い間、体を悪くして寝たきりなんです。意識もなくて。」
意外な事情に、
「あ…すみません。」
「いえ。だから、おチビちゃんとユタカさんを見てると、私たちもこうだったかもなって。一緒にいられるだけで嬉しくて…」
「……」
そう話す横顔は、姉の優しさと、寂しさに満ちていた。
意識のない妹さん…。
猫ちゃんの背負っているものは、僕には思いの及ばないところにあった。僕とチビが兄弟のようにケンカしたり遊んだりする姿を、妹さんと重ねて見ていたなんて…。猫ちゃんのこと、あんまり知らないんだな僕。
美しい横顔に目を奪われながらも、今のやりとりを少し後悔していたその時、チビを撫でる猫ちゃんの手がピタリと止まった。
「ユタカさん。」
明らかにさっきとは違う声色。部屋の向こうで片づけをする研究員や看護師たちに聞かれないよう抑えたささやき声だ。
戸惑う僕に、
「時間がありません。今から私が言うことを聞いてください。」
「なんでしょう。あらたまって。」
空気を察して、窓外の緑の芝生を眺めているフリの横顔で答えた。
「このあと犬巻さんから説明があると思います。」
「説明?なんのですか?」
質問には答えず、
「決して、彼女たちの言葉に流されないでください。どうすべきかは、ユタカさんが自分自身の心に従って決めてください。」
「え?」
思わず見た。
「もう一度言いますね、どうすべきかは、ユタカさんが自分自身の心に従って決めてください。」
「え?なんのこと?」
「私の中でも結論が出なくて…。ユタカさんとおチビちゃんをずっと見てきて、これは他人が決めてはいけないことだと思いました。」
「どういう意味ですか?」
「今まで巻き込んでしまってごめんなさい。実は……」
”バタン!!”
その時、大きな音でドアが開いた。
「ついに来たってこと?」
犬巻が入るなりコートを脱ぎながら言った。
「そのようですね。」
ヤギヒゲ教授やツルタ弁護士が追いかけるように続く。
猫ちゃんは、僕との会話なんてなかったように仕事の顔に戻り、速やかに報告した。
「検査の数値はクラウドに共有しました。」
「ファイル名は?…」
「ステージ4です」
「ステージ4、ああ、これね。」
コートをチビのベッドの上に放り出し、老眼のアームを耳に差し込みながら、タブレットに指を滑らせる。「はい、きたきた。」早る気持ちか、古い指輪が画面に当たってコンコン音がする。慌ただしい大人たちに僕だけ置いて行かれながらも、チビの身になにかとてつもなく特別なことが起こっていることだけは感じた。
「ステージ4についての汐妻教授の論文もアップしました。眠り続けたのは兆候かと。」
父の論文?ステージ4ってなんだ?
ヤキヒゲ教授が興奮して「ステージ4か…こんな日が本当に来るなんて。」なんだか嬉しそうな感情をかみしめている。
だからステージ4ってなんなんだ?
「あの…」
邪魔しないよう気を使いながら、僕は思い切って聞いてみた。
「ステージ4ってなんですか?良くないことでも…?」
皆ピタリと止まった。
ヤギヒゲとツルタが僕を一瞥し、互いの顔を見つめ合った。やがて猫ちゃんに目線をパスする。猫ちゃんが意を決した表情で犬巻を見ると、観念したように、
「そうね。予定より早いけど、仕方ないわ。」
とタブレットを置いた。
◆
僕とチビたちは長い廊下を歩かされた。
黙々と進む犬巻の背中を追いかけながら、ぼんやりと白く光る通路に並ぶたくさんの研究室を通り過ぎた。窓から覗く光景はさまざまで、まるで美術館に並ぶモダンアートの絵画のようだった。
液体の入った透明の大きなガラスチューブが何十と並び、小さな気泡がたくさん立ち上ってゆくのを研究員がじっと見つめる部屋。
象ほどの巨大な顕微鏡のモニターを数人が頭を突き合わせながらのぞく部屋。
真っ暗な中、針金の先から火花が飛び散るたびに、ゴーグルした研究員が浮かび上がる部屋。
どこへ連れて行く気なのだろう。
犬巻たちが口を開かないのは、どうせこれからイヤというほど長い話になるからなのだろうか。どこまでも続くサイエンスアートな風景を眺めながら、猫ちゃんのさっきの言葉を思い返していた。
"決して、彼女たちの言葉に流されないでください。"
"どうすべきかは、ユタカさんが自分自身の心に従って決めてください。"
どういうことだろう。
どんな選択をせまられるというのか。猫ちゃんの様子を盗み見たが、何もなかったように無機質な横顔だった。
突然、何かの塊とぶつかりそうになった。
あわわわわ、と避けると、スーッと滑るように音もなく動く丸い物体に「シツレイ」と言われた。球体ロボットの白くつるんと丸いボディを、一行は当たり前のように受け流したが、チビはうわあと喜んで付いて行ってしまったので、慌てて連れ戻したりした。
物珍しそうにはしゃぐチビを、犬巻はチラリと見た。
「気を付けて。その辺を触ると黒焦げに感電しましてよ。」
「えっ」
「えっ」
チビと同時に驚くと、
「おっ、シンクロ。」
とヤギヒゲ教授が喜んだ。
「冗談ですよ。繊細な装置もありますのであまり触らないで下さいね、って意味です。」と猫ちゃんが優しくフォローし、「ここは広いので、迷子にならないようちゃんと付いてきてくださいね。」
とだけ付け加えた。
人知れずいろんな研究が行われている。
僕とチビのようなクローン実験なんて氷山の一角なのかもしれない。
階段を降りたり上がったり、置いて行かれないよう速足でついて行くと、やがて廊下の一番奥らしき場所にたどり着いた。
そこには、窓もなくドアだけがぽつんと佇んでいた。
犬巻が首にぶら下げたIDカードをスライドし、瞳をかざして虹彩認証チェックを行うと、カチリと小さく音がする。
"覚悟は?"とばかりにこちらをうかがい、ゆっくりレバーのノブを動かし重そうなドアを押しながら中へ入る。近未来的なデザインのこの建物には似つかわしくない、少し古臭い建材の匂いがした。
壁のスイッチを入れると、電灯が部屋を照らした。思ったほど広くはない。昔ながらの木製デスクや時代物のランプ灯で揃えられており、古い大学の研究室をそっくりそのまま移植したことを感じさせる。
「お父様、汐妻教授の研究室です。」
目に飛び込んだのは、部屋の中央にそびえる大きな透明のガラスチューブがひとつ。樽ほどの大きさだが、中は空っぽだ。水族館でクラゲを見た水槽に似ている。
天井からたくさんつながっている管たちが、ここに何かが入っていただろうことを物語っている。観賞用のクラゲや熱帯魚ではなさそうだ。
冷たいガラスの表面にそっと赤紫のネイルの手を添え、思い出すようにつぶやいた。
「この部屋です。ここでクローンの実験が行われました。」
「じゃあ、チビはここで…」
チビが走り出し、
「これ!兄ィとぼくだよ。」と指さした。
デスクには研究機材とたくさんの本が整頓されて並んでおり、その傍らに写真が2枚飾られている。
これ僕?チビ?同じ顔でどちらか見分けがつかなかったが、幼い頃に撮ったものらしい。「兄ィとぼくだって。」チビには違いが分かるようだ。写真の日付を確かめると、一枚は5歳の僕の写真、もう一枚は5歳のチビだった。
「さ、座ってください。
ご希望どおり ”タネあかし” のお時間ですわ。」
タネあかし?…ってなんだ?
「別に秘密にしていたわけじゃありませんわよ。あなたたちのステップが進むと同時に、計画されたプログラムの順番で、適正なタイミングでお伝えしているだけ。何度も言ってますけど。」言い訳がましく眉を上げる。「これで全部よ。今からお話しすることは、私たちが分かっているすべての情報になります。ツルタ弁護士の立会いの下、あなたにきちんと説明責任を果たしたとして正式に記録されますので、そのおつもりで。」
事務的な言葉を受けて、後から入ってきたツルタ弁護士。
汗で少ない前髪がへばりついた頭を、どうもと下げた。
■秋、第26話 タネあかし
「”タネあかし”のお時間ですわ。」
犬巻の言葉。どういう意味だろう。
僕が知りたかった秘密。クローンが誕生した本当の理由がわかると言うのか。
チビの生まれた父の研究室。目の前にそびえる巨大なガラスチューブが生々しく饒舌に何かを語りかけてくるようだ。
父が使っていたであろうさほど大きくないテーブルにぐるりと犬巻と猫ちゃん、僕とチビ、ヤギヒゲ教授とツルタ弁護士とが窮屈に座った。
テーブルの上には惑星のオモチャが飾られていた。星を眺めるのが好きな父らしい。この模様は”木星”かな。目のように見える部分は確か大気の渦だと父に教えてもらった記憶がある。確か地球が3個入っちゃうほど巨大なのだそうだ。
見回すと、棚にはブラキオサウルスやロケットのトイたちもたくさん飾られている。父はこういうオモチャが好きな人だった。遊び心にあふれていつまでも子どもみたいな大人だった。彼の意志を感じるものを見て、久しぶりに父の呼吸に触れた気がした。
古い丸イスがやや不安定で、お尻を動かすたびにきゅうきゅう鳴る。父もこんなふうに鳴らしたのだろうか。
「正直ここまで来るとは思っていませんでした。」
ここまで?と、犬巻に尋ねようとしたら、
「ステージ4のことですよ。」
と口を挟んだのはヤギヒゲ教授。まるで授業中、算数の答えが分かって嬉しくて出しゃばるガリ勉小学生のよう。犬巻をうかがうと、彼女は黙ってうなずく。発言権をもらった教授は嬉しそうにホワイトボードにへばり付いて崩れた字で書きなぐった。
「ステージ1というのは行動がシンクロすること。これは早かったですね。会うなりすぐでしたから。」
うんと犬巻がうなずく。
「ステージ2は同じ夢を見る。ステージ3は相手と記憶を交換し始める。サル…サルスケ…。」
「サルノスケですか?」
「そうそう、サルノスケ。おチビちゃんが夢の中であなたの過去の記憶を見て、自分の脳にコピーした。」
「ええまあ。」
「そして今回、ステージ4。それは、”脳の上書き”です。」ペンで大きく”脳の上書き”に丸をした。
「のうのうわがき?」
「そのステージに差し掛かったのです。」
脳の上書きってなんだ?
「ユタカさんとおチビちゃんの脳のコピーが進むと、やがて圧倒的に量の多いユタカさんの記憶がおチビちゃんの脳内を占めていきます。」
そりゃそうか、人生が長い分、記憶の量も圧倒的に僕が多い。
真っ白なノートのようなチビの脳に、僕の20年分が一気に書き込まれるからな。チビも頭が良くなっていいんじゃないの…。
と、よく考えもせず、キャスター付きの丸イスに乗って滑って遊ぶチビを眺めた。あの小さな頭にコピーされるのか。
チビは大人の話なんかには興味も示さず、夢中で”しゅーー、しゅーー”と空気ボンベの音をマネしながら、丸イスにお腹を乗せて研究室の中をうつ伏せのまま宇宙遊泳している。
…いや、ちょっと待って、”脳内を占める”?
「このまま進んだら…?」
よくぞ聞いてくれましたと笑顔で、
「この子の意識は消滅します。」
「その先は?」
「あなたの意識が、とって代わることになります。」
「とって代わるって?」
「この子の脳をあなたの意識が支配するのです」
「え、え、ちょっと待って。意味が分かんない」
「簡単に言うと、体はおチビちゃんでも、頭の中はあなたになるのです。もう一人あなたができるってこと。素晴らしい。本当に起こるなんて。」嬉しそうにヒゲをさする。
この子が僕になる…
呆然とする僕を覚ますように、犬巻ははっきりとした口調で、
「いつかはどちらかを選択しなければなりません。」
「選択?」
思わず猫ちゃんの方をうかがうと、こっそり気づかれないよう長いまつ毛を2回瞬き、瞳で返事した。
あの言葉…
”彼女たちの言葉に流されないでください”
”自分自身の心に従って決めてください"
もう一度そう言われたような気がした。
犬巻が続ける。
「あなたの命はいつ終わるか分からない。脳内のガラスの破片がいつ血管を破ってもおかしくない状態。でも…」
「でも?」
「おチビちゃんの体をもらって、意識はあなたになれば、その先は…」
「その先は、なんですか?」
「もう一度人生をやり直せるのよ、あなたが。このまま、放っておきさえすれば。」
「チビは?チビの意識は?チビという人間は?」
「存在しなくなるわ。」
ガシャン!!
丸イスとチビが転がっていた。
「いてててて」
もしかして聞いていた?
「チビだいじょうぶか?」
「宇宙ステーションにぶつかっちゃった。」その顔は無垢な8歳児のままだった。
良かった…夢中になってたから聞いてなかったかな。小難しい大人の話はよくわからないからいいようなものの、チビが目の前にいるのにこんな酷いことがよく言えるな。
「痛かったね。危ないからこっちで遊びましょ」察した猫ちゃんが手を引いて「ほら、ロボット。かわいいね。ゼンマイで動くみたい」棚に飾ってあるおもちゃたちの元に避難させる。
”ジ―ジー”というゼンマイ音を立てながら、ロボットがゆっくり前に進むと、チビは「うわあ」と喜んで、猫ちゃんの腕にしがみついた。
その様子を横目で確かめながら、心の中で思った。うん、わかったよ猫ちゃん。”自分の心で決める” だよね。
決意をもって、問い正す。
「チビの体を横取りしろっていうんですか」
「横取りだなんて…元はひとつの体なんだから。気にしなくていいわ。」
とても大したことないことのように笑顔を見せた。
「なんてひどいことを」
思わず息を飲んだ。
「あなたが、新しい体を手に入れるの。」
「いやいやいや。そんなことできるわけないでしょ」
「すべきよ。」
「ちょっと待ってください。」
「あなたのためよ」
「おかしいですって。チビの人生を奪い取れるわけないでしょ。」
「そこまで行けば、実験が成立するのよ。」
「はあ?実験が成立?どういうこと?」急に何言ってんの。行く末には何か僕たちの知らないゴールがあるっていうのか。
「ふう。」犬巻は息をついた。立ち上がって、ネイルの塗り具合を爪の先から確かめながら僕の周りを一歩一歩踏みしめる。
「……」
ゆっくりと屈み、僕の鼻を噛みちぎりそうなほど顔を近づける。深く刻み込まれた皺にファンデーションの塊が詰まっているのが分かる。
そして一言。
「あなたに決定権はないわ。」
生ぬるい説得はあきらめたようだ。強い口調で僕に言い放った。
「やっとここまできたのよ。もう止められない。」
「止められないって、何を?」
「もう手遅れよ。」
「何が手遅れなんですか?」
「あなたたち2人が一緒に暮らすだけで、どんどん記憶の上書きは進んでいくわ。もうシンクロが始まった以上、誰も止められない。歯車は回り始めたの。」
もう止まらない?このまま暮らし続けたら、チビが消えるまでまっしぐらってこと?
「なんてことを…。最初から、こうなると?」
「理論上はね。私たちも確信はなかったわ。」
「知ってたなら、どうして…」
「まさか現実にこんなことが起きるなんて。あなたとおチビちゃんが、会うなり見事なシンクロをはじめた時でも、まだ信じられなかった。でも、そこから一緒に暮らすうち、夢を通じて記憶を交換し始めるのを見たとき、驚いたわ。お父様…、汐妻教授の理論は正しかった。」
「父が…?実験のために僕たちを会わせた…?」
「いいえ。お父様はむしろ会わせることに反対したわ。こうなることを一番わかってた人だから。」
「だったらなぜ?」
「汐妻教授が亡くなったから、反対する人がいなくなった。政府では早く実験を再開しろ、2人を会わせろと声が挙がっていたの。勝手に自分の子どもでクローンを作ったなら、実験に提供するべきだって。国の予算よ。機材もすべて国の設備。民間の出資者だって黙っていない。このテクノロジーを手に入れたら、この国は大きく発展する。上が検討した結果、会わせようって。」
「国の発展?僕がチビの体を奪う実験と、どう関係が…」
「ほら、新しい体を手に入れられるでしょ?」
「え?」
そこで、僕は気づいてしまった。
それが本当なら、なんと恐ろしいことだろう。
「もしかして、…永遠の命?」
犬巻は、僕の言葉をはぐらかすように手慰みに木星のオブジェをクルクル回す。
「……」
業を煮やして詰め寄った。
「”永遠の命”なんですか!?クローン研究の本当の目的は。」
犬巻は振り向き、言った。
「そうですとも。人が永遠の命を手に入れることが、本当の目的です。意思をそのままに、新しい肉体に着替えていくの。これが成功すれば、これからどんどんクローンを増やしていくわ。」
「なんてひどいことを」
「少子化対策…そんなのはもっともらしい表向きの理由。人口を増やすのに、誰でもかれでも増やせばいいってもんじゃない。無能な人間を増やしても意味がない。社会には、優秀な人間はせいぜい2%しかいない。その2%だけを増やせばいいんです。それ以外は寿命で死んでいけばいい。」
「そんな不公平な。」
「クローンの研究の最終目標はそこにあります。もしも、アイソシュタイソやホーキンク博士、スティーブジョズブが生き続けたら…」
トップレベルの経営者。ノーベル賞学者。世界で活躍する芸術家。金メダルアスリート。
その天才たちを増やし、長く生かせれば、世界との競争に勝つことができる。この国がもう一度勢いを取り戻せる。
この大義名分のもと、政治家は喜んで政策を後押しした。自分たちもおこぼれで永遠の命にありつくことができるのでは、と期待して。実は優秀な選ばれた者たちだけを延命させる、とんでもなく不平等で差別的な政策なのだ。
「誰か別の人で実験すればいいじゃないですか。そうだ、犬巻さん、あなたたち自身でやればいい。」
「とっくにやりました。」
「へ?」
「その猫塚でね。」
思わず猫ちゃんを見ると、目を背け小さく頷いた。
「とんでもない失敗作でした。お父様、汐妻教授の協力が無いと、どうもね。」
「失敗作?そんな言い方…。で、どうなったんですか?」
「ずっと寝たきり。」
「…寝たきり?」
「遺伝子操作が上手くいかなくてね…」
えっ!?それって?「もしかして…?」
思い出した。さっきの猫ちゃんの言葉。
" 私にも年の離れた妹がいるんです。…体を悪くして寝たきりなんです。意識もなくて… "
「なんてひどいことを…。」思わず猫ちゃんに訴えた。「この人たちに、そんなことさせていいんですか?人権問題ですよ、これ!」
感情的な僕の言葉を、まるで優しくいなすような澄んだ瞳で言った。
「…私は元々養護施設にいたんです。」
「え?」
「ずっと身寄りがなくて、学校の友だちが羨ましかった…。だから、私に家族ができるのならと…。」
「だけど…」
「寝たきりだけど、妹に会えるだけで私は幸せですよ。いつかは元気に目を覚ましてくれると信じています。」
「……」
何も言えなくなった。
猫ちゃんのようにクローンの存在で救われる人がいるのか…。
もしかして、今の僕も?チビによって救われている?
…そうなのかもしれない。
父の死後も、犬巻たちはクローンを作ろうと試みたが、どうしても成功しなかったという。たとえ世の天才たちのクローンを作ったところで、単なる肉体のコピー。それだけでは意味がない。遺伝子は同じでも、育つ環境や人生経験など後天的なもので大きく違う人間になる。双子レベルでは不十分。100%完全に同じ人間でないと、脳のコピーは成功しない。
ところが、シオツマ法で生まれた高いクオリティのクローンならば可能になる。オリジナル人間とクローンが一緒に過ごすだけで脳がコピーでき、同じ意識の人間が2人存在することになる。オリジナルの古い身体は、いつか寿命で姿を消す。すると残った一人が、完全なる「生まれ変わり」となる。つまり「着替え」が終了。しかもクローンは、身体は子ども、知識は大人という、人生をリードした形で再スタートできるのだ。
「あなたたちシオツマ法で生まれた最高傑作は、見事なシンクロを果たしている。他に例のない、世界で唯一無二な存在なのです。
今、世界各国で研究の競争は激化しています。でも、お父様は研究データをあえて残さなかった。だから、あなたたちは研究対象として世界から狙われています。」
「僕たちが…。」
犬巻は片方の眉を上げ、おどけた表情で、
「…ま、もっとも、本来は”天才経営者”とかもう少し優秀な人材で実験したかったのですが…」
ちょいちょい失礼だな。
さらに、ヤギヒゲ教授が意外な言葉で焚きつけ、
僕を惑わせようとする。
「実は、あなたもクローンかもしれないんですよ。ユタカさん。」
「へ?」
「あなたがクローンである可能性があります。」
「可能性って?」
「かなりの可能性です。半々くらいかも。どっちかわからないんです。汐妻教授があまりに極秘に進めていたので。」
「何を言ってるのか、わからないです。」デスクの下に這いつくばってティラノサウルスと片方の運動靴を戦わせているチビを指して、「じゃ、あのチビは?」
「同じく。クローンですよ。」
「いやいやいや、2人ともなわけないっしょ。僕は22年前にちゃんと生まれていますよ。」
「22年前、生まれてすぐの赤ん坊から、お父様がDNAを採取してクローンを作った記録が残されていたんです。」と父の分厚い資料を見せる。
「僕がアタマ悪いのかな。意味が分かんないです。」
「あくまで想像ですがね…」
22年前、母は体が弱く、出産のとき”母子ともに”亡くなってしまった、と仮定する。
「えっ?オリジナルの僕が死んだ?」
「最後まで聞いてください。」
妻と息子まで失った父・汐妻教授は悲しみのあまり、赤ん坊からDNAを採取してクローンを2体作っていた。つまり22年前に、僕もチビも一緒にクローンとして生まれたというのだ。チビの細胞はバックアップとして13年間冷凍保存され、僕が自動車事故に遭った時、父が人工的に誕生させた。
そんな可能性を教授たちは推測している。
ん?ん?
…僕もコピーで、チビもコピー!?
嘘でしょ?嘘だよね?僕もチビとおんなじ?父と母の実の子供じゃなかった?
「どっちかわからないんです。そう、あなたもこの溶液プールから生まれたかも。」
空になったチューブを見つめる。ここに僕も入っていたのか。細かい泡が立ち上る溶液の中で、管につながれた2つの胎児が浮かぶ光景が浮かんだ。
「本当に?」
「とも考えられる、ってだけですけどね。」
「......。」
言葉が出なかった。
「ショックだろうが、気にしてはいけない。そもそもコピーなどと呼べぬほど精度の高いクローン。むしろ2人とも本物と言ってもいいほどですよ。」ヤギヒゲ教授は誉め言葉になっているのかどうかわからない言葉で慰めた。
僕はオリジナルじゃなかった?コピーだった?
自分のアイデンティティが崩れると、途端に不安になった。
僕はもうすぐ死ぬただのクローン?そもそも、いなくなっても最初から数に入っていない存在。なんなの?僕
「さっきの話に戻りましょう」
動揺した僕を見て、ここぞとばかりに犬巻が畳み掛ける。
「おすすめコースは今まで通り。毎日一緒に生活し続けて、おチビちゃんの脳とシンクロしていくだけ。簡単よ。そうすれば、その先には…」
「その先には?」
分かっていても、たまらない気持ちで聞いた。
「その先には、あなたの意識がおチビちゃんの体に住み着いて、新しく若くて健康な体を手に入れることができる。想像してくださいな。今の知識で小学生になったなら、誰よりも優秀で競争力が高い。どんな人生が待っているか…最強よ!これだわ、これ!凡人のあなたでさえ、人生をリードできる。これが優秀な人間だったら…量産すれば日本はすごいことになる!」と興奮している。
でも…でも…
揺らぐ。
確かに心は揺らいだ。だって、僕はもうすぐ死ぬんだもの。
もしかしたら生きていけるかもしれないって聞かされたら…。
「猫ちゃん、どうすれば…?」と助けを求めようとしたが、彼女の目を見て思いとどまった。彼女はここでは本心を言えない。コッソリ忠告してくれたじゃないか。
そうだ、”自分自身の心に従って決める”しかない。
グラグラ揺れる弱い僕の心を見透かして、犬巻が猫なで声になる。
「ね、そもそも2人とも、同じ人間なのよ。元々1人なんです。もとに戻るだけよ。一緒の体になるために生まれたんですから。だから、後ろめたく感じる必要なんてありませんわ。おチビちゃんは”IPS細胞”だと思えばいい。IPS細胞で作った臓器をあなたに移植したと思えばいい。同じようなものよ。ユタカさんが幸せになれば、おチビちゃんも喜んでくれますわよ、きっと。…ね。」けばけばしい付け睫毛をパタパタさせながら、甘い言葉でささやく。
「だけど…だけど…」
精一杯、抵抗を試みようと言葉を探すが、何も出てこない。彼らの言うことは、もしかしたら正しいんじゃないかと思ってしまうくらいに、僕の心は動揺していた。
「じゃあ聞きますけど…。」
ずっと無言だったツルタ弁護士が口を開いた。唐突な方向からだったのでついビクッとしてしまった。思わず「いたの?」
冷静な無表情さで、今までの皆のやりとりを一歩引いてずっと何も言わず眺めていた。すべての情報を一人静かに分析したかのような迫力。脂で額に貼り付いたわずかな髪の毛を前に突き出しながら僕に近づいた。
「え?」
グイッと乗り出し、ランプで照らされた細い目を見せたことのない鋭さで、僕を凝視した。
「じゃあ聞きますけど…」
「え?はい…」
「このまま黙って死にます?」
心が揺れた。
ダメ。
ダメダメダメダメダメ。
そんなこと思っちゃ。
あとで考えよう。うん。今は。
その日は、チビの顔が見られなかった。

■冬、第27話 行方不明
変な感じだ。
心がざわついている。
あれから1ヶ月、ずっとだ。
「チビの体を乗っ取れ」と言われてから…。
このまま死ぬもんだと思い込んでいた。あきらめていた、この命。
正直、ずっと怖かった。
でも、「死ななくていい、生き続けられる…」って言われて、忘れていた欲がくすぐられた。一度は閉じ込めた『生きたい』っていう気持ちを呼び起こされた。
「自分自身の体なんだから。元々ひとつになる予定の体なんだから。元に戻るだけ。気にしなくていい。」そんな逃げ道までもらってしまった。
僕がその気になれば。生きられる。僕として。
でも…
もちろん、そんなことするわけない。そんなことできるわけないよ。もちろん。
大切なチビだぞ。一緒に暮らしてきて味わったはずだ。今まで感じたことのない”家族”っていう気持ちを。死ぬ前に、残された少ない時間に、こんな思いを教えてもらえたこと、心から感謝していた。この子に未来を託す夢は見ても、未来を奪い取ってはいけない。そんなのあたりまえだ。
どうしようもできないまま、いたずらにひと月が経ってしまった。
こうやって日々暮らすうち、僕の意識がどんどんチビの脳を上書きして占領していく。なんとかしなければ。うかうかしてはいられない。
でも、どうすれば…?
でも…でも…でも…
でも、が続く。
家にいても、妙に意識してしまう。
チビは何も知らない。
いつものように絵でも描いているのだろうか、居間のテーブルで熱心に紙に書きなぐっている。赤い服の白いヒゲ。サンタさんだな。
チラチラ見ながらも、動揺をさとられまいか不安で仕方がない。なにせ、意識がシンクロするから。
「ねえ兄ィ、今度バスでおでかけしようよ。」
「ごめん、忙しい」
「どうしたの?」
案の定、チビが僕の顔を覗き込む。
「……」
心を悟られまいとして、ぶっきらぼうにあしらってしまう。
「遊んでないで、さっさと宿題しなよ。」
「うるさいなあ。あとで。」
ぷいと下を向き、赤鉛筆でサンタの服をグリグリこすっている。だんだん言葉が思春期じみてきた。幼い子どもらしさと大人の知識が脳内で共存しづらいらしく、ちょっとイラついている。それが生意気に思えてしまって、僕もイラついた。
僕の気も知らずになんだよ、お前のことで思い悩んでるんだぞ。考えすぎたら頭まで痛くなってきた。
「言うことくらい聞けよ!お前のために言ってんだから。」
「もうー、あとで、って言ってるじゃん!」
チビの肘が色鉛筆の缶ケースをはじいた。
ガシャーンと缶の衝撃音が床に跳ねて、飛び散るたくさんの色鉛筆。まるでチビの反抗心が弾けて飛び散ったようだ。青鉛筆の芯が折れ、台所まで転がっていった。
カッチーンときて、つい言ってしまった。
「自分でできないでしょ!僕はもうすぐ死んじゃうの!チビはそのあと一人で生きていかなくちゃならないの!!」
「え…?」チビの顔色が変わった。「死んじゃう?」
しまった!
「いや、ちがう…」
「死ぬって…?もうすぐなの?」
ああ、言っちゃった…。動揺した僕の表情を読み取ったのか、
「…兄ィいなくなるの?」
悲しげな目で僕を見上げた。
「……」何も言えない。
「ねぇ!どうなの?」
「…い、いや、ずっと一緒にいるよ」
「嘘ついてる。ぼく、わかるもん」
そりゃそうだ。シンクロですべて感じてしまう。同じ人間に嘘はつけない。
「う…う…」
チビの心が大きく乱れ始めるのを、シンクロで感じた。
”ガターン!”
いきなり立ち上がり椅子を倒した。と思ったら、チビは赤鉛筆を投げ出し、玄関を飛び出していった。
暇そうに待機している取材陣や警備の黒服たちをすり抜け、家の前のバス停のベンチを飛び越えて、向かいの家の塀の隙間に飛び込んだ。子猿のようにするすると風景に飲み込まれ、またたく間に姿を消した。
皆、唖然として見送るしかできなかった。
いいんだ。いい。落ち着けば、そのうち帰ってくるさ。
頭をもたげた罪悪感を抑え込むために、そう自分に言い聞かせた。
◆
チビが姿を消して、何時間も経ってしまった。
どこへ行ったかわからない。
小さな足でも行けそうな近所は全部探した。
でも、どこにも見当たらなかった。あたり前のようにいなかった。まるで最初からチビなんて存在しなかったかのように。
冬の日没は早く、すっかり辺りは暗い。近頃めっきり冷え込んで、夜遅くになるとアスファルトの冷気が足から骨の髄に染み込んだ。今、何してるの?こんな厳しい寒さの中、小さなチビはどこで過ごしているんだろう。ずっと一緒だったから、チビがいないことに慣れていなかった。不安で胸が締め付けられた。
ごめんよ。ごめん。あんなこと言わなきゃよかった。後悔の念が僕を責める。
犬巻は、外国の機関に連れ去られる可能性がある、もしくは過激な人権保護団体がむりやり保護してしまうかも。「先に見つけないと取り返しがつかない。」と心配し、極秘に捜索チームまでもが組織された。
おまけに
「あなたも危険です。もう家で待機していてくださいな。」
と足止めを食らった。「猫塚、ちゃんと見張ってて。」と言い残し、屈強な警備の黒服たちを引き連れて表の報道陣を蹴散らしながら出ていった。
残された僕は、床に散らかった色鉛筆を片付けた。一本ずつ探しながら缶ケースに戻し、折れた芯を拾っていると、ふと、あのことが頭をよぎった。
夢の中でよく見る影、『ヒトカゲ』だ。
まさか、さらわれた…?
いやいや、
「夢の中の話。現実世界と関係あるわけない。」
変な考えは、ぷるぷるっと頭を振って打ち消した。
「これ、おチビちゃんの絵ですか。」
猫ちゃんが、テーブルの上の一枚の紙ッペらを眺めていた。
飛び出す前まで、チビが一所懸命書きなぐっていた紙だ。
淋しそうな笑みで「ほら」と渡された紙を手に取ると、汚い字が踊りながら「サンタさんへ」と書き出されていた。
クリスマスプレゼントをお願いする手紙だ。そういうところはまだまだ子どもだな。
サンタと僕とチビだろうか、3人で手をつないだ姿の絵も描かれている。
” サンタさんへ
げんきなからだをください
ぼくはいいから、
にぃにげんきなからだをください
なければ
ぼくのからだをあげます
だいすきなんです
ずっとだいすきなんです
にぃともっといっぱいあそぶんです
ずっとずっといっしょにいるんです
でも
もうひとつもらえるならキックボードほしいです ”
「………」
胸がしめつけられた。
幼いチビにそんなこと言わせて。プレゼント欲しいだろうに。
なのに僕はどうだ。チビの脳を乗っ取って、自分だけのうのうと生き続けようと一瞬でも誘惑にかられた。恥ずかしい。恥ずかしすぎる。僕はなんてひどいヤツだ。
こいつを守らなきゃいけない。そうだよ。僕の命なんかより、若い未来のあるこの子の命を守るべきだ。そうだよ。そう。
描きなぐられた下手クソな絵の、チビと僕のつながれた手を見つめながら決心した。
「僕は一人で死にます。」
「え?」
驚いた様子で猫ちゃんは僕の顔をまじまじと見た。
「猫ちゃん、言ってくれましたよね。自分の心で決めてください、って。」
「ええ、だけど…」
「決めたんです。」
もう迷いはない。僕は彼女の目をまっすぐ見た。「チビとは別れて暮らすことにします。チビの人生はチビのものです。僕が奪ったりしません。もちろん誰にも奪わせません。」
この結論を僕が選ぶことは予想していただろう彼女も、いざとなると戸惑いを隠せない様子だった。
「……そう、そうですよね。でも……」下唇を噛んで「死ぬなんて言葉は使わないで…。」
「僕は充分。幸せでしたよ。猫ちゃん、ありがとう。」
「……」
彼女は顔をそむけた。メガネの奥を僕に見せないようにうつむいたショートヘアを揺らして。
「チビを探しましょう。」家になんていられない。
「それは犬巻に止められ…」
「チビを守りたいんです。チビを探せるのは僕だけです。僕に協力してもらえませんか。」
「………」
やがて何かを断ち切るように、猫ちゃんは「わかりました。」と立ち上がり、「ユタカさんの判断は正しいと思います。」
「ありがとう。」
「どこか心当たりはありませんか?おチビちゃんの考えそうなことは、ユタカさんわかるはずですよね。」
「チビが行きそうなところですよね…。さっきだいたい探してしまって…」
コトリと、湯飲みが置かれた。
「まあまあ、お茶でも飲みなはれ。果報は寝て待てといいまっしゃろ。」
ばあちゃんが言う。
「ばあちゃん、心配じゃないの?もうこんな時間だよ。そんな悠長なこと言ってたら…」
ん、待てよ。
「ばあちゃん、なんて言った?」
「お茶でも飲みなはれ。」
「ううん、そのあと。」
「果報は寝て待て。」
「そうだよ!ばあちゃん!そう!さすがばあちゃん!ありがと!」
僕が勝手に盛り上がるから、猫ちゃんは「えっ?えっ?どうしたんですか?」とキョロキョロ。
「そう、果報は寝て待て。寝ればいいんです。」
「どういう…?」
「僕が寝るんです。そして、夢を見る。今は…夜の10時を回りました。チビはいつもはとっくに寝てる時間。もし今、寝ていたら?もし夢を見ていたら…?」
「…おチビちゃんの夢に入れるかもしれない!」猫ちゃんは嬉しそうに目をまんまるにした。
「そう。どこで寝ているのか、それまでの行動とか、記憶をたどれるかも。」
「なるほど。でも離れていて、シンクロできるんでしょうか?」
「たぶん。一度、チビが友だちの家にお泊りさせてもらった時、家にいる僕と夢がシンクロしたことがあります。ほんのわずかにでしたけど。それくらいの範囲はギリギリいけるかと。」
「だとしたら、できる限り近づかなきゃ。心当たりの場所を周りましょう。」
「どうやって?寝ながら歩くことなんて…」
”カチャリン”
猫ちゃんがニコリとしながら僕の目の前にかわいいネコのキーホルダーをぶら下げた。その先には、車のキー。
「なるほど。」
「あとは、どこを探せば…。」
「いいものがありますよ。」
2階の枕元から持ってきた『夢地図』を広げる。
PCの図形ソフトで製図した地図に、日々鉛筆で汚く描きなぐってくたびれたヨレヨレの紙。毎朝、目覚めたらすぐに枕元の地図を引っ張り出し、寝ぼけ眼で描くのが習慣になっていた。
夢の中で行った場所、話した人、何が起こったか…すべてのディテールを場所ごとに整理して記録していた。その内容は、日々変化しており、昨日まであった場所や物、人が、今日はなくなっていたり現れたりする。まるで生き物のようだ。
「分かりにくくてすみません。現実世界と位置が違うので…。まずはこのあたり、砂遊びした公園やセミ捕り神社から学校を中心に探して、そこから広げていきましょう。」
「ここはなんですか?」
「2人で探検した駅前の再開発エリアです。何度か忍び込みました。そのあたりもお願いします。」
警備のいない裏窓から壁の隙間をぬって、こっそり抜け出した。塀と塀の間をすり抜けながら闇に紛れていくのはお手のものだ。チビとの探検がこんな時に役立つとは。
まずは、猫ちゃんの運転する車の助手席で眠ることに。
シートを倒し、家から持ち出した脳波計測キットを頭に装着された。タブレットを操作しながら、
「おチビちゃんの夢とシンクロが始まったら、大脳皮質が反応するはずです。」
「寝られるかなぁ。」
狙って脳をハッキングすることは初めてだ。焦ると緊張して、なかなか寝付けない。頭まで痛くなってきた。
「どうしました?」
「いえ、だいじょうぶです。どうもね、寝られなくて…」
猫ちゃんが「特別ですよ。」と睡眠薬を2錠渡し「ドーピングですけど。」と笑った。 「気をつけてください。夢の中で、自分が夢を見ていることに気づいてしまったら、目が醒めやすくなりますので。」
頼むチビ、寝ていててくれ。
夢を見ていないと、君の脳内に入れない。
■冬、第28話 夢の中へ
チビはどこへ消えたのだろう。
チビの夢に入ることはできるだろうか?
家を飛び出したチビ。もう夜の10時。眠くなる時間のはず。
どこかで眠ってさえいてくれれば、離れていながらも夢の中に入り、どこにいるか聞き出せるに違いない。
毎晩、クローンのチビとは同じ夢を見ていた。けど、夢をつなげるために眠るというのは初めてだ。少し緊張する。
猫ちゃんの運転する助手席で目を閉じながら、眠りに入るイメージを浮かべてみる。真っ暗な夜に深く深く潜っていくイメージ。
平泳ぎで夜の闇を掻きながら、深く…深く…。
学校の近くを走っているあたりから、車の揺れが心地良くなってきた。
猫ちゃんのセンスのいいほのかな香りが心を凪のように落ち着かせ、ウインカーのカッチカッチという音が優しく響いている。
ああ、薬が効いてきたかも。
闇を掻きつづける…
深く。。。深く。。。
深く。。。。。。。
深
く
。
。
。
。
。
◆
。。。。。。ふう。
頭がほんやりするなぁ。
居間で、ばあちゃんがテレビを観ている。小さな背中。
ガヤガヤ、テレビのノイズだけがかすかに騒いでいる。
「ばあちゃん。」
返事がない。
「ばあちゃん。ねえ、ばあちゃん…?」
返事がない。
なんとなく「行ってきます。」
ぼおっとしながら、玄関の引き戸をガラガラ開ける。
…と、そこは面接会場。
そうか、今から入社試験受けるんだっけ。
しまった。なんにも用意してない。手ぶらだし、おまけに部屋着。
「タイムマシンで過去の自分に何を伝えますか?」お堅い面接官の質問が飛んでくる。
すみません。ちょっとお待ち下さい。出直します。ごめんなさい。ごめんなさい。
逃げるように面接室を出る。
…と、ドアの外は、木々が立ち並ぶ神社の境内。
セミの鳴き声が響く。虫取り網を引きずりながら、空を見上げて何かを探すように、とぼとぼ歩く。
何か探してるんだよなあ。セミだっけ?なんだったっけ?
気が付くと、左手に何かを持っている。折りたたまれた紙だ。
広げてみると、地図。
なんで持ってるんだっけ、これ。
あれ…誰か見てる?
視線を感じて、反射的に振り向く。
見回せど、誰もいない。間違いなく人の気配を感じたような気がした。
わかんないけど、なぜかざわざわ、気だけが焦る。
とにかく急がなきゃいけない気がして、何百本もの木々の中を走り抜ける。
…と、いつの間にか、まぶしい光の中を歩いている。
コンクリートの床。廊下だ。並ぶ窓から差す光のシャワー。
子どもたちがたくさん歩いている。長く伸びた廊下に並ぶ2-3、2-4、2-5と書かれた札。ドアの窓からのぞくと黒板とたくさんの机。
ああ、学校か。
誰かを探してたような気がする。
すれ違う子どもたちの顔を覗くが、どの子も違うようだ。誰を探していたのか、思い出せない。
やがてどんどん子どもたちが増えて、人の波に僕は押し流されそうになる。
いきなり前に立ちはだかる人。
いじめっ子のサルノスケだ。ちょっと小太りの大きな体で無言で通せんぼをしていた。
襟首つかむなよ。なあ行かせてくれよ。急いでるんだよ。
声を出そうとしてもまるで喉の奥に何か詰まっているかのように、出ない。押しのけようとしても腕に力が入らない。
そうだ、地図を持ってた。
もみくちゃに流されながらポケットから引っ張り出し、両手を掲げ天井にかざすように広げる。
ここが学校で…廊下ががここ…。あれ、廊下のロッカーに矢印が書かれているぞ。
どこだ?ロッカー、ロッカー…。あった!
廊下の隅っこに古ぼけたロッカーが申し訳なさそうに佇んでいる。
サルノスケの腕をすり抜け、子どもたちの波をクロールでかき分け、ロッカーの岸にたどり着く。手をかけるとひやりと冷たい取っ手。思いっきり引っ張るとロッカーが開いた。中へ飛び込んで見たものは…
…そこは、”路地裏”。
薄暗く狭い湿った路地裏に足を踏み入れる。
地図を頼りに入り組んだ路地の隙間を抜け、家の塀を渡り歩いた。バランスをとりながら塀の上を歩くが、足元のコンクリートがフニャフニャ柔らかく、どうもフラフラする。
”キキッ!”
突然、雨どいから飛び出した黒ネズミに肝を冷やして、あっと、足を滑らせ、身体が宙を舞った…
そのままの勢いで、真っ逆さまに落ちるかと思ったその瞬間、救われるように背中をキャッチしたのは、
”滑り台”。
長い長い滑り台に身体をもっていかれ、ものすごいスピードで体が流されていく。ジェットコースターのように右へ左へ勢いよく滑って地面に放り出された。
” どしん 。どしん。どしん。” 3回跳ねて着地。
「いてててて。」
反射的に口にしてお尻を抑えたけど、なぜだか痛くない。
周りを見渡すと、たくさん遊具が並んでいる。公園だ。
ふと、また誰かに見られているような視線を感じた。
急いで振り向くが、
…しかし、誰もいない。間違いなく誰かが僕を見ていた気配を感じたのに。
そうか、あいつに違いない。夢でよく見たあの ”ヒトカゲ”。
毎晩ずっと、夢の端っこで僕とチビの様子をうかがっていた謎の影、"ヒトカゲ"だ。また出てきやがったな。しつこいな。
「わかってるんだぞ。そこにいるんだろ。」
怖い時に虚勢を張ってよく言うやつだ。ちょっとビビっている証拠。
邪魔しないでくれ、今、相手にしてる暇はない。
地図によると、公園の真ん中に印がついている。
ああ、この砂場のことだな。近づいて中を覗き込むと、大きな砂山があった。
両側にトンネルの入口が掘られている。これ、僕たちが作った砂山だよな。「僕たち」って?あれ、誰と作ったんだっけ?
……まあいいや。
砂山の薄暗いトンネルの入口に、手を少し入れてみた。ひんやりとざらざらしめった土の感覚。
何もない。
もっと奥、もっと奥へと手を入れる。爪の間に砂の粒が挟まりながら、肘まで突っ込んだその時、指先がフニャッとしたモノに触れた。
「わっ」
一瞬気持ち悪かったが、よくよく握ってみると…、温かくて…柔らかい。
小さな手だ。
子どもの手。確かに柔らかな子どもの手。クネクネ動いてこちらを探るように握り返してくる。懐かしいような安らぐ感覚。
ん?…確かよく知ってるような…誰か…誰か…、そう!
「チビだ!」
そう叫んだ瞬間、手をつかまれ、すごい力で土の山の中へ吸い込まれた。
闇へ吸い込まれながら、視線を感じ背後を振り返る。と、残された公園にぽつんと立つ、あの”ヒトカゲ”。奴が僕を見送っているのがチラリと見えた。
「やっぱりお前だな。」
文句のひとつでも言ってやろうと思ったが、その間もなく、やがて遠くへ小さく見えなくなってしまった。
気がつくと、そこは…家。
夕焼けに色づいた、見慣れた僕たちのおんぼろ家の玄関の前だ。
「戻ってきちゃったな。」
しくしく誰かが泣く声がする。バス停のベンチ。
誰かが座ってる。よく見ると……
チビ。
一人、背中を震わせ一人で泣いている。
おお、チビ…チビかぁ…どうした、なんで泣いてんだ。
ん?…チビ…?
「そうだよ!」
思わず叫んだ。
「チビ!探してたんだよ!心配してたんだよ。家を飛び出したんだよな…。」
やがてフォーカスが合うように、記憶がよみがえった。
もしかして…、もしかして…、
「これ…、夢?」
そうか、思い出した!チビの夢とつながったんだ!
ついにつながった!
よし、よーし、よし。こいつの夢の中にコネクトしたぞ。
チビ、どこかで眠ってるってことだな。僕も目が覚めないようにしなきゃ。
しかし夢ってのはよーくできてんな。リアルすぎて全然気づかなかったよ。
注意しながら、後ろからそっとチビの肩に手を回してみたら、気がついて振り向き僕の顔を見た。
「…………。」
目を丸くしてまじまじと見つめ、
「兄ィ!!」
今度は思いっきり僕に抱きついた。喉の振動が胸に響くほど、激しく号泣した。
「兄ィ!兄ィ!もう大丈夫なの?!体、大丈夫なの?!」
「ごめんな。ごめんな。大丈夫だよ!大丈夫だ…」
胸が詰まった。
そう、これは夢。
チビが今、現実の世界のどこで寝ているのか?確かめなきゃ。
「チビ、今どこにいるの?」
「今?ここにいるよ」
「そうじゃなくて、これはチビの夢の中だよ。僕が入ってきたんだ。本当のチビはどこかで寝てるはずなんだ。今、どこで寝てるの?わかるかい?」
「うーん、起きて見てみるね。」
と目をこすり始めたから、
「ダメ、ダメ、起きちゃダメ。」慌てて止めた。
チビの夢が覚めたら、僕がチビの世界から追い出されてしまう。寝ている間だけなんだ、チビの頭と通じているのは。そう、一縷の望み。だから…、
「どこにいるのか、最後に見た景色を思い出してみて。」
「なんだっけなあ…」
「うん…思い出しそう?」
「んー……」
「ふんふん。」
「んー、わかんない。」
なんだよ。
「わかんないけど…」チビは立ち上がって「行かなきゃ」とつぶやいた。
「なに?どこへ?」
クラクションの音が響いた。
遠くから低いエンジン音が近づいてくる。バスだ。
やがてバス停の前で止まると、ぱっくり自動ドアが開いた。
顔の無い運転手と目が合う。乗るの?どうするの?という牽制の空気。
「ん?なになに?」
僕の手を放し、チビが嬉しそうに乗り込んだ。
「ちょ、ちょ。」
慌てて僕も後を追うように乗り込む。
一番後ろのシートに身を沈めたら、ゆっくりとバスが動き出した。
窓を覗くチビに、
「ねえ、どこに行くの?」
と聞いても、笑って答えない。
輝く夕陽であふれる街。琥珀色の光の中を泳ぐように走るバス。
クリスマスソングが流れる。浮かれた家族連れや子供たちがたくさん乗っている。幸せを絵にかいたような風景。
チビの記憶か?願望か?
幻想的な絵画のような、それでいてリアルなような不思議な空間だった。
遊園地前の停留所に止まった。
「ここ?」
と聞いたが、チビは降りようとしない。
「もっといいところ。」
と笑顔で答える。
ああ、このシチュエーション。まるでデジャヴュのようだ。どこかであったような…。
そうだ。絵本だ。
僕とチビのお気に入りの絵本。
寝る前に枕元で父に読んでもらっていた「バスでお出かけするお話」だ。
チビの願望が夢になっているのだろうか。夢が絵本の中に入ってしまった。
動物園、ショッピングモール、スケート場…、次々とバス停に停まっていく。だけど、
「ここ?」
と聞いても、チビは頬を夕陽に染めながらまぶしそうに笑って、
「もっといいところ。」
とこたえるだけ。絵本のストーリーのとおりだ。
やがて日がどっぷりと沈み、暗い山道を進む。
カーブを曲がったその向こう、遠くの木々のシルエットごしに、たくさんの細かい光の粒が蛍の大群のように現れた。
やがて近づくにつれ、それが大きなモミの木の美しいクリスマスツリーだと分かる頃には、見上げるほどそびえ、その雄姿で僕らを圧倒した。
キキキと止まると、静かになった車内で「終点です」マイクの声がつぶやくように言った。
バスを降りると、空気は凍てつくように寒い。白い息が吐き出されるのが楽しくて、チビがハアーとタバコを吸うマネをしてはしゃいでいる。僕まで寒くなるなんて、チビの夢はリアルだな。
きらめくイルミネーションの一粒一粒が、寒く澄んだ空気で光を放っていた。言葉にできないほど果てしなく美しかった。
目を移すと、そう、レストラン。温かな光がぼんやり見えている。
そうだよ、絵本の筋書き通りだ。
ウッド調の建物の、大きな分厚い木のドアを開いてみると、部屋の温かさがあふれて足元に流れてきた。奥に目をやるとツリーの見える窓際に、人影が2つ揺れていた。それを見て、僕の胸が”ドキリ”と波打った。
”ヒトカゲ” だ!
こんなところに?
その”ヒトカゲ”は男女のシルエットを形どって座っていた。
一体、何者なんだ?煌めくイルミネーションの光で、よく顔が見えない。
「わぁっ!」
いきなり走り出すチビ。
「ダメ!そっちは!」
飛びついた男性のヒトカゲは、笑ってこちらを振り向いて見た。まぶしい光にぼんやり溶けていた輪郭が少しづつ鮮明に、やがてハッキリと姿を現わした。
その顔を見た途端、僕は思わず息が止まりそうになった。
「まさか、そんなはず…」
チビがその腕にぶら下がりながら、歓喜の声で叫んだ。
「父ちゃん!」
そこにいたのは…父。
まぎれもなく、亡くなった僕たちの父ちゃん、汐妻教授だった。
■冬、第29話 父の答え
チビがヒトカゲに飛びついて、叫んだ。
「父ちゃん!」
そこにいたのは…父だった。
「まさかそんなはず…」
甘えるチビを抱きしめながら、父が僕に微笑みかけた。
「やあ、よくここまで来たね。」
「何?これ、どういうこと?父ちゃんは死んだんじゃ…」
久しぶりに父ちゃんに会って、張り詰めた緊張が切れたように膝をついた。
なんでいなくなったの?
どうして何も僕に教えてくれなかったの?
僕ね…、僕ね…、
淋しかったけど頑張ったよ。
あふれる感情が押し寄せ、子どものように声を上げて泣いた。
でも…。
「ちょっと待って…」
ふと、我に返った。
僕は今、チビの夢の中にいる。
だからこの父は、正確には "チビの記憶に残っている父の姿" ということか。僕の知っている父ちゃんより少しだけ歳をとっている。
肌までリアルだ。よく覚えているな、チビ。
隣の女性は母だ。
僕もチビも写真でしか見たことないので、動くことはないが写真のとおりの笑顔で優しく微笑んでいる。こう見ると綺麗だったんだな。
目の前の父は言う。
「今、ユタカがここにいるということは、2人が出会ったということだね。今の私は、チビの記憶に刷り込んだ私の残像だよ。」
「残像?」
「毎晩、絵本の読み聞かせをする時に、この子の記憶に刷り込んだんだ。録画された映像みたいなものだよ。」
空間に、その様子が浮かび上がった。まるでホログラムのように。
秘密基地の中、毛布にくるまったチビに父が絵本を読み聞かせる姿。
「絵本を読んであげたあと、チビに、ある秘密のお話をたくさんした。」
「秘密のお話って?」
「どうしてクローンを作ったか。」
「え?チビ、なんで言わなかったの?」
チビに問うと、
「ん?なんのこと?よく覚えてない」と秘密基地の毛布から顔を出した。
「なにせ幼い子どもだからね。理解はもちろんしていない。眠りにつきそうなまどろみのとき、私はチビに耳元でささやき続けた。おとぎ話を読むように、何度も何度も。」
寝そうになるチビのそばで、ささやく父の姿が見えた。
「そんなの覚えているわけ…」
「覚えているんだ。人間の脳はすごい可能性を秘めている。チビには意味が理解できなくても、脳細胞にきちんと刻み込まれている。自転車の乗り方や箸の持ち方は一生忘れないだろう?」
「うん…」
「問題はその記憶を取り出せるかどうかだ。」
目の前に大きな図書館の無数の本棚が広がった。
僕とチビの姿も浮かび上がった。
「うわぁ、すごい。ご本がいっぱいある~」
ふわふわとチビは逆さになりそうになりながら喜んでいる。
「巨大な記憶の棚に人生すべての経験が記録されている。そう、君ならチビの記憶に入り込んで捜索ができる。」
「猫ちゃんたちは正しかったんだな。」
「だから思ったんだよ。もしもいつか君たちが出会うことがあったら、こうやってチビの記憶の奥に刻み込んだ私の話を見つけてくれるに違いないと。その時の君なら、父ちゃんの話が理解できると思う。私の命が尽きる前に真実を残しておきたかった。」
見つけたよ。見つけた。
この記憶の残像は、父ちゃんの残した手紙なんだね。
夢の中の”ヒトカゲ” は、僕がチビの脳を占領してしまう前に、父ちゃんがこのことを知らせるため、ずっと様子を窺っていてくれたんだね。
「一緒にいられなくてすまない。見たかったなあ。お前の成長する姿を。
どうだい?大人になるまで、いろんな事があったかい?いろんな事を学んだかい?一生を捧げるやりたい事は見つかったかい?好きな人はできたかい?」
うん、少しだけど大人になったよ。僕一人じゃダメダメな人生だったけど。でも、父ちゃんがチビを残してくれたおかげでね。ほんの少しだけど、父ちゃんの子を想う気持ちがわかった気がするよ。ほんの少しだけどね。
父は静かに微笑んで、
「君の知りたかっただろう秘密。どうしてクローンを誕生させたのか、本当の理由を話すよ。」
確かにずっと聞きたかった。
けど、今となっては、なんか聞くのが怖いような気もしていた。クローン誕生の理由。
父は僕の目を見つめて言った。
「実は…、君たちのお母さんの望みだったんだ。」
「母ちゃんが?クローンを作ることを望んだの!?」
「正しくは、望んだのは”兄弟”。『私たちの子どもには兄弟が欲しいね』彼女はずっと言っていたんだ。2人や3人の子どもたちと一緒に食事ができる温かい家族。それがかけがえのない夢だった。でも…」父は目を伏せ、「お母さんは、自分の病気を知っていた。死期を察していたんだ。叶うことのない夢と分かっていた。」
「それで…」
「そう、子どもには兄弟がほしい。お母さんのせめてもの願いだった。自らの命を犠牲にして赤ん坊の命を残した彼女の願いだ。どうにか叶えてあげたかった。だから、クローンの弟を生み出すことにした。」
そうだったのか…。
「じゃあ、最初生まれた赤ん坊は僕?死んだんじゃなかったの?」
「赤ん坊は…君だよ。元気な赤ちゃんだった。お母さんが命を懸けて元気に生んでくれた。チビは、君が13歳の時に誕生させた。」
「おかしいな。クローンが作られた時期は、僕が生まれた時と同時かも、ってヤギ教授から聞いたけど。」
「いいや。その時は、赤ん坊だった君の細胞をほんの少し採取しただけだよ。」と笑った。
「どういうこと?」
「赤ん坊の細胞が必要だったんだ。いいかい、たったひとつの細胞にもDNAがある。見てごらん。これが君のDNA情報…つまり”設計図”のようなものだ。」
僕の目の前に映像が浮かび上がった。
僕の体のCGのようなものと、それを取り巻くように大量のアルファベットが螺旋状の波のように押し寄せてきた。
「なんだかたくさん出てきたよ」
「ヒトの設計図の情報は32億ほどある。」
「げ、そんなに?気が遠くなる」
「この設計図で、人の体がどんな姿や形になるのかが決まってくる。だけどクローンをつくるには、ただ1つの設計図があればいいってわけじゃない。過去にさかのぼって、生まれたばかりの赤ちゃんの設計図も必要なんだ。」
「そんなに必要なの?」
「実は、人の遺伝情報は変わっちゃうんだ。」
「DNAって、一生変わらないものなんじゃないの?」
「DNA…つまり設計図は変わらなくとも、完成形は変化するよ。ほんのわずかだけどね。成長するなかで、環境や生活習慣の影響を受けて、結果は変わっていくものなんだ。」
「どういうこと?もっと理系を勉強しときゃ良かった。」
「見てごらん。」
今度は、目の前に野球のグラウンドが浮かび上がった。青々とした芝生に選手たちが散らばっている。
振りかぶったピッチャーが投げたボールをバッターが打った…、
そこでストップ。
「ちょっと待って、これと何の関係が?」
「君は外野だとする。で、バッターの打ったボールを捕ろうとする。フライが飛んで来たら、ボールの角度やスピードでキャッチする着地点を予測するだろう?」
ボールの軌道を点線が描いて、落下地点を示される。
「うん…まあ…。」
「でも、時には横風が吹いて球がずれるかもしれない。その横風の情報も必要だよね。」
軌道がずれてボールの落下地点も横に移動する。
「それとおんなじ。赤ちゃんから13歳…毎年いくつものDNA情報から計算して、成長して大人になった時の姿かたちを予測する。その情報を、クローンを培養する時に編集して書き足しておくんだ。オリジナルと全く同じ成長を遂げられるように。」
「はあ…、わかったようなわかんないような…。」
「それが、私の開発したシオツマ法の秘密だよ。他の誰も知らない。」
ここまで聞いたら、もっと知りたくなった。
「じゃあ、じゃあ…、」
聞きづらいけど、ええい、この際いいや。「やっぱりきっかけは交通事故?僕が死んだときのための身代わりでチビを誕生させた?」
「いいや、君の代わりが欲しかったわけじゃない。事故はただのきっかけに過ぎない」
「だとしたらなぜ?」
「チビへの愛情だよ。」
とつぜんチビが小さく小さく縮みはじめた。どんどん、どんどん小さくなる。手のひらに乗りそうになってもまだ縮んでいく…。
ついには、ちっぽけな細胞のカケラになった。
溶液チューブの水槽が現われ、カケラはその液にポチャンと入ってふわふわ浮き始める。
やがて風景は研究室に変わった。テーブルには、あの”木星”のオモチャ。
あの頃の若い父がいる。何をしているんだろう。
チューブに浮く細胞のカケラを、父が眺めている。
出勤した時も、仕事の合間にも、お弁当を食べている時も、毎日毎日…。
楽しそうに笑って何かを話しかけている。その目は、とても愛情にあふれた父親のまなざしだった。
「その時はまだ小さな細胞。君の弟として13年間保存された赤ちゃんの細胞だけど。私は、13年間毎日細胞を見るたび愛しくなった。愛情が芽生えたんだよ。どうしても廃棄できなかった。だって、君と同じく僕の愛する息子、ユタカだからね。クローンだって生まれる権利がある。」
「そうだったんだ…」
「しかし、研究を進めるうち、2人を会わせてはいけないことが分かった。シンクロが進むと、どちらかの意識が相手の脳を占領してしまう副反応の危険性を発見してしまった。」
父が思い悩む姿。
「そんな時だ、交通事故があったのは。君を事故に巻き込んでしまったことを死ぬほど悔やんだ。自分を責めた。
しかし事故は、私が死んだことにして身を隠すには二度と訪れないチャンスだった。チビを育てるために。このクローン技術は間違った使われ方をしてはいけない。すべてを秘密にするべきだと決めた。」
その後、父は身を隠し、かつて僕と父が暮らしたようにチビを育てたそうだ。赤ん坊から小学生という同じ時間を僕と過ごしたように、もう一度過ごすことは至極のひと時だったそうだ。
「なにかと扱いの難しいティーンネイジャーの君も見てみたかったけどね。」
くしゃっと目を細め、父は笑った。
僕の着ていた服や、おもちゃなど日用品はすべて僕の物を持って行って使ったという。
全く違う子供として育てることも考えたが、一生会う事のできない僕との生活を憧憬するがあまり、捨てきれなかったそうだ。
「もうしわけない。私も息子を失いたくなかった。君と別れるときは胸が張り裂ける思いだった。二人の息子を同時に愛することができない宿命への苦悩が、そうさせてしまった。」
結局、僕はオリジナルだった。
でも、もうそんなことはどうでもよくなった。僕は僕、チビもチビ、2人とも本物だから。この世に生を受けたなら、本物なんだ。
僕は思った。
「だったら…、だったら母さんのクローンを作れば良かったのに…」
「考えたさ。でもね、いずれ同じ病気で亡くなる悲しい運命を繰り返させたくなかった。」
「…そうか、そうだよね。」
「それに、赤ちゃんとして生まれ変わった彼女が、私との数十年の歳の差を埋めることはできないからね。」
と寂しく笑った。
◆
それから…
僕たちはレストランで家族4人揃って食事をした。
見たことのない色鮮やかなオードブル、キツネ色に光り輝くホッカホカの七面鳥…。ほっぺが落ちるほど美味しく、なんとも美しいクリスマスディナーだった。
何を話したか覚えていないが、たわいもない話だ。
チビは初めて会う母ちゃんにも抱きついて甘えた。
暖かくて優しくて、とても幸せな時間だった。
チビと僕の長い間の夢が叶った気がした。
この時間を過ごしたくて、チビはここまでやってきたのだ。
やがてテーブルのキャンドルの炎が揺れ始めた。
それを横目で見た父は、食後のコーヒーを飲み干しカップをカチャリと置いた。
「そろそろだな…」
行ってしまうの?
「君たち2人が出会ったのは、本人同士引き寄せ合ったのだろう。
でも、一緒にいては駄目だ。離れて暮らしなさい。チビの頭の中の記憶は、君の記憶の量に押されて、いずれ消えてしまうだろう。とにかくその前に…。」
「分かったよ、父ちゃん。チビのために離れて暮らす。約束するよ。」
「君はチビと会って、かけがえのない経験をしたはずだ。自分が何者か?人生って何か?命とは何か?いろいろ考えられたと思う。」
「イヤというほど考えさせられてるよ。毎日ね。」おどけてみる。
「人生にとって大切なものは、自分が心から安らげることのできる人を見つけることだ。家族でも友だちでもいい、自分のことを犠牲にしても守りたい人。それが一番の幸せだと思う。だから父ちゃんは幸せだったぞ。お母さんがいたし、お母さんがいなくなったあとでも、ユタカと、チビのユタカという2人がいてくれたからな。本当にありがとう。」
僕の方こそ、ありがとう。
チビと一緒に暮らしたことは間違いかもしれないけど、幸せだったよ。
「ユタカ。会えてうれしかったよ。もう1人のユタカを頼んだぞ。」
父は僕とチビの肩をつかんで抱きしめた。
そのぬくもりや感触ははっきり感じられた。チビの脳に鮮明に残されているのだろう。懐かしかった。
「話せてよかった。それじゃ。」
「もう会えないの?」
「そろそろ残像もここまでだよ。」
少しずつ影が薄くなってきた父。
そうだ、聞きたかったことを思い出した。
「最後にひとつ。曲…あの曲、なんていうの?」
「ああ、これだね。」
口笛を吹いてくれた。姿が透けてきた父の奥に、消えそうなキャンドルが揺れている。
クセのある口笛。甘美な調べに涙が出た。
「ホルストの”木星”。クラシックの名曲だよ。」
父の言葉に吹き揺らされるように、キャンドルの炎が消えていく。
立ち上る煙に吸い込まれるように、すうっと父の姿も消えた。
レストランのテーブルにぽつんと残されたチビと僕。
美味しかったごちそうもだんだん薄く消えていく。
「消えちゃったね。」
「消えちゃったね。」
同時につぶやいた。
「父ちゃんは消えたけど、僕はちゃんといるからな。一緒だからな。」
「うん。」
やがて寒さが僕たちの背筋を襲った。なんだろう。体がぞくぞくする。
それにしてもバスに乗っていたときの街の様子がリアルだったな。クリスマスソングも、乾いた街の匂いも、この寒さも…。
「まてよ…寒い感覚だけ妙にリアル…。そうか、今、チビは寒いところにいるんだ。どこだ?どこだ?寒いところ…。」
その時突然、
今日の家でのチビとのやりとりが頭にフラッシュバックした。
”ねえ兄ィ、今度バスでおでかけしようよ。”
”ごめん、忙しい。”
そこで僕は気づいた。やっと気づいたんだ。
「バスだ!」
「ん?」
「もしかして、バスに乗った?」
「うん?一緒に乗ったよ」
「そうじゃなくて、チビが寝る前。現実の世界で。」
「ん?あ…ああ、乗ってたかも。」
「バス?なんでバスなんかに!?乗ってどうしたの?」
「レストランに行けると思って。そしたら父ちゃんや母ちゃんに会えるかもって。」
「どこまで覚えてる?」
「うーん、覚えてない。」
「覚えてない、か…。」
だとしたら、バスに乗りながら途中で眠ってしまったんじゃないのか!?
そうだ!その通りだ!
ということは、今、バスの行き先にいるはず!どこだ?
とにかく、実世界に戻って探そう。
「チビ」
「ん?」
「兄ィは先に起きるね。」
「どこ行くの?」
「チビのいる所。探しに行くよ。」
「うん、見つけてね。」
「わかった!かならず探し出すからな。待ってろよ!」
僕は、夜の闇をゆっくりと見上げる。
よし、鼻の孔から大きく息を吸って…
起きよう。
起きよう。
起きよう。
深い夢の底から、夜の闇を平泳ぎで掻いて、上へ上へ。。。。。
。
。
。
上
へ
。
。
。
。
◆
。。。。。。ふう。
眠い。
なんだかとても疲れたな。
まどろみながら、意識と記憶が混乱している。あれ、何してたっけ。
ここは? 暗い…。車…の中かな。
「目、覚めました?」
猫ちゃんの顔…。
「大丈夫ですか?泣いてましたけど。」
頬が濡れている。
「あ…はい。」袖で拭いた。
「このあたりで脳波計が反応したので、車を止めてみたんですが…。」
「脳波計……?」
あれ、なんだっけ……記憶が混乱してる……
このあたり……チビと会って……バス……
「バスだ!」
ガバッと飛び起き、驚く猫ちゃんに、
「バスの行き先です!家の周辺を走っているバス。それも…そんなに遠くないはず…」
急いでバス会社に問い合わせた。町を走るバスはどこに行きつくのか。
「はぁ…最終の運行は終わってますね。運転手もほとんど帰ってしまって…調べようがぁ…」
電話の声は、なんともやる気のないバス会社の警備担当。業を煮やしていると、猫ちゃんがスマホのMAPを僕に向けた。
「ユタカさん、この近くです!」とスマホを後部座席に放り、素早くギアを入れて、アクセルを踏んだ。
◆
やってきたのは、バスの終点。
急ブレーキで車を横づけにして飛び降りる猫ちゃん。
「ほら、車庫があります!」
走る背中を見ながら、ちょっと頼もしいなんて思ったりする。
同じバスがずらりと並ぶバス駐車場。まるでクローンの大量生産だ。
一つ一つドアを開けてもらって中を確かめた。
乗車口を駆け上がり、座席を全部調べる…。いない。
乗車口を駆け上がり、座席を全部調べる…。いない。
同じことの繰り返しにくたびれてきた17台目。
一番奥の席を覗いたとき、
座席の下の隙間から、縮こまって横たわる見慣れたパーカーを発見した。
逸る気持ちもそのままに、駆け寄ると…、
チビだ!
「チビ!チビがいました!」
動かない。
「おいっ、チビ!大丈夫か?」
体が冷え切っている。
猫ちゃんが手際よく首に指を当て、チビの口元に耳を近づけると……
ニッコリうなずいた。
「良かった…」
優しく揺り起こすと、
やがてチビは「うーん」とうなって目を開き、しばらくキョロキョロ見回してから、僕を見た。
「兄ィ…?」
「バカ、心配かけんなよ。」
「だって…」
「悪い子にはサンタさん来ないぞ。」
「ごめん。」
「寒くないか?」
「寒い。でも…」
「でも?」
「ごちそうおいしかったね。」
「だな。」
僕の上着をかけるフリをして抱きしめた。
◆
「なんでバスなんかに?」
帰りの車に揺られながら、毛布にくるまれたチビに尋ねた。
聞けば、チビは家を飛び出したあと、バスを見かけて思わず心が引き寄せられたらしい。バス停でたくさんの家族連れや子どもたちに紛れて乗り込んだという。
「父ちゃんに会えるかと思って。」
以前、バスの絵本を読み聞かせた夜。夢を見たそうだ。
バスに乗って森のレストランで父と食事をする夢。
バスに乗ったら、その先でもしかしたら父に会えるんじゃないか。
父なら、兄ィの体をなんとかしてくれるのではないかと思ったそうだ。
「お腹すいたね。」
チビが後部座席から身を乗り出して僕と猫ちゃんに言った。
「そうだな、夢であんなにごちそう食べたのに。」
「どんな夢だったんですか?」
ハンドルを握りながら猫ちゃんが聞いた。
僕とチビは目を合わせて、
ひ・み・つ!
ひ・み・つ!
とシンクロで笑った。
「帰ってばあちゃんのご飯食べような。」
「猫ちゃんも一緒に食べるよね。」
バックミラー越しに猫ちゃんはニッコリ笑って、「一緒に食べようね。」
「ウホウホ、みんなでゴハンだ。」
妙な喜び方でおどけてはしゃぐチビ。
「今日は早く寝ないとサンタさん来てくれないぞ。」
「もう眠くないよ。」
「バスで寝すぎちゃったからな。」
「寝られるように、あの口笛、聴かせてね。」
「ああ。」
流れる街の光。
クリスマスイルミネーションが冷たい冬の風に乗って雪のようにキラキラ舞っているようだ。
チビが家を飛び出し、無事見つかった。
けど、僕の命のことは何も解決していない。またゆっくり話してやろう。
チビと暮らす毎日は楽しかった。できることならずっと一緒にいたい。
でも、チビとはもう一緒にはいられない。
” 離れて暮らしなさい "
そう父は言っていた。そばにいたら僕の記憶がチビの脳内を上書きしてしまう。チビの体を乗っ取らないためにも、一緒に暮らすことはもうできない。
年が明けたら、お正月のお節料理やおもちとか家族らしい体験だけさせてやろう。
思い出をつくって、さよならしなければ。
「兄ィ。」
チビが後ろから呼ぶ。
「うん?」
毛布に顔を半分埋めながら、
「メリークリスマスだね。」
「おう、メリークリスマス。」
「兄ィ…、猫ちゃん…、だいすきだよ。」
「お、おう。」
そんなこと言うなよ。
街の灯りがにじんで見えなくなってきた。
僕は窓を眺め続けた。
涙を誰にも気づかれないように。
■冬、第30話 別れます
「何?悪い話かしら」
犬巻は、僕ん家の玄関戸を後手で閉じながら、いぶかしげに言った。
「まだ記者がうろちょろしてるのね。しつこい。」
確かに今日はいつもよりまして表の人が多い。ご丁寧に市民ボランティアまでもが、可哀そうなチビと僕を人権擁護するためチラシを配っている。
「チビと別れて暮らします。」
朝、そのことを犬巻に告げるために電話したら、一言も聞かず、
「なら私がうかがいます。私一人で。猫塚はダメ。どうも最近あなたたちの味方ばかりするの。」
と愚痴をこぼしながら、古くて汚れた僕たちの家へやってきたのだ。
◆
僕の話を聞いて、犬巻はテーブルに置かれたばあちゃんのお茶も飲まずに激怒した。
「今さらです!」
「すみません…。」
頭を下げるしかできなかった。
「こんなに素晴らしい成果を上げてるのにどうして。」
「成果って、チビの人生を奪うことですよね。父も反対しています。」
「父?反対?なんのこと?」
父との夢の話については教えられない。
「あ…、い、いえ。」
「時間がないの。あなたには申し訳ないけど、命がなくなる前に早く記憶を移して。」
「できません。」
「あなた、死んでしまっていいの?世界で初めて、不老不死を実現させるのよ。重要な役割を担ってるんです。一時の感情でこの大きなプロジェクトを水の泡にしないで。」
その時だ、外でざわざわ声がした。
取材クルーたちの声らしい。なんだろう。
犬巻も気になったのか、外の方をチラッと見たが、なんなのと肩をすくめて気にとめなかった。
「どれだけ投資したと思ってるの。国や実業家の期待を背負ってるの。あなた一人のセンチメンタリズムだけで人類の宝を壊さないでください。」
「そうなんですけど…やっぱりこれって人体実験じゃないですか。」
「実験の何が悪いの?考えてみなさい。薬品、手術…今あるすべての医療行為は、先人たちの臨床実験のおかげよ。世界で最初にパスツールが子どもにウィルスを植える実験をしたから現代にワクチンがある。当時は非難されたけど、今は英雄。誰かが最初にならなきゃ。」
「チビの未来を奪いたくないんです」
「おチビちゃんは、あなた自身なの。あなたの一部。爪とか髪とか、あなたから生えてきた身体のパーツだと思えばいい。元に戻るだけ。気にすることないわ。」
「そんな言い方…」
「なんとか成功させたいの。」
「すみません。本当にすみません。」
「契約書にサインしたでしょ。」
外がざわざわしてきた。
「騒がしいわね」
犬巻が怪訝な顔で外をうかがう。
だが、僕だけが気づいてしまった。
テーブルで向かい合わせに座る犬巻の、その肩ごしに見えるテレビ。
そこに、妙な映像が映っていることに。
それは、さっきまでばあちゃんが観ていたワイドショー。
画面上にLIVEと書いてあり、まさに今、僕と犬巻がテーブル越しに話す姿が映っているではないか。
これって、この部屋の柱に据えられているカメラ…、つまり僕とチビの生活を毎日分析しているいつものカメラ映像…だよね、これ?
試しに頭を掻いてみる。少しの遅れで、テレビ画面の僕も頭を掻いた。
え?テレビに流れてるってこと?表のざわつきの正体はこれだった?
なんでこれが?なんで?
頭はパニック状態。
…だけど
…まあいい。腹が座った。
もしみんなに知られちゃったのなら、それでいい。
聞いてくれ。聞いて考えてほしい。
覚悟に変わった僕の表情に、何も知らない犬巻は「何?」と一瞬たじろいだが、まさか気のせいね、と思い直した様子。
言うべきことを伝えよう。
「犬巻さんには感謝しています。」
「は?」
「このチビと出会えたことは、人生の宝物でした。
僕の命はいつ終わるかわかりません。来月か…明日か…。今夜、晩ごはんのオカズを目の前にして、一口も味わずに事切れるかもしれません。
そんな僕が生きる希望をもらえたんです。このチビのおかげで。チビと一緒に暮らしたおかげでね。死んだあとも、このチビが生きてくれることで、生きる希望が湧きました。”死んだって構わない、この子に未来を託すことができた”、そう思えるようになりました。」
「………。」
犬巻が鬼の形相で僕を睨んでいる。
彼女越しのテレビ画面に映る”ミニ犬巻”の顔もダブルで怖い。
「でも、いいことばかりではありませんでした。一緒に過ごすことで、彼の人生を奪ってしまうことがわかりました。だからもう、一緒には暮らせません。親でもなく、兄弟でもなく、子でもなく、ある意味もっともっと近い存在。究極の家族。なのに、もう一緒には暮らせません。」
「だから気にしなくていいの。」
「僕は、この子を守らなければなりません。一緒にいられないけど、先に死んでしまうけど、でも守り続けます。」
「そんなこと言わな…」
「お願いがあります。」
「は?何を?」
「犬巻さん、あなたは内閣府の方ですよね。国の大切なことを決める人たちなんですよね。」
「ええまあ。それが?」
「どうか、この子を…、そしてこれからも生まれるかもしれない、クローンの子どもたちを守ってください。そんな法律を作ってください。」
「あなたね、そんな簡単じゃ…」犬巻は眉をひそめ、真っ赤な唇はへの字。
「彼らの人権を保証して欲しいんです。誰からも奪われず傷つけられない人権を。クローンはオリジナルの人間の所有物ではありません。オリジナルが着換える新しい服ではありません。
お願いします。お願いします、クローンに人権を!この子に幸せな未来をください!」
「………。」
犬巻は微動だにせず、僕を見つめていた。
表の人々も静まり返っている。
「ん?」
その時、犬巻は気づいてしまった。僕の目線に違和感を感じたのだ。
振り向いて背後のテレビに目をやり、
「なによこれ…!?」
駆け寄って両手でテレビを鷲掴み。そこに映る自分たちを見て、わなわなと震え出した。
「ぬぬぬぬぬぬ…」
振り向いたその顔は鬼の形相。見たことないインパクト。しまった…。
「カメラを切って!」
犬巻はもう一度言った。
「カメラを切りなさい!」
「いや、僕はあの…知ら…」
”プツン”
映像が消えた。漆黒の画面に吸い込まれるように。
消えた?どういうこと?僕の頭は混乱していた。
その瞬間、静寂を破るように、
「うわぁぁぁ」
表で歓声が挙がったのが聞こえた。
記者たちも市民ボランティアも。ちゃんと言葉は聞き取れないが、どうやら僕とチビを応援しているような、そんな優しさにあふれている声だった。
やがて、犬巻が僕の目を睨み続けながら言った。
「もういいわ。猫塚。」
え?
「はい。」
頭上で猫ちゃんの声がした。
ミシミシ古い木がきしみ階段を降りてくる足音。
「え?なに?」
犬塚ごしに現れる白くて細い足。足元を探りながらゆっくりと。
やがて二階から降りてきたその姿は、タブレットを片手にしたまぎれもない猫ちゃん。
いつからいたの?
犬巻は、僕の目を凝視したまま猫ちゃんに向かって、
耳を疑う信じられない言葉を発した。
「これでいいんでしょ。」
「ありがとうございます。」
え?
猫ちゃんは、申し訳なさそうに、
けど安心したような穏やかな表情で犬巻の傍らに立った。
すると鬼の形相がふにゃっとゆるんで、
「あーあ。」
犬巻は一転、あどけない少女のような背伸びをした。
「しょうがないわね。これで私、チョー悪者よ。」
え?え?
「芝居を打つしかなかったわ」肩をすくめて言った。「猫塚もうるさいしね。しつこいったらありゃしない。」
どういうこと?
「映像を流したのは、私の指示よ。」
◆
実は、すべては犬巻自身の意志だった。
猫ちゃんに自宅カメラの映像を、ネットに接続して公開させたのだという。
「ユタカさん、あなた頑固ね。どうしても言うことを聞かないから実験は失敗。私の立場はヤバすぎ。だったら、根底から覆るような大混乱でもなきゃ、ウヤムヤにならないでしょ。」
実験失敗の責任を問われるくらいなら、犬巻はこっちを選んだというわけだ。
テレビでも取り上げられ、世界中にも配信された。クローン計画の是非を世の中がどう判断するか…未来は世論に委ねられた。
「こんなのバレたら懲戒ものだわ。クローンの体を待ち望んでる年老いた投資家たちは怒るでしょうね。ああ、こわいこわい。」
「犬巻さん…」
「私も立場がありますので、実験を意地でも進めようとしているポーズは見せておきました。” 勝手に配信された、あなたの策略にハメられた "、っていう筋書きにしておくから。よろしくね。」
「は、はい。」
「ま、それでも相当立場はあやういかも。ふふふ。」
「それなら先に言ってくれれば…」
「あなた、お芝居ヘタでしょ。」
犬巻は、声を上げて笑った。猫ちゃんを見ると、優しく微笑んでいる。
「言っておきますが…」
犬巻は背を正し、「私は今でもクローン推進派よ。」
ハッキリと念を押した。
「私の責務は、この実験を成功させて、人類の新しい進化をもらたすことなの。私は諦めてはいないわ。お父様の汐妻教授がいなくても、私たち研究チームで一番早く成功させてみせる。あなたたちのクオリティを超えるクローンを作ってみせます。」
僕は猫ちゃんを見た。猫ちゃんは、僕に神妙な顔でうなずいた。犬巻は、指先のホコリをふっと吹き飛ばし、言った。
「たとえ私たちがやらなくても、いつかはどこかの国の研究機関で実現するでしょう。時間の問題。ユタカさん、あなたがどんなに頑張っても、この流れは止められない。人間はね、思いついた事は実現せずにはいられない。そういう生き物なの。」
「でも…」
「だいじょうぶよ。ちゃんと、クローンの人権を守ることは、約束します。本人たちの意思を尊重します。安心なさい。そのかわり、もしもオリジナルとクローンの2人ともが『いい』って言うなら、シンクロ実験することは許してね。本人たち2人が心から望むなら。いいでしょ。」
僕には、答える言葉が見つからなかった。
「とにかく…」
ふぅーっと、深呼吸して犬巻は言った。
「あなたとおチビちゃんの生活をこの数ヶ月ずっと見せてもらいました。そこのカメラでね。最初はただの研究対象だったわ。シンクロが進んでいく様子はとても興味深かった。記憶が移り始めたときは興奮しました。現実に起こるなんて。でも、それとは違う感情で、私自身毎日見るのが楽しみになっていた事に気づきました。あなたとおチビちゃんが、一緒に生活する様子。遊んだり、話したり、ケンカしたり…。やがて互いを思いやるあなたたちを見て、これは1人の人間のコピーなんかじゃない。2人なんだ。家族になったんだ。と思えるようになりました。だから、今回はあきらめます。きれいさっぱり。しょうがないわねえ。」
「ありがとうございます。僕たちのために…本当にすみません。」
「あなたたちのためじゃないわ…、保身のためよ。」
犬巻はいたずらっぽく笑いながら、
「ま、もっとも、今回ダメでもいいの。本来はもう少し優秀な人材で実験したかったから。就活に落ちこぼれた学生なんて、2人も3人も増やしたって価値はないわ…。」
とウインクした。
「ちょいちょい失礼ですって。」
僕も笑った。
猫ちゃんを見ると、笑顔でうなずいた。
◆
玄関に腰掛け、高そうにテカる靴を履きながら、犬巻が背中で言った。
「あなたたちお似合いね。クローンとしてじゃなく…、」
「え?」
よっこいしょと立ち上がり僕の目を見て、
「家族として。」
「…はい!」
嬉しくて頭を下げた。
「じゃ、元気でね。」
玄関扉に、手をかけ、
「さあ、蠅たちをどう追い払おうかしら。」
ガラッと開けた。
またたくフラッシュ。響くシャッターの音。
飛んでくる質問の嵐の中、犬塚は消えていった。
■冬、第31話 涙の大晦日
暮れも押し迫った、大晦日の午後。
おせちに入れ忘れた栗きんとんを買うため、ばあちゃんのお使いでスーパーに行った帰り道。
鼻歌で歩く僕とチビの横に、黒塗りのセダンが音もなく止まった。
「ちょっとお話、いいですか。」
下がったウインドウから顔を出した男は、”議員秘書”の馬尾と名乗った。
ドアが開いて、綺麗な白いシートの助手席が現れた。つい身を滑り込ませそうになったら、
「知らない人の車に乗っちゃダメなんじゃないの?」
口を尖らせたチビにたしなめられた。
犬巻や世間にすべてぶちまけてしまったこないだの一件が、僕を少し大胆にさせてしまったのかもしれない。
「そうだよね。ごめん。」
僕は周りを見渡した。公園がある。そうだ…、
「あの…、あそこでなら…。」
◆
巨大なタコの形をした滑り台遊具。
横腹から人が入れる土管状の穴がある。
その中で、馬尾秘書と僕とチビ3人で並んで膝を抱えて座った。窮屈そうに足を折る秘書。
「なんか、すみません。」
「いえ。人目に触れないので。」
生まれて初めて秘書と言う人種を見た。手を触れたら切れてしまいそうなくらい真っ直ぐプレスされたズボン。話を聞きながらも頭の中では、”よく「秘書がやった」と擦り付けられる気の毒な立場の人なんだよな…”、なんてくだらない事を考えたりしていたら、
「年明けすぐに通常国会があります。参考人招致に来てもらえませんか。」
と内々に打診された。「政府与党が主導するクローン実験に巻き込まれた被害者として、洗いざらい喋ってほしい。」というのだ。そうか、犬巻たち政府とは敵対する野党政党なんだな。
「つきましては打ち合わせの段取りですが…」
さくさく先に進もうとするので、僕はチビの顔をチラリと見た。大人の話なんて興味もなさそうなチビ。秘書にもらった土産の仕掛け絵本に興奮してページをめくる無垢な横顔。
…確かに僕が死んじゃった後、こいつを守るためには法の整備なども必要なのかもしれない。だけど、チビをまた好奇の目に晒すことにもなる。
たとえ目論見通り政権がひっくり返ったとして、この人たち新しい政府はチビの事を大切に思ってくれるのだろうか。犬巻の言ったとおり、クローン実験の誘惑に負けたりしないだろうか。またチビが利用されるのは勘弁してほしい。
エコバック内で転がる栗きんとんの瓶を布の上からいじりながら、そう思った。
「少し、考えさせてください。」
丁重にお願いすると、
「せっかくのいいお話なんですけどね…お心が定まったらこちらへ。」
と名刺一枚置いて、残念そうにテールランプを光らせ走り去って行った。
だけど…、正直どうでもよかった。
みんな外野がいろいろ言って惑わせるけど、そんな騒ぎなんて僕にはもうどうでも良い。
僕の気持ちは全く別のところにあった。
大事なことがあるのだ。
残されたわずかの時間を、チビと最後の思い出づくりに費やさなければ。
「あと一週間くらいならシンクロ度合いもそんなに進まないから大丈夫です。しっかり思い出を作ってください。」
猫ちゃんが言ってくれたので、年末年始で線を引くことにした。
そこまでは楽しもう…。これが済んだら、お別れだ。
そう自分に言い聞かせていた。
◆
夜…。
最後こそは、とてもあたりまえのことをして過ごそう。
派手ではないけど穏やかな、何気ないごく普通の生活をしよう。
だから、皆で紅白を観た。ベタなことがしたかった。とてもあたりまえに。
チビとばあちゃんと、それから猫ちゃん。
すきま風に背中を凍えながら、コタツに皆で足を並べ暖をとる。ばあちゃんが作った年越しの”にしんそば”をすすり、家族らしい行事を楽しめる幸せを噛み締めた。
幸せは、甘い出汁の味がした。
近ごろ増えた頭痛に、こめかみを指の腹でさすっていると、
「だいじょうぶですか?」
猫ちゃんがのぞいた。
照れ臭さと心配かけたくない思いが入り混じって、ごまかしの質問で返した。
「犬巻さんたち、これからどうなってしまうんですか?」
「…わかりません。でも、ちょっとやそっとではへこたれない方たちですから。」
と優しく笑う。
「ですね。」それにしても、「猫ちゃん、大晦日なのに付き合ってもらってすみません。いいんですか?お休み。」
「身寄りもないので。」
「あ、すみません。」
「いいんです。」と笑顔で僕を安心させ「それに…」チビやばあちゃんを眺めながら、
「なんか本当の家族みたいで居心地良くて…」
ごーん、とかすかに除夜の鐘。
自分がほめられたわけじゃないけど、照れくさかった。
やがて新年を迎えるカウントダウン。
「5…4…3…2…1…ゼロ…」
皆でささやかに新年を迎える。
たった1秒違うだけで西暦がひとつ変わる感激に、どこかで若者たちがおどけてはしゃぐ声が、夜の街角のアスファルトにはね返って遠く響いている。
「あけましておめでとうさんでございます。旧年中はほんにお世話になりました。本年もどうぞよろしゅうお願いいたします。」
午前0時過ぎの新年の挨拶は毎年恒例の神聖な儀式だ。ばあちゃんに倣って、僕たちもあらたまって畳に三つ指をついてつつましやかに行われる。
いつもは9時に寝るチビも、夜更かしの甘い背徳感と、特別な日だから許されるという解放感が手伝ってか、大いにはしゃいだ。
猫ちゃんの耳元でささやいていたので、
「何話してるの?」と聞いても、
「ひ・み・つ」と言って2人笑った。楽しそうで良かった。
「なに?」
いたずら心で食い下がってみる。
「なんでもないよ」
「だって今、コソコソ隠し事みたいに。」
と僕が突っ込むと、チビが、
「隠されて困ることでもあるの?」と笑った。
近ごろ、少し大人びたセリフを言うことが増えた。僕の話し方だ。かなり知識がシンクロしはじめている。やばい。もう時間がない。
チビに人並みの思い出だけは作ってやりたい。それさえできれば、この生活ももうすぐで終わり。僕がこの家から去る時だ。ばあちゃんとチビが一緒に暮せば寂しくなかろう。
今夜は興奮してつかれてしまったようだ。やがてチビは電池が切れたようにこてんと寝てしまった。
二階の布団に寝かせたあと、猫ちゃんは、何かを察してか、
「まだ人いっぱい歩いてますね。大晦日は電車ありますから。」
と寒空の下、ダウンを羽織って帰っていった。
◆
ばあちゃんに全部話そう。
コタツで少し寒そうに背中を丸めたばあちゃんは、お茶を飲んでいた。
時計の振り子の音がカッチカッチ響く。
チビが起きてこないよう気を配りながら、全部つまびらかに話した。反応をうかがいながら、丁寧に言葉を選んで話し続けた。ばあちゃんは、表情一つ変えずに最後まで聞いてくれた。
時計の歯車が小さくカチリと動き、ボーンとひとつ鳴った。
「知っとったよ。」
ばあちゃんが、ぽつりと言った。
「難しいことはわからへんけどな…」
僕の命についても、チビの存在についても、ばあちゃんは知っていた。父がいなくなるとき聞かされていたそうだ。ずっと黙って僕と暮らしていたという。
「春におチビのゆーちゃんが現れたときは、ほんに肝がつぶれるかと思うたわ。生き写しとは正にこのことやわ。」
「…チビのことお願いしていい?」
「いつこの日が来るか、と思うとった。就職とかでいつか出ていくやろて。なーんも心配せんでええ。」
昭和の京女は気丈に振る舞う。
「ばあちゃん。今までありがとう。」
「身体に気ぃつけて。生水飲んだらあかんよ。腸、弱いさかい。」
「わかってる。」
「ばあちゃんより先に死んだら、ばあちゃん許さへん。許さへん。絶対に許さへん。化けて出るさかいに。」
「頑張るよ。その場合、化けて出るのは僕なんだけど。」
と僕はおどけて見せた。
「悪い冗談を。ババ不幸もん。」
とばあちゃんは小さな頬でふくれた。そして、「もう、先ぃ寝よし。ばあちゃんは、もう少しお茶を飲んでいくさかい。」と後ろ手で僕を「シッシッ」と追い払った。
「ごめんごめん。わかったよ。」
「はい、行きない、行きない。」
「じゃ、お先に。」
「はいはい。おやすみやす。」
「おやすみ。」
僕は階段に足をかけた。
その時、
コタツ布団に深く体を埋め、見えないように肩を震わせ泣いているばあちゃんの背中に気づいたが、
僕はまともに見ることができなくて段を駆け上がった。
■冬、第32話 最後の日
最後の日。
その日は、突然やってきた。
残酷な現実ほど、ドラマチックには訪れない。日常に紛れ、とてもあたりまえのようなすました顔をして、さらりとやって来る。
年の始めの日が最後になるなんて、皮肉な話だ。
◆
その朝は、目が覚めてからずっと悩んでいた。
チビに話さなきゃ。
「もう一緒には暮らせない。」
なんて言えばいいんだろう「お前なんかと一緒に暮らしたくないんだよ。迷惑なんだよ」ドラマみたいにわざと突き放すのかな。切ない気持ちを抑えて、心にもないことを言って。チビがあきらめやすいように。
…くそ、頭が痛い。
朝からそんな迷いを懐に忍ばせながら雑煮を食べた。ばあちゃんが作ってくれた、たっぷり鰹節をのせた白味噌のお雑煮。おせちのくわいが、パサパサしていつも以上に喉に引っ掛かった。
チビにお年玉を渡してみた。生まれて初めて人にお年玉をあげた。ポチ袋を買うのも初めて。いくら包めばいいか、分からなくてググったりした。
あーあ、大人になっちゃったな。
お年玉でキックボード用のヘルメットを買おうと、一緒に自転車屋さんに出かけた。キックボードは、行方不明のゴタゴタがあった夜、サンタが慌ててプレゼントしたモノだ。
道すがら、いろんなことを考えてしまった。”チビにどう話せばいいのだろう”、”これから一人で生きていけるかな”、”ばあちゃん大丈夫かな”…、考えれば考えるほど、頭を離れなくなった。
残された今の時間を楽しまなきゃいけないのに。こうしている間も、どんどん砂時計の砂は落ちていく。
「………」
僕は、黙って地面を眺めながら歩いた。
「えいっ。」
チビが塀の上に飛び乗った。僕があっけにとられていると、
「そこは危険だぞ。」チビが僕の足元を指差す。
「は?」
なにもあるわけない。
「そこにはワニがいるんだ。危険だぞ早く登れ!」
いつものやつね。はいはい。
チビのノリに乗っかってみたら、少しくらい気が楽になるかな。
「ほんとだ!隊長、足に噛み付いて離れません!」
「早く!」
「はい隊長!」
塀によじ上った。
「危なかったな。」
「ギリギリでした、隊長。」
作戦変更。僕とチビは、思いに誘われるまま道草を楽しむことにした。
塀の隙間をぬって、裏路地のジャングルを抜けていく。
チビの背中を追いながら、こうして町を探検ごっこできるのも、これが最後かなと噛み締めた。
◆
やがて足が向くままたどり着いたのは、駅前のあの再開発エリア、建設中のショッピングモール。
以前忍び込んで、警備員に追いかけられた思い出の場所だ。
春のグランドオープンに向けてまだ整備中なのだろう、お正月休みで工事も止まっていた。切りそろえられた芝は、やや冬のベージュに染まっていたが、その美しい近未来的な建築や遊歩道の造形はそのままに悠々とそびえていた。
どんよりとした冬の空。影のない風景が寂寥感をかもし出している。
誰もいない静寂。
まるで、”突然すべての人が消え、世界中に我々だけしかいなくなったよう…”
いつもの妄想ごっこが脳裏をよぎる。
” もしかしたら地球人たちは全員誘拐されてしまったのかもしれない。残された人類最後の我々だけが今、ここに立つ。”
…なんて。ワクワクするようなストーリーが頭の中でふくらんできた。
チビと目が合った…同じことを想像している。意識のシンクロだ。
ワクワクがふくらんできた。ふくらんで、ふくらんで…。
「きゃー」
「きゃー」
チビと僕は、同時に奇声を上げて走り出した。
静寂をごまかしたかったわけではない。誰もいないこの地の覇者になったような勇気が噴き出してきたのだ。走って、走って、転がって、また走って。あの曲”木星”をラララと怒鳴るような声で歌いながらはしゃいだ。この興奮、たまらなく楽しい。
いつまでもずっと続けばいいのに…。
◆
「はあ、はあ…、」
2人とも息が切れ、どちらからともなく、枯れてチクチクする芝に腹を見せて寝ころんだ。
「これなに?」
チビが僕の上着のポケットを指す。
「ん?ああ、これね」ねじ込まれていた紙を取り出し、「夢地図だよ。」クリスマスの夜から入ったままだ。
「見せて見せて。」
チビは思いのほか食いついた。そうだよな、見せたことなかったかもね。
折りたたまれた地図をばあっと広げる。
「これはな、今までチビと一緒に見た夢が書いてあるんだ。ほら、ここがセミ捕りした神社でしょ。それからここが学校。これは泥だんご公園だ。」
「そうそうそう。うわぁー、空を飛んだ場所まである。」
目をキラキラさせている。
「夢でも本当の世界でも、いろいろ遊んだな。」
「そうだね。いろんなとこ探検した。」
楽しい思い出が次々蘇ってきた。
「一緒に秘密基地も作ったし、うまい棒も食べたし。」
「水風呂、気持ち良かったね。」
「工作もいっぱい作ったな。」
「勉強はヤだったけど。」
「それはそれで兄ィは楽しかったよ。」
僕が教えたこと。…どうして勉強しなきゃいけないか?…どんな大人になって欲しいか?…友達を裏切っちゃいけないよとか…いろいろあふれてきた。
「学校は楽しい?」
「もういじめられなくなったよ。友達いっぱいできたし。…兄ィに教えてもらった通り、いじめられてる子を助けたよ。」
「…そうか。偉いなぁ。」
少しずつ…少しずつだけど、出会ったときから成長している。
良かった…。
ちょっとした好奇心。男同士だし、猫ちゃんのことも、どう思ってるのか突っついてみた。
「どうなの?」
「大好きだよ!」
ためらいがなさすぎて面食らった。「ぼくと猫ちゃんと兄ィ、3人で結婚するの。」
そうだよな。子どもらしく無邪気に答えるわな。ある意味ずるい。
「兄ィは?」
「え?あの…僕は…あのぅ、あれだ…。大人にはな、いろいろあってな…。」
「わかってるよ。僕、兄ィの頭の中、わかるもん。」
「うるへぇ。」僕は赤面し、頭を小突いた。
「いてっ」とチビは笑う。
そんな戯言をご機嫌で交わすうち、うつ伏せに草を指先でいじるチビの背中を眺めていると、何でも話せる気がした。
だからかもしれない。僕の中であの話題が舞い降りた。
「別れて暮らそう 」という話。
…そうだ。今、言おう。
「チビ。」
あらたまって呼んでみた。
今から言うよ。小さく意志を固めたその時、
「イヤ。」
先手をとられた。
「まだ何も言って…」
「嫌。」
「ちょっと聞いてよ。」
「イヤイヤイヤ。」
「大事な話なんだよ。」
「イヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤ、いーや!」
チビは飛び起き、いやだいやだと逃げまわった。
広場中を駆けずり回って、植栽にぶつかり、ベンチを蹴とばし、散々逃げわまった。息が切れる。素早いが、動きは読める。なにせ自分自身だから。
やがて僕のそばをすり抜けようとしたその瞬間、左手で足首を捕まえた。
「いやだよ、イヤ!絶対イヤ!」捕まったバッタが手のひらの中を蹴るように、手足をバタバタ暴れさせた。
「ちょっと聞いてよ。」
体中の芝を払いながらなだめるが、
「聞かない。イヤだから。」
「何がイヤ?」
「行かないで!」
「え?」
「行かないで。」
思わず手を離した。
「わかってるの?」
こくりとうなずく。
「一緒にいるの!ずっと!」
「………」
「兄ィ、どこにも行かないで!」
…そりゃそうか。脳のシンクロだ。僕の考えなど悟られてしまう。
「このまま一緒にいると、チビが大変なことになるんだよ。」
「兄ィが僕の頭に入ってくるんでしょ。」
「入るっていうか…。」
「僕とくっついて、一人になるんでしょ。」
「まあ、そんなとこか。」
「わかるけど、よくわかんない。」
そうか。理解力はまだ小学生だもんな。僕の考えが読めたとしても、チビの頭にはちょっと難しいか。
「いいよ。」
「え?」
「兄ィとくっついていいよ。」
「そういうわけにはいかないよ。チビいなくなっちゃうんだぞ。」
「いなくならないよ。くっつくだけだし。」
「そうはいかないんだよ。」
「行かないで。ねえ、絶対行かないで。キックボード一緒にやるって言ったじゃん…。」
チビは拳で僕の胸を叩いた。
「いたっ。」じんとする胸を見た。
チビは、無言でまた叩いた。
叩いて、叩いて、叩いた。何度も何度も。僕の体が倒れそうになるほど揺れた。
チビの息が荒くなり、顔を真っ赤にして、ぼろぼろと涙がこぼれだした。言葉にならず「んっ…、んっっ…」息をこぼしながら、僕を叩き続けた。
小さな拳が僕を突くたび、痛くはないけど心に刺さった。
離れたくない。楽しかったこの日々。一緒に暮らせて本当に幸せだったのに…。
「んっ…、んっっ…」
小さな体は、やがて力なく腕をおろし、ぽつりと言った、
「行かないで…」
思わずチビの小さなシャツを引き寄せ、強く抱きしめた。
チビは、堰を切ったように大声で泣き始めた。
我慢してた感情があふれ、僕も子どものように泣いた。
静寂で満たされていたはずの冬の空に、2人の泣き声が響いた。
◆
その時は突然やってきた。
なにやら頭に変な違和感を感じた。こめかみの奥の方、痛みでもなく、しびれでもなく、鈍い感覚。
残酷な現実ほど、ドラマチックには訪れない。日常に紛れ、とてもあたりまえのようなすました顔をして、さらりとやって来る。しかも僕らの都合などお構いなしに。
胸元のチビが気づいて「?」僕の顔を覗きこむ。
とっさに「なんでもない。」
「兄ィ、アレ、来たの?」
まるで、当然知っていたかのようにささやく。
「わかるか?」
「わかるよ。なんかわかる。お医者さん行こう。」
「つったって、自転車屋さんに…。」
強がったが、景色をぼんやり消すように暗い霧が視界に押し寄せてきた。
「悪い、チビ、ちょっと座るわ。」
腰を下ろそうとしたら、崩れ落ちてしまった。
大声でチビが叫んでいる。
芝がチクチク触れる耳に、誰かが駆け寄る足音。
どんどん近づいてくる。
誰?警備員か?もういいや、叱られても…。
眼の前に現れ、草を踏むスニーカー。
しゃがんで覗き込んだその顔は…、
…猫ちゃん。
どうしてここに?
そのあとは、覚えていない。
■冬、第33話 さよなら…
「ゆうちゃん、起きたか?」
気が付いたら、ばあちゃんが泣きながら僕を見ている。
ここは…?
クリーニングの匂いがする。固くプレスされたシーツ。
ああ、まただ。病室のベッド。見ると、僕の右手が、隣のベットに寝るチビと手をつないでいた。
「あれ、なんで…?」
「あんた、正月早々ばあちゃんに心配かけたらあかん。」
と、突然の光。
「ユタカさん、ちょっと眩しいですよ。はい、この指見てください。」
ペンライトで眼球を照らされ、猫ちゃんが細いきれいな人差し指を左右に動かして見せる。その指を目で追いながら聞いた。
「どうしたんですか?僕…。」
猫ちゃんは、僕の腕に巻きつけた脈拍計の圧迫帯にポンプで空気を送りながら説明してくれた。
あの時、倒れた僕を猫ちゃんがすぐさま応急処置し、救急搬送で多摩の遺伝子工学研究所に運んでくれたのだという。
「猫ちゃん、どうしてあそこに?」
「おチビちゃんのおかげです。」
チビはまだ横になっている。僕の体調不良がシンクロしているそうだ。
「実は、わかってたんです。」
「?」
「ずっとおチビちゃんは感じていたんですよ。」
チビは僕の頭痛をずいぶん前から知っていたという。僕自身でさえ気づかない症状の進行を正確に感じていた。
例えば肺や腎臓。双子のように体内に2つある臓器は、片方が不調になった場合、機能を補うためにもう一方が敏感に反応して倍の働きをするという。僕とチビの脳は同じ構造。チビの脳が僕の脳の異常を補おうと、センサーのように感じ取ったのだそうだ。
「不思議ですね。まだまだクローン医学は分からないことだらけです。」
”いよいよ今日” ということも、チビは察していた。僕よりもハッキリと。だから猫ちゃんに「もうすぐ兄ィの頭が、バンってなりそう。」と予告していたらしい。そう聞いて、
「そういえば…」昨夜を思い出した。
………大晦日の夜。猫ちゃんにコソコソ耳打ちするチビ。
” 何話してるの?"
" ひ・み・つ " 笑う2人………。
「ああ、だから…。」
「そうなんです。だから実は今日も…。」
猫ちゃんは僕とチビが出かけた時、こっそり後をついて来てくれていた。僕たちが路地を抜け、あの再開発エリアに行くのを遠くから見守ってくれていたのだ。
「2人とも進むのが早くて、塀に挟まっちゃいました。」
フフフと寂しく笑う。
「なんで僕たち手をつないでいるんですか?」
「覚えていないんですね、ユタカさん。」
僕がここへ運ばれた処置中、並んだベッドで横たわる僕とチビが、意識もないのになぜか手を伸ばしあっていたという。
気づいたばあちゃんが、「ゆうちゃんの手!」と叫んで、医師や看護師さんたちと一緒に、チビのベッドを僕の傍へ近づけてくれたそうだ。
「確かに、夢を見たかも…。」
巨大な水風呂の渦巻き洪水の中にいた。
虫ほどの小さな僕とチビが激しく流されていた。
水中メガネとシュノーケルのチビが僕を助けようと手を伸ばす。だが手が届かない。もう少し…もう少し…。激しい水しぶきをはねのけ、手がつながった。
……また、一緒に夢を見たんだな。
夢の中で、あのまま僕が行ってしまいそうになるのを、チビが引き止めてくれたのかもな。
「猫ちゃん、教えてください。僕、どうなるんですか。」
「…………。」
猫ちゃんは、言葉に迷った。ばあちゃんが背中を向ける。
「いいですよ。分かっています。」
「あの…………。」
「そうなんですよね。」
「…………はい。」
小さくうなずいて僕の目を見つめ、言った。
「ガラスの破片が…、脳の血管を突き破りました。」
破れた箇所から血液が流れ出て脳内組織に大量に流れ込んできており、手の施しようがなくなった。流れ来る洪水の夢はそういうことだったのかもしれない。
やはりチビと一緒に暮らしたことが影響していた。2人の脳のやりとりが盛んになり、通常より脳内血管の働きが活発になった。それでガラスが大きく動いてしまったのだ。だけど今さらだ。原因が分かったところでどうしようもない。
もうすぐ手足の感覚に異常が見られ、やがて、ちゃんと話せなくなり、朦朧として意識がなくなるはずだという。
「…そう、ですか。」
かすかに薬品の匂いの漂う空気を大きく吸って、白い天井を眺めた。
もう時間の問題だな。
なんだよ、
別れて暮らす必要……なくなっちゃったじゃん。
「兄ィ…」
チビが目を覚ました。
「おお、チビ。」
まるで学校の廊下ですれ違ったかのようなありきたりな挨拶をしてみた。
「ありがとな、いろいろ。」
「うん。」
「もっと遊びたかったな。」
「うん、もっと。遊ぶよね?」
「そうしたいんだけど…。」
チビは、僕の目を見つめた。
「………。」
「………。」
その時だ、チビと僕の頭に同じ思いが同時に閃き、2人叫んだ。
「猫ちゃん!」
「猫ちゃん!」
突然シンクロで大声を出したもんだから、「わわっ」と驚いて、猫ちゃんが酸素濃度計を落っことした。
「すみません、シーツをもってきてくれませんか。」とお願いすると、
「シーツ…?なんで…」怪訝な顔。
「それと、ロープも!」
「それと、ロープも!」
「シーツとロープ…?どこかで見たよう…」
やがて猫ちゃんの瞳が輝いた。
「!」
いつもの笑顔で「はいっ!おチビ隊長」と敬礼してウインクした。
◆
やがて僕のベットの上には、大きなシーツが天井から吊られてテントのようにふわりと覆いかぶさった。まるで大きなゆりかごのように、僕たちのベッドをやさしく包む。
そう、あの「秘密基地」だ。
特別に処置室の窓を開け放してもらった。すると、柔らかい風がシーツを揺らし、辺り一面が泣きそうなくらいに美しい夕暮れのオレンジ色に染まった。
チビが僕のベットに潜り込んでくる。
「兄ィ…」
「チビ隊長、せまいです。」
「兄ィ副隊長、お歌やって。」
僕は、ささやくような微かな口笛で父の子守唄… ホルストの『木星』を奏でた。
病室の秘密基地に響く、甘美なメロディ。
チビは、幸せそうな表情で僕の傍らでずっと聞いていた。
ばあちゃんと猫ちゃんが鼻をすする音がする。
「うるさいよ。」
からかうと、
「失礼しました、副隊長。」
と猫ちゃんは泣きながら敬礼した。
「猫ちゃん、ありがとう。」
ありがとう。僕の人生で一瞬だったけど、
こんなふうに泣いてくれる女性がいてくれて、幸せでした。
命がもう少しあったらな…。
「…あの」
「…あの」
同時に猫ちゃんと言葉が出た。
「シンクロしちゃいましたね。」
「シンクロしちゃいましたね。」
ぷっと、2人して笑ってしまった。
「クローンでもないのに。」
なんだか気が楽になった。
猫ちゃんになにか言っておきたい。でも、なんて言ったらいいのだろう。
だって僕たちには、もう、なにかを育む時間もない。
「あの…えっと…」
「スキだよって。」
「えっ!?」
驚きすぎてベッドから落ちそうになった。猫ちゃんもメガネの目をまん丸にした。
チビだ。
「兄ィね、猫ちゃんのこと好きだって。ボク、兄ィの頭の中わかるもん。」
「いや、あの…いえ…えっと…」
否定もしにくいし…どんどん顔が紅潮するのが分かる。「はい。すみません。こんな時に。」
恐る恐る猫ちゃんの顔を覗くと、
まるい眼鏡の瞳から大粒の涙があふれ、
「はい!」
長い睫毛を瞬くごとにきらめく雫がぽろぽろ宙に舞い、今まで見たことのない美しい笑顔で微笑んでくれた。
「今まで、ありがとうございました。チビをよろしくお願いします。」
「は…い…」
泣きじゃくって返事が聞こえなかった。
ばあちゃんも泣いている。
「ありがとうばあちゃん。」
「ゆうちゃん、気張りぃ。目ぇ開けて。しっかりしい。」
しわくちゃの手で僕の手の甲をペシペシ叩いた。
「ばば不孝でごめんね。」
「あほ言いないな。順番間違ごうたらあかん。ばあちゃんが代わりに逝くさかい。」
手ぬぐいで涙をぬぐうが追いつかない。
「別れて暮らす必要なくなっちゃったね。」
「どあほ!」ペシペシ叩き、「センセ、なんとかなりまへんのかいな。ウチを代わりに逝かせておくんなはれ。」医師の白衣の袖を引っ張って振り回す。
「ばあちゃんは元気でいてもらわなきゃ。チビをよろしくね。」
「あかん、お気張りやす。ゆうちゃん、あかん…。」
僕の手に額をこすりつけ、
「おおお…」と嗚咽してむせび泣いた。
ああ、だんだんぼんやりしてきた..。
もうすぐなのかな。
「チビ」
「なに?」
不安そうに目を見開く。
「兄ィな、ちょっと時間がなくなってきたみたい。」
「なんの?」
「そろそろ行かなきゃ。」
「行かないで。」
「バスに乗らなきゃいけないんだ。お空の向こうに行かなくちゃ。宇宙の向こう、見てくるね。」
「…ダメ、兄ィ…」
チビは泣いた。僕につかまって泣いた。「ボクの体を使って。ボクはいいから。兄ィが生きてくれればいいから。」
涙と鼻水でぐちゃぐちゃにしながら泣いた。
「ぼくは兄ィのニセモノだから僕の体使って!」
僕の胸元にすがりつく。
「チビ、お前はニセモノなんかじゃない。本物のユタカだよ。」
「兄ィ、死んじゃうの?兄ィ死なないで。」
医師が引き離そうとするが、シーツを掴んで離さない。
「ねえ、兄ぃ、死なないで。お願い起きて。」
ベッドにしがみついて、泣きじゃくっている。
「ボクの体を使って!ボクの体、兄ィと同じだから。使えるよ。ねえ、ボクの血とかいっぱい使って!」
鼻水と涙で顔をぐちゃぐちゃになっている。大人の力でも剥がせないくらい両手両足を振り回しながら泣き叫ぶ。
「兄ィとボクは同じだから。くっつけたらひとつになるよ。お願い。兄ィを死なせないで!お願い!お願い!」
心の底から叫びたくなるくらいチビが愛おしかった。込み上げる感情に涙があふれた。
「ねえ!お願い!使って!」暴れるチビ。
”ごめんな、チビ。ごめんな。これでいいんだよ。これでいい。チビの未来を守るために…”
そう言いたいけど、もう声が出なくなってきた。
話したいけど…話せない。
神様、もう少しだけ…。言いたいことがあるんだ。
”チビ、目を見てくれ。涙でぼやけるけど、ちゃんと見て。
僕の目だ。そうそう、そうだ。目を読んで欲しい。さあ最後の心のシンクロだよ。”
” 分かるかい?僕の話したいこと… ” 心で問う。
「うん!わかるよ兄ィ!分かる!」
チビが声をあげたのが遠く微かに聞こえる。
”チビ、正直に思ってること言っていいかい。どうせ君にはバレちゃうし。”
「うん、なに?」
”…こわいよ。チビ。”
逝くのがこわいよ。この世から消えてなくなっちゃうんだもんな。もうすぐ真っ暗になっちゃうんだな。こんな風に頭で考えることだって、もうすぐできなくなるんだな。
自分の意識が「無」になってしまうこと、なかなか想像できないよ。「宇宙のむこうにはなにがあるの?」っていう質問と同じだね。その先なんて誰にもわからない。その先があったら、さらにその先は?あるようなないような。だから、やっぱり、こわい。
でもね。
君がいてくれて、楽になったよ。
僕はいなくなってしまうかもしれないけど、君がいる。
君がこれから迎えるであろう未来を想像するだけで、ワクワクするよ。
ハタチになったチビの姿を見たかったな。
その時、僕と並ぶと面白そうだね。そっくりなんだろうな。
将来君は結婚して子どもを持つかもしれない。僕たちに良く似た一重で人見知りの子。男の子かな…女の子…? 君の子どもに会いたいなぁ。僕の子どもだよって、ちょっぴり思ってもいいかな。
僕がこの世に生きた証として、君がいることがこんなにも支えになるなんて。君に命をつないだことが、こんなに嬉しいなんて。僕の肉体は滅びても、君に伝えたこと、いろんなものが残る。そう思えるだけで救われるよ。
チビの目から涙があふれる。
僕一人しかいなかったとしたら、どんなにか不安だっただろう。
ここまで走ってきて、バトンを渡す相手がいないと思って死ぬところだった。
今、バトンを渡せる君がいることを心から幸せに思うよ。
人間は世界中みんなで、命のバトンリレーをやっている。子どもがいる人だって、いない人だってカンケイない。誰の子だっていい、みんな一緒に育てていくんだ。力を合わせてより良い世の中をつくることで、人類は命をつなぐ。
全員でひとつの種(しゅ)なんだ。
陽が沈みそう。
ああ...もうすぐかな。
わかる。もうすぐだ。そんな気がするよ。
2人の心は今ひとつになってきているから分かるよね。
チビ、教えたこと、忘れないでね。
「うん、分かった。兄ィ。」
泣きじゃくるチビ。
これからいろんなことがあるかもしれない。
どうか僕の代わりに恐れず体験していってほしい。
自分を誇りに思ってほしい。
誰にも真似できない自分を。
自分を愛して。
本当にありがとう。生まれてきてくれて。
本当にありがとう。僕たちの未来をよろしくね。
こまったな。涙が止まらない。チビの顔がにじんでぼやける。
一瞬だけど…ほんの一瞬だけど、チビの顔が、大人に成長した姿に見えた気がした。
その姿はまるで僕とそっくりだった。
「あ…あ…あ…」
いっそう涙があふれた。最後の夢かな。
意識が遠のいていく。
そろそろ…、バスの出発だ。目を閉じるね。
みんな、ありがとう。
さよ…な…ら。
そして…、
「僕」は命の幕を閉じた。
そう、僕たち”ユタカ”は、ひとり。
本当にひとりになった。

■次の春、最終話(第34話) 未来へ
…というわけで、以上が、
僕がクローンと暮らしたワケだ。
それから、どうなったかって?
世の中は変わった。
犬巻が約束してくれた通り、クローンの人権を守っていく法案が国会で提出された。おまけに、同じ人間が同時に2人存在することを法律で禁止するべきだと、議論され始めた。
政府は、人道に反したクローン人体実験の責任を追及され、近く政権交代するだろうと言われている。大晦日に現れた”議員秘書”の思惑通りなのか。
とにかく良かった。しばらくはチビのことは安心だ。
だけど、現実は意外と複雑で…。
あの時、犬巻は言っていた、「人間はね、思いついた事は実現せずにはいられない。そういう生き物なの。」と。
新政権も実は密かにクローン研究に興味津々だという。経済発展のためか、お偉いさんの命のためか。お得意の”法の解釈”で、うまいことやるつもりか。
おかげで犬巻たちはこっそり役職に残され、安泰だ。
そうでなくとも、やがてどこかの国がクローンを作り始めてしまうかもしれない。
これは避けられない運命なのか。だとすれば、世界の人々は、クローンを ”多様性" と受け入れ、彼らの幸せを願う社会を作って共生していくべきなのだろうか。
「クローンは善か?悪か?」…そんなの誰にもわからない。
クローンの社会進出によって差別や貧富の差が生まれ、人口爆発で食糧難が激化するかもしれない。
また一方では、愛する家族、愛する我が子を亡くした人にとっては、神からの贈り物になるのかもしれない。
ただ一つ言えることは、善か悪かは、その術を手にした人類がどう使うかに委ねられている。
ほら、もしかすると…
皆さんのそばにも、
いつの日かそっくりの奇妙な兄弟が現れるかもしれない。
その時、あなたはどのようにお考えになるのだろう。
◆
こんなこともあった。とっても小さな出来事だけど。
僕とチビが考えて応募した”ゆるキャラ”が、ひっそりと山陰の小さな港町で採用された。そこに行けば、町のイベントで僕らのゆるキャラを見ることができる。ホームページに動画がアップされ、頭の尖ったイカが踊っていた。なんて素敵なことだろう。
星の数ほどたくさん応募したけど、やっとひとつだけ。
でもいい。最高だ。少しは僕の生きた証が残せたかな。チビにはチャレンジする楽しさを知ってもらえたかも。夢を果たせなかった僕の代わりに、将来はデザイナーを目指すのかな…。もちろん別の分野でも何でもいい、好きなことを胸を張って好きと言える、そんな人になってくれたら、それだけで嬉しい。
◆
そうそう、入社面接でのあの質問。
「あなたはタイムマシンで過去へ行きました。
そこで出会ったのは、子どもの頃の自分。
未来から来たあなたは、一体何を伝えますか?」
…なんて言うか、答えが見つかったよ。
「未来は自分で変えられるよ。楽しんで。」
ってね。
◆
…え?僕?
僕は、死んだあとどうなったの…、って?
…どうしよう…言ってもいいかな…
…本当は、秘密なんだけどね。
チビの小さな頭の脳内。
記憶の中、チビの意識の奥の奥に潜っていくと………
………そんなはるか奥の入り組んだ場所に、
シーツで作ったテントの秘密基地がある。
そこで僕の ”意識” はひっそりと暮らしている。
毛布と懐中電灯をもって、大好きなうまか棒を食べながら。
チビの意識を乗っ取らないよう、ひっそりと。
チビはまだ気づいていない。まさか自分の脳の奥底に僕がいるとは。
実は、一緒に暮らしていた頃、脳がシンクロを繰り返すうち、ほんの少しだけ僕の ”意識のカケラ” がチビの脳にコピー着床されていたようだ。
それに気づいたのは、僕が死んだあと。
僕の意識はチビの脳内で目覚めた。コピーされた意識の種が目を覚ましたのだ。でもその時は、まだまだ小さく、ボンヤリ不確かな意識だった。
それからの数か月、
僕は、チビの記憶の世界でさまよった。いろんなところに散らばっているであろう、かすかな僕の意識のカケラを少しづつ拾い集めた。学校の机の中や路地裏の隙間、絵本の間に挟まっててたことも…。
それらをひとつにまとめて、なんとか僕の意識は、自立してモノを考えられるくらいまでには大きくなった。
そう、僕たちはひとり。
本当にひとりになった。
ほら、見てごらん。
たった今、
チビは四ツ谷駅のそば、外濠土手の桜並木を歩いているようだ。
彼の目、耳、肌…、五感を通して、かすかに感じる。
今年も美しい花びら群がはち切れんばかりに咲いている。
春の強風で宙に舞う幾千もの花びらが白くキラキラと光っている。
実に鮮やかだ。
手をつないでいるのは…
ああ、猫ちゃんだね。隣にばあちゃんも。
そばにいてくれてるんだね。皆、笑ってる、よかった。
あれ、もうひとり。小さな女の子がいる。
5歳くらいだろうか、車椅子に座って、スチール製のギプスを足に添えている。
その瞳は…、猫ちゃんの瞳と同じ。麗しい ”虹彩” 。
美しいその笑顔は、猫ちゃんの幼い頃を彷彿させる愛らしさに満ちていた。
よかった…意識が戻ったんだね、妹さん。
よかったね、猫ちゃん。
こんにちは、”小さな猫ちゃん”。チビと仲良くしてやってね。
ずっとここから、こっそりチビの人生を見守ることにしよう。
決して邪魔しないように。
そう、僕とは別の、チビはチビの人生を歩むべきだから。
彼の成長を、これからの未来を、見守ることを楽しみにここで生きていこう。
いつか大人になったら、僕と全く同じになった顔…僕より歳をとった顔…。いろんな姿を見てみたいな。
どんな仕事をするのかな。結婚するのかな。我が子をこの手で抱っこするのかな。その子は、どんなにか可愛らしいだろう。
なにもかもが楽しみで仕方がない。こっそり、ここで味わせておくれ。
お願いだ。どうかどうか、幸せでいてね。
君の人生は、きっと素晴らしい。
皆もいることだし、なんだかうれしくなってきちゃった。
そうだ、ちょっとだけ…。そう、ちょっとだけいいよね。
聞こえなくてもいい。
なんだか叫びたくなったんだ。
”おーい、チビ。
ありがとう”
「あれ?」
チビがピクリと反応した。
「兄ィ…?」
辺りを見回して、首をかしげる。
「どうしたの?」
覗き込んだ猫ちゃんの顔。久しぶりのアップ。
「今、兄ィの声が聞こえたよ!」
「え?そんなわけ…」
怪訝な表情。
「ううん、聞こえた!兄ィだよ!兄ィ!」
「まさか…」
「絶対そうだって!」
やばい。チビの人生を邪魔しちゃいけないのに…。
すると、ばあちゃんが、
「そやな。」とチビの肩をそっと手のひらで抱き、すべてお見通しのように皺だらけの顔で穏やかに笑って言った。
「ゆうちゃんはな、みんなの中におるんよ。ずっと。」
猫ちゃんは嬉しそうに、
「はい。います。」と笑った。
その表情を見て、妹さんも嬉しそう。
「そうだよね!」
チビは、胸に手を添えて叫んだ。
「兄ィ、見えるかい。みんな元気だよ!」
見えるよ、見える。
ちくしょう、泣けてきたじゃないか…。
「兄ィ。」
なに?
「ぼくも、ありがと!ずっと一緒にいようね。」
うん、一緒にいようね。
幾千もの花びらが、春の気まぐれなつむじ風に抱かれ、
5人をくるりと巻き込んで踊りながら空へ空へと昇っていった。
それはまるで、
みんなの未来を祝福するかのように、とても優しかった。
…チビ、
今夜、夢で会えるかな。
会えたら、いっぱいお話しようね。
そして、一緒に父ちゃんと母ちゃんに会いに行くんだ。
そう、バスに乗って。
(おしまい)
【★あとがき】
シオツマのnoteはすべて無料です。お代は頂戴しません。 少しでも多くの方に楽しんでいただけたなら…それだけで幸せです。
