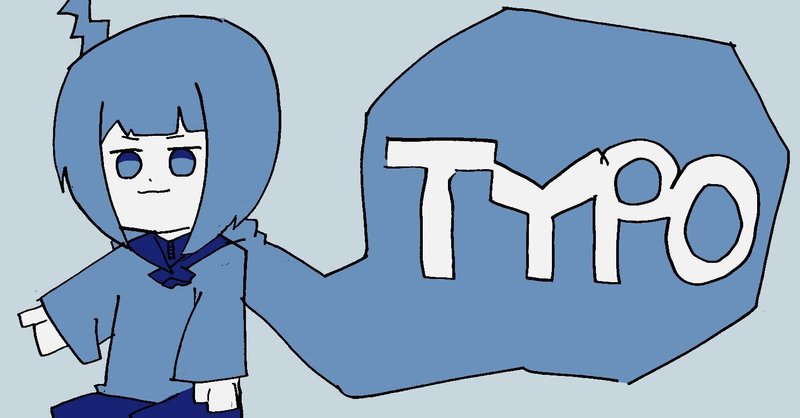
デジタルフォント時代にタイポグラフィ史を振り返って考える本
各種Office製品やDTP環境の普及によって、フォントを誰でも気軽に使える現代ですね。
フォントについての記事や本も多く出ていて、ただ何となくPCで使える文字、としてではなく固有の名前を持った制作物だという認識も普及しつつあると感じます。
今回取り上げる本
そんな中、今回とりあげる本はタイポグラフィの専門家によるタイポグラフィ史の専門書です。タイポグラフィという言葉の意味は概ね、文字を適切に扱う技術だと捉えておくととっつきやすいです。
ロビン・キンロス (著), 山本 太郎 (翻訳)『モダン・タイポグラフィ 批判的タイポグラフィ史試論』(グラフィック社、2020年)
まとめ
専門的に書体開発をするようなタイポグラファーに向けて、タイポグラフィの歴史を記述した上で論争をしかける本という印象です。
ただ、そこまでの専門的な知識のない状態で読んでもおもしろく読むことができたので出てくる固有名詞にどこまで馴染みがあるかによって評価が変わってくるかと思います。
ハウツー的なデザイン本で取り上げられる「タイポグラフィ」はフォント自体の歴史や政治性よりも、成果物であるフォントの印象に焦点を当てて解説しているものが多いと感じていました。
なので、本書のように豊富な参考文献と実例を踏まえた上でタイポグラフィについて語るものは貴重で、フォントやタイポグラフィに関わる人たちに(文章堅めですが)おすすめな本だと思います。
取り上げている記事
OVERKAST代表/ÉKRITS編集長の大林寛さんと帝京平成大学 助教の中村将大さんのプロジェクト「デザインのよみかた」内で本書を取り上げている記事がありました。
本書とほぼ同時期に、日本でタイポグラフィについての本『タイポグラフィの領域』を書かれた河野三男さんをゲストに迎えて、本書についてとタイポグラフィについての考え方等を話されています。
ページ中ほどの河野さんの発言部分、本書を読んだ上でどう活用するかのヒントになりそうな部分がありました。
SNSでたびたび問題になる炎上があります。SNSは、同じサービスであれば、みんなが同じ活字、組版の設定でコミュニケーションをしている。それがゆえ、意見の違いや、齟齬が許せない感覚になるのかなとも想像しています。おのおのの手書きであれば、ああはならないかもしれない。駅のトイレの落書きとか、誰も真に受けないでしょう。なんかいってら、ですませてしまう。だけど、活字というおおやけなるもので、それが再現されると、ある種、フォーマルなものになってしまい、正面から受け止めないといけないようにみえてしまう。
一人ひとりの声や背景は異なっていて違うことを言っていても、それが同じような文字で公的な場所に出ていると、文字は同じなのに意見が違うのが不快に感じられやすいということですね。
タイポグラフィや書物にまつわる歴史の中でも、口述筆記や手書き写本等のほぼ個人で制作を完結していた時代から、匿名の複数の個人による大量生産が可能になった現代に至るまででフォントやタイポグラフィの置かれた立場や役割は大きく変わっていそうです。
気になった部分
本書は基本的に時系列で「モダン」なタイポグラフィが始まったときから現代までを記述していて、目次は下記の通りです。
1 モダン・タイポグラフィ
2 啓蒙主義の諸起源
3 19世紀という複合体
4 反動と反乱
5 新大陸における伝統的な価値
6 新しい伝統主義
7 ドイツの印刷文化
8 北海沿岸の低地帯諸国の印刷文化
9 ニュータイポグラフィ
10モダンな人々の移民
11 終戦直後の状況と復興
12スイス・タイポグラフィ
13 モダニズム以降におけるモダニティとは
実例
出典:文献解題
出典:参考文献
全体を通して知らなかった固有名詞やフォントの名前が多く出てきて、ひたらす付箋を貼って読んでいました。
より現代に近い部分で、13 モダニズム以降におけるモダニティとは の章のフォントを提供している会社たちによる「フォント戦争」の部分は現在にもDTP現場に残っているものとして興味深く読めました。
(前略)フォント業界はにわかに熱に浮かされたようになり、株主総会や業界の会議は、まるでドラマの見せ場のような状況であった。このような雰囲気の中で、「フォント戦争(Font wars)」という言葉が流行した。予想を超えたことであったがアップル社とマイクロソフト社とが同盟関係を結んで、PostScriptType1の代わりとなる新しいフォント形式を開発するために力を合わせたのだ。それは1991年のTrueType形式の発表というかたちで具体化する。フォント形式はアップル社が開発し、マイクロソフト社は画像出力技術(これはTrueImageというものであったが、所期の役割を果たせずに後には頓挫する)を開発したのである。
現在においてもフォントのバージョンによる問題は現場で多発するものですね……
https://helpx.adobe.com/jp/fonts/kb/postscript-type-1-fonts-end-of-support.html
本書は西洋におけるタイポグラフィの歴史を記述した本なので、日本やアジア圏は取り上げられてはいないですが、終盤読んでいて写研とモリサワの事情とかを思い出しました。今ではデジタルフォント開発で協力しているようなので乞うご期待ですね。MM-OKL……
読後に
帯の推薦文にマシューカーター氏によって「タイポグラフィの歴史を論じた書物としてこれ以上に優れたものはない。」と推されているように、タイポグラフィ史の記述として信頼がおける本だと思います。
本書に立ち向かうためには別のタイポグラフィ本も読んでいかなければならないなと思いました。
デザイン一般のブックリストとして前に作りましたが、フォントやタイポグラフィ系でも勉強用に別途作っても良いかもしれません。
とりあえず手持ちの『タイポグラフィ』や小林章さんの本を読みつつ……
では。
書籍代となります!
