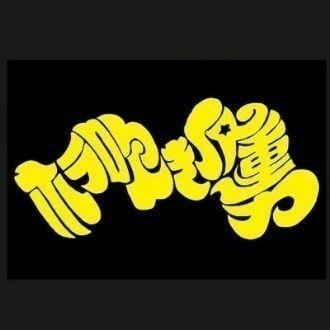2018年2月の記事一覧
ポプテピピックについて考える
ポプテピピック、というより大川ぶくぶの作品は「ヒトコマ切り取ったものがどこからかSNSに流れてくる」事によって広まったように思う。
こういうタイプのギャグ漫画は時々見受けられると思う。「伝染るんです」も自分にとってはカワウソやカッパをヒトコマ切り取ったものが、リアル世界で「回覧」のコピーで回ってきて知った作品だった。
そういえば、谷岡ヤスジの作品も、牛が「オロ?」とか言っているヒトコマのコピ
鉄道趣味の閉鎖性について
(拙ブログ「俗世界の車窓から」より一部加筆)
例えば飛行機雑誌でファントムやトムキャット、イーグル、ホーネット、あるいはジャンボジェットの特集を毎回次々やっても文句は来ないだろう。クルマの雑誌でフォードGT40や427コブラの特集をやっても同様だろう。
ただ、鉄道雑誌に関しては「アメリカネタ」、もっと言うなら「海外ネタ」を快く思っていない勢力が間違いなく存在する。実際感じるし、Wikipe
「ドラえもん」と性へのめざめ
自分が小学校4年の頃にテレビ朝日版「ドラえもん」の放送が始まった。
それからしばらくした頃だろうか、友人が「『ドラえもん』ののび太達って、自分達より年上なんじゃないか? 」と言ってきたのだ。当時は「ドラえもん」は学年誌の連載が主で、のび太達は「自分達と同じ年齢」だったのだ(自分は単行本派だったが)。 友人がこんな事を言った理由が最初はよく判らなかったのだが、少し後になって「ドラえもん」の単行本