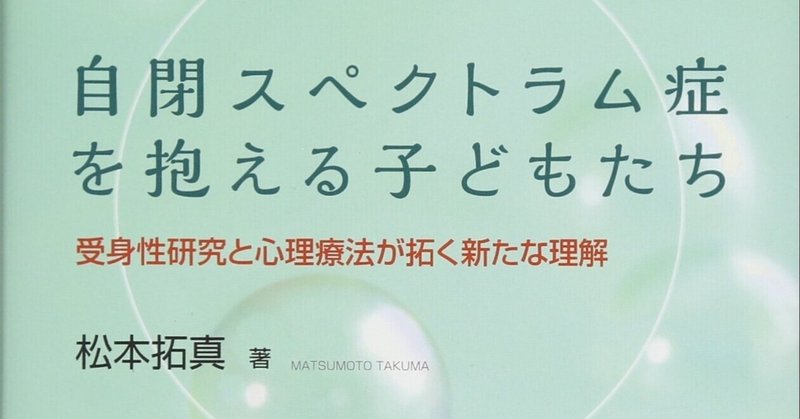
『自閉スペクトラム症を抱える子どもたち 受身性研究と心理療法が拓く新たな理解』を読んでみた
こんにちは。
ものくろです。
今回ご紹介する本は,松本拓真『自閉スペクトラム症を抱える子どもたち 受身性研究と心理療法が拓く新たな理解』,金剛出版,2017年。です。
本書を選んだ理由は,ウィングとグルード(Wing & Gould, 1979)の自閉スペクトラム症の対人関係の3パターンである孤立(aloof),積極奇異(active but odd),受身(passive)の3グループの中で,一番見過ごされやすい受身グループに特化した内容であるからです。①孤立は他者に関心がない状態,②積極奇異は自分から関わろうとするけど少し変な方法を用いてしまう状態,③受身は誘われれば言われた通りにする状態です。
では、なぜ受身グループが見過ごされやすいのかといえば、本書によると,
では、なぜこの本では受身グループの問題を中心に取り上げるのか。他の方法では対応しにくい問題だと私が考えているからです。第1章で私が出会った男児Aの「自分がない」という問題と母親の苦悩を思い出してください。一生懸命療育などに取り組んだ結果,親が求めることを子どもができるようになっていました。しかし,子どもが人から何かを言われるまで動かず,自分の好きなこともなさそうで,何を考えているかわからないという受身性の問題には通常の療育のアプローチでは対応することが難しいのです。さらにいえば、親が一生懸命やればやるほど,子どもが受身的になっていくという落とし穴にはまってしまう皮肉な問題がここにはあります。
つまり,受身型の自閉スペクトラム症は,他者に関心をもつことが難しい孤立型や,自分から関わろうとはするが相手のことを考えずに一方的に関わってしまう積極奇異型と違って,命令されればその通りに動いてしまう過度な従順さを抱えていることが課題なのです。
しかし,教育の現場などでは,大人の言われた通りにできる子どもは良い子(大人にとって扱いやすいという意味であり,悪く言えば大人の言いなり)であり,問題となることが少ないことが問題となってしまうのです。
では,自閉スペクトラム症の受身性という課題(特に「自分がない」こと)に対して私たちに何ができるのかというと,本書ではそれが心理療法となります。
ですが勘違いしてほしくないことは,心理療法が自閉スペクトラム症を治すわけではないということです。
では,何を目指すのか?
それは,自閉スペクトラム症を抱える人が障害特性を抱える中で生じた他者との関係の傷を癒やしていく営みであると同時に,その人の体験を知ることにも繋がることです。
本書によれば,
セラピスト側が心理療法は自分を知る営みだと考えていようとも,利用する側からすれば,心の傷つきを癒やす方法や悩みを解決する方法として求められます。保護者は自閉スペクトラム症を治して欲しいと心理療法に期待するかもしれません。この期待に対する一般的な応答は,「自閉症は,脳の機能障害であって,心の病ではない。だから心理療法で治せない」というものです。私も基本的に同じ意見なのですが,この考えは「自閉スペクトラム症を抱える人の心は傷つかない。だから心理療法は意味がない」という極論にすりかわりやすいことを不思議に思います。同じ人間であるわけですから,ある状況に置かれたときに深刻に心の傷を抱える場合があるでしょう。心理療法は,自閉スペクトラム症に対してではなく,それを抱える人の心の傷に役に立つのです。
本書の内容は、以下の通りです。
はじめに
第1章 自閉スペクトラム症の子どもに必要なこと
第2章 自閉スペクトラム症の一般的な理解:「相手が見えない状態」
第1部 自閉スペクトラム症の受身性の研究から
第3章 なぜ自閉スペクトラム症の受身性に注目するのか?
第4章 受身性が発達していく過程:ある家族の物語から
第5章 「うちの子に受身性など関係ない」といえるのか?
第6章 受身性の3水準モデルと「自分」の生まれ方
第2部 自閉スペクトラム症を抱える人に心理療法ができること
第7章 健全なコミュニケーションと自分と他者のバランス:精神分析的心理療法の考えから
第8章 身体がまとまりを得ることとその利点:赤ちゃんの観察から
第9章 子どもの心理療法はどう始まって,どう進むの?
第10章 子どもの意志に居場所を与える:Aとの心理療法1年目
第11章 出てきた意志を消さないために:Aとの心理療法の小学校卒業まで
第12章 自分に知らんふりをするのをやめる:Aとの心理療法の中学校時
第13章 子どもの障害受容って簡単にできるの?
第14章 家出・放浪をした青年期男性の心理療法:他者からの操作か社会性の発達か?
おわりに
本書は,著者の松本先生が2015年に大阪大学大学院に提出した博士論文が元になっています。しかし,専門家ではなく一般の読者が読みやすいように,なるべく専門用語を用いず,柔らかい表現を用いて書かれているため専門外の人でも読みやすいことが素晴らしい点です。
また,本書は計200ページを超えるそれなりに分厚い本ではありますが,各節の最後にある「この節のポイント」を読むだけでも大雑把な理解ができる点も素晴らしいです。
第1部までは自閉スペクトラム症の受身性について一般的な説明がなされていますが,第1部を読むだけでもネットサーフィンやSNSで仕入れた情報よりもより正確で詳細な理解を得ることができるのでオススメです。
第2部では,赤ん坊のOちゃん,小学校から中学校までの約6年間カウンセリングを継続したAくん,大学生のPさんの3人に行ったカウンセリングの経過が書かれています。特に,Aくんとのカウンセリングは詳細に描かれており,Aくんとの最後のカウンセリングでは危うく読者も泣いてしまうような別れの寂しさを感じられたほどです。また,大学生のPさんにしか見えない「バーチャル」の存在の話などは,とてもリアリティがあり考えさせられる内容となっております(内容の加工はしてありますが,もちろんノンフィクションです。)。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
もしこの記事が少しでもお役に立てましたら、♡(スキ)をしていただけると嬉しく、励みになります。そしてフォローしていただけましたら、頑張って書いた甲斐があるというものです。
ではまた〜👋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
