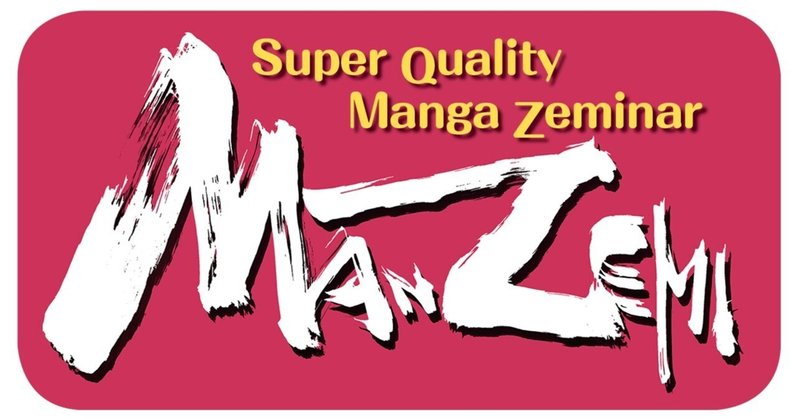
小さな出版社と独立系書店の生き残り戦略
◉noteのオススメに、興味深い内容があったので、ご紹介も兼ねて。雑誌の数は休刊が相次いでどんどん少なくなり、出版社はもちろん倒産や廃業するところもあり、町の本屋さんもどんどん潰れています。出版の未来は暗い……と嘆いて見せれば、簡単なんですが。それでは不安を煽るマスコミ仕草。現状は現状として、認識しつつも、可能性や未来を語りたいところです。
出版市場が縮小する中、「ひとり出版社」など零細版元が台頭している。従来の「売れる本」の常識に縛られない個性的な本作りで10万部単位のヒットを生み出す。紙の書籍・雑誌の販売額は10年で3割減ったが、零細版元の本を扱う小型の「独立系書店」と共に、出版大手や取次による全国一律の大量流通システムに風穴を開けている。
Inside Out
ヘッダーはMANZEMIのロゴより、平田弘史先生最後の揮毫です。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■寄席は減り落語家増■
例えば、落語。江戸時代は 現在の23区にあたる地域に 700軒以上の寄席がありました。700軒と言っても、何十人 か入る大きな寄席もあれば、10人も入ればいっぱいの小さなところもあり、単純比較はできませんが。これが明治時代には、400軒ぐらいに減り。昭和の時代にはわずか4軒まで減りました。新宿末廣亭・池袋演芸場・浅草演芸場・上野鈴本演芸場。
他にも国立演芸場や上野広小路亭など、いくつか寄席ありますが、常打ちの演芸場ではなかったりしますので。落語中興の祖である名人・三遊亭圓朝がいた明治時代の100分の1にまで減ったのに、落語家の数は今の方がむしろ多いですし、もっと言えば平均的な年収も、今の方がはるかに良いでしょう。自分は寄席演芸場とは、出版業界における雑誌のような存在だと思っています。新人が修行して世に出るための場所。そういう意味で、寄席の価値観は否定していないどころか、むしろ必要な存在だと思っています。
ただ、立川流や円楽一門会は、寄席から離れても人材育成に成功していますし、それは上方落語も一緒です。もっとも上方落語は寄席を復活させ、上方落語の拠点として、うまく活用している印象です。昭和の時代の寄席とはまた違う形で、時代にあった人材育成のあり方があるのかもしれません。そこら辺をヒントに、出版業界と本屋の関係性も考えてみると、何か気づきがあるかもしれません。
■昭和の夢はもう見ない■
例えば 幻冬舎の創業者である見城徹氏は、昔だったら200万部売れた本が60万部しか売れないと嘆きます。個人的には 60万部でもすごい数字だとは思うのですが。正直言って昭和の時代の、100万部 200万部売れるような本の作り方は、難しいでしょうね。メディア自体、テレビや新聞の影響力がどんどん落ち、年に1冊ぐらいしか買わない人が、買う その一冊みたいな本は、なかなか出てこないような気がします。
【見城徹さん語る出版危機「紙の本は限界。コンテンツで稼ぐしかない」】朝日新聞
「この30年で最悪の状況」――数々のベストセラーを送り出してきた幻冬舎社長の見城徹さんはこう吐露します。紙の本が売れない時代に、出版社はどうやって生き残るべきなのか。率直な思いを語ってもらいました。
(中略)
うちが出した和田秀樹さんの「80歳の壁」で、累計60万部です。この30年間、いろいろなベストセラーを出してきた僕の感覚から言えば、200万部売れてもおかしくない本なんですが、それが60万部しかいかない現実があるんです。
それこそ 昔のテレビ だったら、視聴率が60%だ80%だ言ってた時代もあるわけですが。意味は趣味が細分化して、10%行けば御の字の時代。そんな時代に過去のようなメガヒットを求めること自体がおかしいわけで。もちろんたまに、30%台を超えるような作品が出ないわけではないのでしょうけれど。それは 狙ってやるものではないでしょうね。これは、別note『ネット書店とリアル書店:売れる本の感覚のズレ』でも書きましたが。
以前も書きましたが、プロレス人気が下火になったとき、関係者が「昔のようにゴールデンタイムにテレビ放送されれば、人気は復活する」と語ったそうですが。深夜でも視聴率が取れないのに、どうやってゴールデンタイムに復活するというのでしょう? どうやって高視聴率を獲得するというのでしょう? そこに腹案があるなら良いですが、そんなものはなく。黄金期を懐かしんで、昔の夢よもう一度では、成功などしないでしょう。新日本プロレスを買収したブシロードは、YouTubeで試合を無料で流し、海外の人気を獲得し、東南アジア興行を成功させたり。
そういう、時代の変化に対応できなかった企業や業態は、滅びるしかないでしょう。
■SNSが雑誌になる日■
落語の世界では、何が起きたかといえば。落語の世界ではホール落語によって、寄席の料金よりも高い値段でも、好きな落語家の話をたっぷり聞きたいというファンが増えたわけで。戦後の昭和40年代から50年代に、一気に この動きは加速して。落語協会分裂騒動を経て、5 代目三遊亭円楽の一門と、少し遅れて立川談志の立川流は寄席に頼らない、独自の育成 ルートを確立したわけで。元noteにある、小回りのきく 小さな出版社が増えているのも、結局は 細分化したニーズにどう答えるかという、ひとつの回答でしょう。
これが 昔だったら出版社は、書店のマージンに10%、取次会社にマージンと配送手数料など10%、著者に印税10%、製作費が20%から30%かかって、出版社自体の儲けは40%から50%だったのですが(大雑把な計算で、実際は制作費は発行部数などでかなり上下します)。しかし電子書籍の登場によって、取次会社へのマージン配送料と、製作費(紙代・印刷代・パッケージ代など)が大幅に減り、むしろ 小さな出版社の小さな商売が、少ないニーズに対応できる点で、有利になった部分もあるのです。
例えば、MANZEMI講座の受講生である臼井俊介先生は、地元の個展に併せて、32ページの画集の電子書籍とプリント・オン・デマンド(POD)版を発行したのですが。これ自体はページ数も薄く、100冊も売れれば御の字という、大手出版社ではやる意味がない小さな企画なんですが。個人がやる分には、充分に意味があるんですよね。赤字にはならないし。大手がやるなら、160~192ページぐらいで、2800円から3200円ぐらいになり、初版も3000部は必要ですから。

■専門書店としての寄席■
独立系書店、これはある意味で、上方落語協会の天満天神繁昌亭に当たると思うんですよね。寄席は本来、落語を中心に浪曲や手品、歌舞音曲を見せる場所だったのですが。吉本興業の台頭で、寄席は漫才中心になり。ストリーテリングがしっかりした上方落語は、逆に言えば大衆娯楽として漫才のスピード感や即効性に、対抗できず。桂米朝師匠が落語家になった頃には、30人を切るレベルまで落ちていたのですが。立川談之助師匠でしたか、昔は小さな公民館の落語会のゲストでも、四天王クラスが来てくれたと。
そんな中で、ラジオやテレビの時代に、まず笑福亭仁鶴師匠が売れ、テレビ時代の申し子の桂三枝(現桂文枝)師匠が爆発的に売れ、桂枝雀師匠という爆笑王が現れ、笑福亭鶴光師匠や桂文珍、笑福亭鶴瓶師匠、明石家さんまさんらが売れ全国区の人気に。そうやって、落語家の数が増えて多様性が生まれ。そうなったとき、落語中心の天満天神繁昌亭は、若手の修行の場であると同時に、それは青山ブックセンターや、とらのあなやメロンブックスのような、専門書の書店のような場になった面も。
一般書籍の店とは違う、そこに行けばほしい本がある、専門書の店。もちろん、一般書も売れるやつは置いてある。2018年には神戸新開地・喜楽館もオープンし。将来的には、京都にも上方落語の定席が生まれれば、三都に定席がある状態になるのですから、地域文化としても大きいですね。さらに将来的には、奈良・滋賀・和歌山にも上方落語の定席ができれば、修業の場としても重要でしょうね。それは、全国展開するようなものではないですが、地域の需要を満たす。薄利多売の大きな商売から、厚利少売の小さな商売へ。ウチもいろいろ、実験していきます。
気に入った方は、サポートで投げ銭をお願いします。あるいは、拙著をお買い上げくださいませ。どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
