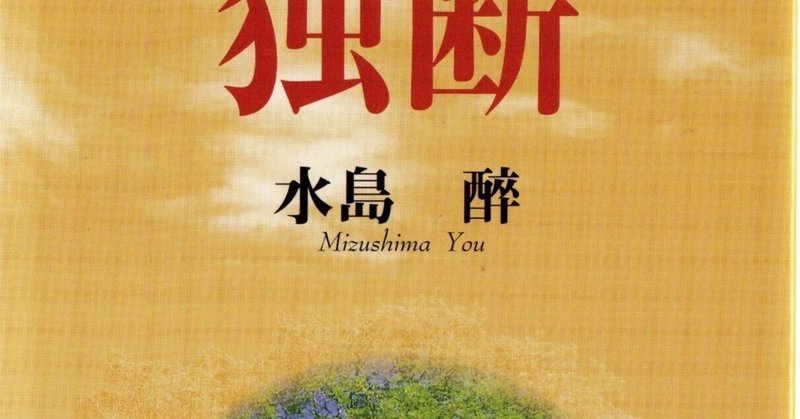記事一覧
独断 2022年2月
全ては「認知的不協和」である。「認知的不協和」とは有り体に言えば、「事実と自分の認識・希望とが異なっている場合に生ずる、心の不快感」である。そして人はその「不快感」を解消するために、事実を曲げて見るという行動にでる。
イソップの「酸っぱい葡萄」が、良い喩えである。枝に成っている美味しそうな葡萄を、狐が何度も工夫して取ろうとするが、どうしても取れない。結局「あの葡萄は酸っぱいんだ」と捨て台詞を
独断 2022年3月
以前に、間違った言葉遣いがさも正しい言葉のように喧伝されていることについて書いた。それがただの素人の意見ならまだしも、大手出版社の記事にも見られるので、これは問題だという私見を述べた。そして、徹底してその間違いを指摘し続けたら、さすがに上から目線の「これが正しい言葉遣いです。覚えておきましょう」などという記事はほぼなくなった。
その代わりというか、最近は「この漢字、読めなければ恥ずかしいです
独断 2022年4月
(承前)もちろんそこに「それで儲けよう」という意図も大きいが、「ルールの創始者になりたい」いう尊大な欲望もかなり含まれているのではないかと、私は勘繰る。
スポーツの金メダル。おそらく何千万・何億分の1人の快挙であり、普通は決して手に入らない。しかしそれが多く報道されると、何だか身近に感じ、自分にも何らかの「金メダル」が与えられてもおかしくないと錯覚するのではないか。
ルールを作る・変える
独断 2022年1月
私が小学生の時に、通っている小学校が創立百周年を迎えた。まだ十年も生きていない当時の自分にとって、百年前というのは果てしなく遠い過去のように思えた。しかし今、この年齢まであっと言う間に生きてしまうと、百年なんて大した時間ではないと思うようになってしまった。
しかしまた最近、百年とは長い時間なのだと再認識するようになった。
私は自分の家に電話(家庭用黒電話)が置かれた日の事を覚えている。そ
独断 2021年12月
金木犀の芳る季節になった。金木犀には少しばかりの思い入れがあるので、毎年少しばかり心を揺さぶられる。今年の初めての香りは所用で遠く出かけた先であったので、京都より数日早く聞くことができた。
香りを愛でるのに、マスクは不要である。邪魔であり無粋である。香りそのものも妨げるし、感じる心も妨げる。
私はラジカルアンチではないので、嫌がられてまでお店の中でマスクを外そうとは思わない。それでも屋外
独断 2021年11月
現実世界は戦争状態であるが、「受験戦争」という名はあれど、受験は戦争ではない。「そんな甘いことを…」という声が聞こえてきそうだが、受験は戦争ではありません!受験を戦争などと例える人は、本当の戦争を知らない人だ。本当の戦争は、自分の意思とは関係なく無理やり参加させられ、ついさっきまで隣で話していた人の腕がちぎれ、足が折れ、首が飛ぶ。明日は我が身。
受験は戦争ではない。自分の意思で参加するものだ
独断 2021年10月
今が「第三次世界大戦」の真っ只中であることを理解している人は少ない。第二次大戦の敗戦以降、日本では「軍事学」は禁止され、戦争抑止の方策を学ぶことすら禁止された。現在「国際関係学」などという名前で学ぶようだが、おそらくそれは「外交の一手段としての戦争」までで、個々の兵器の破壊力(=防御・抑止力)やそれに基づく「相互確証破壊」「戦略原潜の持つ意味」「占領政策」など「戦略」という部分までは防大以外では
もっとみる独断 2021年9月
また「科学」の話を書く。なぜなら「科学」こそが「近代学問」であり、近代人に共通の「言語」だからだ。「科学的思考」ができない限り、欧米近代人とは対等に話せない。だから私は「科学」について、しつこく書き続ける。
先月も書いたが、科学に必要なのは「第三者による実験検証」である。さあ、爆弾を投げ込もう。現在世界を席巻しパンデミックを引き起こしているとされる「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
独断2021.7(2021.6より続き)
[承前] 「鬼」つまり「自分の気持ちが理解されていない」という深層意識の不満は成長の過程で生成されるから、他人との関係ではなく、親との人間関係の中で子の心に形成されるものである。
子供は100%親に依存しなければ生きられない。その親に対して「自分の気持ちが理解されていない」と感じると、それが深層意識に植え付けられる。そしてそれが繰り返されることによって、より不満が強化される。
問題行動・
独断 2021年5月
毎朝の散歩で、鴨川の畔を歩いていた。花は満開、空は快晴、素晴らしい日和である。桜の側で少し佇んでいると、風も無いのに、一枚、二枚と花弁が散ってくる。はてと見上げると、小鳥が枝の上にいる。一口啄んでははらり、また啄んでははらりと、花弁で遊んでいるようだ。これはまた風流な。「梅に鶯」なら桜には何だろうと思いを馳せていると、妙な疑問に行き着いた。
小鳥が花弁を千切って遊ぶのは「自然」で「風流」だ。
独断 2021年4月
ハッシュタグ(#)をつけて「#マナー講師」とすると、これは嘲笑の対象である。SNSの発達と共に雨後の筍のように湧いて出た「自称マナー講師」たちが、いい加減なことを教えているからだ。両掌をお臍の上あたりに重ねて肘を左右に張って頭を下げるお辞儀が、最も有名なその例の一つである。そんなお辞儀の仕方は日本にはない。
今は猫も杓子も誰でもマス(大衆)に向かって発信できるので、「自称××」は無数にいる。