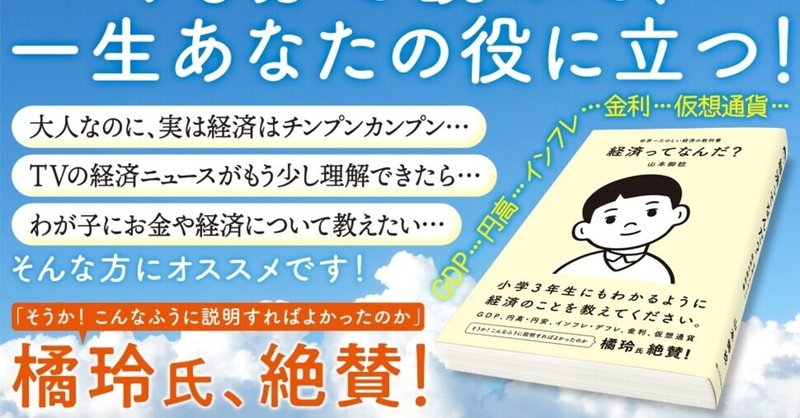
おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書6
第4章 銀行ってなんだ?
◉銀行にお金を預けると、少し増える
ねぇ、おじいちゃん。あの世にもテレビってあるの?
テレビ? ないなあ。でも、下界に降りてきてテレビをみることはできるよ。
へー、そうなんだ。じゃあ、昨日の夕方のニュースみた? 最近、泥棒の被害にあう家が多いんだって。
え? それは危険じゃないか。もし、この家に泥棒が入ったら……おじいちゃんは全力で領太を守るぞ。
守るって言ったって、幽霊なのにどうやって?
それは……こうやって。
うわ! 誰? 何その顔! 鼻の穴から目玉が出てるよ! やめてよおじいちゃん! 夢に出てきそうだよ!
凶悪犯には、こんな顔も……。
もういいってば! わかったから! おじいちゃんに守ってもらうから! それより、ぼくのお年玉を泥棒に盗まれないように、どこかへかくさなきゃ。
お年玉?
そうだよ。最初に会った時に相談したでしょう? 保育園の時から貯めていたお年玉をママに預けていたら、ハワイ旅行の資金に使われそうになってるって話。そのお年玉を取り返して、机の引き出しにしまっておこうと思うんだけど、もし泥棒が入ってきたら全部盗まれちゃう……。ねぇ、おじいちゃん。どこにかくしたらいいと思う?
それは、悩むまでもない。銀行だよ、領太。
銀行? 銀行にお年玉をかくすの?
かくすんじゃなくて、預けるんだ。
預ける?
そう。銀行の一番の役割は、お金を安全に預かってくれること。他の言い方でいうと、お金を「任せる」という感じかな。お金を貸してくれるところでもあるんだけど、それについてはあとで説明するとして。銀行にお金を預けることを「預金する」というのだけど、預金するためには、まず銀行で預金口座というものを作ってもらうんだよ。
ヨキンコウザ?
今いくら領太から預かっているか、領太はいついくらお金を出し入れしたかなど、お金の動きを記録しておく仕組みを「預金口座」というんだ。領太専用のお金の帳簿って言うとわかるかな?
おこづかい帳みたいなもの?
そうそう。おこづかい帳みたいなもの。預金口座には一人一人違う番号が与えられて、他の誰かと絶対に間違えないようになっているんだよ。
知らない人にお金を任せて本当に安全なの? そういえば、テレビのニュースで銀行強盗って言葉を聞いたことがあるよ。銀行にあるお金を盗みに入る人がいるってことでしょう?
そういった悪党が入ることも想定して、銀行にはしっかり管理されている金庫があるから大丈夫。それに、銀行にお金を預けると、少し増えるんだ。
え? お金が増える? どういうこと?
銀行にお金を預けると、すぐにお金を使うことができない(引き出せない)という不便があるよね? あと、領太がさっき言ったみたいな不安もあると思う。知らない人にお金を預けて本当に安心なの?って。そういった不便や不安に対して、「ごめんね、でも預けてくれてありがとう」というおわびというか……そう、お礼だ。お礼の気持ちで、銀行は預かったお金を少しだけ増やしてくれるんだ。その増やしてくれた分を「利子」や「利息」というのさ。
リシもリソクも同じ意味?
あぁ、同じだよ。細かく言うと、お金を借りた際に支払うお礼が利子、お金を貸した際に受け取るお礼が利息という使われ方をしてきたけれど、基本的には同じ意味と思っていいよ。不安や不便は時が経てば経つほど大きくなるから、預けている期間が長くなればなるほど利子も大きくなるってわけ。なお、借り手から貸し手に支払われる、あるいは貸し手が借り手からもらう利子の元金(貸し借りした実際の金額)に対する割合のことを金利というんだ。
預けると、どんどんお金が増えるってこと? いくらくらい?
最近は、本当に少しかな。例えば領太が1000円預けたとすると、1年間に1円くらい。
え? そんだけ?
30年くらい前の1986年だと、年金利が7%ぐらいだったから、今の金利を0・1%だとすると70倍、1000円につき年間70円くらいもらえたんだけどね。
70倍? そんなに違うの? なんで?
それはね、経済成長と関係しているからだよ。
ケイザイセイチョウ?
金利は経済成長によって変動する
領太は毎年、学校で身長や体重を測定して、身体の成長を測るよね? それと同じように、日本という国全体の経済の成長を測ることによって、銀行に預けたお金にどれくらい利子をつけてくれるのか、つまり金利が決まるんだよ。
経済を測るって……どういう意味?
経済とは、なんだっけ?
お金のやりくり。
そう。だから、「経済を測る」というのは、国全体のお金のやりくりを把握するって意味だよ。
国全体のお金のやりくりって、毎年変わるの?
あぁ、すごく変わる年もあれば、あまり変わらない年もある。領太のおこづかいも変わる
だろう?
ぼくのおこづかいは、成績によって変わるよ。テストで90点以上を10回連続で取ったら、500円アップしてくれるの。でも、そんなことは一度もないけどね。
経済成長によって金利が決まるシステムも、領太のそのテストととても似ているよ。国内で新しく生産されたモノやサービスによって儲けたお金(付加価値)の合計を出すと、国全体の経済力を測ることができるんだ。例えば、さっき話に出た1986年。
金利が今の70倍だった年?
そう。1000円で利子が70円ぐらいもらえた年。その頃は今と違って、パソコンなどのコンピューターはまだ家庭ではほとんど使われてなくて、会社などでようやく使われ始めた頃なんだ。急にみんながコンピューターを使いだしたから、コンピューターが売れに売れて、コンピューター会社の人は、「もっとコンピューターを製造して売りたいけど、工場が小さすぎて需要(ほしい)に追いつかない!」と困っていたんだよ。そんな時、もしも領太がコンピューター会社の社長さんだったらどうする?
えー? ぼくが社長? 想像つかないなぁ。でも……この前、図工の時間に町の模型を作った時、一つの机だけじゃスペースが足りなくなったんだ。でも、班みんなの机を寄せて作ったら無事に完成できたから……たくさんのコンピューターを作るためには、工場を大きくすればいいんじゃないかな。
正解だよ! 領太。素晴らしい機転だね。領太の言う通り、工場を大きくすればたくさんのコンピューターが作れる。でも、工場を大きくするためには新たに建物を建設したり、必要な材料も集めなきゃいけないよね。手伝ってもらう従業員も増やさなきゃならない。ってことは、当然お金がかかる。
うん、それはぼくにもわかる。
だよね。お金を持っていないのに、どうしてもお金が必要な時はどうしたらいいと思う?
ママだったら……我慢しなさいって言う。
そうだね。でも、コンピューターを作る会社が我慢しちゃったら、作ってほしいと思っている人たちは困ってしまうよね。それにコンピューター会社もせっかくの儲けのチャンスを逃してしまう。そんな時は、お金を借りるんだ。
お金を借りる? 誰に?
◉銀行はどうやってお金を儲けるのか?
銀行だよ。さっき少し話したけど、銀行はお金を預けるところでもあり、お金を貸してくれるところでもあるのさ。
ぼくにも貸してくれるの?
大人になって、必ず返せるという約束ができるならね。
100円なら、借りてもすぐ返せる。
そうかもね。でも、借りたお金には利子がつくから、借りた分より少し多く返さなきゃいけないんだよ。
リシって、預けた人のお金を少し多くしてくれるあれ?
そう、その利子。預けた人はもらうことができるけど、借りた人は逆に、銀行に借りた分よりも多く返さなきゃいけないんだ。そうしないと、銀行はお金をあげるばかりで、従業員にお給料を払うこともできなくなっちゃうからね。
そうか、銀行も儲けを出さないとやっていけないものね。
その通りだよ。銀行にとっては、預金の利子と貸出の利子の差が儲けになるからね。銀行は、国全体のお金のやりくりを確認しながら、お金を預けてくれている人たちにいくらあげられるか、貸している人にいくら払ってもらうかの割合を決めるんだ。
じゃあ、「必ず返します」「利子も払います」って言えば、誰にでもお金を貸してくれるの?
いや、口約束じゃお金を借りられないんだ。例えば、家を買うために何千万円ものお金を銀行から借りる場合は、何十年もかけて毎月少しずつ返すことになる。何千万円ものお金を一気に返せないからね。だから銀行は、借りた人が毎月の給料をいくらもらっているかなどを調べて、毎月ちゃんとお金を返してもらえるかを確認するんだよ。例えば、新しい会社を作るためのお金を貸し出す時は、その商売がどれくらい儲かるかとか、反社会的な勢力と関係がないかとか、さまざまなことを調べて、そのテストのようなものに合格した人だけにお金を貸し出すわけ。専門用語では、お金を貸すことを「融資」というんだよ。
ふーん。そういえば前に、おばあちゃんから似たような話を聞いたことがあるなぁ。大昔の日本で、春に稲の種を借りた農民が、秋の収穫が終わったあと、お米を多めに返していたとかなんとか。
ぉおー! そんな話をおばあちゃんが? それが利子の始まりともいわれている昔話だよ。
でもさ、銀行のお金はもともとみんなの預金なのに、お金を企業に貸しているのは銀行ってことになるの?
そうだね。銀行のお金は、もともとは預金者のものだから、銀行が企業などにお金を貸し出すことを「間接金融」っていうんだ。
カンセツキンユウ?
「間接」とは、「何かと何かの間に入る」という意味だよ。
つなぎめってこと?
そうだな、つなぎめでもあるな。間接金融は銀行における「何かと何かの間」のつなぎめなんだ。何かと何かとは、なんだと思う?
これまでの話だと、預金者と企業が「何かと何か」ってことになるよね。預金者と企業の間に入って「つなぎめ」になるのが、銀行ってことじゃないかな。
そうだよ! いいぞいいぞ。その通りだ!
ところで、銀行がもらう利子の割合の金利ってやつを決めたり、国全体のお金のやりくりを測るのは、どこの銀行がやるの? じゃんけんとかで決めるの?
いい質問だね、領太。金利をどうやって決めるかというと、日本銀行が会議を開いて決めるんだ。日本銀行が決めた金利を指標あるいは参考にして、民間の銀行も金利を決めていくんだよ。
日本銀行?
そうだよ、日銀と呼ばれている日本銀行は、お札を発行している銀行さ。
え? お札って、千円札とか五千円札とか一万円札とかのお札?
そのお札。小銭などの硬貨は、銀行とは別の造幣局ってところが作ってるんだけどね。日本銀行は、一言でいうと「銀行のための銀行」なんだよ。
ん? 銀行のための銀行? それって、どういうこと?
次回、第5章 「日本銀行ってなんだ?」へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
