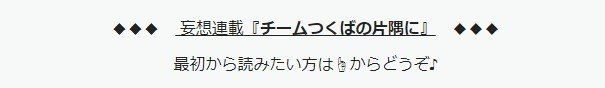36.筑波の吟遊詩人
「テレ東火炎砲」のあおりを食らい、伸び続けるアクセス数に辞め時を見失った私は、結局「第95回箱根駅伝関東学生連合まとめ」を1月末頃まで更新し続けるはめになった。
その検索作業中に、気になる記事を見つけた。
文春オンラインの「雑草たちの箱根駅伝」連載第1回、中央大学の中山顕さん(当時4年)のエピソードである。
「雑草」という言葉に私は引っかかった。
「雑草」とは「雑草でないもの」との比較として使われる言葉だ。
「公式試合」で実績のない学生さんをそう呼ぶことに、少しモヤッとするものを感じた。道端に生えている「雑草」にも、イヌタデとか、オオイヌノフグリとか、スズメノカタビラ(実家の地域ではビンボウグサというちょっとヒドイ名前で呼んでいたが)とか、ちゃんと名前はあるのだ。
リンク先の記事を読み始めたが、そこには自分の理解できない世界があった。
入学が決まった後には、当時の浦田春生監督に自ら「練習に参加したい」と電話をした。とはいえ、5000m15分台の記録ではなかなか入部の許可は下りない。なんとか寮外から日常の練習に参加する「準部員」という形式で話がまとまったという。
(上記記事より引用)
希望してるのに入部できない…???
私は陸上界のことだけでなく、いわゆる「体育会」の世界を知らない。
大学では、一度は体験してみたいと弓道部に入ったが、恥ずかしながらマジメな部員ではなかった。
部自体は大会にも出場していたし、ほとんどの人が真面目に練習していたけれど、運営自体は緩やかで上下関係もほとんどなく、私のような半分幽霊部員にも皆やさしかった。
だから「望んでも入れない」ということに、純粋に疑問が沸いた。
彼の並々ならぬ努力に尊敬の念を禁じ得ないと同時に、希望しても入部できないというシステムに、門外漢ながら素朴な疑問を持ちました…>https://t.co/VeWe7s5ctf @YahooNewsTopics
— うっしー (@miracle6719) January 22, 2019
注)ここから先の部活運営に関する記述は、あくまで私個人の価値基準に基づいた感想であり、他の大学の現行システムを否定するものではないことをあらかじめ申し添えます。
「一定の実力がないと練習についていけないから」という理由は、一見、学生さんのことを思いやった内容に思える。しかし、あくまで「大学の部活動」である。プロチームではない。
私のように遊び半分な輩はともかく、真剣にその競技をやりたいと思う学生さんの意欲こそ、教育的見地からみて最も尊ばれるものではないのか。
たとえ実力に差があったとしても、同じ目標に向かって互いに切磋琢磨すること。その中で育まれるものにこそ「大学で部活動をする」価値がある。
私は、学生スポーツとはそういうものだと信じて疑っていなかったのだ。
このとき、私の頭に浮かんだのは、彼のことだった。
中央大の記事をみて、彼のことを思い出している> Readyfor 16分半だった僕でも本気になれば箱根を目指せる~上迫彬岳~ #readyfor https://t.co/54JQijRkaG
— うっしー (@miracle6719) January 22, 2019
上迫彬岳(うえさこ・あきたけ)くん(当時2年)である。
この連載をずっとお読みくださっている方には、彼についての説明は不要かもしれないが、簡単にご紹介する。
昨年(2019年)6月、筑波大学の陸上競技部長距離パート(≒駅伝チーム)において、チーム改革の直接的なきっかけを作ったプレイングマネージャーである。26年振りに箱根駅伝に出場した原動力の一人として、各種メディアでも取り上げられている。
彼の最初の手記は、2018年8月、クラウドファンディングの新着情報として公開された。チーム改革が起きる1年前である。
冒頭に、手記を書くことになった経緯についての記述があった。
川瀬駅伝主将から僕が指名された時、初めは「自分には場違いだ」という気持ちしかありませんでした。
(上記手記より引用)
だが、私は彼の手記を読み終わったとき、「川瀬くんはこのプロジェクトのことを語るのに『最もふさわしい人物』を選んだのだ」と思った。
上迫くんの文章には、心が震えるような「物語力」があった。
自分が筑波大学で箱根駅伝を目指したいと思った経緯が、まるで一つの伝説であるかのように、情感豊かに描きだされていた。
特に、川瀬くんの前の駅伝主将であった河野誉さんとの交流に関する記述は、ひときわきらきらしい輝きを放っていた。
入部した当初は、実力不足と浪人のブランクで、朝練習さえも一緒に走れない日々が続きました。1ヶ月経って、やっと、1キロ4分ペースに3キロまで付けるようになりました。メイン練習など論外で、チームメイトと同じ練習なんて、まったく消化できない日々が続きます。
見かねた当時の河野誉・駅伝主将が「夏合宿まで俺が練習を立てて面倒をみてやる!」と救いの手を差し伸べてくれたのです。そう、僕が筑波大学を目指すきっかけとなった人物、都大路の2区で区間賞を獲得しながらも筑波大学に入学した憧れの先輩です。河野先輩の指導を受けながら、夏頃には、何とか人並みに走れるようになっていきました。
(上記手記より引用)
我々はなぜ、歌を聴いたり、マンガや小説を読んだり、映画を見たりして感動するのか。それらが紡ぎだす「物語」に、自分の心が共振するからだ。
自らの夢を、他人の心にも響くように語ることのできる能力は、誰もが持っている才能ではない。
彼は、筑波の吟遊詩人だ。
吟遊詩人とは、諸国をめぐり人々にいろいろな物語を聞かせ楽しませることを生業とする、いにしえの職業である。
吟遊詩人は、(本人たちは意図していなかったけれど、結果的に)異なる土地や生活環境に住む人々の間に「共通の文化」を醸成する役割を担った。
中世ヨーロッパでは、ゲルマン民族の英雄叙事詩である「ベオウルフ」の成立に影響を与えたと言われている。日本に置き換えるなら琵琶法師である。琵琶法師が語る「平家物語」に込められた仏教的価値観が、中世以降の社会通念に大きな影響を及ぼした。
残念ながら、筑波大学の箱根駅伝の歴史は、四半世紀も途切れたままでいる。現実問題として、実力がなければ箱根には行けない。だが、今は遠くても、箱根駅伝復活を本気で信じる者が物語を紡いでいかなければ、志そのものがすたれてしまう。
彼のような部員が生き生きと活動できるチームであるならば、必ずいつか箱根駅伝に出場できる。「吟遊詩人」たちが放つ「物語力」が、異なるプラットフォームで生きてきた仲間たちに、共通の「文化」となる素地を提供するからだ。
誰でも入部できるからこそ、様々な能力や価値観を持った人材が集まる。
競技力の面ではまだ足りないかもしれない。けれど上迫くんの存在に、筑波大学が目指すものの本質があると思った。
私は、1月3日に公開された「筑波大学箱根駅伝復活プロジェクト」のレポートで、彼が相馬くんの給水係を担ったことを知っていた。
今年、彼は相馬くんと一緒に箱根路を走りました。彼を給水係として送り出した筑波大チームの心意気を感じて涙しました。(記事後半に本人手記あり)https://t.co/K8F4NrxTPm
— うっしー (@miracle6719) January 22, 2019
当時の私は、かなり楽観的だった。
上迫くんのあの手記の熱情がチーム全体に伝わっているなら、彼を給水係として送り出したことは、チームの総意として当然の選択だと思えた。
筑波大学は、チームとして確実に成長してきている。
だが私は、実情を少し読み違えていた。そのことを、もっとずっと後になってから知ることになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?