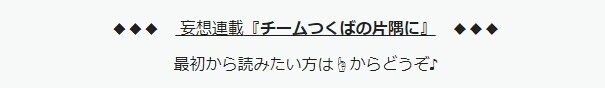51.金栗四三翁のDNA
26年振りに箱根駅伝予選会を突破した後、筑波大学には「奇跡の予選会突破」の秘密を解き明かそうと、各方面から取材が殺到した。
これらの取材記事から、我々「外の人間」は、弘山さんの一見「指導放棄」とも思える行動がきっかけで、チーム内改革が起こったことを知らされた。
だが、それはあくまで最後の一押しであっただろう。
25.予感で告白したように、前年秋の時点で、陸上シロートの私が、ネット上に公式発表されている情報だけで「いずれチーム内に葛藤が生じるだろう」という予感を抱いたくらいである。
長年トップアスリートを指導してきた経験豊富な弘山さんが、毎日彼らと接していて、そのことに気づかないはずがない。
普通は、指導者や周りの大人が雰囲気を察し、調整の場を設けたりする。そうすれば、水面下で事はおさまったかもしれない。
弘山さんはそうはしなかった。
学生さんたちの自主自立を信じた。
だが、幸か不幸か、彼らのポテンシャル(競技力の面だけではなく、様々なことへの対応能力)が高かったことが、事態をややこしくした。
本人たちは全くそう思っていないかもしれないが、周りの環境への対応能力の高い人は、自分ががんばればいい、と自己完結しやすい思考癖がある。
そのため、事態は問題を内在したまま、行きつくところまで突き進んでしまったのだ。
ゆえに、弘山さんはほんのちょっとだけ刺激したのだろう。
もっと彼らが自分勝手で、忍耐に乏しかったら、はやい段階で各々のエゴがぶつかり、チーム改革はもっと早く起こっただろうが、こればかりは、運命としかいいようがない。
ネット上に立ったさざ波(前掲の紹介記事中で、弘山さんは「けがに対する考え方の違い」という言葉で説明している)に関して、「筑波大学は今回の事情を説明すべきである、それがクラウドファンディング支援者への責務ではないか」という趣旨の意見が、当時ネット上に流れていた。
私はそうは思わなかった。
筑波大学箱根駅伝復活プロジェクトは、「学生さんの人間的成長」も含めてのプロジェクトだと思っているからだ。
ただ単に箱根駅伝に出場したいという目的だけなら、私はクラウドファンディングに参加していない。
学校を卒業して社会に出たとき、一人前の社会人として、自らが発言したことに対する責任は自分が負わねばならない。
他人と意見が食い違うことは、世の中ではよくある。それに、前も述べたように、これは「チーム内」の課題であって、周りが介入する問題ではない。
組織に内在する問題を、一人一人が自分の課題として捉え、みずから話し合い、物事を決める。
それは、学生さんたちのこれからの人生を考えた時、箱根駅伝に出場することと同じくらい、貴重な経験だと私は思う。
解決すべき課題と真剣に向き合ったとき、今の自分をアップデートしなくてはならない、という切実な葛藤が生まれる。
その葛藤を「知と技」で乗り越えることが、彼らの大先輩である、金栗四三氏の教えではなかったか。
箱根駅伝の父、金栗四三氏は、日本人初の五輪選手としてストックホルムオリンピックに出場し、「日本人の体力不足、技の未熟」を痛感した。
世界に追いつくための「手段」を模索する過程で、個人で努力することの限界を感じ、駅伝という団体競技を構想するに至った。
箱根駅伝の実況アナウンサーが必ず唱える「箱根から世界へ」というキャッチフレーズは、この金栗氏の想いを凝縮したものである。
科学技術が進歩し、トレーニング手法も飛躍的に研究が進んだ現在、陸上競技界における、駅伝の存在意義については、様々な議論がある。
世界の長距離界をいま牽引しているのは、ケニアやエチオピアといったアフリカ勢で、彼らが駅伝競技に力を入れているという話はきかない。
また、現在プロランナーとして活躍し、東京五輪へのマラソン競技出場が内定している大迫傑(おおさこ・すぐる)さんは、長野の駅伝強豪校である佐久長聖高校へ越境入学、早稲田大学時代も駅伝で活躍したが、彼にとって駅伝はまさに「手段」であって、駅伝競技自体への思い入れはそれほどなかったように思う。
そうした事例を掲げて「駅伝不要論」なる極端な意見もあるときく。
しかし、陸上シロートの素朴な感覚では、駅伝をフツウの団体スポーツだと思えば、問題はもっと単純になる気がする。
長距離走をしたいかどうかと、駅伝をしたいかどうかは別の事案である。
なぜなら、根本的に別のスポーツだからだ。
今の日本の長距離陸上界に問題があるとすれば、本来別の事案であることを、分離して考えられていない部分にあるように思う。
駅伝が誕生した経緯は、「日本人が世界に追い付くための手段」としてだったかもしれない。
でも、駅伝そのものが魅力的であったから、100年もの間、箱根駅伝は続いているのだし、今も日本各地で多くの駅伝大会が開催されているのではないか。
走るというシンプルな行為に「複数人でタスキをつなぐルール」を与えることで、団体競技としての「楽しさ」が生まれた。
競技場の中ではなく一般道を走ることで、沿道に住む、スポーツに縁のなかった人へもスポーツの魅力を伝える役割を担った。
駅伝競技が持つ、こうした素晴らしい価値を、現代に再定義する。
そのことは、駅伝を創った金栗四三のDNAを受け継ぐ、筑波大学の使命のように思えてならないのだ。
---
そんなわけで、筑波大学の新体制について、私個人としては全く心配しておらず、むしろ「みんなよくがんばったね」と胸が熱くなる想いだったし、なんなら尾原くんが副主将を引き受けていたことに、心の中でいいねボタンを100万回くらい押していた。
唯一心配だったのは、様々な憶測や批判がネット上を飛び交う中「支援者の方々の期待を裏切ってしまったのでは」と、当事者の学生さん達が不安に思っていないだろうか、ということだけだった。
支援者(サポーター)とは、物事が順調に進んでいるときには必要のないものだ。苦しい時に支えるからサポーターなのである。
今、一番苦しく、不安な状況にある彼らを支えなくて、いつ支えるのか。
筑波大学陸上競技部に縁もゆかりもない、ただの陸上シロートが、手の内にたった1枚握っていた「最強のカード」。
一度きりしか使えないそのカードを、切った。
迷いはなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?