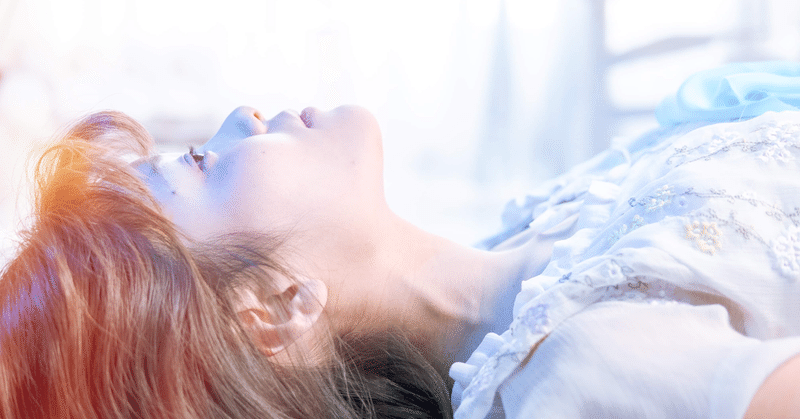
「書き残し」続けていく
わたしにとって、「読書」というのは娯楽に過ぎなかった。
お母さんが本が好きで、幼いころから毎晩のように寝る前に本の読み聞かせをしてもらっていた。
「もっと!」と駄々をこねるわたしに、「今日はここでおしまいね」とお母さんは本を閉じ、文字の読めなかったわたしは次の日を待ちわびながら眠りについた。
英才教育だったこともあり、読み書きの会得はものすごく早かった。4歳のとき、幼稚園に入る前にアンパンマンの力で覚えた。
それからは、来る日も来る日も飽きもせずに本を読み漁った。幼稚園では本棚の前を陣取り、おもちゃの取り合いで喧嘩するクラスメートを横目に黙々とすべての本を読んだ。
はじめは絵本、そして絵本に飽きると家にあった「エルマーのぼうけん」に手を伸ばした。
自分の知らない世界に連れていってくれる本の世界は、知らないお友だちと遊ばなければいけない現実よりもとても楽しかった。
お母さんは物持ちの良い人なので、8歳のときに彼女が読んでいた「星の王子さま」と「モモ」を譲り受けた。ガツンと頭を殴られたような衝撃を受けたのを覚えている。「モモ」で書いた読書感想文は、市内のコンクールにも選出された。
中学で渡米しても、洋書そっちのけで日本の小説ばかり読んでいた。中学生らしく、石田衣良と東野圭吾にはどハマりしたし、江國香織や山田詠美を読んだときは少し背伸びしている自分に酔いしれた。
そんなわけで、生まれてから今に至るまで毎日毎日性懲りもなく本を読んでいたわたしだが、やっぱり「ビジネス書」だけはどうしても好きになれなかったし、昔の古い言葉をがんばって訳したような難解な哲学書も苦手だった。
でも最近、「この人の思考が好き」と思える人がいて、単純だけど「この人の本棚の中身をぜんぶ読んだら、この人の思考をインストールできるのでは」と思うようになってから変わった。
自分で本を選ぶと、どうしても自分の好みに引っ張られて楽なほうに流れていってしまう。
でも、勧められた本はちがう。
時には共感できないこともあるけれど、生ぬるいお湯にキンと冷えた水をさすような、ゾクリと身の毛がよだつ発見がある。
今まで目をつぶっていた方向に、無理やり首をひねられるような感覚に陥る。
そのたびに、「あぁ、人としての1番の幸せは、言葉が理解できることだったんだ」と思い知らされる。
もう死んでしまってこの世にはいない人の言葉に涙することができる。
直接会わずとも、同じ思いを抱いている人と一体化したような気持ちになる。
すごい。
だから人は言葉を残していくんだ。
いつか、自分と同じように悩む誰かに贈るプレゼントのように。
そんなわけで、最近は作家にこだわらず、選り好みをせず読書を楽しんでいる。
言葉をなぞるだけで、その人が生涯をかけて考えていたこと、経験をしたこと、伝えたかったことを断片的にでも知れるって、嬉しい。
だから、わたしも書き続けたいし、書き残していきたい。
サポートは牛乳ぷりん貯金しましゅ
